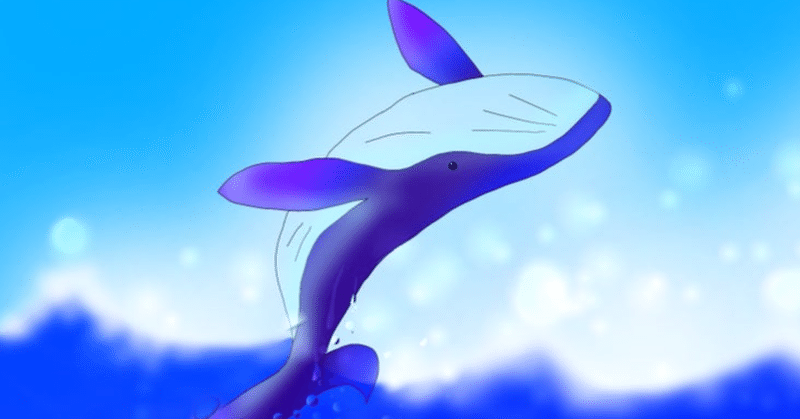
【短編小説】クジラになった同級生
昔は、みんな色々なものになりたがった。さとるくんはポケモンマスターになると息巻いていたし、ひまりちゃんはプリキュアになると言っていた。僕はこの頃から仮面ライダーになりたかったし、マサヤンはセロテープになりたいと言っていた。
だから僕は、将来の夢について発表する授業で、「おおきくなったら、クジラになりたいです」とノゾミが言った瞬間、教室が大爆笑に包まれたのを不思議に思った。僕たちはまだ小学五年生で、クラスの半分以上はサンタを信じていた。
担任の女教師は少し戸惑っていたが、生徒たちがノゾミを馬鹿にしていることに気がついて、すぐに声を張り上げた。
「こら、人の発表を笑わない!」
僕たちはわりと素直なクラスだった。面白ければ笑うし、面白くなければ笑わない。悲しいときにはわあわあ泣くし、楽しいときにはニコニコ笑う。この時は、僕たちのクラスのよいところが、悪い方向に発揮されてしまった。
しかしノゾミは、大多数の嘲笑に負けず、「わたしは、おおきくなったらクジラになりたいです」と声を張り上げた。彼女の声には力強い意志が通っていて、僕たちは本当に人間はクジラになれるのではないかと思った。僕たちの知らないところで、例えばアメリカの研究室とかそういった場所で、人間をクジラにする研究が行われていることだってあり得る。
僕はノゾミの顔を見つめながら、彼女のクジラに対する思いを聞いた。ドキュメンタリー番組でクジラの特集があったらしい。ノゾミは北極海を泳ぎたいと言った。過酷な環境での生活は大変そうだけれど、それはクジラに限った話ではないと言った。
ノゾミは本当に、本当に人間がクジラになれる前提で話を進めていた。彼女の話術には小学生とは思えない説得力があった。
僕は、自分のプリントを見た。
「はい優」と書かれた箱の中には「仮面ライダー」と書かれた跡だけが残っていた。
僕はもう一度、ノゾミの顔を見つめた。
授業が終わる頃には、クラス全員が「人間はクジラになれる」と信じていた。
しかしその洗脳も翌日にはすっかり効力を失っていた。クラスメイトはノゾミをからかい始め、それがイジメすれすれのところにまでエスカレードしたのはこの時からだ。
運良く、イジメには発展しなかった。ノゾミ本人はあれをイジメだと思っていたかもしれないが、当時の僕にはそれを判断するだけの能力はなく、未来の僕はそれを否定できる根拠を本人から聞いていた。ともかく僕は、あの時のことを鮮明に覚えている。
僕は図書室から戻ってきたばかりだった。ノゾミの話を聞いて、母から「人間はクジラになれないわよ」と言われてから、僕は何となくクジラの本や海の本を読むようになっていた。実は僕たちが知らないだけで、人間がクジラになる方法があるんじゃないか、と思ったのだ。しかし有益な情報は存在せず、僕は書籍を読み終えた後の、あのふわふわとした高揚を身に宿して教室の扉を開けた。
「あ、ヒロシ! お前も何か言ってやれよ!」
ナオヤがそう言って、ノゾミのことを見た。ノゾミは我関せずと言わんばかりの態度で本を読んでいる。
僕はこの時、どうしてこんなことを言ったのかを上手く説明することができない。僕は何もかもを無視して席に着くことだってできたのだ。それこそナオヤみたいに彼女の夢を馬鹿にすることだってできた。しかし僕はそうしなかった。
「どうせ泳ぐなら、南の海の方がいいんじゃないかな」
ノゾミが本から顔を上げた。そして、僕の方を見た。今朝のニュースでやっていた「二段階右折」のような動きだった。僕は一歩後ずさりをした。
ノゾミが席を立ち、僕との距離をつめてくる。僕はもう一度後ずさりをしたが、ノゾミの方が速かった。
「どうしてそう思うの?」
食いついてくるノゾミは、クジラというよりシャチのようだった。僕はしどろもどろになりながら答えた。
気がつけば、クラスの全員が僕とノゾミの会話に集中している。
「南の海の方が、なんだか楽しそうだなって」
ノゾミは、ふふっと笑った。
「クジラは、旅をするのよ」
そして、僕の手を取って図書室へと直行した。
彼女は僕の手首を掴んでいた。僕たちは廊下にいる人々の注目を浴びながら歩いていた。図書室の近くの掲示板には、図書委員の人たちが作った「今月のオススメ図書」のコーナーがある。今月は丁度動物がテーマだったが、そこにクジラはいなかった。
ノゾミは僕にクジラの事を教えてくれた。雄大な海を泳ぐ巨躯は確かに、どっしりとしたかっこよさがあったので彼女がクジラになりたがるのも頷ける。
「極地――北極とか、南極のことね。寒いところの海はエサが豊富なの。でも、寒くて大変な場所じゃ子育ては難しいでしょ。だから暖かい海で子供を育てて、食事のために極地へ泳ぐの。ほら、ここに書いてある」
僕は文字を目で辿ったが、彼女の言った通りのことが書いてあった。僕は素直に感心した。
「ヒロシは何になりたいの?」
不意に、ノゾミがそんなことを聞いてきた。
「廊下に貼り出されてるでしょ」
僕はそう答えてクジラの目を見た。
あの日、将来の夢について考える授業の際に使ったプリントは、教室の後ろに貼り出されている。しかしみんなは他人の夢に関しては無関心だった。友人のをそれとなく覗いて、パティシエとかパイロットとかユーチューバーとか、そういったよくある夢を見て「ふーん」と思う程度だ。
そんな僕に、ノゾミはふふ、と可愛らしい笑い声を上げた。
「ホントの仮面ライダーになれたら、教えてね」
僕は跳び上がった。
「何で!?」
「跡になってたのが見えちゃった。ごめんね」
ノゾミが謝ることではないが、僕はしどろもどろになった。しかし、小学校高学年になっても仮面ライダーになりたいと言う僕のことを、ノゾミは笑わなかった。
「変だと思わないの?」
「何が?」
「もうこんな歳なのに、仮面ライダーになりたいって思ってるところ」
「どうして? 困っている人を助けたいって思ってるんでしょう? 素敵な夢じゃない」
僕は彼女の言葉にすとんと納得できなかった。僕は仮面ライダーになるために俳優の道を選んでいるのだ。それは誰かを助けるための仕事じゃない。そんな僕の考えを読み取ったのか、ノゾミは僕の目をじっと見つめながら言った。彼女の目は、クジラの目によく似ていた。
「ヒロシみたいに、困っている人を助ける仮面ライダーになりたいって思った子供たちが、実際に困っている人を助けるのだとしたら、ヒロシはその、子供たちにそういう『優しさ』を教える立場になりたいってことなんでしょ? だったら、それは直接的じゃなくても、人を助けることに繋がると思うよ」
そしてノゾミは照れくさそうに笑って「実際、私のこと助けてくれたじゃない」と付け足した。
僕は、ノゾミに「どうしてクジラになりたいの?」と聞くようなことはしなかった。海を泳ぐだけなら人間にだってできるし、潜るにしても、スキューバダイビングという方々がある。冷たい海に潜るだけなら別にクジラになる必要はない。しかし僕は、なんとなくノゾミの夢を受け入れていた。
結局、僕たちは皆似たようなものだった。
あの時、歌手になると言っていたミホは都内の音楽機器の事務として働いている。漫画家になりたいと言っていたカツヤは何度か原稿を持ち込むも花は咲かず、ラーメン屋のバイトをしている。バンドを組むと言っていたナオヤは公務員として、生活保護申請の窓口にいるらしい。
僕たちは全員、それぞれの、しかしどこか似たり寄ったりな挫折を経験していた。仮面ライダーになりたかった僕は、結局鳴かず飛ばずの俳優として活動している。そろそろ年齢的にも仮面ライダーになるのは難しいだろう。出演が叶ったと思いきや、一話限りのゲスト出演。腰に変身ベルトはなく、「恋人を人質に取られるも、怪人に怯えて逃げる」という情けない役だ。
今回の主役を務めるのは、今をときめく話題の人気俳優だ。ライダーベルトを装着する姿も様になっているし、子供たちの憧れとして申し分ない。嫉妬はなかった。それほどまでに彼は仮面ライダーとして完璧だった。仮面ライダーのファンとして、彼以上の人材はなかった。
僕ではなくてよかった。
仮面ライダーが、僕ではなくてよかった。
そう、思ってしまうくらいには。
ロケ地は沖縄だった。ここから船で沖へと出る。監督はクジラと遭遇することのないよう細心の注意を払っていたが、地元の担当者は「こればかりは、確実に出ないということはありませんから」と言った。
僕は台本を見る。恋人役の女性が怪人の人質になったところで、彼女の名前――希美の名を呼ぶ。その後は湧き出てきたザコ怪人にビビって悲鳴を上げながら逃げるだけだ。
そういえば……ノゾミは、クジラになれたのだろうか。
僕たちは船で沖へと出て、撮影を始めた。恋人役の女性が不調らしく、台詞を間違えたり忘れたりした。監督が少しイラついてきて、現場はピリピリし始めた。それでも今日のうちにある程度撮影をしなければならない。予定より大分難儀したが、いよいよ僕の番になった。
怪人が僕の恋人を人質にする。僕は大声で彼女の名を呼べばいい。いざ、怪人が僕の顔を見る。そのとき、僕は遠くに黒い塊を見た。潮を吹くそれは――。
「ノゾミっ!」
これは後になって聞いたのだが、監督はこの時の僕の演技で機嫌を治したのだという。主演の俳優から何度も感謝された。
僕の迫真の演技は彼女の名前を呼ぶところだけでは終わらなかった。ザコ怪人に怯えて逃げるとき、船のデッキが少し濡れていた。僕はそれに足を取られて転びそうになったのだ。幸い、何とか体勢を持ち直して逃げることができたが、そのときの「足のもつれ具合」が絶妙だったらしく、この話が放送されると「これ、ほんとにコケてない?」とネットで話題をかっさらうことになる。
僕と入れ替わりで、ライダーベルトを装着した俳優がデッキへ飛び出していった。僕は船の後ろに回って、沖縄の海を見た。
「あ、ヒロシさん、見て下さい。クジラが出たんですよ」
「撮影の邪魔にはならなかった?」
「ええ。まるで監督の声を聞いていたみたいです」
僕はもう一度沖縄の海を見た。エメラルドを砕いたかのような水がうねっている。カアァット! と監督が声を張り上げたのが聞こえた。僕はほっと息をついた。
撮影は無事に終わった。僕はしばらく海を見ていた。一頭のクジラが頭を出して、船と併走し始めたとき、船内はちょっと色めいた。
「ノゾミ!」
僕がそう声をかけると、クジラは返事をするようにして、ざぶんと巨躯で波を起こした。僕はおおきく手を振った。クジラがひれを高く上げた。
「なぁに?」
呼ばれたと思ったらしい希美役の女優(本名が希望の望と書いてノゾミ、らしい)が僕のそばに来た。僕は何も考えずに答えた。
「クジラだよ」
彼女は、メイクで長くなったまつげをぱしぱしさせて「知ってる」と笑った。
僕はこの時、彼女もノゾミのことを知っているのかと錯覚したが、彼女は僕のそんな様子には気づかず、船についてくるクジラを眺めながら言った。
「撮影前まではみんなクジラが出ないようになんて言ってたのに、終わった途端これよ」
そう言ってクスクス笑って、彼女は船室へと戻っていった。しばらくはヒールの音がコツコツと響いていた。
クジラは――否、ノゾミはまだ海面にいた。
少し周囲の様子を窺った。これが聞かれていたら少し恥ずかしいからだ。幸い周囲には誰もいないとはいえ、僕の頬は少し熱くなった。
「僕、俳優に、なれたよ!」
当時の口調で声を張り上げると、ノゾミは満足したようにして泳ぐのを辞めた。ぐんぐん、ぐんぐん、小さくなっていくノゾミは船と十分な距離が取れたと判断すると、派手に潮を吹いた。
それはまるで、応援のようだった。僕の未来を祝福しているようにも見えた。そして僕は潮騒の中で、ノゾミの声を聞いたのだ。
――"仮面ライダー"になれたら、教えてね。
気の利いたことを書けるとよいのですが何も思いつきません!(頂いたサポートは創作関係のものに活用したいなと思っています)
