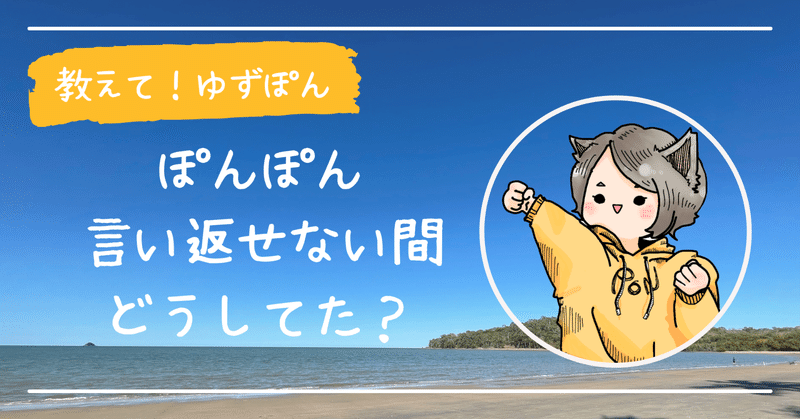
No.4 ぐぬぬとの付き合い方【教えて!ゆずぽん】
【Question】
質問をいただきました・:*+.\(( °ω° ))/.:+*:・(伝われこの喜びよう)
音声バージョンはこちら
今回も楽しく勉強させていただきました!
僕も冗談が好きで言いたいのですが、英語が未熟なので言葉が出てこなくてぐぬぬってなります…!
きっとゆずぽんさんにもそんな時があったのかなと思うのですが、どう対処されてましたか?
今回「も」……人ってひらがな一文字で幸せになれるんですよみなさんご存知でしたか。いつも楽しく読んでくださっているようで、感謝感激妖怪飴玉降らしをズーミンさんに差し向けたいところです。迷惑だと思うんでやめときますが。
のっけからとんでもねぇテンションですみません。安定の1日フル稼働のち深夜治安イマイチのマックからお送りしているもので。
英語ではなくてもやっぱりこの手の質問てたまに受けるんです。というか、母語で喋ってる時は、質問というよりは呆れ笑いと共に言われることの方が多いです。
よう喋るなぁ!
口の回る小娘だこと。
お前んちは静かな時がないのか
まあよく次から次へと言葉が出てくるねぇ。
どうしたらそんなにうまいこと面白い返しができるの?
1個は妄想です。さあどれでしょう。
しょーもないおふざけはさておき、質問は至って普遍的というか、この「ぐぬぬ」ってすっごく普遍的だと思うんですよね。英語だと、母語との差が大きい分それを感じやすいってだけで、日本語で喋ってたって「うまく言葉が見つからない」なんてことは本当によくあると思うんです。
特に日本は、言語構造的にも文化的にも、あとそこまで詳しくないけど地政学的にも、言語化とか明言を避ける傾向にあったから、そもそも英語圏なんかと比較しても、喋り言葉が発達してないような気はするんですよね。
「言わずもがな」とか、「皆までいうな」みたいな雰囲気が強いってことは、「輪をもって尊しとなす」といえば聞こえはいいし、おもてなしマインドなんかは海外からの賞賛の的になったりする。だけど、こと英語学習、そして英"会話"になると、文構造の違い云々じゃなく、大前提として、日本人は、自分の思いや考えを明言する訓練を受けてきた機会が少ないような気がします。
学校でのディベートなんて形ばかりのものが多いし、就活なんかの面接には「模範回答」があって。それをいかに尤も"らしく"、自分っ"ぽく"作り込めるか。やっぱり「正解」に帰着しようとする構造ばっかりが目に付くのは、長年塾講師として中学生を相手にしてきたからでしょうか。
英会話なんて学校のテストじゃねぇんだ、唯一無二の正解なんてあるわけないだろ。そもそも、コロナ前は誰も「ソーシャルディスタンス」なんて使ってなかったじゃん。この1単語からもわかる通り、言葉そのものが生き物みたいに栄枯盛衰を繰り返してるんだから、そこに完璧とか正解を求めること自体ナンセンスやねん。そんなことより、自分の中にある何かを、自分なりに探り探り、しっくりくる言葉を当てはめて表現できることが尊いんだよ。
自分の言葉で喋れる子は強い。これは私の信仰の1つですね。私が敬愛してやまない若松英輔さんも同じようなことをおっしゃっていました。もっと美しい、けれど素朴な言葉で。
【Answer】
この手のことは一生ぐずぐず言っていられるので、質問を受けた直後の生柑橘の回答を、本編としてズーミンさんにお贈りしようと思います。
First of All…
てことで、この質問を見て、最初に思ったんですが、
うまい返しに関して一番ぐぬぬってなってるのって、プロのコメディアンじゃね?
「そんな時があった」と言ってくださっているところから察するに、私はそれを乗り越えたとか、もうそうではない人、「元ぐぬぬ族」とでも捉えてくださっているようです。ありがたいことですが、別に日本語でも英語でも、私の生活は相変わらず「ぐぬぬ族」だらけですはい。
運転中とかぽけーっと真顔でお夕飯食べてる時とか寝る前とか、不意に「ぬああ〜〜〜こう言い返せばよかった!!!!」って、面白いことに限らず一人反省会なんて日常茶飯事だし、あの時なんて言えばよかったんだろうっていまだに答えの出ないシーンだってそれはそれはあるし、最近は特にUberの配達員で運転する時間増えたから、それはそれはもう考えてます。次同じような会話が発生したら…なんて、イメトレもする。安全第二…はダメですね、気をつけます。
でも、コメント主さんが聞きたいのはこんな「私だってまだまだですよ!」とか、「みんなも同じです!」とか、そういう混ぜっ返すような答えじゃないと思うので、真剣に考えてみました。配達しながら。そしたら道間違えた。お客さんごめん。
[①ゆずぽんのテクニック]
先日の記事よろしく、ここからは私なりに意識していることや、使っていることをサクッとご紹介していきます。
まず、自分の中でのパターンとか、鉄板ネタを構築する。これをやっておくことで、「自分の発言で人が笑ってくれたこと」に対しての成功体験が作れます。咄嗟の返しの前に、自分のエピソードトークとかトリビアで人が笑ってくれるパターンで自信をつけましょう。人前でお芝居したこともないのに即興劇に上がったら大変なことになりますよね。まずは練習できるものから。接客業って同じような質問や場面が繰り返されるから、実験には最適なんですよね。もし不発でも、仕事中だからずっとそれにかかずらってもいられないし。
そうやってもぎ取ったひと笑いの事例集はこちらから読めます。
それから、これに関しては私は日本語でもやってるっぽいんですが、人が私との会話で使った冗談は私も擦る。相手の語彙で喋るってことです。他の人が言ってた面白い表現を他の人に使うのもありです。パクれ。日常会話にいちいち著作権とか商標とかつける人いないんだから、パクリまくれ。
一例を挙げます。
上の記事で言及したバイト先の中のとある上司は、研修中のバッヂをつけている間、She has a Chinese name.なんて冗談を言うんですね。なんでかわかります?
名札が実名じゃなくて、trainingなんですよ。だからこれを、真ん中で区切って中国名っぽく「トレイ・ニン」みたいにわざと発音するんです。そんなイジリ、私からしたら美味しいことこの上ないです。
研修期間を訪ねるのに、
When can I get back my real name?
いつ私の本当の名前は取り戻せる?
て冗談まじりにすることでシリアスな空気をちょっと避けたりとか。
別の新しいバイトが入ったら、
Now we have the same name here! We are Trai・NIn!
That's his joke.
今のとこ、ここでは私たち同じ名前だね!トレイ・ニン!
あ、これ彼の冗談ね。
って仲良くなったりとか。
まだオーダー取るのに慣れてなかった時に、
Sorry for your inconvenience, that's why my name is like a Chinese. Trai・Nin.
ご不便をおかけしてしまってごめんなさい。だから私の名前は中国語っぽいんですよね…トレイ・ニンって。
って無理やり和ませちゃったりとか。
それはそれは擦りまくってました。なんならいまだにたまに使いますよ。
I may have to change my name back to a Chinese one!
中国名に戻した方がいいかもしれん!
とか、なんかやらかした後に。(その前にちゃんと真剣に謝りますけどね!!?そして3ヶ月経った今はちゃんと本名の名札つけてますよ!!ご安心を!!!!)
とまあ、こんな感じで周りの人の言葉を借りちゃうわけですね。
Fake it until you make it.
真似て学べ(できるようになるまでは真似しておこう)
私の好きな言葉です。
それから、これは言葉云々ではないですが、正しいかより、「冗談なんだけどさ、これ」って雰囲気を表情とか声のトーンとかで出せるのが楽な気がします。演技指導できるような身分でもなんでもないんですけど。私は欧米の人の片眉だけあげるのとか、ニヒルな表情作りたくて練習してたら右眉だけ上手くできるようになりました。結果的に顔の左右非対称度を上げてしまった気がする。
[②ゆずぽんのリアル]
別に滑るよ。べ・つ・に、すべりますよ。大事なことなので本当は海辺で北半球に向かって絶叫したかったけど、2回言うに留めました。毎日滑ってるから!!!!3回目。あと逆に相手が乗ってくれたのに聞き取れなくてしらけさせちゃうこともあります。
でも、なるべくそのまま黒歴史フォルダにぶっ込まない努力はしています。時間があるなら、その人に直接なんて言ったか教えてもらう。まあ時間がないならないでしょうがないけど、でも日本語でだって冗談が通じないとか、白けるとか、気まずいとか、あるじゃん?てな訳で、自分の中ではかなり確度の高いネタを得意になって使ったら、墓穴を掘ったこともあります。大親友に話したら、「それは氷点下通り越して絶対零度だわ」と、滑り方に対しての最高評価をいただきました。彼を笑わせたのは嬉しいですが、出来事自体は喜ばしくないです。まさに難有り有難い。あーあ。
そんなわけで、私の最大の失言は記事にするので、お楽しみに!
[③ゆずぽんのマインド]
だからって、全方位に気を配ってると何も言えなくなるよ。と言うのがこの項目で伝えておきたいことです。失礼なこと言っちゃったら素直にごめん!ていう用意をしといて。プライドとか恥を隠そうとしない強さを、大体の人は受け入れてくれます。精神論でごめんなさいね。あと魔法みたいな方法があるわけでもなくてガッカリさせたらそれはそれでごめんね。言葉という魔法の使い手ではあるんですけど、なんでもポイッとできるわけではないんです。上達の秘訣は……コケ慣れろ。だんだん受け身も上手くなりますから。
レンタカー屋さんのバイトで、お客さんを空港にお迎えに行った時のことです。うちのお客さんの例に漏れず、てっきり観光かと思ってなんの疑問もなく尋ねました。
Are you here for holidays?
-Nah, funeral.
葬式って言われた時の気まずさは本当にきつかった。これはやらかしたてほやほや、昨日のこと。穴があったら入りたい通り越して許されるなら私が棺桶に入りたかった。
これは完璧主義なところのある自分に言い聞かせるためでもありますが、
自分だけのおしゃべりマニュアルを作るには、試行錯誤しかないです。人を笑かすのが上手い人は、人より滑ってる。マインドがお笑い芸人なのかな?
お母さんが一番たくさんお皿を割るのは、お母さんが一番たくさんお皿に触ってるからです。母数の問題ってことですね。
Life is progression, not perfection.
師匠の有難いお言葉です。部屋の壁に貼ってあります。
[④ゆずぽんのメッセージ]
アドバイス、っていうとなんか烏滸がましいし、あんまこの言葉を自分から出すのが好きじゃないんで、敢えてメッセージとさせていただきます。
ズーミンさんをはじめ、ぐぬぬ族と睨み合いをしているそこのあなたへ。
ぐぬぬ、との付き合い方を変えてください。
ぐぬぬを見る目を変える、というのかな。こういうの「認知」っていうんですけど。ものの捉え方ですね。超絶雑にいうと色眼鏡とか、効果付きフィルターです。その人が何色のメガネをかけてるか、どんなフィルターをかけてるかで、世界の見え方は違ってきます。
簡単な例を出すと、運動会当日、朝起きたら雨だったとします。
えーさいあく、とか、あーあ、って思った人は、運動会をいいものとか、活躍の場とか、まあ楽しみにしてた人。
わーやった、とか、よっしゃ!って思った人は、同じものに対して、めんどくさいとか、辛いだけだから行きたくないなとか、勉強する時間が奪われるとか、何にせよ運動会に乗り気ではない人の発想ですよね。
脳科学者の中野信子さんがよく出される例えで、「雨が降ったのは運がいいことだと思いますか、それとも運が悪いことだと思いますか」みたいな問いかけがあります。
雨そのものに良し悪しはなくて、判断するその人の状況による、という話です。それを「認知」と呼んでいます。これをちょっと具体的に応用してみました。
質問者さんのコメントから察するに、
「ぐぬぬ」ってなるのは、いわば「良くないこと」
今のどこぞの柑橘みたいに、「ぽんぽん」冗談や言葉が飛び出すのが「良いこと」
まあこれ、面白いことに音のイメージ的にも噛み合っちゃってるんですけどね。
でも、本当は違うんです。いつだって物事や出来事に色付け、意味づけをしているのは私たち自身の捉え方でしかない。
年中考えるとか、しょっちゅう「ぐぬぬ」があるのは成長したいから。それは素晴らしいことだと、私は思います。もういいやって投げ出してない証拠。
だから、ぜひ、ずっとぐぬぬってなっててください!
とはいえ、です。ぐぬぬばっかだとたまに息切れした時にやめたくなっちゃうから、定期的に何ヶ月か前の自分を振り返ることをお勧めします。別に日記とか記録とか、あるに越したことはないけど、普通に思い出してみるだけでも、伸びが感じられて良いです。これを感じるための「鉄板ネタ作り」ってわけですね。成功体験がないと、成長意欲は続かないので。あ、これ質問に限らず向上心強い人が燃え尽きないためのコツ、というか経験則です。
「できた!」ばっか見ててもなかなか成長しないし、だからって「できない!」ばっかり探してても(人間、特に日本人はそもそもこっちが得意らしいですが)気が滅入っちゃいますよね。だから、
できない!でもちょっと前はこないだの「できた!」も「できない!」だったわけだから、きっとこれも「できた!」にできるはず
これが成長ってやつで、英語学習でも筋トレでもなんでも、同じなんじゃないでしょうか。
「できた!」って嬉しいけど、本当にその喜びを感じられるのは、その前に「ぐぬぬ」が、「できない!」があったからですよね。
物心つくよりも前に、意識せずともできていたこと、極端にいえば呼吸とかって、「できた!」って思えないじゃないですか。
あなたが「できた!」を味わいたい限り、その影に「できない!」別名ぐぬぬ族はついて回ります。
だから、そいつごと「よしよしお前ら、一人ずつ"できた!"に塗り替えてやるから覚悟しとけよ」と不敵な笑みでも浮かべてたらいいんじゃないかと思います。
もしくは、「こんなに真剣にうまいこと言って人を笑わせようとしてる自分、おもてなし精神強すぎじゃない?」くらいに内心自惚れてもいいかもしれません。冗談が好きって、人を笑顔にするのが好きってことじゃんね。
答えになってるのかなってないのか、それはここまで読んでくださった方の認知次第ってことで締めを諦め逃げを打って終わろうと思います。
何かしらあなたの目から、「知らず知らず濁っていた鱗」をはたき落とせていたら僥倖です。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
