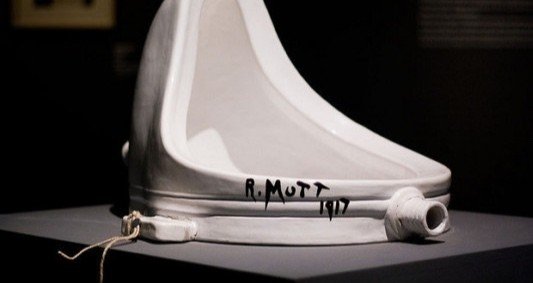#ピエール・ユイグ

Nicolas Bourriaud『The reversibility of the real Pierre Huyghe』読書メモ
ニコラ・ブリオーといえば、リクリット・ティラヴァニャを連想するけれど、ピエール・ユイグについてもいろいろとテキストを書いている。これはTateで見つけたテキスト。タイトルを訳すと”ピエール・ユイグの本質の裏返し”が、適切だろうか。 ユイグの作品は時間の経過を使い、認識と記憶とをハックするかのような作品であり、白昼夢を見せているような、そんな不思議な感覚がある。 The French art critic Nicholas Bourriaud examines the wa

George Baker, An Interview with Pierre Huyghe, October Vol. 110, Autumn, 2004 読書メモ 《Streamside Day Follies》
美術史家 George Baker によるピエール・ユイグへ2004年5月にニューヨークで実施されたインタビュー。それが October に掲載されていた。PDFのダウンロードは有料だけど、オンラインで読むならタダでいい。 この頃はHugo Boss Prize 2002を受賞した後。 インタビューのタイミングは、ピエール・ユイグがニューヨークのDiaで展覧会を終えた後、展覧会開催の9か月前からニューヨークに滞在していた。展覧会の終了は1月、インタビューは5月に受けている