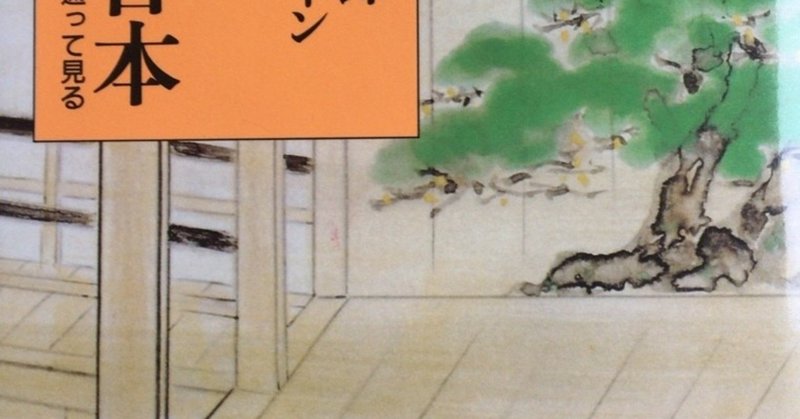
世界のなかの日本―十六世紀まで遡って見る
"この人の魂の質量は重い。そのくせ、ひとと対いあってるときは軽快で、この人の礼儀感覚がそうさせるのか、他者に重さを感じさせない。精神の温度が高いのか、たえず知的な泡立ちがある。"1992年発刊の本書は、文明批評でも知られた二人が【日本近世から現代まで】を自由に語り合っている対談集。
個人的には、主宰する読書会の準備の為に近代日本文学を調べていた際に、ふと2019年に亡くなったドナルド・キーンを懐かしく思い出し手にとりました。
さて、そんな本書では、日本文化や文学に造詣の深かった2人。ドナルド・キーン、司馬遼太郎が表題通りに16世紀まで遡って1990年当時まで、鎖国や遊びの精神、日本語の成熟、日本精神の在り方について自由に対談しているのですが。
近世は『星には興味がなかった』また『表札が庶民の家になかった』から江戸の切絵図(地図)が土産として重宝されたといった文化話。君と僕、お父さんお母さんは『明治以後の新しい日本語』である。夏目漱石が『日本語の文章を成熟させた』文学話などの雑学は流石に【視点が多彩で】興味深かった。
また対談集と一括りにしても、相手次第によっては、やたらと緊張感があったり、互いに噛み合っていなかったりと様々にあるわけですが。この対談集からは【互いに対するリスペクト】が端々から感じられて、心地よい読み心地でした。
二人のファンの方はもちろん、比較文化としての日本風俗や文学好きな方にもオススメ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
