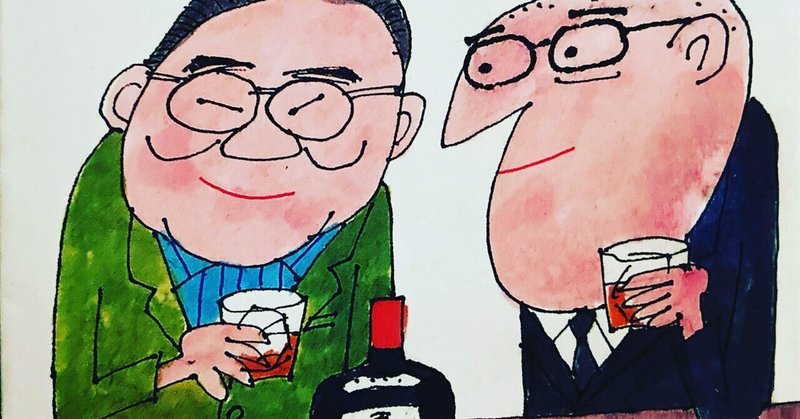
やってみなはれ みとくんなはれ
"名を捨てて実を取るという考え方に立つならば、世の中は、がぜん、暮らしやすくなる。住みよくなる。私は不思議な安堵感をおぼえた。はたらきやすい会社だと思った。"1969年発表の本書は社内宣伝部出身の芥川賞・直木賞作家コンビが綴った私小説的な幻のサントリー社史。
個人的には、著者2人の名前こそ知ってはいましたが全く作品は未読な中、2人が共にお世話になっていたサントリー70周年に原稿を寄せていたのを知って興味を持って手にとりました。
さて、そんな本書ではざっくりと山口瞳が最初に創業者の鳥井信治郎と『戦前のサントリー』を、そして後半は開高健が『戦後のサントリー』をバトンを受け取る様に、また著者達それぞれの私事を交えながら、割と自由に書いているのですが。
"社史"ということで、普通は先入観的に考えてしまう創業者への美辞麗句が踊っているわけではなく【ヘンコツぶりや欠点】に関しても2人とも遠慮なくズバズバと書いているのに、おおらかな時代の空気だったのか。あるいは【それが許される風通しの良い社風なのか】とか考えてしまいました。
また、特に開高健より後に入った山口瞳。東京の出版社から途中入社した彼から見た、大阪人らしい実利優先【やってみなはれ みとくんなはれ】と次々と新分野に挑戦していく様子の描写は、やはり『黎明期の企業史』としてわくわくするもので【会社の成長=自分の成長】と実感として多くのビジネスパーソンが感じられたであろう高度成長期、会社も個人も幸せだった時代を少し羨ましく感じました。
著者2人のファンはもちろん、サントリーに縁のある方へ。また、戦前から戦後にかけた企業史としてもオススメ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
