
人間として正しいかどうか、は国境を越えた普遍性を有する【本:生き方】
常に、「人間として正しいかどうか」を人生の羅針盤とすると、選択と決断に一貫性がでる。現代のミレニアル世代として、ふと立ち止まって「これは、また異なる意見だ」と思うときもあるけれど、学ぶことが非常に多い稲盛和夫氏の哲学本。
・人生の指針:思想、哲学、理念
・人間は、何のために生きるのか「生きる意味」と「人生のあり方」を根本から問い直してみたい
・日々誠実に努める
・魂を磨いていくことが、この世を生きる意味
・人間として正しいことを追求するという力強い指針
・働くということは、もっとも深遠かつ崇高で、大きな価値と意味をもった行為
・人生と仕事の結果=考え方×熱意×能力
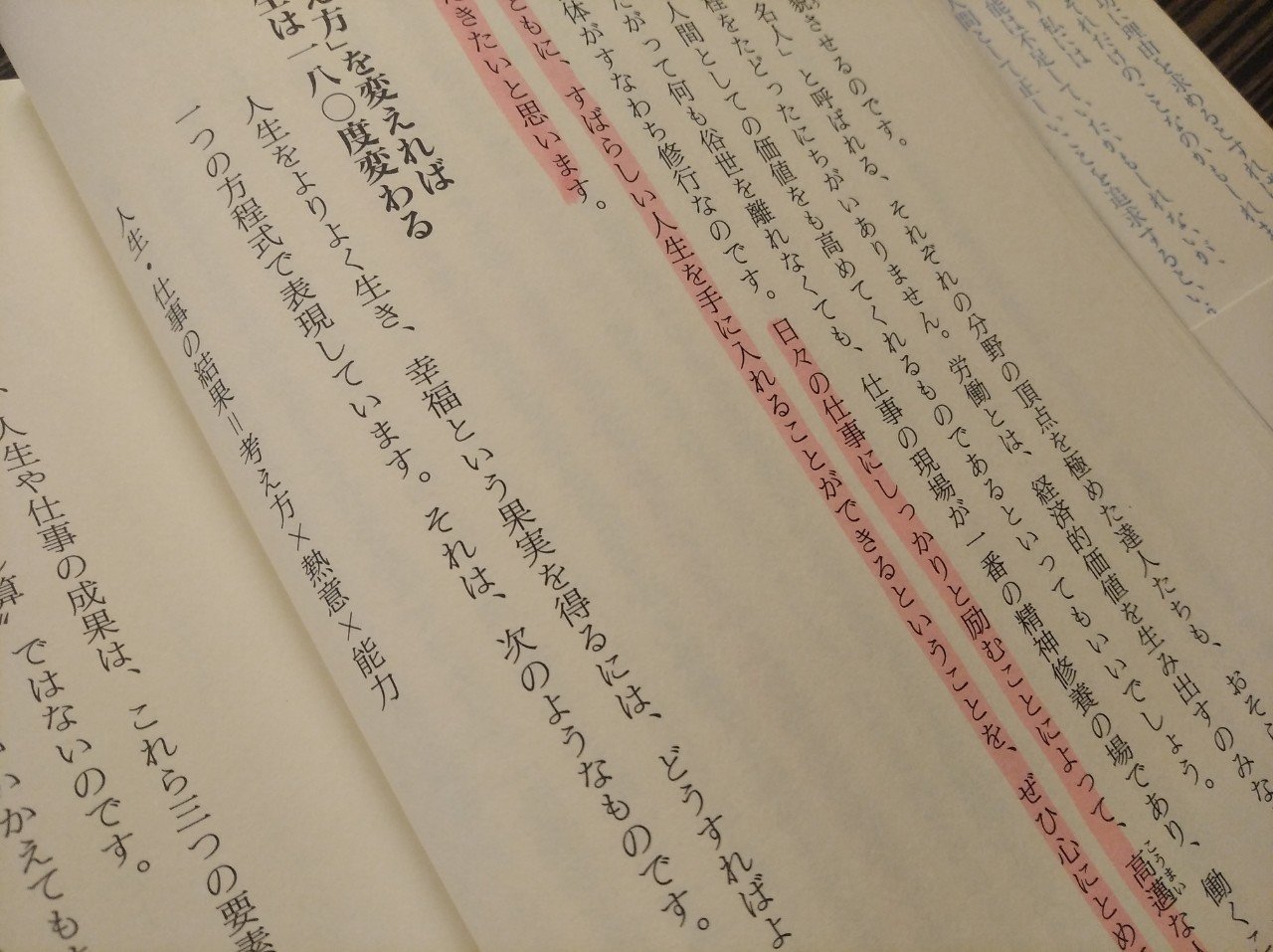
・よい心がけを忘れず、もてる能力を発揮し、つねに情熱を傾けていくことは、宇宙の法則に沿った生き方である
・すみずみまでイメージできれば実現できる、見えるまで考え抜く
・今日よりは明日、明日よりは明後日と、改善をつけくわえる創意工夫する心が、成功へ近づくスピードを加速させる
・「生きた哲学」という判断や選択の基準となる原則原理
・損をしてでも守るべき哲学、苦を承知で引き受けられる覚悟
・「自分に打ち勝つ」こと。利己的な欲望を抑えること、自分を甘やかそうという心をいさめること。
・海外での交渉場面。とりわけアメリカでは、物事を判断するのに「リーズナブル(正当である)」という言葉がよく出てくること。その正当性や合理性のものさしとなっているのは、社会的な慣習や常識ではなく、彼ら自身がもっている原理原則や価値観。道理に照らして正当であると思ったことは、堂々と主張したほうがよい。そうすれば、もともとロジカルな文化をもつ欧米の人たちは、その正当性を十二分に理解、尊重してくれるはず。
・人間として正しいかどうか、は国境を越えた普遍性を有する
・お釈迦様が説く「六波羅蜜」(ろくはらみつ)
1.布施(ふせ):利他の心をもつこと
2.持戒:戒律を守ること
3.精進:何事にも一生懸命に取り組むこと
4.忍辱(にんにく):苦難に負けず、耐え忍ぶこと
5.禅定(ぜんじょう):心を静めること
6.智慧(ちえ):以上の5つの修養に努めること

・日本が目指すべきは、経済大国でも軍事大国でもなく、徳に基づいた国づくりでは
・天台宗「忘己利他」:物欲を追求するのではなく、自分のことはさておいて、人さまのために尽くしていく
・道徳の欠如の根底には宗教の不在がある

・「足るを知る」:自然界は調和と安定を長く保ってきた。人間ももともと自然界の住人であり、かつては、その自然の摂理をよく理解し、自分たちも生命の連鎖の中で生きていた。それが、やがて食物連鎖のくびきから解き放たれ、人間だけが循環の法則の外へ出ることが可能となった。同時に、他の生物と共存を図るという謙虚さも失ってしまった。
・宇宙の流れと調和すること
・動力、思い、意識、力、愛、エネルギー
創造の場所であるカフェ代のサポートを頂けると嬉しいです! 旅先で出会った料理、カフェ、空間、建築、熱帯植物を紹介していきます。 感性=知識×経験 மிக்க நன்றி
