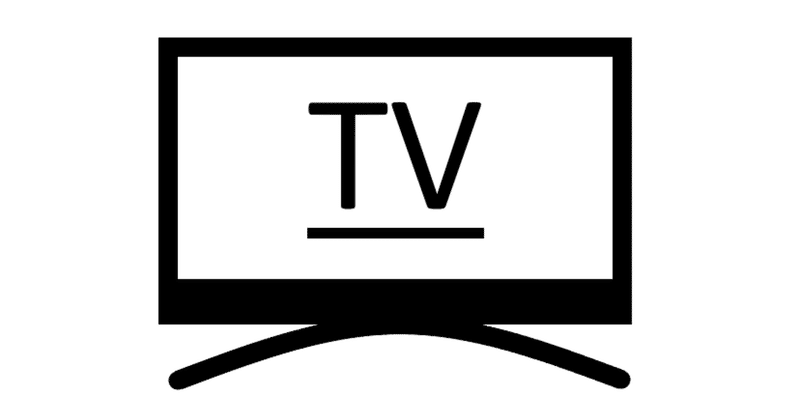
テレビ放送記念日
1953年2月1日に、日本初のテレビ本放送がNHK東京放送局でスタートしたことにちなんで制定された記念日。
私の家にはいまテレビがない。テレビや新聞の煽る情報が鼻につくので、消去したいと思ったからだ。"俺は載せられないぞ!"と鼻息を熱くしているガキにすぎない。読者の皆様には耳タコで、”もういいよ、それ”と云われそうだが、この議論を少し復活させていただく。といっても、あくまで昔話。思い出をたどるだけだ。
70年代と80年代、すなわち私がテレビをまだ見ていた時代のことである。
お茶の間時代。いまは隔世の感がある。読者の中にはそうきいてわからない人もいると思う。つまりは消えてなくなったが、かつては、テレビは一家に一台がせいぜいだった。夕食後の団らんは一家で同じテレビ番組を見ていた時代があったのだ。その頃、日本の経済成長はめざましく”ジャパンアズナンバーワン”という本が出てほかの国から称賛を受けたりもして調子に乗っていたのだ。中流家庭を目指して頑張っていた。中流から外れる家に後ろ指を向けて、イジメ文化を作っている間に内側から闇は迫っていた。それが露出してくるのが、80年代だが、闇の原因は70年代に仕込まれていたと思う。露出の一つがテレビが2台以上買えるように家から始まる。いわゆる個室の誕生である。この個室から家庭内暴力となって闇が噴出するのである。当時テレビを作った人たちは、このことをよくわかっていた。その闇が高度経済成長に仕込まれている矛盾によるものだと見抜いていた。「モーレツからビューティフルへ」「気楽にいこうよ、のんびり行こうよ」などなど、70年代のCMや流行語に経済一辺倒な社会にブレーキとなるようなワードを飛び出させる気概をもっていたのである。
◯コント55号とドリフターズ
”茶の間”というコンテンツにふさわしいバラエティ番組の中心となっていたのは、コント55号だった。やがてソロになった萩本欽一がお茶の間に颯爽と登場する。ライバルにはドリフターズがいた。ドリフの「全員集合」は視聴率50%超えのお化け番組である。その笑いの特徴はメンバー5名のチームワークである。いかりや長介が統治する世界の中で次第に他のメンバーによってやり込められるというストーリーがリズミカルに笑いをとった。萩本欽一が下ネタに頼らないのに反して、ドリフは平気でスカトロを茶の間に届け、さらに食べ物を粗末にした。これがPTAの不評を買った。そんな状況の中で75年スタートの”欽どん!”は、ただ見てゲラゲラ笑っているだけの茶の間の前に座っている人々をTVの中に招き入れたが、PTAの不評をよそに、茶の間に居座る子供は笑い続け、ドタバタに飽きてきた思春期の子供は茶の間を離れ個室でラジオを聴くようになっていたのである。ここまではそれぞれの笑いのスタイルの発現であった。しかし、それぞれのスタイルで勝負するという時代は次第に移り変わっていく。70年の終わりに個室にこもりそうな感度高い人向けに「THE MANZAI」を仕掛け、これが漫才ブームというムーブメントを興す。これをベースに出てきたのが、個人技をいかした「俺たちひょうきん族」でチームワークよりも、アドリブやハプニングで笑いをとるという「全員集合」とは真逆の路線であった。それが80年代なのである。
時代が移り変わっていくものであることをよく知る横澤プロデューサーが、漫才ブームからでてきた「笑っている場合ですよ」の昼帯で、アンダーグラウンドのタモリを起用し「笑っていいとも」をスタート。これが横澤氏自身も思いもかけず長寿番組となった。そして、そこにいわば萩本欽一の流れを組む小堺一機をくっつけるのである。ドリフVS欽どんを冷戦だとすれば、あえてそれをクロスオーバーするようなカオスで、わざと昼のコーナーをタモリが長引かせ、13時からはじまる番組の小堺一機が怒って登場させるような”枠超え”を行った。既成の枠を取り外し、テレビの世界と現実世界とを溶かしていった。
◯キャンディーズからピンク・レディーへ
1970年代はアイドル全盛時代といわれる。71年の6月1日に南沙織が「17才」でデビューしたことがそのはじまりとされる。「全員集合」のマスコットガールをしていた3人が「キャンディーズ」という女性ユニットを組み、次々とヒット曲を世に出した。歌って踊れてコントにも参加できる(フルスタックアイドル)。その茶の間での視認性の良さでスターダムを駆け上がった。そして5年という活動期間を経て、「普通の女の子」に戻っていく。 そもそも普通の女子がテレビにでたからウケたのだ。ちょうどその頃、スター発掘番組「スター誕生!」にクッキーという名の女性デュオが登場した。クッキーというのが「キャンディーズ」を意識したものであったのは間違いない。がしかし、スター発掘番組ではフォークデュオだった素材で、阿久悠と都倉俊一は大博打を打った。彼らは山本リンダでヒットを攫った路線をこのデュオでやってのけたのだ。それが茶の間に届いたとき、驚くべき変化が起きる。「ピンク・レディー」、名前からしてもお色気路線なのだが、なんとこの振り付けを真似し始めたのは女子たちだったのだ。キャンディーズが男性のみを虜にしたのを超えて、男女をともにファン層に取り込んでいくのだ。これが、のちの松田聖子に引き継がれていくのである。時代はウーマンリヴの幕開けだった。「異性に好かれる」というプロトタイプは次第に破壊され、ジェンダーフリーになっていくのである。雑誌「クロワッサン」はこの時代をうまく引き継いで、嫁にいけとばかりに云われる年代の女子を自立させていく。
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
当時のテレビ・ラジオ・雑誌といったメディアを作っていったのはIT業界の言葉を使えばフルスタックな辣腕テレビマン達だった。その万能さが時代を先読みしモーレツを批判していたのだが、その作り上げるやり方がやはりモーレツであった。そしてそのチグハグが、時代とぴったりと合っていたという僥倖のタイムリーヒットであったのだ。出る杭は打たれるというより、タイムリーゆえに舞い上がってしまって、振り上げた拳の下げどころがなかったのではないだろうか・・・梯子を外されて価値観の復古が起きる。
自立したはずのクロワッサンの読み手が結婚相談所に内緒で通うというチグハグさは、文化の多様性ではない気がするのだ。このnoteのひそかなテーマであるHistoryOfIdeaは、時代を作るのは経済でなく文化だと標榜する。この時代は半分はそのとおりであるが、実は先読みした思想を切り口に時代を批判するだけで現実解まで落とせておらず、目的の手段化のようなものが起きている気がしてならない。スタイルから入って、行動をはじめる。これだけでもやらないより何百倍もマシだ。が、たしかに出だしはよいが実が伴わないようなことが起きてくる。その原因は、ひとことでいえば哲学がないからである。あるいは哲学はあるにはあるが、目移りして自分探しをしてしまうような内向きにその力が働いて外に出てこないのかもしれぬ。出たとこ勝負しかありえない”混沌が好き”というだけなのは単なる思考停止である。
ジャパンアズナンバーワンといわれた日本経済も生産性を誇っていた時代から結果が出せない時代へと変わっていくのを体現したようなものである。
80年代後半は、そんな実が伴ってはいないが経済だけが発展するというチグハグをみせて推移する。”このままだとやばいぞ”と批判し続けたテレビは、梯子をはずされたというより、むしろ伸ばされて宙に浮いてしまった感じだ。
85年にプラザ合意が成立する。日本は、東京だけでアメリカが買えると豪語し、内側では歪みがあるにも関わらず、株価は上昇していってバブルになっていく。
「ニューアカデミズム」はそんな時代に登場してくるのである。浅田彰、西部邁、中沢新一などなど、一流の頭脳が茶の間にも漏れ出したのだ。
中でも、浅田彰の書いた「逃走論」は記述内容の難解さにも関わらずよく売れた本だとして知られる。「大人」になることを戦略的に拒否するスキゾキッズたちは、既成の職業につかず、ノマドワーカーとして世の中を渡り歩こうとした、リクルート社が「フリーター」という言葉をこの頃使ったのはポジティブな意味だったのだ。個室に閉じこもった暴力はいったんここで「おたく」となって昇華し、アンダーグラウンドから表舞台に引きずり出された。
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
1989年に昭和が終わる。茶の間ではロッキード事件で騒がせた田中角栄が政界を引退し、中国では天安門事件が起きて、さらには東西ベルリンの壁が崩壊する。
タモリの昼番組が予想外に長引いてしまったように、マスコミの批判にも関わらず、経済の数値だけは上昇を続けてしまった。
その実情は、時代は専門性を必要としているのに、いつまでもジェネラリストばかり欲しがる人事制度をもって人々を会社に縛り付けた結果、時代の変化についていけない保守的、ほどほど人間ばかりを作って1億総中流という歪なスタイルだけであった。ジェネラリストを望む人事では、馴れない仕事ばかりさせられるので、生産性は下がっていく一方だった。結果を出すために残業しか手立てがなく、家庭で過ごす時間はかりそめになって、茶の間に集まっているのにその実は「岸辺のアルバム」であった。
大事なのは茶の間なんて幻想だったという自覚だったはずなのである。しかしそれでもテレビの作り手が強いられたのは、持ち家を持つローンとその裏側をつくる生命保険という既得権保守装置のCMであった。(実にチグハグだ!)ありていの言葉ではっきりいおう。日本お得意の理系を育てるはずなのに、文系を煽り続けたのだ。家庭内暴力を解決しようとする「家族ゲーム」は切り口はよかったが、所詮”テレビが作るもの”であった。そんなヒーローは一般家庭に一向に現れなかった。専門性の権化である「おたく」の評価も宮崎事件で一気にマイナスの評価になった。ニューアカの頭脳の評価もオウム真理教によって汚されてしまった。そのままバブルが弾けて、自由なはずの「フリーター」は、就職したいけれどできない人というマイナスの評価のレッテルに使われるようになってしまう。
テレビの現場をそのまま見せて、視聴者も参画できるオープンな場としたのはさすがフルスタックな頭脳がよく回転し、どんな視聴者が現れても、ハプニングコンテンツとして、番組の中で調理するという腕ききのテレビづくりは功を奏していた。それは70年代に「ぴあ」がやってのけたプロとアマの垣根を壊したというか、インターネットの出る20年も前の先見的決断力だったといえよう。それでも経済は変わらなかったというより、いつまでも続く栄光なんてないんだってだけだ。いつまでも続く栄光なんてないのだから実力をつけなければいけないのに退廃の出たとこ勝負だけを煽った結果だ。
家庭内暴力の解決策はフリースクールでも戸塚スクールでもなかったはずなのに、解決策をTVは提案せずに、家庭にボールを預けたままになった。でもボールを預けるはずの家族、しかも茶の間なんて、所詮マスコミ自体が作り上げた現象にすぎない。そんなものないものはないんだ。時代は変わったのだ。もはやノスタルジーを求める中年の白痴化しか効果のないテレビ番組をみようとする人がどれほどいるだろうか。
テレビの先達は頭が良すぎ、行動力も有りすぎた。世相がそれを巻き取れなかった。移り変わっていく時代の価値観を先取りする先見は中途半端でちらかしたまま残ったのだ。ほかのメディアのチェックに忙しい世の中では、その残骸からダイアモンドを見つける時間があるほど暇人はいないはずである。
------------------------------------------------
<来年の宿題>
・”TVはみない”なんて書かないよ絶対
------------------------------------------------
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
