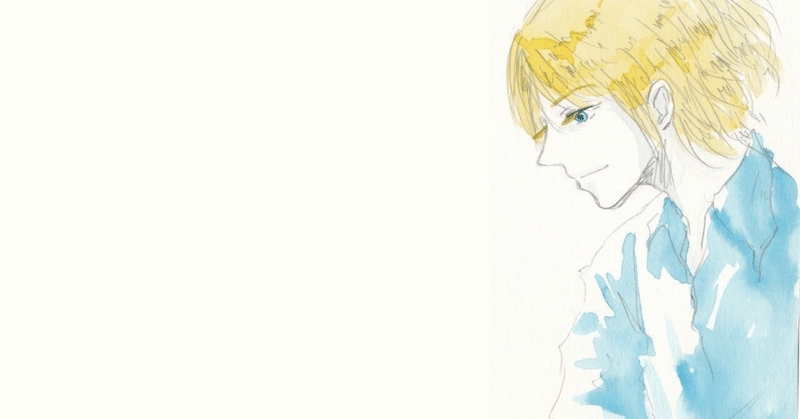
レオとジャヴェール
【ジャヴェール】
子供は、生まれる前に自分の母親を選ぶという話を聞いたことがある。
だけど僕はそんなのは嘘っぱちだと思う。
子供を育てる資格もないどうしようもないクズの大人たちが、子供を産み落とした言い訳に考え付いたに違いない。
自分の判断ミスやだらしなさを、生まれてきた子供に責任転嫁しているだけだ。まだ生まれてもいない、細胞すら存在していないものが、自分の母親を選べるわけがない。
何を好んでアバズレ女の腹に宿るだろうか。父親に関して言えば犯罪者だ。一緒にいた母親も逮捕されて刑務所の中で僕を産んだらしい。生まれた後、僕はすぐに施設に預けられた。母親の顔すら知らない僕には、親が恋しいという気持ちすら芽生えることもなかった。
小さい頃から大人たちにさんざん言われた
「生まれた時からお前は不憫な子だ。」
という言葉が、自分の未来を暗示するようで恐ろしかった。
僕はその恐怖から逃れるために、小学校に入る前から毎日必死に勉強をしてたし、運動をたくさんやって身体を鍛えた。施設の先生がそうすると立派な大人になれると言っていたからだ。
11歳になった今は、学校でトップの成績と、他の子よりもがっちりとした身体と、学校の中での地位を手にしていた。何年か前まで僕を刑務所生まれだの親がいないだのと馬鹿にして虐めていたやつらは、もう僕と目を合わせることすらできなくなっていた。立場が逆転はしたけれど、僕は彼らを虐めたりはしない。それは弱く愚かな人間のやることだ。僕がそうしなくても、彼らはいずれ罰を受ける。
この世界は、悪人が幸せになることは決してあってはならないのだ。
先生が言った通り、毎日の努力で立派な大人になれるのかもしれない。以前僕は神父様から「ジャヴェール、君は本当に賢い子だな。将来きっとたくさんの人を救えるようになるだろう」と褒めてもらった。とても嬉しくて、それから毎日毎日お祈りを欠かさなかった。そうだ、僕はきっとたくさんの人を救うことができる。神様、どうか僕をもっと強い人間にしてください。これからも絶対に嘘もつきません、悪い奴がいても見て見ぬふりなど絶対にしません。だから、どうか僕にもっと力を。
お祈りの時間が終わった後、ふと、隣にいたレオに話しかけた。
「レオ、君はいつも神様に何をお祈りしているの?」
レオは僕と同じ孤児院にいる同じ歳の友人だ。同じ歳だけれど、僕と違って痩せていて色白で女の子みたいなやつだ。
「僕はいつも同じさ。毎日こうやって我慢をしますって。人にぶたれてもね。とにかく毎日毎日神様にお祈りしてお礼を言う。生きていることに感謝しますって。そして月に一度お願いをするんだ。」
「どんな願いなんだい?」
「それは、ママとまた暮らせますようにってさ。」
「君はママが大好きなんだな。」
「うん、そうだね。」
「レオは頑張っているから、きっと大丈夫だ。また虐められたら僕に言うんだぞ。」
「ありがとうジャヴェール。でも、大丈夫さ。君にばっかり頼っていても、僕が変わらないと意味がない。大人になってもジャヴェールが僕のそばにいるわけじゃない。僕は僕で、強くならないと。」
「そういやあ、君は全く泣かなくなったな。強くなっているんだ。」
「ジャヴェール、君なんかは最初から強いじゃないか。」
「僕は強いんじゃないんだ。楽しかった思い出がないだけさ。君が泣いていたのは、幸せな過去と現状を比べているからだよ。何かを失ったり、絶望したり。僕にはそもそもそんなものがないだけさ。だから、最初から泣かないんだ。」
「そうか・・・なら、これから一緒に楽しい思い出を作ろうよ。なあ、僕と友達になってほしいんだ。」
「何言ってんだよ、僕はとうに君と友達のつもりだったよ。」
「本当かい?そう言ってくれて嬉しいよジャヴェール。僕は、君に助けられてばかりだったから友達なんて言うのはおこがましい気がして・・・」
「レオ、友達を助けるのは当たり前のことだ。それに、君も僕を助けている。」
「僕が君を?」
「そうさ。こうしてたくさん話をしてくれている。僕には、普通に話してくれる友達がいないんだ。みんな僕にはよそよそしい。」
「それは・・・正直気持ちはわかるな。それには理由がある。」
「え?教えてくれよ。何をどうしたらいいんだ?」
「簡単だよ、こうやるのさ。」
レオはジャヴェールの口の端を両手でグイッと持ち上げた。
「ははは、ほら。こうするといい顔だ。僕も初めて見たよ、君の笑った顔を。なかなかハンサムだよ。」
「なんだよ、からかっているのか?」
「そんなわけないよ。みんながよそよそしいのは君がいつも仏頂面だからさ。君は頭もよくて体も強い。だから周りの子は笑ってくれないとちょっと怖いんだよ。だから、これからはこうやって、自分で無理にでも口の端を上げると良い。」
「そうなのか・・・ああ、でも僕は無理に笑いたくない。だから、やっぱりこのままでいいよ。」
「まあ、その仏頂面が君らしくもある。なあ、今度勉強を教えてくれよ。」
「もちろんだよ。」
僕は同じ歳の子には馴染めなかったが、レオと話すのだけは楽しかった。毎日のようにレオといろんなことを話した。勉強を教える時もあったし、時には答えの見えないことを二人でずっと語り合った。
雲の大きさや虹の形について。女の人の匂いについて。学校で一番怖いバンディ先生のシャツの変な柄について。お金や犯罪について。将来について。
二人とも「教師になりたい」と言った時は驚いたな。
レオと話していると話題が尽きることがない。いつまでもこうやっていたいと感じる。
僕は上手く笑えないけれど、それでいい。レオ、君が笑っている顔を見ていたらもう十分に満足なんだ。
こんな関係をなんていうのかな。なんでも話せて、心が落ち着く友人のことをだ。
辞書には「親友」と書いてあった。
【レオ】
なあジャヴェール。君にママのことを訊かれた時、本当のことを話せなかったんだ。嘘はついていないよ。神様の前だから。でも、本当はもう僕のママはいないんだ。僕を産んだ後、すぐに病気が悪化して、3歳になる前に死んでしまったのさ。
何で話さなかったのかって?それは、君にそんな話をすると泣いてしまいそうだったからさ。僕は、君の前でもう泣きたくなかったんだ。
去年のことを思い出すよ。そう、あれはクラスのキャンプ費が紛失した時。君が僕を守ってくれた時だ。
誰かが言ったんだ。「レオのカバンを調べなよ。あいつだけ親がいなくてキャンプに行けないから盗ったんじゃないか」って。
実際キャンプにはジャヴェールも行かないんだけれど、ジャヴェールは強くて頭がいいから、彼をからかう人は誰もいない。僕は強くないし賢くないし、孤児院にいるから、こうして見下されるんだ。
クラスのみんながわあわあと騒ぎだした。担任のアラン先生は「みんな、騒ぐんじゃない。盗ったやつはきっと後で名乗り出るはずだ。」と言って、僕の方を見た。つまり、先生も僕を疑っているのだとわかった。なんてことはない。こんなことはいつものことだ。そう思いながらも僕はつい涙が出そうになった。
すると君は、突如立ち上がり、怒るでもなく騒ぐでもなくこう言った。
「皆さん、騒がないでください。わあわあと、まるで動物園みたいだ。」
その言葉にみんなはギョッとして、ジャヴェールの言葉に聞き入った。
「レオはキャンプに行けないのではなく、行かないのです。彼はキャンプより本を読むのが好きなだけです。じゃあ、そのお金を使って本をたくさん買いたかったのか?それも違います。僕も同じ孤児院ですから。あそこは決まったお小遣い以上のものを持っていないかっていつも部屋や持ち物を調べるんです。どこかでモノを盗んだりしないようにね。皆さんがレオを疑うのは、彼が孤児院にいるからですか?つまり、親がそばにいないからですか?しかし、子供は親を選べないのです。彼の母親がどうであっても、彼自身には何の関係もない。アラン先生、以前授業の中で『子供が親を選んでいるという説もある』とおっしゃいましたね。ここでそれについても僕の考えでは否定したいと思います。なぜなら僕の母親は顔も見たことないアバズレ放浪女です。誰が好んでそんな女に宿りますか?僕は母を選んでいない。レオも同じく母を選んでいません。僕自身はアバズレ女から生まれていますが、勉強も一番できるし、規律も一番守っています。わかりますか?孤児院だから、親がいないからキャンプ費を盗った、なんて理由は成立しないんです。僕がそうしないのと同じく、レオにも泥棒をする理由がない。」
君が言うことが正しいかどうかもわからなかったけれど、あまりにもつらつらと話すから、みんな唖然としていたよね。そして君は、
「ですが、皆さんが納得するために僕がレオのカバンやポケットを調べましょう。レオ、いいかい?」
そう言って、僕のカバンやポケットをみんなの前で調べた。
もちろん、何も出てこなかったけれど、仏頂面の君にあちこち調べられているのがなんだかこそばゆくて、恥ずかしくて、でも優しくて・・・僕はまた泣きそうになったんだ。
もちろん何も出なくて、あげくにキャンプ費は先生同士の連絡ミスで、とっくに回収されていたことが放課後にわかったんだ。
驚いたのは次の日だ。
アラン先生が
「いやいや、みんなすまなかった。キャリー先生がすでに回収していたのを聞いてなくてね。まったく困ったもんだな。みんなも連絡はきちんとするんだぞ。いやぁ困ったもんだ。じゃあ、授業を始めよう。」と言うと君は、
「ちょっと待ってください。それはキャリー先生にすべての責任があるということですか?」
とみんなの前で訊ねた。
「・・・い、いや、そうとは言っていないだろう。ただ、お金を回収するならばきちんと連絡するべきだと。」
「これは僕の推測ですが、キャリー先生はお金の回収袋が放置されていたから、紛失してはいけないと回収したのではないですか?そして、それならばすぐにアラン先生に言うはずです。つまり、アラン先生が回収袋を放置していたのを、キャリー先生が見つけて心配で保管し、それを伝えようにもアラン先生はその場にいなかったのではないですか?つまり、回収袋のことを忘れてそのまま別の教室の授業に行った。ああ、すみません、僕の推測と言ったのは本当でして、その推測を確認したくて、先ほどその話を直接関わった先生6人から話を聞いてきたところなのですが、それは事実ですか?」
「き・・・君は何のつもりだ!私を馬鹿にしているのか!」
「そんなつもりはありません。僕は規律のために確認したいのです。それが事実であれば、アラン先生は学校の規律に背いて、みんなにキャリー先生の連絡ミスだと嘘を伝えたことになります。」
「・・・ジャヴェール、何が言いたい?」
「僕は教会でいつも神様に誓っています。自分に不都合な事実があっても決して嘘はつかないと。先生はどうですか?」
「・・・ま、まあ、嘘と言えばそうとも取れるかもしれないな。」
「ではまず、レオに謝るべきではないでしょうか?」
「なんだと?!」
「先生はレオがクラスの皆から犯人だと誤解されている時にも、愚かな彼らを制しなかった。それどころか、盗ったなら名乗り出るだろうと言ってレオの方を見た。あれではまるでレオが犯人だと言ったのと変わらない。先生、学校と言う場所は、先生が間違ったことをしても、それが正しいことのようにされてしまうところなのです。だからこそ、そうすべきではない。先生が今自分に不都合な事実を隠す嘘をついたのなら、まずはレオに謝るべきです。そしてキャリー先生にも。」
クラスメイトを「動物園」とか「愚かな彼ら」とか平気で言う君に、僕はさすがにギョッとするのだけれど、先生に対してもまったくひるまないその姿は、先生よりも怖かったよ。
アラン先生は少しの間、君を睨みつけていた。
「・・・君は裁判官にでもなったつもりか?」
「いいえ。僕は自分の中の正義を通して、意見を述べているだけです。そうするかしないかは先生が決めることです。ただ、規律に違反していた生徒はみんな罰を受けます。この前は授業に遅れただけで教室の外に立たされている生徒もいましたが・・・先生は授業がありますので、教室の外に立っておくわけにもいかないでしょう。」
僕は思わず吹き出しそうになったが、ジャヴェールの顔は大まじめだ。
「ジャヴェール、君は・・・いや・・・うん。わかった。レオ・・・その、すまなかった。」
「いえ、平気です。」
まるでクラスのみんながジャヴェールに叱られたように静まり返っていた。
「今日は・・・自習にする。」
そう言ってアラン先生は教室を出た。
なあジャヴェール、今も君のあの仏頂面を思い出すよ。そんな君は僕らよりとうに大人なのかと思っていたけれど、僕と2人でいる時の君の目は、まるで赤ん坊のように澄んでいるんだ。
【ローズ】
あたしの人生には幸せなんか関係ないと思っていたの。
貧乏な家庭に生まれて、家の手伝いばかりで学校も通わせてもらえなかった。12歳になる前に妹が生まれた時はすごく嬉しかったけれど、その妹もある日突然知らないおばさんに連れていかれた。母さんは「あの子はお金持ちの家に行って幸せになれるのよ、あの子のためなの。」と言っていたけれど、本当はどうだったのだろうか。妹が消えてからは、あたしは毎日悲しくて悲しくて泣いてばかりだった。
母さんはそんなあたしを見て小さな声で「役に立たない子」と言ったのを覚えている。ある日母さんは仕事をするって派手なスカーフを巻いて出てったきり、もう帰ることはなかった。
あたしはただ食べるものが欲しかった。最初は、外で座り込んでいた時にかなり年上の男に声をかけられたのが始まり。なんとなく、女ってそうやってお金をもらうような気はしていたの。母さんも、きっとそうだったから。
学校なんか行かなくても、世の中のことは外に出れば三日でわかる。あたしは外で男に身体を触られてお金をもらったり、だんだんと夜の街を徘徊したり、人のものを盗むような連中とも関わりだした。
そんなある日、ショーンと出会ったの。窃盗犯の仲間の一人で、他の連中はしょっちゅうあたしに「ローズ、安くしろよ」ってからかったり、盗んだお金であたしを買ったりしていた。でも、ショーンはいつもあたしには優しかったな。一度も触ったり、あたしをお金で抱いたことはなかった。
「ローズ、身体を売るのはもうやめろよ。」
「どうして?そうしないとお金がないわ。死んじゃうもの。別に平気よ。目をつぶって歌を歌うように息を吐いてればいいの。」
「俺が稼いでやるよ。お前はそんなことをするのは似合わない。」
「稼ぐ?人のものを盗んだりすることが稼ぐって事?あたしはそんなのごめんだわ。あたしはちゃんとお客を幸せにしてるし、お客は喜んでお金を払ってくれてる。泥棒だけは絶対に嫌。」
「違うよ。もう、そんなことはやめるんだ。聞いてくれ。真面目に働くんだよ。朝から晩までどんな仕事だって平気だ。強い身体だけはあるから。俺はお前を愛してるんだ。だからつまり・・・結婚したい。」
「・・・結婚?馬鹿じゃないの?あたしたちにそんな資格あるわけない。」
「人を愛するのに資格なんか必要ないだろう。」
「汚いのよ。あたしも、あんたも。」
「いいじゃないか。二人同じだ。それにローズ、君は誰より美しいよ。」
あたしは言葉が出なくなって、代わりに熱い水が目から溢れ出ていた。ああ、これって、あたし泣いているんだ。
人って、嬉しい時にも泣くのね。
「ローズ、愛してる。俺たちは生まれた場所が悪かっただけなんだ。きっと生きなおせる。二人なら絶対にさ。もう、この街を出よう。」
二人で街を出てすぐだった。あたしはお腹に赤ちゃんがいることに気づいたの。もちろん、誰の子供かなんてわからない。
それでもショーン、あなたは飛び上がって喜んでくれたわよね。
「俺の子供だ!きっと男の子だ。レオって名前にしよう。」
「そんなのわからないわよ、女の子だったらレオは変でしょう。」
「きっと男の子さ。」
なんて、すぐに言いだして気が早いったら。
ショーン、あたしなんかが親になってもいいのかしら。
でも、あなたとだったら、何でも許される気がしてしまうの。ずっとこのまま、あなたとお腹の赤ちゃんと。
そんなある日、家に警官が現れた。昔の仲間が逮捕されショーンが首謀者だと証言をしたって。
「ショーン、あなた、真面目に働いてるって・・・」
「違う。俺はもう盗みなんかしていない!昔の仲間とも縁を切ってるよ!信じてくれ!」
「・・・お願いします。主人はずっと真面目に農夫や掃除屋しかしていません。ちゃんと調べてください!」
「奥さん。あんたたちの元居たところも知っているんだよ。離れたつもりでも、そう遠くはないんだ。悪い奴らはだいたいあの街で生まれた連中だ。」
「でも、違うんです。私たちは、二人でずっと・・・」
警官はローズの耳元でささやく。
「覚えてないだろうが、俺は昔あんたを買ったこともある。そりゃあ具合が良かったよ。なあ・・・少し融通利かせたら、旦那は早く出れるぜ。盗みは間違いだったと言ってやるよ。」
そう言うと警官は顎でショーンを指した。
もう一人の警官はショーンを縛り付け、引いていく。
「ローズ!何かの間違いだ。絶対にすぐ戻る!身体を・・・冷やすなよ。」
「ショーン!」
「おい、そいつを連れて先にいけ。俺はこの女を、もう少し調べる。」
ローズは目の前が真っ暗になった。
近づいてくる警官にすがるしかない。
「お願い、乱暴なことはしないで。お腹に子供がいるの。」
「へえ、心配するなよ。すぐ終わる。旦那を助けたいだろう?いいからじっとしてろよ。」
ショーンが連れ去られるとすぐに警官はローズを壁に押し付け、後ろからスカートをまくりあげた。
手のひらにペッと唾を吐き、その手をローズの股間に擦り付け、そのまま自分の固くなったものを無理やりに押し込んだ。
ローズは痛みと恐怖で小さく声をあげる。
「ははは、相変らずいい具合じゃないか。ほら、すぐに濡れてくるぞ。」
警官はこの世で1番下品な笑い声をあげながら激しく腰を動かす。
そのあまりの醜さと気持ち悪さにローズは吐き気を催す。痛い。痛い。気持ち悪い。赤ちゃんが痛がっているかもしれない。ごめんね、ごめんね。
ショーン、あたしはもうずっと、あなただけの女になりたかったのに。
絶望の中、ローズはかつてのように、目を閉じて、歌を歌うように、息を吐いてしのいだ。
警官の行為はおそらくあっという間に終わった。
「約束よ・・・お願い。あの人は今は本当に真面目に生きてるの。」
「ああ、しかし調査にしばらくはかかる。その間、俺があんたの様子を時々見に来てやるよ。」
警官の薄ら笑いを見るとローズは激しいめまいを感じた。
そして、そのまま激しく咳き込んで倒れた。
反射的に口を押さえたその手のひらには、どす黒い血がべったりと張り付いていた。
【レオとジャヴェール】
「ジャヴェール、君と話したいんだ。」
「いいよ。どうしたんだい?」
「ぼく、もうすぐこの施設を出るよ。」
「・・・なんだって?」
「学校も変わるんだ。遠い町に行く。」
「どういうことなんだ?まさか、どこかの家に・・・」
僕はとてつもなく嫌な想像をした。孤児院には、時々里親希望と言う大人がやってきては、僕らの様子を見に来ていたが、あんな奴らのことを僕は信じていない。
あいつらは犬や猫と同じように外見のいい子供を物色しているだけだ。
その証拠に、引き取られるのはいつも肌の白い、青い目が大きく、体の小さい子ばかりだ。だからレオもその対象になってもおかしくない。
僕にとってレオは、誰よりも美しかった。
「ジャヴェール、本当は、僕のママはもういないんだ。小さい時に死んでしまった。」
「何だって?」
「ママは僕を産んでからどんどん弱っていったらしい。僕が施設に来たのも、ママがほとんど動けなくなったからなんだ。本当は、ほとんどママの事は覚えてなくて、毎日忘れてしまうから、毎日お祈りの時にママの事を思い出していたんだよ。君に本当のことを言わないままで、ごめん。」
「でもレオ・・・じゃあ君はどこにいくんだ?」
「ショーンが、一緒に暮らそうって。ショーンは僕のパパなんだ。」
「パパがいたのか?なのになんで今まで施設に・・・」
レオはそれには答えず、ほんの少し微笑んだ。
「ジャヴェール、教会に行こうよ。」
夕方になる前の教会は静かだ。レオとジャヴェールは二人並んで座る。
西日が射し、レオのさらさらの髪が白く光る。
「なあ、ジャヴェール。僕はね、ここでお祈りをする時間が好きだったんだ。時々、君が話しかけてくれて、君のいろんな話が聞けた。今日は、ここで話すのも最後かもしれないな。」
「レオ。今僕はとても変な気持ちだ。何故か自分が君に辛い思いをさせてるような気になってしまう。」
「ああ、それは僕もよくある。」
「そうなのか?僕は初めてだ。こんな気持ち。」
「僕らは神様ではなく人間だからさ。勝手に自分が誰かの特別な存在だと思い込んでしまう。だから、その相手に何もしてやれなかったと責任を感じたり悲しくなったりするんだ。だから、僕も同じで君が不機嫌な時や、絶望を感じている時、なぜか僕のせいのように思うことがあるよ。」
僕にとって、レオは特別だ。レオにとってもそうじゃないのか?ジャヴェールはそれを言葉にはできなかった。
「君は僕よりうんと頭が良く賢いから、きっと素晴らしい大人になる。なあ、ジャヴェール、僕はここを出てからも、毎日君のことを思い出すよ。大人になってもだ。毎日こうやって西日が射した時に、君の色んなことを思い出して、何があっても勇気を忘れない。約束をしたいんだ。」
「約束?どんな?」
「どんなに時間がたっても、会わなくっても、僕らは友達だ。どんな時でも、僕たちはお互いを信じて見守っているってことを忘れない。それが約束さ。」
「もちろんだよ。僕は、今までだってずっとそう思ってきたんだ。これからもそれは変わらない。」
だけど。
嫌なんだ。
君と離れたくない。
誰のことも大事に思ったことなどない。
親だって、先生だって、学校で会った誰にも。
僕の世界には美しい人間はレオしかいないのだ。
神様、お願いします。
どうかレオと僕を引き離さないでください。
僕にはレオしかいないのです。
どうか、どうか。
気づくとジャヴェールは大粒の涙を流していた。
レオはジャヴェールの泣いてる姿を見て、優しく微笑んで、ジャヴェールの頭を撫でた。
「ありがとう。ジャヴェール。僕のことを思って泣いてくれているんだね。僕は本当に、君に会えて良かった。僕は誰よりも幸福だ。最高に優しい、強くて優しい友達がいるんだから。」
「レオ・・・僕は、僕はこれからどうしたらいいかわからないよ。」
「大丈夫さ。君はうんと賢いし、強い。そして誰よりも優しいんだ。」
レオを見ると、やっぱり泣いていた。レオの美しい青い瞳が、涙で溢れてまるで美しい湖のようだとジャヴェールは思った。
お互いに涙を流しながら、しっかりと抱き合った。
ジャヴェールは心臓が高鳴る。
本当は、ずっと前から知っていた。レオを誰よりも愛していることを。
「なぁ、ジャヴェール、僕は今君にキスをしたいような気持ちになっているんだけど、やっぱりそれは変だからやめておくよ。」
「・・・当たり前じゃないか。」
レオ。
君も、ずっと僕の気持ちを知っていたんだな。
言わずにいてくれて、ありがとう。
【教師】
小学校ではいつの時代にもやんちゃな生徒がいる。僕が通っていた頃もそうだ。どいつもこいつも簡単に誰かに相槌をうち、わあわあと動物園みたいで愚かだ。
そんな中でも、時々素晴らしい才能を持った子供はいるものだ。時には貧しくて辛い思いをする子供もいるが、僕らの時代とは違い、今の子供達は生きるチャンスが増えている。国が子供の学費支援までしてくれるのだから、いい時代だ。
レオとはしばらく手紙のやり取りをしていたが、やがて途絶え、僕からの手紙も宛先不明になって戻ってくるようになってしまった。
それでも僕はあの日の約束を忘れていない。
僕たちは離れていても、何があったとしても、ずっと友達だ。
信じている。
約束したんだ。
それに、毎日僕は神様にお祈りを続けたのだ。
「ジャヴェール先生、校長がお呼びでしたよ。」
「ああ、わかりましたすぐに。」
校長室のドアをノックする。
「ジャヴェールです。校長、失礼します。」
「ああ、ジャヴェール君、今日から赴任した新任の先生に色々と教えてほしんだ。ええと、名前が・・・」
さらさらの金色の髪。蒼い湖のような瞳の美しい青年は、振り返り微笑んだ。
「・・・校長。紹介は不要です。」
「うん?知り合いなのか?」
「はい。私の・・・」
やはり、神様はいるのだ。
こうして僕の願いをかなえてくれるのだから。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
