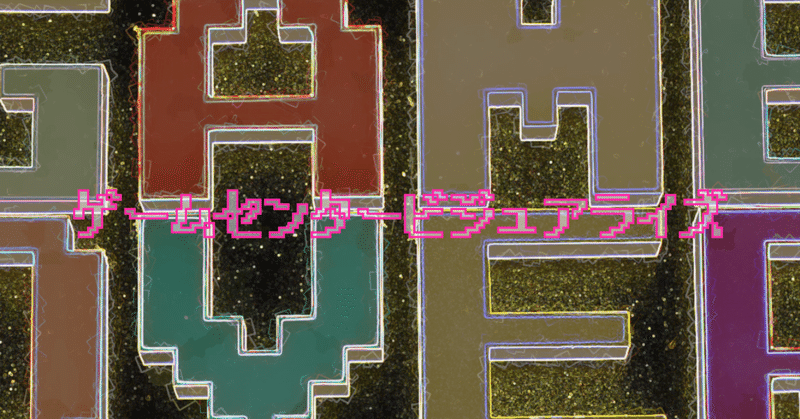
ゲームセンタービジュアライズ#3
前回、前々回と書いたけど好きなゲームやゲームセンターにいい思い出もあるので次を書く。
#1
#2
デパートの屋上とかにはエレメカがあった。エレメカもそれなりに遊んだし廃れた時代になっても置いてある場所に行くとやはりやったりした。ゲームセンターにはそういうものはなかったけど大型筐体があった。初期の頃はやはりタイトーのスーパースピードレースのようなもの。あるいはセガのターボ。レースゲームが好きだったから印象は残る。ゲームセンターにはピンボールなどの大きなものもそれなりにあったが、エレメカのようなのはなくブルーシャークのようなガンシューティングとか、名前は失念したが黄色い色の潜望鏡の筐体。マリンデートやクレイジーバルーンのようなアップライト筐体、そして今回触れるアタリの大型筐体があった。
重力と慣性と管制塔の画面
ゲームセンターの入り口に大型筐体のゲームがあった。それはセガ販売でアタリ製のルナランダーだった。アタリのアステロイドは入っていたのだけどルナランダーは遅れて入ってきた。その画面はシンプルだがアステロイドと同じベクタースキャンが特徴的で、画面上には色々なパラメータが表示され、いかにも宇宙船とか司令センターのような趣があり、NASAとかで見た映像の一部のようで興味深かった。それ以上に筐体の大型レバーに目を奪われた。大型レバーといっても車のシフトのようなものではなく、飛行機というかそんな感じで、表現するなら岡持ちの持ち手をレバーにしたような、昔の飛行機のスロットルのような、そんなものだった。他には左右に傾くボタン、緊急噴射のボタン、それだけだった。ゲーム自体は名前の通り月面着陸で平らな土地に着陸船を降ろすだけのシンプルなものだが、無重力の慣性が計算されているようで、難しいものだった。いわば着陸シミュレーションだった。だからシンプルな画面に燃料や左右の慣性の加速度的数値なのかな、それに重力や高度が常に変動され表示される。高度などはその時にいる場所の真下の土地までの距離という、やっぱりシミュレーションのようなものだった。ゲーム自体はシンプルだがその慣性が難しく、着陸船は非常に脆い。だから慎重に降ろす。そういうゲームである。それを見るだけで緻密な感じがしてわくわくした。着陸地点が狭い場所ならスコアは二倍、三倍、五倍と増える。最初からある燃料がなくなるまでプレイでき、燃料は噴射した分だけ消費される。緊急噴射ボタンを使うと大量に消費された記憶。無事着陸したら燃料が加算され次の面へと進むのだけど、私の場合は三面程度だった。最初の燃料が五千ほどだった記憶があり、左右の慣性、重力への対処が難しく二倍程度の得点の面積がやっとだった。五倍の場所はチャレンジするにもクラッシュしてしまう。しかしまたやりたくなってくる。そういうゲームだった。アタリのベクタースキャンのゲームは何種類か遊んだが、この慣性の感覚、科学的な雰囲気、そういう体験はこれ以外にない。いやラスタースキャンのゲームであろうとそれは同じだと思う。感覚的にはパソコンゲームのようだったった。
空は水色で海は青く船は…
何も関係ないのだが、いや関係あるのかもだけど、私のいた場所は船や潜水艦にとても縁がある場所で、沈んだ潜水艦の慰霊碑などがあり、子供の頃からそういう場所で遊んだりして育った。ある日ゲームセンターに行くと水色と青のゲームがあった。それがセガのディープスキャン、駆逐艦で潜水艦を倒すゲームだ。海が青、空が水色という分かりやすいグラフィック。しかし船が真っ赤だ。単純な色は同じセガのヘッドオンにも似ていて分かりやすい。そういう見た目が派手なゲームだった。音もカツーンみたいな音がしていてなんだか刺激的だった。駆逐艦の機雷は合計で六個あり、それを左右、グラフィック的には前後だが落とし分ける。それらが敵を倒したり底について消えるまで次の機雷は放てない。上限が六個なのだ。それが微妙なゲーム性になる。敵の潜水艦には番号がついていて潜水艦番号ではなくスコアの値。深い場所の敵なら得点が高いとかではなくランダムだったのかな。実際には浅い場所の敵からの攻撃の方が脅威でもある。特に機雷を消費している最中には。とてもシンプルなゲームだけどなかなか遊び応えがあって、そこそこ遊んだ。中央下部にレーダー画面があるのも特徴で、それも遊び応えの一つだったかもしれない。後にセガサターンのダイナマイト刑事でも遊んだ。ダイナマイト刑事のようなバカゲーにもなぜかしっくりくる感覚。いや、ダイナマイト刑事が船上の話だからなのかな。まあ脱線したけど原色あふれる画面、思ったよりも深い楽しさ、そういう記憶がある。とても印象深かったゲーム。
不自由な合体
ある日ゲームセンターに行くと新しいゲームがあった。一瞬ギャラクシアンかなと思ったけど違う、全然違う。そこには少し歪な文字で日本物産株式会社と書かれていた。ハイスコアにも同じキャラクターで同じ文字が。漢字というのも驚いたが、ナムコの完成された英数フォントに慣れていたのでなんとなく歪に感じた。しかし味があった。それがムーンクレスタなのだけど、ゲームを始めると合体分離のギミックに驚く。今までに体験したことのないそれは、自機の大きさが理由でもあった。一号機二号機三号機。どんどん大きくなってゆく。合体したそれは特大で、やってみれば敵の的のようにも感じた。一号機は小さくショットは一つ、二号機は少し大きく二つのショット、三号機は最大で左右外側に二つのショットがある。二種の敵が二つの色違いで四つ続いた後、合体となるのだが、ここにもカタカナとひらがなのフォントで合体せよと指令が出る。合体自体は難しくもないが、無重力を表現したような慣性があるので初めてするときは少しドキドキする。無事合体すると次の敵になる、そしてくり返し三機分が終わると一面のクリアである。ミスをせずすべて合体すると合計五ショットを発射することになるが、速射とか連射の感はなく自機が大きくなるデメリットが大部分を占める。二周目以降は敵のスピードが速くなり厄介。というか二周をクリアできてなかった。やってみると短調なゲームだけど、やはり合体というギミックが大きく、合体したから強くなるという幻想があるとはいえ、大いなるそれに惹かれてプレイしてしまう。音もきれいな音でギャラクシアンにも似ているが頑張っている。その時もいまでもそれらに惹かれていて何度も思い出す。頭の中にはいつでもサウンドと場面が思い浮かぶ。そういうゲームだった。
事件だ!
ある日事件が起こった。それは今までのゲームとは明らかに違うタイプのゲーム。強制横スクロールで様々な場所を進んてゆく。そして空中へのショットと地上への爆弾、その二つの打ち分け、それがコナミのスクランブルだった。コナミはセガのフロッガーと同じものをリリースしていて知ってはいた。フロッガーがコナミ開発だったよう。でもコナミをはっきりと意識したのはこのスクランブルからだ。話によると世界二番目の横スクロールゲームらしく、世界初はなんと前回触れたディフェンダーのようだ。私としては時系列は逆なんだけどタイプも違う。このゲームの要所は強制横スクロールに尽きる。しかも縦画面の強制横スクロールなのだ。ゲームは一見シンプルだが二つの打ち分け、ステージ構成など多少複雑な面はある。一面は山岳地帯、二面は洞窟、三面は隕石、四面は要塞だろうか、五面は要塞内部に見える、六面は敵中枢若しくはボスだろうか、というような流れで一周である。集中してできればそんなに難しくはないのだけれど、それが進むにつれて難しくなる。一面の山岳地帯は簡単で実機を狙う地対空ミサイルも発射されない。こういう敵がいますよ的なアドバタイズのようだ。ここで重要なのがFUELの存在、実機には燃料があり進むにつれて淡々と減ってゆく。画面に敵と共に配置されているFUELを破壊することである程度充填できる。ここが問題になってくるのだ。一面は敵が配置されているだけ、そして二面の洞窟だがここは少し厄介でUFOっぽい嫌らしい動きをする敵が出てくる。ショットの連射もあり、地表に配置されているFUELの破壊に気をつけながら進めば大した問題はないが、一面よりは緊張する。三面の隕石はレースゲームのように避けることだけを考え、地表のFUELに気をつける。問題はここからだ。四面の要塞らしき場所はレンガで作られた要塞に地対空ミサイルが埋もれていて効率的に破壊するのが困難だ。しかも狭くギリギリの場所もあるのでタイミング悪く放たれないように地上爆弾をうまく打ちながら進まなくてはならない。しかも地上爆弾はFUELも重要だ。ここが焦りになる。五面の要塞内部はレンガで囲まれた場所を進む。敵は出てこずFUELのみが連続して出てくる一本道の迷路だ。一本道なのになぜ迷路か。それは強制スクロールが問題だからだ。強制的に進むのでうまく進まないとレンガの壁に衝突である。迷うという意味ではないが衝突して終わってしまう迷路だ。要塞内部の後半ではFUELが出てこなくなり焦る気持ちを煽られる。そして最終面の中枢というかボスにたどり着く。ボスというか、ボスらしきもの。攻撃はしてこない。KONAMIと書いてあるビルがあるその星の中枢らしき場所には何かが置いてあり、それを破壊すれば一周である。ここもそうだがFUELが出てこないので迅速に破壊しないと終わりである。シューティングゲーム自体の難易度はクリアできないほどは難しくないのだが、FUELが減るという焦りとの戦いがある。しかも二周目はFUELの減りが目に見えて早い。FUELを破壊して充填すれば問題ないのだけれど、減るスピードを見ているとどうしても焦ってしまう。それがこのゲーム、自分との戦いである。私は二周できなかったメンタルの弱い人間だけど、うまい人はいた。しかしこのアーケードゲームとして、いやゲームとしてのマイルストーンを思う存分遊べた。あの時代を過ごせたことは今思っても幸せだった。その頃はそんなことは思わなかったしただ単に熱中していただけだけど、この体験は頭と体に刻まれている。コナミの存在。それを知り、遊び、熱中した。その思い出があるのを嬉しく思っている。
今回書いたゲームが発展したり続編ができたりした。例えばテラクレスタやグラディウス。それらにつながることをその時は知らなかったが、今になってみれば大いなる一歩だった。そういう場面にいた。それはとても嬉しいことだと思える。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
