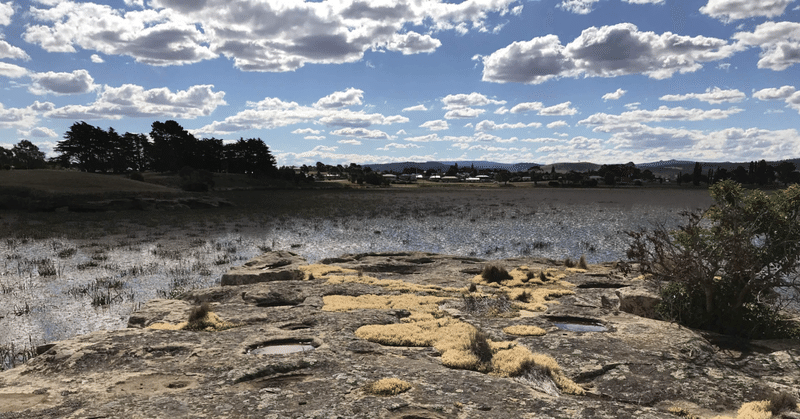
[未発表原稿]SFと進化論
『人生の土台となる読書』のために書いたけど、ページ数の都合で入らなかったものです。筒井康隆と『地球の長い午後』の話です。
『人生の土台となる読書』では進化論の話を多く紹介した。
そもそも進化論に興味を持ち始めたのは大学生のときに真木悠介『自我の起原』を読んだのがきっかけだったのだけれど、よく考えてみると、それ以前から興味を持つ下地はあった。
それは中学生のときにハマっていた筒井康隆の作品の中に、「メタモルフォセス群島」と「ポルノ惑星のサルモネラ人間」という2つの小説があって、それが好きだったことだ。
どちらも架空の動植物がたくさん出てくるSFで、奇妙な動植物が奇妙な生態系を作っているという、進化論的な面白さに満ちたものだったのだ。
「メタモルフォセス群島」の舞台は核実験から数十年経った太平洋の小島だ。
生態系の調査に来た主人公たちは、足が生えて移動する果実や、木の枝に融合している小動物や、人間の生首にそっくりの果実をつける植物など、放射能の影響で奇妙な進化を遂げた動物や植物を目にすることになる。
そして、ただ奇妙な生き物が出てくるだけではなく、その奇妙さにちゃんと「こういう風にして繁殖するための生存戦略なのだ」という理屈がつけられているのがいい。
「ポルノ惑星のサルモネラ人間」の舞台は、ある地球外の惑星だ。この星の動植物はとても奇妙だ。動物はほとんどが草食で、動物同士で食ったり食われたりすることがない。そして殺し合うことがないかわりに、この星の生き物はすべてとても性的でいやらしいのだ。
動物の姿かたちや鳴き声は卑猥で、種が違っても平気で交尾をする。植物もわいせつなものばかりで、胞子で動物を妊娠させる草や、からみつくことで動物を性的な絶頂に導く藻が、そこらじゅうに生えている。そして、その生物たちのいやらしさにも、きちんと生態系の中で役割があるのだ。
「するとつまり、こういうことになりますね。まず、クジリモ、タタミカバをくじり、オスのタタミカバ射精する。その精液中にある蛋白質などを食ってバクテリア繁殖する。クジリモがバクテリアの分解した排泄物を吸収して植物性蛋白質に変え、これをタタミカバが食う。つまり三者再生系ということになりますか」
どうしてそんな奇妙な生態系ができあがったのか。その理由にもSF的な解決が用意されているので、気になった人は読んでみてほしい。
そして、筒井康隆のこの2つの小説には、インスパイア元になった小説がある。SFの古典名作として有名な、ブライアン・オールディスの『地球の長い午後』だ。これもめちゃめちゃ面白い。
ここから先は

曖昧日記(定期購読)
さまざまな雑記や未発表原稿などを、月4~5回くらい更新。購読すると過去の記事も基本的に全部読めます。phaの支援として購読してもらえたらう…
ꘐ
