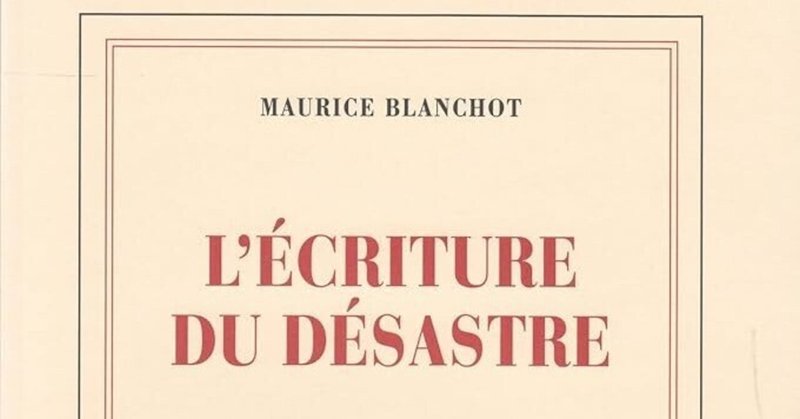
モーリス・ブランショ『災厄のエクリチュール』試訳
Maurice Blanchot, L’écriture du désastre, Gallimard, 1980.
気になったところを気ままに翻訳して、メモとして残しておきます(追加編集していく予定です)。
◆書くことと受動性との間に何らかの関係があるとすれば、それは、両者が主体の抹消〔effacement〕を、主体の憔悴〔exténuation〕を前提としているからだ。すなわち、時間の変容〔un changement du temps〕を前提としているからである。いいかえれば、存在することと存在しないことのあいだに身を持した、実現されざる何ものかが、しかしずっと以前からすでに到来していたものとして〔comme étant depuis toujours déjà survenu〕おとずれるということを前提している──中性的なものの無為、断片的なものの黙せる断絶。
◆受動性。受動性を喚起させることができるのは、ただ逆さまになった言葉〔un langage qui se renverse=みずからを反転させる言語〕によってのみである。かつてわたしは、〔受動性なるものを喚起するために〕苦痛に仮託したのだった。すなわち、わたしに耐えることができない苦痛である。耐えることができないという、その非-能力のなかで支配からも一人称の主体としての地位からも排除された自我は、権利を奪われ〔destitué〕、位置を失い〔désitué〕、義務さえも失って〔désobligé〕、〔苦痛などを〕受ける能力を有した自我としてのわたしを失う。苦痛がある、苦痛があるとしよう、〔そうすると〕苦痛を耐える「わたし」はもはや存在しない。苦痛はみずからを現前せず、現在へともたらされることがない(ましてやそれが生きられることはない)。苦痛は現在なしにある。始まりも終わりもないものであるかのように。時間は根本的に意味を変えてしまったのだ。現在なき時間、自我なき自我。経験――認識の一形式――によって明かされたり隠されたりするとは言いえない何か。
◆受動的な静穏〔quiétude passive〕(わたしたちがキエティスムについて知っていることがらによって、その姿が思い描かれるかもしれない)にほかならない受動性というものがある。それから、不安の彼方にある受動性がある――それでも、目的も終わりも持たない、主導権も欠いた誤りの、熱狂的で、不規則でもあれば規則的でもある、倦むことのない運動のなかにある、受動的なものを保持しながら〔不安の彼方へ赴くのである〕。
◆受動性。受動的な状況、不幸、強制収容所の状態における最終的な圧伏、欲求を持たない水準にまで落ち込んだ、主人なき奴隷の隷属状態、生命にかかわる活路にさえ注意を向けぬ無関心としての死ぬこと──わたしたちはこうした状況を思い起こすことができる。いずれの場合においても──それが事実を正確に映さない漠然たる知であるとしても──共通の特徴を見て取ることができるだろう。すなわち、匿名性。自己の消失。あらゆる至高性=主権の、いや、あらゆる従属の消失。逗留の消失。住処をもたずに彷徨すること。現前の不可能性。分散(分離)。
◆書くことがとるに足らないというのは明らかなことだ。書くことは重要ではない。エクリチュールとの関係は、まさにそこから決定される。
◆与えること、それは何かをひとに与えることでもなければ、自己を与える〔捧げる〕ことでさえない。というのも、かりに与えるという行為がそのようなものだとしたら、与えるとは守ることであり庇護することである、ということになるからだ――贈与されるのが、あなたから奪うこともできず取り返すことも引き取ることもできないものという特徴を有しているとするならば〔?〕。これはエゴイスムの極致であり、所有の狡知である。贈与とは自由の権能ではなく、自由な主体の崇高なる実践でもないとすれば、贈与たりえるのは、みずからは有していないものでしかありえない。強制のもとにありながらも強制を超えているもの、際限のない刑苦への嘆願のなかにあるもの、そのようなものでしかありえない[……]。
◆欲望。すなわち、すべてをすべて以上のものたらしめるとともに、すべてがすべてでありつづけるようにせよ。
◆場所も、公式も探し求めずに。
◆読まないこと、書かないこと、話さないこと、だが、そうすることでわたしたちは、すでに述べられた言葉や〈知〉を、そして相互了解を逃れ去って、未知なる空間へと入るのである。ひょっとすると、与えられるものを誰にも受け取ってもらえない、苦悶に満ちた空間へと。災厄の豊饒さ。その空間においては、死も生も、つねに通過される。
◆「しかし、わたしの眼には、偉大さは苦痛のなかにしか存在しない。」(S.W.[註:シモーヌ・ヴェイユのことか])わたしはむしろこう言おう。苦痛による以外に極端なものは存在しないと。過剰なる苦痛ゆえの狂気、甘美なる狂気。
思考すること、みずからを抹消すること。すなわち、苦痛の災厄。
◆沈黙を守ること、それこそ、書く者だれしもが我知らずに望んでいることがらにほかならない。
◆沈黙を守ること。沈黙はみずからを守らない。沈黙は、沈黙を守ろうとする作品に頓着しない──沈黙とは、待ちのぞむべきものを何も持たない待機の要請であり、ある一つの言語活動の要請である。つまり、言説としての全体性をみずからに前提しながら、一時に力を使い果たし、言語自身に分離をもたらし、果てしなく断片化してゆく、そのような言語活動の要請である。
◆たしかに、書くことは、手をつなぐのを拒むこと、あるいは固有名で呼ばれるのを拒むことであると同時に、拒むことではない。書くとは、不在者をそれと認めることなく受け入れ、告げること──あるいは、不在のうちにある言葉によって、思い出すことができないものと関係をもつことである。思い出すことができないもの、それは、保証されざるものの証人であり、主体における空虚に応答するのみならず、空虚としての主体にも応答するものであり、死――あらゆる場所の外部に場所をもつ――が切迫するさなかにある主体の消失である。
◆「オプティミストは書くのが下手だ」(ヴァレリー)。だが、ペシミストはそもそも書かない。
◆不在の意味を見張ること。
◆弱さとは、涙なしに泣くこと、嘆きにみちた声のつぶやきであり、あるいは、言葉なしに話すもののざわめきであり、見かけというものが枯渇し枯れ果てることである。死ぬことの受動性に際して何も為すことができない暴力(それこそ圧政的な支配そのものではなかろうか)、そのようないかなる暴力からも、弱さはみずからを遠ざける。
◆災厄の特徴。勝利や栄光は災厄に対立するものではなく、かといって、やがて来たる衰退は栄華のうちに見られるといった常套句とも異なって、勝利や栄光は災厄に属するものでもないということ。災厄は反対物を持たない。それは〈単純〉なものではない。(それゆえ、災厄を特徴づけるもののうちで、弁証法よりも異質なものは存在しない。弁証法こそ、みずからの破壊的な契機に還元されてしまうのではなかろうか。)
◆奇妙なことに、受動性とは、けっして充分に受動的ではないのである。というのも、ひとは無限なものについて語ることができるからだ。おそらくそれは、たんに、受動性がどんな定式化からもみずからを遠ざけるからにすぎないということなのだろうが、しかしながら受動性のうちには、受動性がつねにそれ自身の手前に至り着くよう呼びかける、そうした要請のようなものが存在するように思われる──受動性ではなく、受動性への要請であり、超えることができないものへと向かう過去の運動である。
受動性〔passivité〕、情熱〔passion〕、過去〔passé〕、否=歩み〔pas〕(否定であるとともに歩みの痕跡あるいは運動でもある)、こうした言葉上の意味の戯れは、わたしたちに意味の横滑りをもたらすが、しかしそれは何ものでもなく、わたしたちを満足させる返答を信頼するのと同じような仕方でそれに頼ることはできない。
◆一般的にいって、死ぬこととは、絶えざる切迫である。だが生は、そうした切迫によって、欲望しながら持続する。すなわち、つねに既に過ぎ去ったものの切迫である。
◆苦痛は、無垢であることに苦しむ──だから苦痛は、苦しみを和らげるために、有罪たらんとする。しかし苦痛における受動性は、いかなる失敗からも逃れる=みずからを遠ざける〔se dérobe〕。失敗の外部にある受動形としての苦痛は、救済の思考からひとを救済する。
◆災厄が身体を持つのではなく意味を持つ、という危険。
◆書くこと、形なきもののうちに、不在の意味を「形づくる」こと。不在の意味を、である(意味の不在ではなく、欠如した意味でも、潜勢的あるいは潜在的な意味でもなく)。書くこと、それはひょっとすると、不在の意味のようなものを表面にもたらすこと、未だ思考ではないが、すでに思考の災厄であるような受動的な衝動を迎え入れることなのかもしれない。思考の耐え忍び。彼ともう一人の間には、接触があり、不在の意味という隙間が──友愛が──あるだろう。不在の意味は、消失の彼方へ向かう衝動の「肯定・断言〔affirmation=ヴェイユを示唆するか?〕」を維持する。そして、死ぬことへの衝動は、そうした肯定・断言とともに消失を、失われた消失を運び去ってゆく。存在を通過することのない、意味未満の意味──意味のため息〔soupir du sens〕、息を引き取った意味〔sens expiré〕。そこから、書いて注釈をおこなうことの困難が生じてくる。というのも、注釈は何ごとかを意味し、意味作用を生み出すが、不在の意味に耐えることができないからである。
◆忍耐〔patienceはラテン語pati「受ける・苦しむ・耐える」に由来する〕によって、わたしは災厄の〈他者〉への関係を引き受ける。ただし〈他者〉は、わたしがこの関係を請け負うことも、この関係を受忍するためにわたしがわたしでありつづけることさえもゆるしてくれない。耐え忍ぶ自我へと自我が結ぶいかなる関係も、忍耐によって断ち切られる。
◆自我の狡知。経験的な自我を犠牲にし、超越論的あるいは形式的な〈わたし〉を保護すること。みずからの魂を(あるいは知を、非-知さえも)救うために、みずからを無化すること。
◆思考しないこと。留保なしに、過剰に、思考のパニックめいた逃走のなかで、思考しないこと。
◆思考すること、それは、後ろに隠れた思考〔arrière-pensée=下心・魂胆〕として災厄を名づけること(呼ぶこと)であるかもしれない。
どのようにそこに至ったのか〔そう考えるようになったのか?〕、わたしにはわからない。だが、思考に対して距離を保つよう導く思考へと、わたしが辿りついたということはありうる。というのも、思考がそれを、距離を与えるのだから。しかし、思考の果てまで(果てについての思考、縁についての思考という形のもとで)赴くことは、ただ思考を変えることによってのみ、可能であるのではないか。そこから、次のような命法が導かれる──思考を変えぬこと。できることなら、思考を反復すること。
◆忍耐〔patience〕とは、この上ない切迫性である。忍耐は言う、わたしにはもはや時間がない、と(あるいは、忍耐に残された時間とは、時間の不在、始まりに先立つ時間なのだ──非-出現の時間のなかで、ひとが死ぬのは現象学的な仕方によってではない。あらゆる人にも、自分自身にも知られずに、フレーズもなく、痕跡を残すこともなく、したがって死ぬことなく──じっと耐えるようにして〔patiemment〕死ぬのである)。
◆死なしに死ぬかのように、生きていることなく生きること。書くことは、こうした謎めいた命題へとわたしたちを送り返す。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
