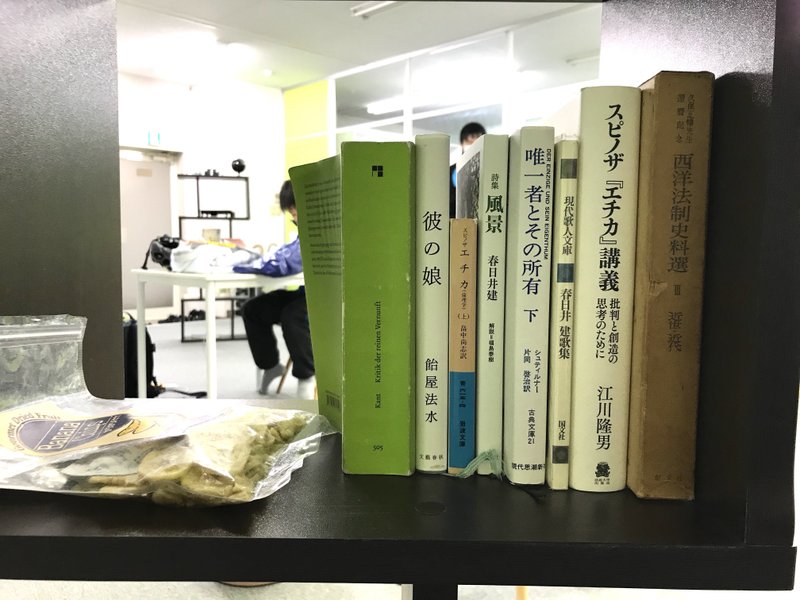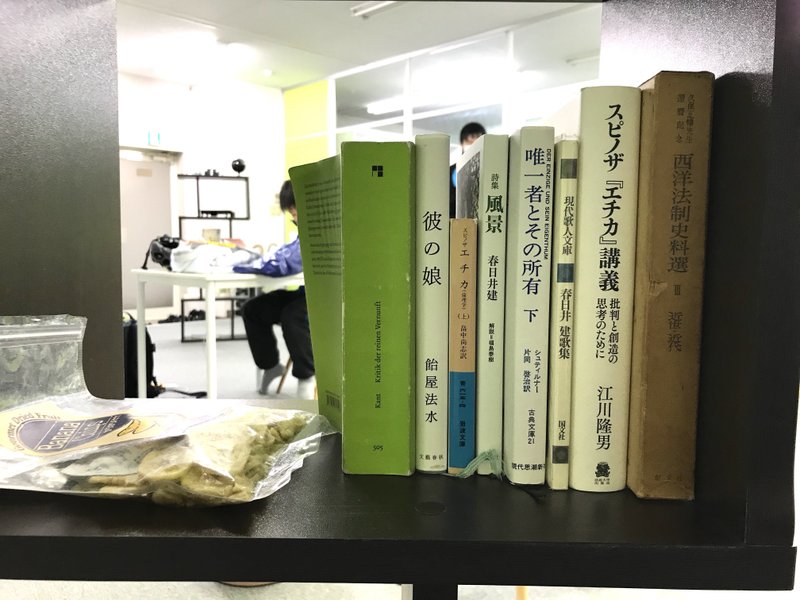パラリアの二次会 第22夜 これまでとこれからの「日本社会のしくみ」 の解説
おはようございます。パラリアの二次会の解説も、いよいよ22回目です。
音声はこちら
【内容の解説】 今回は、小熊英二(用語解説参照)の著作、『日本社会のしくみ』について、話を進めています。
この本の中では、現代日本の雇用状況は、3種類に分けられると言われています。
①大企業型は、大都市近郊に住むサラリーマンで、収入はそれなりに多いものの、子供の教育にお金をかけたり何なりとおかなげかかります。
②地元型は、地元での密なネットワークがあり、近隣住民や親戚との助け合いが見られ