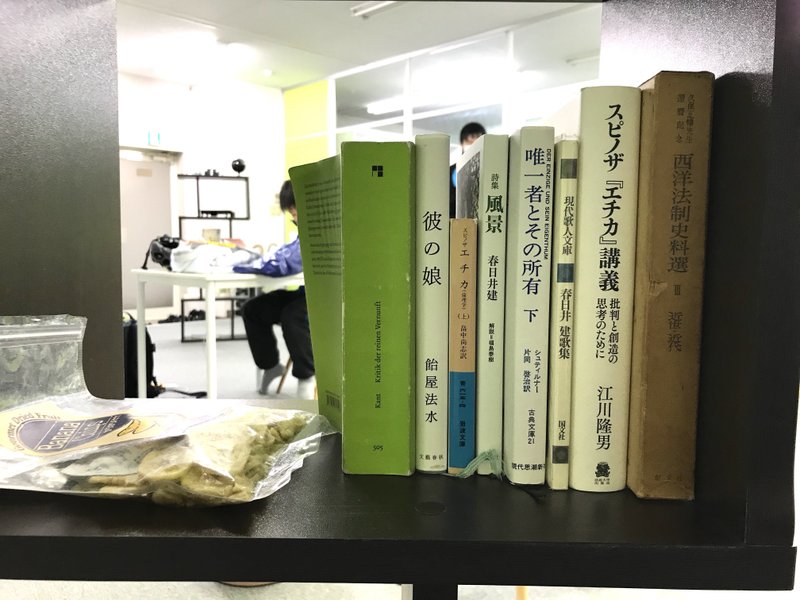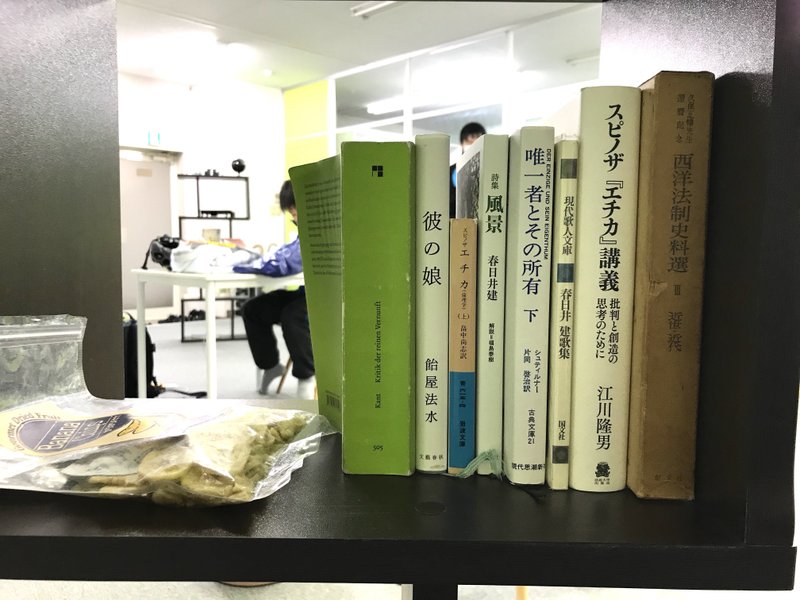パラリアの二次会 第26夜 総括・後編:わたしたちはどこへいくのか の解説
いよいよパラリアの二次会の解説も今回で最後です。今回も前回に引き続き、総集編です。
音声はこちら。
【今回の話の流れ】 まず、ここまでの復習(これについては前回を始め、何度かまとめられているので、そちらをご覧ください)をした後、現在及びこれからの社会・教育を論じます。まず、現在は「成功したいから頑張るのではなく、失敗したくないから頑張る」という時代です。競争に敗れたら悪いことがあるから競争するという、ネガティヴな競争になっています。背景には、2000年以降の日本がが、中国