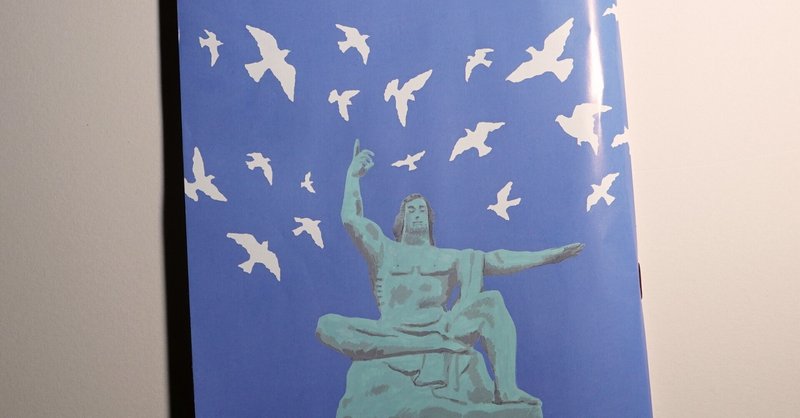
esprit
あの狂乱バブルに向かう1980年代に、ドラマ「北の国から」を描いた倉本聰さんは1935(昭和10)年の生まれ。一時代を築いたニュース・キャスター筑紫哲也さんも1935(昭和10)年の生まれ、かの永六輔さんは1933(昭和8)年の生まれ。野坂昭如さんは1930(昭和5)年のお生まれ。
野坂昭如さんの「火垂るの墓」はあまりにも雄弁に反戦を、文化でせつせつと訴えられた名作すぎる名作。プラカードに「反戦」と文字で記して行進すことが恥ずかしくなるくらいにレベルが高い、そしてサスティナブルな、沁み入るような「反戦」運動だ。もちろん、徒党を組むのではなく、一人の人間としての反戦運動でもある。
戦後生まれや戦後育ちに欠如しているのは、このエスプリかもしれない。
野坂さんたちのような才気あふれる方々だけではなく、街角からも、そういうエスプリは消えかかっている。
うちのオヤジも亡くなってしばらくたつけど、フランス映画が好きで、ジャン・ギャバン、ミレーヌ・ドモンジョさんのファン。下町の「代々職人の家の子」だったんだけど。
海軍士官でもあったオヤジは、直接的に「反戦」を表現することはなかったけど、僕の記憶には戦災孤児たちへの支援を続けた親父の姿がある。子どもの頃、オヤジは僕に歴史を物語り「ブラタモリ」のように東京を語り、毎週末を博物館で過ごさせ、そして僕に戦争を語った。
(うちのオヤジは、野坂さんたちより少しだけ年上の世代になるけれど、ほとんど同じ時代を見てきた世代だと思います)
戦後育ちの僕ら。戦前に比較すれば教育機会に恵まれたようにも思える。でも、その実、戦後教育は戦中の教育をオブラートに包んだけの軍隊式。だから行進の練習を学年全体でし、「班」があり「班の連帯責任」という考え方があった。
(オヤジは、朝礼のたびに「前に倣え」であり、行進の練習ばかりしている学校を、教育の場ではなく「軍隊より軍隊だ」と評していた)
「学校」は、精密化した大きなシステムの部品にされる、そのための調教みたいなものだった。でも、僕ら自身は、学校、中学校、高校など学校と名前がついたところを卒業してきたんだから、ちゃんとした教育を受けてきたつもりでいる。
僕らは「大量生産」の道具であり「大量消費」の道具にされたのだろう。そして消費文化だけが発達し、街も生活文化も各人も色を失い、味わいを失い「画一」に塗りつぶされた…
だから、反戦を志してもプラカードに「反戦」という文字を書き、群になってシュプレヒコールを上げることくらいしかできない。しかも、たいていの僕らは「プラカードに反戦という文字を書き、シュプレヒコールを上げる」ことと「火垂るの墓」のような反戦運動の違いを「質的」に評価することができないし、後者の反戦を運動運動と評価することができない。
だから、サスティナブルな主張ができない…
オヤジたちの世代は戦争で男性の三分の一が犠牲になった世代だといわれています。現に、我が家も男兄弟二人のうち一人が亡くなっています。筑紫さんたちの世代だと空襲の犠牲者となった方も居られるし、ご両親を亡くされて戦後の混乱の中で亡くなっていった方も少なくはない(「火垂るの墓」が描くのも戦災孤児の物語で)。
そうやって、戦後は少数を宿命づけられたはずのオヤジたちの世代をして(戦争の)抑止力になっていたのは、彼らに戦争の実体験があっただけでなく、街場の文化に花があったあの時代を知る世代に特有のエスプリがあり、だからこその説得力があったからなんじゃないかと思っている。
物心ついて「進駐軍」から記憶を始めるオフクロたちの世代。それに続く戦後世代。すでに工場の部品になることで糊口をしのぎ、大衆化して以降の大学しか知らず、その大学も適当に出てきた世代。彼らには自分があるようでなく、あくまでも「群れ」を求めてしまうのが宿痾です。
だからね。
できる人は「呼びかける」のではなく、自分一人でいいから自らのライフデザインの改革を。
自分の快楽や求める利便性のために…ではなく「こうあったらいいな」と思う「社会」をイメージし、それに即した自分の暮らしをデザインする。
「反戦」だから「反戦」と叫ぶのではなく、群れになるわけでもなく、ただただ戦争を呼び込まない清楚な暮らしを目指す。そうやって単純に与えられるを待つ消費者をやめると、そうしたことから何かが見えてくるし、「反戦」を政治闘争にしない方便が見えてくるはず。
たぶん、オヤジたちの世代には、そういうことに気づいていた人たちが少なくなかったんでしょう。複写するのではなく、その姿勢を見習って自分で考えていきたいと思っている。
