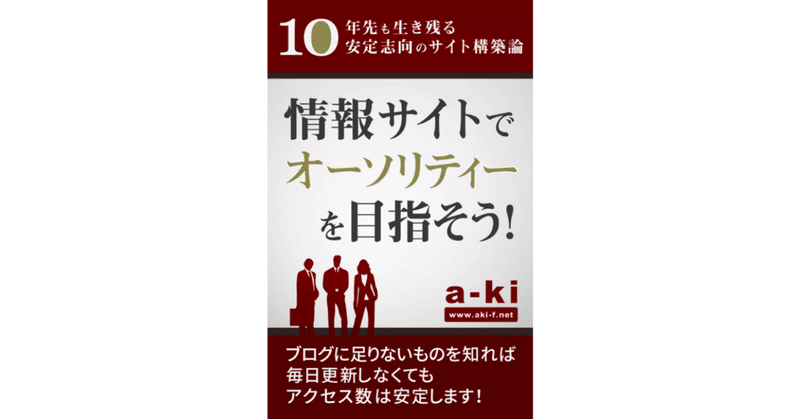
情報サイトでオーソリティを目指そう!【本のアウトプット】
アウトプット11「情報サイトでオーソリティを目指そう!/a-ki著」
【読んだ理由】
・サイト構築の本質を理解したかったため。ウェブ適当に漁ってたら良さそうだったからkindleで読みました。
【アクションプラン】
ランチェスター戦略の強者戦略と弱者戦略が再現性高そうなので、実践してみる。
【学んだこと】
本書では「オーソリティーサイト」をキーワードに、長く安定的にアクセス数を集める情報サイトの構築術を解説している。
オーソリティサイトとは
オーソリティは権威や威信を表し、心臓外科の権威や日本文学の権威といったアカデミックで少し威圧的なイメージが浮かぶ。
しかし、実際そんな堅苦しいものではない。
日本人メジャーリーガーといえば、イチロー
リアクション芸人といえば、出川哲朗というように誰もが認める存在になれば、それはそれでオーソリティ。
→ウェブ上では、〇〇といえば、このサイトというように誰もが認めるサイト、特定のジャンルで知名度がありユーザーの信頼が厚いサイトのこと
例)料理のレシピサイト=クックパッド
▼サイトがオーソリティ化するとどうなるのか?
1.SNSやQ&Aサイトで言及されやすくなる
例)「○○について教えてほしい」という質問に対して「ここのサイトを見たら良いよ」「あのページに詳しく書いてあるよ」と言及される。
2.サイトに書かれていることが定義とみなされる
口コミが広がると、ソースとしてサイト内の情報が信頼されるようになり「このサイトに書かれているから正しい」と思われ始める。
3.引用が増え継続的に被リンクが増える
サイトに書かれていることが定義→他のサイトから引用される→被リンクが増える→SEOの順位があがる→引用がさらに増える
サイトをオーソリティー化するなら、
主役は人(ブロガーや影響力のある人)ではなく情報。
ブログだけではなく、情報が主役になるようサイト構成を最適化した、いわゆる「情報サイト」を構築する必要がある。
情報サイト構築の流れ
Webサイトの表現形態は様々。
┗個人運営者自身が情報発信できる規模のサイトでは3つの表現形態。
┗「ブログ型」「完結型」「ツール型」
┗本書では「テーマに一貫性があり上記3つの形態のうち2つ以上を組み合わせて作られたサイト」を「情報サイト」と定義する。
コンテンツ表現の3形態
▼ブログ
本書でいうブログ型コンテンツとは「継続的な記事の追加を前提とし、基本的に記事が時系列(投稿順)で整理されるコンテンツ」
メリット:
フロー情報を扱いやすい
定期更新でリピーターを確保しやすい
デメリット:
サイト内で論理的な構造が作りにくくコンテンツ全体の構成が安定しない
ストック情報にフロー情報を混ぜるとコンテンツがフロー情報化してしまうので注意。
┗例)「ようやく梅雨が明けましたね」といった時候の挨拶をストック記事の冒頭に入れると情報が古臭くなってしまう。
┗情報サイト構築の第一歩は、フロー情報とストック情報をはっきり区別する。→〇〇の最新情報(フロー)というニュース型コンテンツ、〇〇の豆知識(ストック)というコラム型コンテンツ。という分け方にするだけで、ユーザーにとっては随分と情報が探しやすいサイトになる。
▼完結型
「予め扱う情報の範囲が任意に決められていて、その範囲内で情報が網羅されるコンテンツ」
完結型の作成手順:
完結型には下準備が必須。
┗まずユーザーがコンテンツを通して何を得ることができるのかを明確にする。
┗その目的を達成するよう全体構造を設計する。
例)ブログは「木を植えていたらいつの間にか森になりました」のイメージ、完結型は「森を作るために木を植える」
完結型には2タイプある:
・カタログ型
・論文型
○カタログ型
末端のページの情報が一つ一つ独立している
親カテゴリーがあってその下にそのカテゴリーを満たすページがある。
○論文型
前後のページに論理的な関係性があるもの
前後のページに関係性があるのが論文型の特徴。1ページだけ削除したり全面的な書き換えが起こると、コンテンツの論理性が破綻する。
例えばピアノの弾き方というコンテンツの場合、「1ページ目:右手の練習」「2ページ目:左手の練習」「3ページ目:両手を合わせて弾く練習」というふうに順番に進みますね。これが逆になるとおかしなことになります。
▼ツール型
ツール型とはユーザーが「使うこと」を前提としたコンテンツ。
用語集や計算機など。
▼3つの形態を組み合わせる
情報サイトでは多面的に情報を表現するためにブログ型、完結型、ツール型の3形態すべてを1つのサイト内に盛り込むのが理想。
ミニサイトから始めてみよう
ミニサイトとは、テーマを絞って小さくまとめた情報サイト。
Q:ミニサイトがうまくいかない原因は?
A:ブログを作ってしまう
ミニサイトがミニであるためには、小さく完成させる必要がある。
ブログ型コンテンツは継続的に記事を増やし続けることが前提なので、ミニサイトのコンテンツとしては不向き。
A:テーマが広すぎる
例)横浜中華街全店食べ歩きというテーマでは150軒近くの店舗があり、全て網羅するには規模が大きすぎる。
横浜中華街飲茶食べ比べなら点心飲茶の専門店が20軒くらいなので100%網羅することができる。
→網羅性100%は大変に思うかもしれないが、100%といっても100/100とは限らない。30/30でも5/5でも良い。情報サイトにおいては分母の大きな50%より小さな分母の100%の方が価値がある。
A:構想が壮大すぎる
あれもやりたいこれもやりたいとアイデアが湧いてくることはいいことだが、まずはひとつのコンテンツを完成させることに集中すべき。
コンテンツの規模に決まりはありません。一通りの情報を網羅しコンテンツが完結するなら総ページ数5ページという超ミニサイトでも構いません。一般的には5~10ページ程度を1カテゴリーにまとめ3~10カテゴリー、全体で15~100ページ程度にまとめるのが適正でしょう。
▼トップページが重要
検索エンジンから訪れてこのサイトは良さそうだと興味を持った時、ユーザーは一旦トップページへ遡りサイトの全貌を知ろうとする。
→しかし、ブログテンプレートのトップページは新着記事の羅列になっていて、どの情報がどこにあるかよくわからない。
ミニサイトや情報サイトのトップページに必要なものはサイトの概要がわかる簡潔なリード文とわかりやすい目次機能です。せっかく完結型で構造化しているのですから、スタート地点になるトップページもサイト全体が見渡せるように工夫しましょう。
情報サイトの競合対策
▼ランチェスター戦略を応用する
ウェブ上にはすでにあらゆる情報がある。ただ作りたいものを作るだけではオーソリティサイトどころか目に触れられないまま終わってしまう。
→ユーザーにとってより価値の高いサイトに育てるためには競合を意識したサイト運営は避けて通れない。
→ランチェスター戦略を応用する
○弱者の戦略
┗自分のサイトが競合サイトより劣位にある場合、検索順位はもちろん、規模、有用性など総合的に劣っている場合の対策。
┗ニッチを狙って差別化
→まずはテーマを絞る。
絞るだけでなく、そのテーマなら1番を取れるという範囲まで絞る。
上位の競合と正面を切って戦うのではなく、むしろ戦いを避けることで居場所を確保することを目標とする生き残り戦略。
小さなマーケットやニッチなテーマで構わないので、競合が手をつけていなもの、あるいは手薄なテーマを狙う。競合が本格参入する前に全力で1番化する。
独自のテーマは制作に手間がかかる、参入障壁が高いものが良い。
サイト全体のテーマは絞りすぎない
┗サイト全体のテーマも、ある程度絞って一貫性を持たせることが大事ですが、テーマを絞るということは競合が少なくなる代わりにマーケットも小さくなるということ。
小さな1番を積み重ねひとつ上の1番を狙う。
なぜ1番でないといけないか。〇〇といえばこのサイトと思い出してくれるのがオーソリティサイト。
思い出してもらえるのは1番だけ。
例)日本で1番高い山は富士山だが、日本で2番目に高い山は?
日本で2番目にでかい湖は?
○強者の戦略
順位がどこである場合でも自分より下位にある競合に対する対策、特に一つ下の順位にある競合をターゲットにした対策。
相手を包み込む
格下競合サイトにある長所をすべて自分のサイトに取り込む。
ライバルが持っている長所は全て自サイトにあるという状態にする。
→相手は弱者の戦略で差別化を狙ってくるが、これをひとつひとつ潰していくことで永遠に追いつけなくなるようにする。
ユーザーに有益な文化圏を作る
質の良い被リンクが付いていることはオーソリティーサイトであるための当然の条件ですが、同様に発リンク先のコンテンツが質の良いコンテンツであることも条件の一つだといえます。
→ユーザーにとってサイトの内か外かあまり関係ない。
→中心に自分のサイトを置きハブになるというくらいの意識を持つのもオーソリティサイトにふさわしい振る舞い。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
