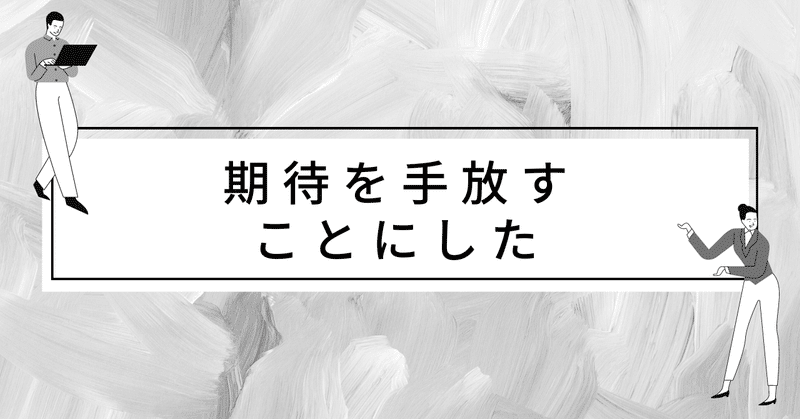
期待を手放すことにした
SIY6日目が終了しました。
ここからの1か月間は実践の期間です。受講生同士で1対1のバディを組み、学びのふりかえりや日々の気づきを相互でシェアしながら、1ケ月後の全体シェアリングに向けてトレーニングをしていきます。
バディ、バディー
buddy
男性同士の友人・仲間・相棒のこと(日本においては性別問わず指す場合あり) ⇒ 友情、二人組
私が重点的にトレーニングしたいと感じたのは、リーダーシップ&インテグレーションという章に登場した「コンパッションを持ってリード」するというワークです。
自分自身への思いやりを実践するセルフ・コンパッションについては以前も少し書きましたが、今回は他者との関わりのなかでのコンパッションについて考えてみます。
自分と他者への思いやり
仏教指導者、禅僧、人類学者であるジョアン・ハリファックスの著書
『Compassion(コンパッション):状況にのみこまれずに、本当に必要な変容を導く、「共にいる」力』の中で、コンパッションが以下のように定義されています。
コンパッションとは人が生まれながらに持つ資質で、自分であろうと他者であろうと、その悩みや苦しみを深く理解し、そこから解放されるよう役に立とうとする純粋な思いである
そして、コンパッションを実践するための資質「エッジ・ステート」として、下記の5つが挙げられています。
利他性
共感
誠実
敬意
関与
この本の原題は「Standing at the Edge」で、意訳すると「崖っぷちに立つ」です。崖っぷちと表現される所以は、5つの資質には良い面と悪い面が表裏一体で存在していて、バランスを崩すと悪いほうへ転落してしまう危険性を孕んでいるからです。
過度に利他性を追求すると自己犠牲に陥ってしまうし、共感も度が過ぎると共感疲労というネガティブな感情がストレスになってしまいます。コンパッションに関してはバランスが重要で、0か1かの話ではないということです。
仕事におけるコンパッション
ワークのなかで「仕事におけるコンパッション」についてジャーナリングをした際に、私は意外と一緒に働いてくれているスタッフさんやパートナーさんに対して、ひとりよがりな期待をしていることに気付きました。
私は自分のキャリアを通して、小さな実績の積み上げが大きな成果に繋がっていくことや、他者評価が自分の価値を決めていくことなどを実感しているので、それを一緒に働く人に伝えようとしています。
その根底には、もっと成長してほしい、もっとキャリアップして欲しいと願う親心的なものがあり、もちろん良かれと思ってそのようにしています。
そして、期待していたほどの仕事をしてくれないときには、声を荒げて叱ったりすることこそありませんが、多少なり不満を憶えることもあります。
期待という感情には、自分の思い通りになって欲しいというエゴが隠れています。そこにコンパッションはありません。あくまで期待したいのは私であって、期待されたほうがそれをどう受け止めるかは様々でしょう。
期待されることで力を発揮する人もいれば、プレッシャーに潰れてしまう人もいます。鬱陶しいと感じる人もいれば、期待されていることすら気付かない人もいることでしょう。
成長やキャリアアップについても、それを望んでいない人にとっては、押し付けられても迷惑な話でしょう。私はその迷惑行為をやっていたんだな、ということに気付いてハッとしました。そして、これから時間をかけてそれを手放すトレーニングをしていこうと決めました。
他者の期待に応えること
一方で難しいのは、お客様からの期待を受け入れ、期待値またはそれを超える成果を提供し続けるというのが、クライアントワークで生き残る必要条件だと考えているという矛盾です。
例えば、ランチを食べようと初めて入る飲食店に行ったとします。そこでオーダーした食事が自分の期待値を下回るクオリティだったとしたら、おそらくその店でまたランチを食べたいとは思わないでしょう。
制作の仕事も同じで、お客様の期待に沿うような仕事ができなかったとき、そのお客様からの次のオーダーはありません。たとえランチ選びに失敗しても笑い話で済みますが、仕事の失敗は事業や企業の存続に関わるので、シビアな判断が下されます。
もちろん、全ての仕事で期待値を超えることができるわけではありません。野球でも3割ヒットが打てれば一流です。ときには大きく空振りをすることもあるでしょう。
ただ、まるで期待に応えることができない人や、そもそも期待に応える気がない(ように見える)人には、期待値を伴わない仕事=誰がやってもよい仕事しか巡ってこない。そういうものだと考えています。
このことは、お客様との関係性が深まるほど忘れがちです。なぜ自分が仕事を依頼してもらえているのか?なぜ自分が選んでもらえているのか?現状に慢心することなく、常に自分に問い直していくことが重要です。
…というような考えも、私のひとりよがりな思想の押し付けかもしれないので、これからゆっくり手放していこうと思います。
それぞれ力量があり、価値観がある
働くということは、かくも大きな矛盾を抱えています。
本質的には、みんな悩みや苦しみから解放されて、幸せに生きたいと願っていることでしょう。しかし、誰しも一人では生きていけないし、他者と関わるからには、一方的な期待や評価とも向き合わなければなりません。
しかし、その向き合い方は各々の価値観によって異なるでしょうし、その価値観さえも時間の流れとともに変化していくことでしょう。
これからは、より皆さんの価値観に寄り添って、それに対して何か役に立てることはないか?という視点で、コンパッションを磨いていきます。
久々に読んだ「志村流」という本に、今回の投稿に通ずるような内容が書かれていました。長くなりますが引用します。
以前のオレは、「オレと同じ土俵に上がって来いよ」っていう気持ちで、新人の放送作家や共演の若手芸人たちにも一生懸命アドバイスしていた。
コント作りは一人ひとりの力が大切で、日々の積み重ねが必要だ。だれか一人でも「手抜きしてもいいや」という気持ちで仕事にかかわれば、結果として、その分クオリティが下がる。クオリティを上げるためには、最低でも一人ひとりが水準以上じゃなくてはならないし、そうあって欲しい、と。
オレの考え方を理解してもらおうと、「何で、わかんないのかなぁ」と、青筋立てながら一生懸命説明してきた。いいものを作ろうという気持ちから。実際、スタッフ全員の力が爆発して、いいものが出来た時の満足感って、何物にも代えがたいものがある。
でも、ある時、「人にはそれぞれ力量があり、考え方がある。だから、その人の出来る範囲で、一生懸命頑張ってくれれば、それでいいじゃない」って、スーッと何か悟りが開けたみたいに、自分でも不思議なほど納得したのを憶えているなぁ。それ以来、妙に枯れたというのか、あまり腹を立てることもなくなってきた。
「共にいる」というのは、そういうことなのかもしれません。
では。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
