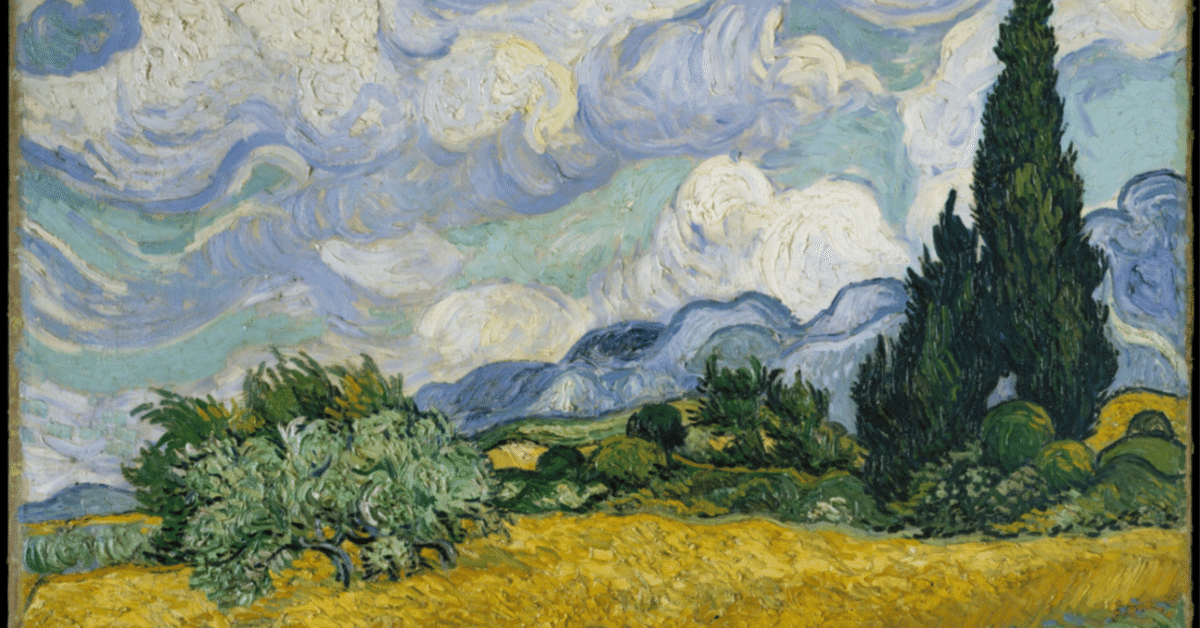
魔法画家の鎮魂歌(レクイエム)第1話
【あらすじ】
ヨーロッパは突如発生した吸血鬼達により支配された。それに伴い、ありとあらゆる人間達の文化は抑圧され、絵画も音楽も、吸血鬼達が好むものへと置き換えられていった。
そうした中で、画家達は突然魔力に目覚め、魔法画家として秘密結社ソレイユを結成し、吸血鬼達にゲリラ的に戦いを挑むようになった。
ソレイユに加入した新人ノルデは、無愛想な先輩ゴッホの下につき、吸血鬼達を駆逐するためのミッションについていた。しかし、ある晩、ソレイユのアジトが急襲される。仲間の裏切りによるものだった。多数の犠牲者を出しながらも、なんとかソレイユ側は勝利を収める。そして、ゴッホを新たなリーダーとして、再出発を図るのであった。
【本編】
その世界の二〇世紀は、悪夢で始まった。
突如現れた吸血鬼達により、世界各国は支配され、ありとあらゆる文化は彼らの統制を受けることとなった。
いつ終わるともしれない暗黒時代が訪れたのである。
* * *
深夜の大西洋上を、巨大飛行船グラーフ・ツェッペリンが飛んでいる。
船底に取り付けられている居住空間「ゴンドラ」内には、客室やレストラン、ダンスホールといった施設が収容されており、長期間の飛行生活に耐えられるよう設計されている。
そのゴンドラ内の、ダンスホールに、異様な音楽が鳴り響いていた。
まるでノイズのような、それまでの音楽とは異なる、破壊的な曲調。古来からの音楽に馴染んでいた人類には騒音にしか聞こえない類のサウンドであるが、しかし、ダンスホールに集まっている者達にとっては心地良い響きとなって耳に伝わってくる。
ダンスホールで踊り狂う乗客達は、一部を除いて、皆、吸血鬼だ。
この空間に、人間は二人だけいる。
一人は、音楽を演奏しているサングラスをかけた青年。彼の名は、ルイージ・ルッソロ。吸血鬼の軍門に降った芸術家結社「フトゥリズモ」のメンバーである。
「ハッハー! みんな欲しいか! これが欲しいか!」
ルイージは、手に持つ、血液が溜まった袋をブンブンと振り回すと、ダンスホールの中央に向かって、袋を放り投げた。
袋は、ホールのど真ん中に立つ木の杭――に縛られている、少女の頭にぶつかった。
たちまち、少女は頭から全身にかけて、血をかぶることとなった。
ルイージの他にもう一人いる、人間。それが、この囚われの少女マリーである。
もともと結わえていた長いブロンドの髪は、見るも無惨に崩れており、血を滴らせている。周りで踊り狂う吸血鬼達を怯えた眼差しで見ては、恐怖で引きつった声を上げている。
「ゆ、許して、ください」
気弱なマリーは、かわいそうなほどに、目に涙を浮かべて、許しを乞うている。
だが、血に餓えた吸血鬼達は、その哀願を受け入れようとはしない。
「血(ブルート)! 血(ブルート)! 血(ブルート)!」
興奮気味に、大合唱が始まる。
誰も、容赦はしようとしない。
なぜなら、マリーは、ただの少女ではないからである。
主にフランスで暗躍している芸術系秘密結社「ソレイユ」のメンバーであり、吸血鬼達から見ればテロリストの一人なのだ。
本来なら、捕らえた時点で、処刑は確定していたのであるが、ただ殺すのでは面白くない、ということで、こうして飛行船内の余興として、提供されることとなったのだ。
「噛みつけ! 吸え! 最後の一滴まで吸い尽くせ!」
ルイージはノイズ混じりの音楽をさらに激しく転調させて、吸血鬼達を煽る。
興奮の極みに達した吸血鬼達は、とうとう、マリーの側へと歩を進め始めた。みんな牙を剥き出しにして、嬉しそうに爛々と目を輝かせている。
マリーは悲鳴を上げた。もう、これは、どうあっても助からない。
無惨に血を吸われて、死んでしまう。いや、死ぬのならまだマシかもしれない。吸血鬼に血を吸われた物の末路は三つある。一つは命を落とす。一つは自身も吸血鬼となる。そしてもう一つは、吸血鬼に命じられるがままに動く、物言わぬ傀儡と成り果てることだ。
操り人形となった者は、意識だけは残っているらしい。人間としての意識はあるままに、かつて仲間だった同じ人間達を襲うこととなる。そんな、悲惨な運命だけは、辿りたくなかった。
「来ないで! 来ないでええ!」
マリーは、最後に、出来る限りの大声を上げて、虚しかろうと抵抗の意を示した。
そんな彼女のことを嘲笑しながら、一番近くにいる紳士風の吸血鬼が、牙を剥き出し、マリーの柔らかな首にスッと頭を近付けた。
直後、その紳士風の吸血鬼の頭が、爆ぜた。頭部がザクロのように割れ、血肉と脳漿があたり一面に飛び散る。マリーの顔にもバシャッと残骸が降りかかったが、彼女はもはや、そのことは気にしていない。
むしろ、ある一点を見据えて、瞳に喜びの色をたたえている。
「あ……ああ……!」
ダンスホールの片隅に立つ、ロングコートを着て、回転式拳銃の銃口をこちらへ向けている、黒髪長髪の青年。
その隣には、少女かと見紛うほど容姿の整った少年。
二人とも、マリーの仲間だ。
すなわち秘密結社「ソレイユ」の同志達。
助けに来てくれたのだ。わざわざ、こんな空の上の、逃げ場のない飛行船の中にまで潜りこんで。
頭が吹き飛んだ吸血鬼の亡骸は、床に倒れ伏したまま、ビクンビクンと痙攣している。普通の銃弾では、ここまでの効果は出ない。おそらく銀の銃弾。特殊な製法が必要となるから、そう数は無い、貴重な武器を、惜しげも無く使った。
「ゴッホだ!」
「あいつが、ゴッホ……⁉」
「ヴィンセント・ヴァン・ゴッホ!」
ロングコートの、長髪の青年を見て、吸血鬼達は動揺を隠さずにいる。
「マジかよ、たった二人で乗り込んできやがった……!」
ルイージは演奏の手を止めて、目を丸くして、驚きとも呆れとも取れる声を上げた。
「たかが魔法画家の一人や二人! ゴッホが何者だというのだ!」
筋骨隆々とした、髭もじゃの軍服姿の吸血鬼が、鼻息荒く前へと進み出てくる。
長髪の青年――ヴィンセントは、ふん、と鼻を鳴らすと、腰のガンホルダーに拳銃をしまった。
「エミール。お前が行け」
「へ⁉」
隣に立つ美少年エミールは、いきなり話を振られて、素っ頓狂な声を上げた。
「ぼ、僕が、戦うんですか⁉」
「実戦を経験したいと言ったのは、お前だろ。俺は黙って見ている。やれ」
「今回が初任務なんですけど⁉」
「魔法は使わなければ意味が無い。まずは慣れろ。話はそれからだ」
「え、いや、その」
エミールが困惑している間にも、軍服姿の吸血鬼は、ズンズンと間合いを詰めてくる。
「俺はマリーを救出する。あの筋肉野郎はお前に任せた」
言うやいなや、ヴィンセントは駆け出した。
「お! 来るか!」
軍服姿の吸血鬼が、両腕を広げて、ヴィンセントを迎え撃とうとしたが、ヴィンセントはその相手をせず、腕の下をくぐり抜けて、一気にダンスフロアの中央へと躍り出た。
会場内は混乱に陥った。
吸血鬼達の一部は、ヴィンセントを殺そうと襲いかかるが、次々と拳銃で撃ち抜かれて、倒れ伏してゆく。大半の吸血鬼は、戦闘力を有していないため、巻き添えを食らわぬようにフロアの端へと逃げている。
「おい! 俺を無視するな!」
軍服姿の吸血鬼は怒鳴り声を上げたが、その後頭部に、ゴツンと石が当たった。
エミールが投げたものだ。
「あーん?」
血走った目をギョロリと剥いて、軍服姿の吸血鬼はエミールを睨みつけた。
「う……や、やっぱり、石くらいじゃ効かないよね……」
エミールは口の端をひくつかせて、いつでも逃げられるように身構えている。
その一方で、ヴィンセントは、マリーを縛っているロープをナイフで切り、彼女を解放してやっていた。
「あ、ありがとうございます、ゴッホさん!」
「魔法は使えるか?」
「すみません、まだ、魔力が尽きていまして……」
「わかった。俺がなんとかしよう」
いまや、ヴィンセントとマリーを取り囲む吸血鬼達は、恐れをなしてか、遠巻きにして動かずにいる。真っ先に飛びかかった者から殺されるのは確実だ。そう簡単に襲いかかれるものではない。
いや、一人いる。
ルイージだ。
それらは楽器の一種なのだろうか、得体の知れない機械類から離れると、ルイージもまたフロアの中央に行き、ヴィンセントと向かい合った。
伊達男風のルイージは、櫛をポケットから取り出し、オールバックの赤毛を丁寧に撫でつけた。
「で? ゴッホさんよ。ここからどうやって脱出するつもりだ? 教えてくれよ」
「お前も芸術家の端くれなら、想像してみろ。それが答えだ」
「だったら、答えは決まっているぜ。打つ手なし、ってやつだ」
ルイージは口の端を歪めると、両手を掲げて、同時に左右でパチンと指を鳴らした。それが、魔法発動の合図だった。
ギャン! と床を削るほどの勢いでルイージは走り出し、ヴィンセントの体に思い切り体当たりした。その動きを見切れなかったヴィンセントは、まともに正面から攻撃を喰らい、後方へと吹っ飛ぶ。
ルイージは体当たりをした後でも、動きを止めない。味方であるはずの吸血鬼達も吹っ飛ばしながら、ダンスホール内を縦横無尽に高速移動する。
「ハッハー! これが俺の魔法『車のダイナミズム』だ! お前に止められるか!」
ひとしきり走り回った後、フロアの隅の機械類の所へ戻ると、再び演奏を始めた。
「これは俺が作った特殊演奏楽器『イントナルモーリ』! 戦いのリズムを刻むぜ!」
ズン! ズン! ズン!
腹の底から響く重低音が、フロア全体にこだまする。その音に混じって、耳障りなノイズも聞こえてくる。
「さあ、続きと行こうか! 『車のダイナミズム』!」
ダンッ! と床を蹴ったルイージは、超高速移動で、ヴィンセントを翻弄する。
いや、翻弄したつもりになっている。
肝心のヴィンセントは、まったく動じていない。埃を払いながら、ゆっくりと立ち上がり、拳銃を自分のこめかみへと突きつけた。
「なんだあ⁉ 勝ち目が無いと見て、自殺でもする気かあ⁉」
「違うな。これは俺の覚悟だ。魔法を使う上で、自分に懸けた誓約」
魔法の発動条件は、人によって異なる。ただ、ひとつ言えるのは、その条件達成が困難であればあるほど、強力な魔法を解き放てる、ということ。
ヴィンセントは、残り一発の銃弾が入っている回転式拳銃の銃口を、こめかみに押し当てながら、ゆっくりと引き金を引いた。
「し、師匠⁉」
軍服姿の吸血鬼に、壁際まで追い詰められていたエミールが、驚きの声を上げた。ヴィンセントが実際に魔法を使うところを見るのは、これが初めてだった。
ズドンッ!
銃声とともに、ヴィンセントの頭部を銃弾が貫いた。パッ、と赤い血が飛び散る。だが、どういうわけか、ヴィンセントは死んでいない。その瞳は、いまだにしっかりと正面を見据えており、意識を保っていることを示している。
魔法が発動した。
「『星月夜』」
しかし、何も起きない。
一旦動きを止めて様子を見ていたルイージだったが、魔法は不発に終わったのだと思い、ハハハと声を立てて笑った。
「なーにが、『星月夜』だよ! 格好つけやがって! 失敗してるじゃねーか!」
その瞬間、飛行船の船体を何かが突き破り、ルイージの特殊演奏楽器「イントナルモーリ」を粉砕した。やかましいくらいに鳴り響いていた音楽は強制的に中断させられた。
「え……?」
目をまたたかせるルイージの眼前に、突如、無数の流星群が降り注ぎ始めた。飛行船の船体を次々と貫いていき、吸血鬼達を押し潰し、砕き、阿鼻叫喚の地獄絵図を作り出していく。
「く、空間魔法⁉」
それは、魔法の中でも上位に入るもの。空間全体に影響を与える、極めて効果範囲の大きな魔法だ。コントロールが難しかったり、敵味方関係なく攻撃してしまったり、といった欠点はあるが、それを補って余りある強さを誇る。
「くそがああ! この飛行船を墜落させたら、お前らも死ぬんだぞ!」
「死なないさ」
ヴィンセントは、ニヤリと笑った。
「エミールがいる」
突然の指名に、エミールはキョトンとした顔になった。
まったく作戦を聞かされていないから、この空間魔法「星月夜」の発動も寝耳に水であり、どうすればいいのか戸惑っていたところである。
それなのに、なぜか、ヴィンセントは自分に対して信頼を寄せている。
「うおおおお⁉ これはなんだああ⁉」
軍服姿の吸血鬼は絶叫を上げていたが、やがて彼もまた、流星の一つに叩き潰されてしまった。
「ぼ、僕に、何をしろと」
飛行船を襲う流星群を前に、自分の命も危うい状況の中、エミールは何をすべきなのか、困惑している。
「お前がかつて、我々の前で見せた魔法、あれを使えば助かる」
「で、でも、上手く発動させられるかどうか」
「発動させろ。させられるかどうか、は聞いていない。絶対に発動させるんだ」
飛行船が傾き始めた。気嚢からガスが抜けていく音が聞こえてくる。もう、長くはもたない。
「何を考えているのか知らないけど、させるかよ!」
エミールの魔法発動を邪魔しようと、ルイージは走り出した。だが、その目の前の空間を、流星が貫いた。床に大穴が空き、勢い余って、ルイージはその穴の中に落ちてしまう。
「わああああああ……!」
叫び声を上げながら、遙か眼下の大海原へ向かって、ルイージは落下していった。この高さで海面に叩きつけられたら、まず助からないだろう。
無論、それは、エミール達も同じことだ。
それなのに、ヴィンセントは冷静な口調で、こう命じてきた。
「合図とともに、一緒に穴から落ちるぞ」
「し、死んじゃいますよ⁉」
「お前の魔法なら、助かる。そのために連れてきたようなものだ」
「だけど、まだ、心の準備が」
「寝ぼけたことを言うな。我が結社に入った時点で、もう覚悟を決めたものとみなしている。いまさら、心の準備がどうとか、悠長なことを抜かすな。戦えば生き、戦わなければ死ぬ。それだけの話だ」
ゴクッ、とエミールは喉を鳴らし、目を閉じた。エミールの魔法発動は、一定の集中力が必要となる。
思い出を、記憶の奥底から引っ張ってくる。それは、まだ家族がみんな生きていた頃の思い出。みんなで出かけた旅行の風景。
崖の上に立つ城。
エミールは、その城を描き続けていた。
吸血鬼達が自由な芸術を許していないことは知っていた。もしも絵を描いていることが発覚したら、家族みんな処刑されることはわかっていた。
それでも、エミールは描かずにいられなかった。内側から湧き出る情熱を抑えることなど、出来そうになかった。
「よし、飛ぶぞ。マリーは俺に掴まっていろ」
「は、はい」
「数えるぞ。エミール、遅れるなよ。3……2……1……ゼロ!」
ヴィンセントとマリー、エミールは、同時に床に空いた穴へと飛び込み、空中に身を投げ出した。
風に流されてどこかへ行きそうになるエミールの腕を、ヴィンセントは掴み、グイッと自分のほうへと引き寄せた。
落下していく三人の頭上で、巨大飛行船グラーフ・ツェッペリンは大爆発を起こした。それでもなお、ヴィンセントが発動した魔法「星月夜」の流星群は、容赦なく船体を穴だらけに貫いていく。
「エミール! まだか!」
バタバタとロングコートをはためかせ、パラシュートも無しに落下しながら、ヴィンセントは怒鳴り声を上げた。
全ては、エミールにかかっている。
その要となっているエミールは、記憶の世界に深く潜りこんでいる。
ともすれば、家族が吸血鬼達に皆殺しにされた、あの日の思い出が蘇りそうになる。だけど、必要なのは、それではない。
城だ。
あの城の風景だ。
心の中に焼き付いている、崖の上の城。あれを思い出さなければいけない。
息が荒くなる。
時々、差し込まれてくる、家族の惨殺死体の光景。倒れている妹に馬乗りになって、血をすすっている吸血鬼の姿。
次第に、あの忌まわしき思い出が、城の記憶を上回って脳内を占め始める。
(やめろ! よせ! あっちへ行け!)
エミールは必死で、余計な記憶を脇へと押しやった。
その結果――
あの日の、家族とともに見た崖の上の城の風景が、鮮明に蘇ってきた。
途端に、エミール達の周りに、透明な膜のようなものが現れた。
膜はやがて、より強固な力を伴い、青白いバリアとなって張り巡らされていく。
そのバリアは「城」の形をしていた。
「よくやった、エミール」
ヴィンセントがねぎらいの言葉をかけるのと同時に、「城」に包まれた三人は、海面へと勢いよく着水した。水柱が立ち、波紋が広がる。だが、三人とも、魔法バリアの「城」に包まれていたので、傷ひとつ負わなかった。
こうして、巨大飛行船グラーフ・ツェッペリンにおけるマリー救出ミッションは、ヴィンセントとエミール達「魔法画家」の華々しい勝利で終わった。
* * *
秘密結社ソレイユの活躍は、世界を支配する吸血鬼達によって情報統制され、一般市民には伝わらないよう握り潰された。
それは、吸血鬼達にとって、あってはならないことだった。
けれども、完全に隠し通すことは出来なかった。人間達による反乱組織や不穏分子は、世界各地に潜んでいる。そんな彼らが、人間が吸血鬼達に大打撃を与えた、という情報を見逃すはずがなかった。
ある日、魔法を使えるようになった画家達。
彼ら「魔法画家」は、吸血鬼達に対抗しうる希望の要であった。
そんな魔法画家が起こした大快挙に、心ある人々は興奮し、未来への明るい展望を夢見始めた。
だが、吸血鬼達も、当然黙ってはいない。
特に世界総統の座につく吸血鬼ノスフェラトゥは、激怒した。自分達よりもあらゆる面で劣る、劣等種族である人間が自分達に刃向かうなど、あってはならないことだった。
「魔法画家どもを一人残らず見つけ出すのだ! 殲滅せよ!」
それが、ノスフェラトゥの下した命令であった。
かくして、魔法画家と吸血鬼達による戦いは、さらに激化の一途を辿り始めた。
* * *
秘密結社「ソレイユ」は、一人の魔法画家クロード・モネによって創立された。
意味するところは「太陽」。
吸血鬼達が弱点とする太陽を結社名に入れることで、彼らを確実にこの世から葬り去るという固い意志を込めたのである。
対する吸血鬼達は、なぜ急に発生したのか、何を目的として世界を支配したのか、その多くは謎に包まれている。
彼らは、昼間は太陽が出ているため、外を歩けない。
だが、高度に発展した科学力を用いて、日中の活動を可能にした。
ヨトゥン・イェーガーと呼ばれる兵器である。巨人を模した、その人型兵器は、中に吸血鬼が乗り込んで動かしている。日光を遮断するので、太陽に焼かれることもない。これにより、昼間においても人間達を支配することができた。
吸血鬼達は、これまでと表面的には変わらない、人間による統治を許した。
それは、彼ら吸血鬼の絶対数が少ないことに起因しており、人間社会を維持、管理するためには、人間達にある程度の裁量を残しておく必要があったからだ。
代わりに、定期的な「食糧」の供給を求めた。
ごくまれに、人間狩りを楽しむ吸血鬼もいるが、それは吸血鬼達の法で禁じられている。乱獲すればあっという間に「食糧」は尽きてしまう。人間の絶対数の管理は必要であった。
各国の為政者達は、吸血鬼達に屈した。自己の権益を守るためでもあり、自分の命が惜しかったからでもある。
こうして、世界各国を束ねる「闇の帝国」が誕生した。
総統ノスフェラトゥは、あえて国家を名乗ってはいないが、人間達は陰で、吸血鬼達による支配体制のことを「闇の帝国」と呼称していた。
そんな闇の帝国に対し、燦々と輝く希望の光をぶつけるのが、太陽の秘密結社ソレイユなのである。
* * *
エミールは、慎重な足取りで、パリの裏路地を歩いている。
たかだかパンの買い出しに出かけるだけでも、吸血鬼達の目を気にしないといけない。
先日の飛行船襲撃事件があって以来、世界各地に厳戒体制が敷かれている。このパリにおいても例外ではない。
表通りから、地響きにも似た、重々しい足音と、機械音が聞こえてくる。
吸血鬼が駆る巨大人型兵器ヨトゥン・イェーガーだ。
エミールはまだ新人なので、あまり顔は知られていない。だから、見つかったとしても、いきなり襲われることはないのだが、それでも、万が一のことを考えると緊張する。
空は曇天。灰色の雲が重たくかかっている。
(この分だと、もうすぐ雨が降りそう)
雨具を持ってこなかったから、急がないと、と思った。エミール自身は濡れても別にかまわないのだけど、パンを濡らすわけにはいかない。
ふんわりと優しい香りが裏路地に漂ってきた。パン屋が近くなってきた証だ。
周りを警戒しながら歩を進めていくと、やがて、古びたビルの裏手に出た。ドアの窓ガラスの向こう側を覗くと、大柄なパン職人がせわしなく厨房を動き回っているのが見える。
コンコン、とパン屋の裏口を叩くと、しばらくしてから、立派な口ひげをたくわえたパン職人が、ドアを開けてきた。
「ほらよ」
ぶっきらぼうな感じで、パンをいっぱい詰め込んだ籠を、エミールに渡してくる。
「ありがとう、おじさん」
エミールがニッコリと笑うと、しばらくの間、パン職人はまぶしそうにその笑顔を見つめていたが、やがて何も言わずにドアをバタンッと閉めた。
「さてと、急いで戻らないと」
そう言った直後、ポツリポツリと雨が降り始めてきた。
慌てて歩き始めたが、雨足が強くなるのは一瞬で、あっという間にどしゃ降りとなった。
かろうじて、建物の軒下に隠れることができたが、この大雨の中、パンを抱えて移動するわけにはいかない。
さて、どうしよう、と思っていると、ふと、向かい側の建物の軒下にも、雨宿りしている女性がいるのを発見した。
年齢は、エミールよりも少し年上だろう。髪を短く結わえており、体にピッタリとフィットした黒いドレスを身にまとっている。目鼻立ちは鋭く、全体的にシャープな印象だ。
彼女と目が合った。
その途端に、彼女はなぜか雨が降りしきる道を横断して、ずぶ濡れになりながらも、エミールのいる側へとやって来た。
そして、エミールの隣に身を寄せてから、艶やかに微笑んだ。
「初めまして。私はエイダ。エイダ・ヴィルストラップ。女優をやっているの。あなたは?」
「僕は……エミール。エミール・ノルデ」
「エミール、ね。うふふ、かわいい名前」
エイダは、ますますエミールに近づいてきて、肌と肌を寄せ合った。顔を覗き込むようにして、真正面から見つめてくる。
「ひと目ぼれしちゃった」
「はい……⁉」
「君みたいな子、すごくタイプなの。よかったら、私の恋人になってくれないかしら」
かつてないほど女性に積極的に迫られ、エミールはすっかりパニックに陥っている。なぜ急に? どうして? エイダの体から発せられる甘い香りは、きっと高級な香水なのだろう、その匂いを嗅いでいるだけでも心の底から誘惑されてしまいそうになる。
しかし、エミールは、すんでのところで冷静さを取り戻した。
パン籠を抱えたまま、少し距離を取り、キッとエイダのことを睨みつける。
「お前、何者だ」
エミールの言葉を受けて、エイダは肩をすくめた。
「あら~、そんなに警戒しなくてもいいのに。私好み、っていうのは本当のことよ」
「僕が誰だか知っていて、近付いてきたな」
「そうね。それはもちろん知っているわよ。魔法画家のエミール・ノルデ君」
エミールは咄嗟にパン籠を足下に置くと、腰のホルダーからナイフを抜き、エイダに向かって突きつけようとした。
が、それよりも速く、エイダはエミールの懐に飛び込んできて、ナイフを持つ手を上から押さえ込んでしまった。
「くっ……⁉」
「魔法が使えなければ、大したことがないのね、魔法画家って」
エミールが使える魔法「城」は、防御魔法である。しかも、発動には時間がかかる。ここまで接近されている状況では、対処のしようがない。
「僕を、どうする気だ」
考えられるエイダの正体は二通りある。吸血鬼の味方か、そうでないか。おそらく吸血鬼の味方ではないかと、エミールは踏んでいた。
「そうねえ、私の家に連れ帰って、ペットとして飼ってもいいけれど」
エイダは唇に指を当てて、妖艶な笑みを浮かべた。
「でも、それは私の本意ではないの」
「じゃあ、何を考えているんだ」
「私の望みは、ただひとつ。今夜、私が出演する舞台を観に来てほしいの」
「舞台?」
「はい、これ、チケットよ」
エイダはドレスの胸の谷間に指を突っ込み、中から丸めた五枚のチケットを取り出し、エミールに渡してきた。
演目は「ラグナロク」。吸血鬼達が信仰する神々の最期を描いた物語だ。
「ノスフェラトゥ総統も観に来るわ」
エミールの耳元に唇を寄せて、エイダは囁きかけてきた。
「ノスフェラトゥが⁉」
驚きの声を上げた瞬間、エイダは、エミールの頬にチュッとキスをして、再び雨の中へと躍り出た。
「絶対に来てちょうだいね♪ 楽しみにしているから♪」
そう言いながら、エイダは舞うようにステップを踏んで、雨の道を突っ切っていき、やがて、その姿は水煙の向こうへとかき消えてしまった。
エミールは五枚のチケットを手に持ったまま、呆然とたたずんでいた。
記事を読んでいただきありがとうございます!よければご支援よろしくお願いいたします。今、商業で活動できていないため、小説を書くための取材費、イラストレーターさんへの報酬等、資金が全然足りていない状況です。ちょっとでも結構です!ご支援いただけたら大変助かります!よろしくお願いします!
