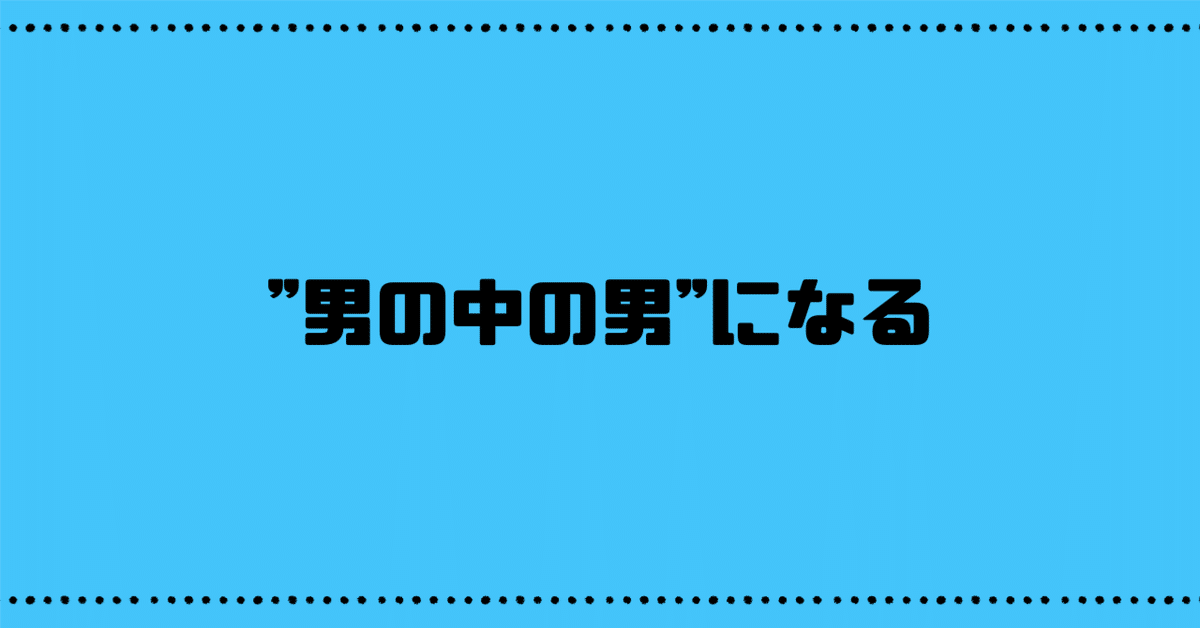
"男の中の男"になる
今日から11月だ。そして、今月は私の71歳の誕生月だ。古稀をおさらばして、次は喜寿(77歳)に向かって、人生の上り坂をコツコツと上っていこう。
そのためには、"汝自身を知れ"と、自らをよく自覚することだ。決して意気がって、若い時のような"登り坂を垂直登攀する"ような無謀なことはしてはならない。歳を重ねて粋な男になりたかったら、意気がって生きることをしてはならない。
中古車は中古車なりに、身の程を知って人生を生き抜くことで幸せな人生を送ることができる。
昨夜もNHKの7時(19時)のニュースを途中まで視聴して、布団に入った。最近は、20時前に寝ることが日課になっている。
そんなことで、今朝は12時前(24時。真夜中だ)に目覚め、何の気持ちの抵抗もなく、徒歩2分の事務所に出向いた。
草花に水遣りして、日めくりカレンダーを捲り、メールの受信の確認と発信をする。ここのところは、イベントの出席者のチェック等がある。そんなことをしていると、アッという間に2時を過ぎる。
それからblogを書いて、朝風呂に入って一寝入りするのが、私のルーティンワークになっている。
これで、夜のパーティが務まるのかと思いきや、それが全く抵抗がなく務まるのだ。
応援団のある先輩を私のイベントにお誘いしたところ、その先輩から、「80も過ぎると、夜は早く眠くなるんだ。朝型の生活になる。だから、小林さんのイベントに参加するのはちょっと難しいと思う。代わりにお昼でも一緒にしないか」と逆にランチに誘われた。
朝型になるのは私も同じだ。しかし、私が主催するイベントになると目が冴える。それは、主の意味は違えども、"随処に主となる"ことなのだと思う。気持ちの問題なのだ。
私の場合は、必須な行事がある夜にあると、それはストレスではなく、逆に"エネルギーの源"になるのだ。人間は、主体的に生きようと前向きな気持ちを持つことで、精神は若返るらしい。
このところ、フェミテックベンチャーであるFlora(株)のビジネスサポートをしている。
日本の企業における"男女の在り方"について、いろいろな企業の皆さんと話をする。具体的な提案をすると、そこで企業の本音が出てくる。そこから、ピンからキリまでの反応がある。
男女の生き方については、以前から思っていたことがあったが、彼らと話していて改めて感じることがある。
それは、"日本男子は、何と柔(やわ)になったものだ"と言うことだ。
私は、大学から応援の世界で生きてきた。
私が応援部の現役の時は、東大は男子オンリーの世界だった。たとえ、女子がブラスバンドに入部してきても、その扱い方が分からないため、1年も経たずに彼女たちは退部していくのが常だった。
それが、私が卒部して何年か経ってから、ブラスバンドに女子が入部して定着するようになり、新たに、バトン部(今のチアリーダー部)ができた。
そして、今は部員の7割以上が女子部員だ。女子が部を引っ張っている。そうすれば男子も気合いが入って頑張るようになる。
私の祖父母のありようも私の男女観に大きな影響を与えているが、応援部も同様だ。そんな男女のあり方がこれからの理想の日本社会だと思うのだ。
しかし、まだまだ、日本の企業はそうではない。一部、前向きな企業もあるが、遅れた企業も少なからずあるのが現実だ。
「女性に光を当てることは逆差別ではないか。その提案は、女性に光を当て過ぎている。もっと男女平等に扱わないのか」と宣う人たちがいる。意外だった。
日本では今まで、男子が大事に扱われてきた。大学までは平等。寧ろ女子は真面目だから、総じて、男子より成績は優秀だった。
しかし、一旦、就職の段階になると、男子は総合職で、女子は事務職。せいぜいが地域総合職だ。少なくとも私が若い時はそうだった。
今でも、底辺にそんな思いがあるのではないだろうか。
女性にはいろいろハンディがある。それは、男女の身体のつくりの違いで致し方ないところがあるが、そのことを当然のことだと思う。なりたい自分になるという"人間の人生という観点"を視野に入れることはしてこなかったように思う。
今は、男女とも、役員や管理職への階段は、平等に門戸は開かれているとは言っても、その門の手前まで行く道程は、男子はアスファルト道路なのに、女子は石が転がっている"でこぼこ道"なのが現実だ。
今こそ、その"でこぼこ道をアスファルトの道にする環境整備"が求められている。それでやっと、ジェンダー平等ではないのか。
それを、"逆差別"だと言うのだ。
何と、日本男子は柔(やわ)になったものだ。真の日本男子なら、女子に下駄を履かせても、寧ろそれを良しとして、正々堂々と戦う。そして、女子と共に肩組みあって戦うという"きっぷのいい、男らしい、迫力ある男子"であってほしいものだ。
「男は強くなければ生きていけない。優しくなければ生きている資格がない」
レイモンド・チャンドラーの「プレイバック」に出てくる有名な言葉だ。
"強く優しい男こそが、男の中の男"ではないのか。
私は、そんな男の中の男でありたいと思う。
不動院重陽博愛居士
(俗名 小林 博重)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
