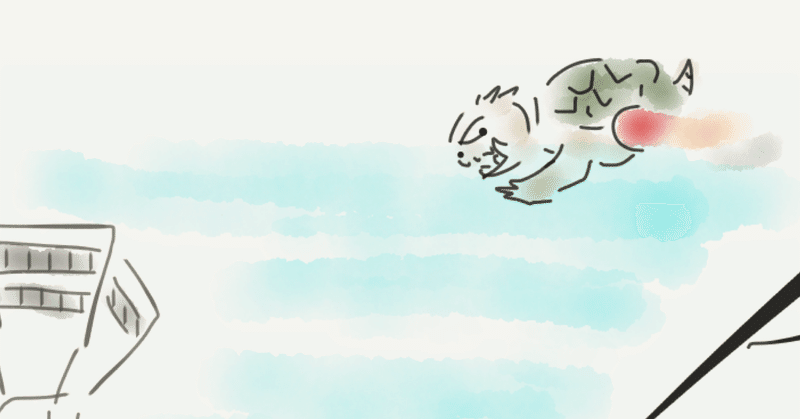
人の営みが築き上げた街には、時間の道がつづられている。
その道はビートルズが世に送り出した曲のように、曲がりくねっていただろうか。
時間軸のビジュアル化はメタファーとしてでしか顕せないから、ロング・アンド・ワインディングロードもありえないとは言えないだろう。
路傍の石ならぬ公園の石垣に残された狛犬は、移転した神社の忘れ物だったと知った。公園に迷い込んでからでは絶対にお目にかかれない狛犬は、いったん公園を出て遠目で見上げてやっと確認できる人知れぬ時間の祠(ほこら)に隠れていた。
東京北区、飛鳥山公園に何年か前まで残っていた狛犬は、仮住まいを悟られまいとするようにひっそりと佇(たたず)み、ひっそりしているうちにその姿を消していた。
街の時間はこのように、ときに時代を浮かび上がらせては沈めていく。
「まさか赤くない消火栓があるとは!」
消火栓が黄色を纏う街がある。
函館の歩んできた道には、文化見本国を追いかけた軌跡が残っている。
それが黄色い消火栓。突如時間の道にその姿を現し、協調性を正されても我が道は譲らずの体で、今でも涼しい顔で街にたつ。

役目を終えた道しるべを見かける場合もある。
それは、遺跡ほど古くはなく、文化遺産にいたるまでもうひと息のところまでこぎつけた現代の孤児。
なにが該当するだろう? と目を凝らせば対象物は割と多岐にわたりそうだが、目に止まったのが操車塔。

路面電車の交差を切り替える人力のポイントは、自動化、合理化の波にさらわれ実用性を欠いたことで、油絵を上塗りするみたいにして時間の道の途中に閉じ込められた。
息の根は止められているから二度と目を醒ますことはないのだけれども、かろうじて抜け殻が残っている街がある。
函館、広島、鹿児島。
路面電車の線路が張り巡らされていた東京にも当然、操車塔はあった。
だけどひとつも守れなかった。
それは、時間の道の補修痕ともいえる老体は、発展の邪魔者でしかなかったからだ。
忙しさに紛れると「儚い夢」はひとたまりもない。
旅は、訪れた街の「流れてきた時間の道」を辿る踏査(とうさ)。
長らくおあずけになっている旅。
心の準備はとっくにできている。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
