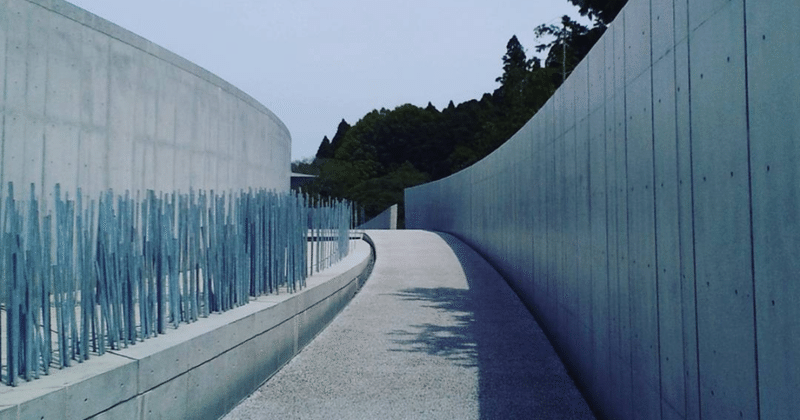
僕らは道具に使われている 〈後編〉
山田監督の1970年作に「家族」という映画がある。50年前。インターネットはおろかパーソナル・コンピューターすら出まわる以前の話。高度成長期の果ての果て、長崎県伊王島に住む一家が、炭鉱閉山に伴う失業を目前にして、新たな生活拠点を求め日本列島を縦断する。一家の道のりは、「家族」というタイトルに漂うほの温かい結びつきや“アットホーム”な気軽さからは程遠い。
陸路をゆく長い移動の合間に、広島の工業団地、大阪万博、東京の雑多な下町に立ち寄るものの躓きの連続で、日毎に疲弊と苛立ちの色が濃くなってゆく。一家の躓きぶりを見ていると「情報弱者」としての庶民の姿が浮き彫りになる。仮にこの一家がスマートフォンを携帯していたなら、この物語は成立しないと言いきれる。それほど、情報に乏しいことが彼らの障壁となっていた。
しかしそれも半世紀も前の話だ。やむを得ない時代性とも言える。それゆえに、見知らぬ人を頼る、離れて暮らす親族を頼るということが、生存のためのひとつのリソースたりえたわけだけれど。そして2020年の僕といえば。道具としてのインターネットから隔絶してしまえば、あの一家と同じように無知の下で途方に暮れてしまうわけだ。50年経っても人間単体では依然として丸裸なのだ。
今や道具=情報という方向へ収斂してきている。何がしかの情報を知っているのと知らないのとで生じうる格差は数えあげたらキリがない。豊かで利便性の高い社会は、溢れかえる選択肢を積み上げてできている。インターネットは目の前に並ぶ選択肢の数を易々と増やしてくれる。同じように無知の下で途方に暮れようとも、つまりはその意味あいは半世紀前の人と僕とでは大きく異なる。
依然として人そのものは裸でも、この数十年間に培われた通信と電脳技術の道具化は、ある種の無知について酌量の余地を取っ払ってしまった。それも順応というかたちでごく自然に。
僕の無知はただの馬鹿だけれど、「家族」の一家の無知は生死の分け目を意味している。前提は道具の有無ひとつだけ。それだけのことなのに。面白いよなあ。1970年以降、どこかで潮目が変わったんだ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
