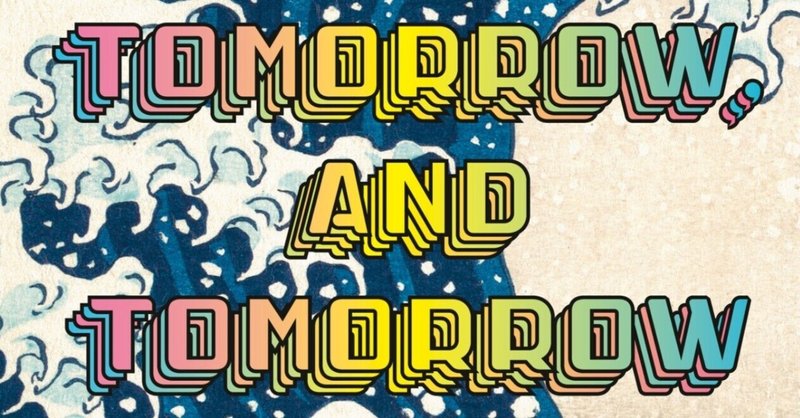
【洋書多読】Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow(214冊目)
『Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow』 By Gabrielle Zevin
総語数: 128,960 words (by Word Counters)
開始日:2023年3月13日
読了日:2023年4月1日
多読総語数:7,936,807+ ? words(※)
本書のことは、僕が英語多読用のコンテンツを探す際にいつも参考にさせていただいている渡辺由佳里さんのブログで知りました。渡辺さんの紹介文を見て「面白そうだ!」と思ってすぐにKindle版を購入したものの長く積ん読状態になっていました。
そうこうしているうちに同ブログで毎年恒例のイベントである、小説、ノンフィクション、児童書などの各ジャンルの中から渡辺さんを含む審査員がその年のベストの洋書を選出する「これを読まずして年は越せないで賞」の2022年版が発表になり、本書は部門別とともに映えある2022年の大賞(総合優勝)を獲得したのでした。
早く読みたい!読まなければ!そして大賞の受賞から2ヶ月半、ようやく手に取ることができた、というわけです。
恋愛小説の枠に収まりきらない画期的な作品
主人公はSamとSadieという二人の男女。彼らがまだ小学生だったころのひょんな出会いから物語は始まります。
二人をつないだのは「スーパーマリオブラザーズ」というテレビゲームです。今ではもう古典ともいうべきゲームですが、本書はアメリカのいわゆる「ミレニアル世代」を題材にした小説なので、この設定はなるほど、という感じです。ちなみに僕よりも5つほど学年が下の世代ということになります。
そんな二人は一旦別れたあと、大学生時に偶然地下鉄の駅で再会し、やがて共同してゲームを作成することになります。ここにMarxという、Samのルームメイトである同い年の男性が加わって3人はゲーム制作会社を立ち上げていくんです。
この3者の関わりが、恋愛・友情・同僚・ライバル関係…といった、あらゆる人間関係を描写するワーディングがすべて当てはまるような、それでいてどれもがしっくりこないような、とても複雑で豊かなレイヤーに彩られて進んでいくというのが本書の読ませどころであると感じます。
そこに、それぞれの人種的なバックグラウンドが重なります。交通事故で足が不自由なSamはユダヤ人の父を持ちますが、実際に彼を育てたのは韓国系移民の祖父母です。一方のSadieはビバリーヒルズに拠点を構えるユダヤ人富豪の家の出。Marxは日本人の父と韓国人の母を持つ日韓ハーフといういささか複雑なマイノリティなのですが、そんな彼らがゲーム業界という自分たちのエスニシティを常に意識點せられざるを得ない状況で屈折した思いを抱えながら生きていくさまは本当に切なくて、胸が熱くなるものでした。
『Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow』は総語数が13万語になんなんとする長編ですが、その長さが全く気にならない、ややもすればもっともっと読んでいたいと思わせてくれるような、そんな一冊でした。
英語はとても読みやすい
渡辺由佳里さんも「(文芸小説であり)娯楽小説」とご自身のブログにおいて本書を紹介されているように、『Tomorrow…』は決して難解で肩肘張って読まなければいけないたぐいの本ではありません。
そのあたりが本書の英語の読みやすさに現れていると思います。読みやすさだけを純粋に語るなら、本書読了後に読んだ『Tom's Midnight Garden』という、イギリスの児童文学のほうが遥かに読みにくく、挿入句や倒置が多用された複雑な英文で書かれていたとすら思います。
ただ、英単語に関してはやはり馴染みのないものが多かったので、Kindle版で意味を調べながら読まざるを得ませんでした。ただ、良書の多読における私自身の傾向がそうなのですが、先が気になってページを捲る手を止めたくないような洋書においては、不明単語の意味をいちいち調べたりする回数は激減します。
それでも十分にお話の流れはつかめますし、かえって読書のリズムが崩れるのが嫌なくらいなのです。もちろん、人によっては「一言一句わからない単語・表現がある状態で読み進めたくない」という方もいらっしゃいますから、僕のような100%読み方が正しいと主張するつもりはありません。
とにかく、個人的にはリーディングの流れを止めたくない気持ちが優先するような、そんな素敵なお話だったと思っています。そしてそれを可能にしてくれるような、比較的シンプルで読みやすい英語表現が多かった、というのが読後の印象です。
Tomorrow and Tomorrow and Tomorrowおすすめです!
そんなわけで『Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow』の読後感を中心にレビューを書いてみました。
本書は完全な洋書でありながら、表紙が北斎の富嶽三十六景をモチーフにしているとおり、考証に日本的なものをふんだんに取り入れているという点で、日本における団塊ジュニア世代、そしてミレニアル世代の人達にとってもまた、大変親しみやすい作品になっているんじゃないかと思います。
一方で、上述のように「人種」を強く意識させられざるを得ないアメリカという社会における「日系であること」「コリアンであること」「ユダヤ系であること」とはどういうことなのか?が描かれています。
それを「自分たちが作りたい理想のゲームとはなにか?」といった物語のレベルに落とし込んで登場人物に語らせる著者の読ませ方もなかなかだと思いました。
20代〜30代の人にはいまいちピンときにくい作品なのかもしれないですが、私達の世代の方にはぜひ手にとっていただきたい一冊だと思います。
この記事が気に入っていただけましたら、サポートしていただけると嬉しいです😆今後の励みになります!よろしくお願いします!
