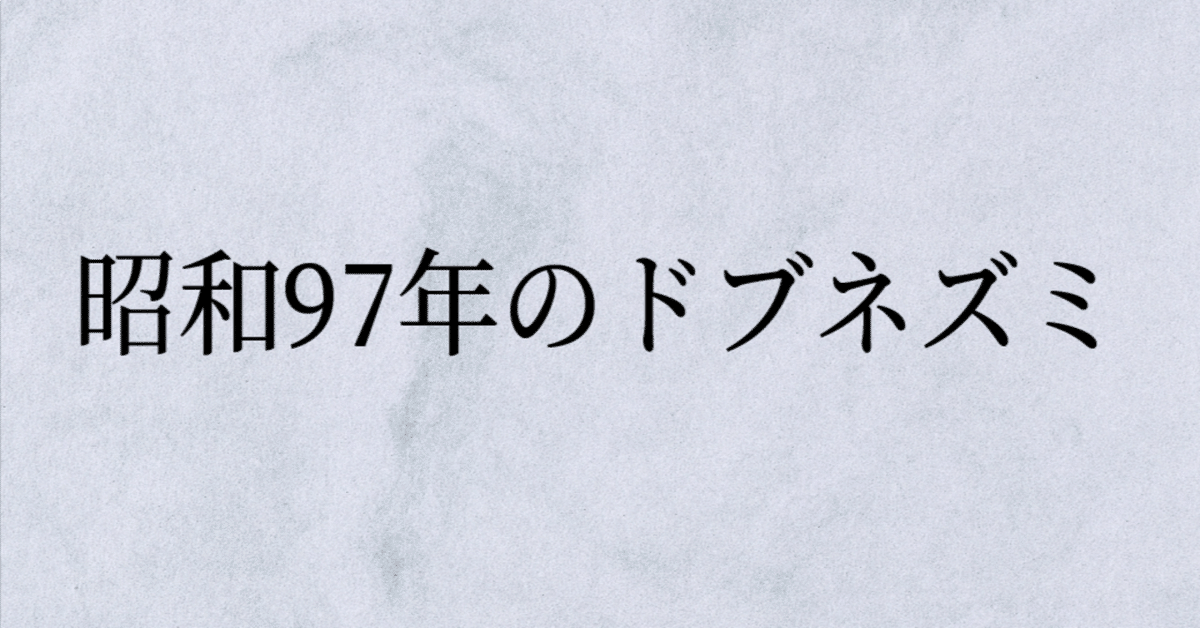
昭和97年のドブネズミ 第二話
2
買い物の帰り道、ドブネズミは自転車のペダルを漕ぎながら、また三十五年前のことを思い出していた。下水道で暮らしていた昭和最後の日々、そして樫本と出会い下水道を出てから過ごしてきた日々について。昭和は六十四年で終わりを告げ、平成は三十一年まで続き、令和が始まって四年が経った。世間はおれのことなんてきれいさっぱり忘れ去っただろう。曲がり角で自転車のハンドルを切ると、スーパーで買った缶ビールと惣菜がかごの中で揺れた。
クレームの一件がきっかけで会社を辞めた後、ドブネズミは無為な日々を過ごしていた。朝は九時頃に目を覚まし、昨夜の晩飯の残りで腹を満たす。テレビやインターネットを適当に見流した後は、散歩をしたり図書館に行ったり映画を観に行ったりして午後の時間を潰す。夕方には酒とつまみになりそうな食料を買い、自宅のアパートで静かな夜を過ごす。そんな生活を一ヵ月ほど続けていた。決して多くはない貯金額だったが、昔から質素な生活を送るタイプであり、半年は暮らしていけるぐらいの余裕はあった。もちろん新しい会社に入ることも選択肢の一つだった。広告代理店というのは結局人と人とのつながりの商売だ。クライアントと信頼関係を築ければ、たとえ自分の属する組織が変わってもクライアントはついてきてくれる。実際そうやってドブネズミは転職してきた。しかし今回、また会社に勤めようという気持ちにはどうしてもなれなかった。台所のテーブルの上には開封された健康診断の結果が置きっぱなしになっている。まあいい、いざとなれば電話一本でまた仕事を始められるさ、ドブネズミはそう高を括っていた。
アパートの部屋に戻ると、ドブネズミはスーパーで買った缶ビールを冷蔵庫に入れ、風呂の準備をした。そのとき玄関のインターフォンが鳴った。シャンプーもサプリメントもまだストックは残っているし、ここ数日は通販サイトで買い物をしていない。彼は首をかしげた。そのままドアノブに手が伸びかけたが、食卓テーブルの上に置きっぱなしにしていたマスクをつけてから、玄関のドアを開けた。
立っていたのは少女だった。ニットキャップを深めに被り、画像アプリで補正したような大きな目に大きな眼鏡をかけている。口元はマスクで隠されていた。
「恐れ入ります」
マスクのせいもあって小さな声だったが、はっきりとした発音で張りのある声だった。おそらく高校生か大学に入学したぐらいの年齢だろうとドブネズミは推測した。しかし普通の学生ではない。不自然に強調された目元のメイクが単なる少女でないことを示している。
「いきなりお邪魔して申し訳ありません」少女は頭を下げた。「あの……リンダリンダのドブネズミさんですよね?」
やはり、とドブネズミは視線を下げた。少女の佇まいから彼は芸能関係の匂いを感じ取っていた。昔、彼自身も身を投じていた業界の匂いだ。広告の仕事に転じてからも、たまに芸能関係の人間に会うと業界特有の人工的な匂いを感じることがあった。
「悪いけど、今は昔と違う。昔の仕事はもうしていない」ドブネズミはドアを閉めようとした。
「待ってください。そのことは知ってます。もう長く業界から離れてることは」少女は玄関のドアを掴んだ。その力の強さにドブネズミは少女の顔を見た。
「君はどこの人だろう」ドブネズミは訊ねた。
少女はドアから手を離して、半歩後ろに下がった。そして両腕を体の横にぴたりと付けて深々と頭を下げた。
「わたし、最近バンドでデビューさせてもらいました、うどんといいます。担当はボーカルでリンダリンダのカヴァーを歌わせてもらってます」
「うどん」
「はい。わたし大阪出身で、好きな食べものはうどんっていう設定になっているので、名前もうどんなんです」
ドブネズミはスマホで偶然見た画像を思い出そうとした。女の子たちが路上に寝そべっているガールズバンドの宣伝用写真。
「そのバンドのことは知ってる」ドブネズミは言った。「ネットの記事で読んだことがあるよ。でもはっきりとは憶えていない。君がその記事の画像に写っていたどうかも憶えてないんだ」
「あ、そうですよね、確かに」うどんは警戒するようにあたりを見回した。「まだデビューしたばっかりで、誰もわたしのことなんて知らないと思います。もちろんこのニットキャップと伊達眼鏡とマスクを取ってお話をすべきなんですが、あんまり外では顔を出すなと事務所に言われていて。今の時代、誰がどこで見てるかわからないですし」
「話って、やっぱり何かの企画かな」ドブネズミは声のトーンを落とした。「おれもそういう業界にいたし、最近まで広告の仕事をしてたからなんとなく想像できる。君たちのバンドがデビューするにあたっての話題づくり。そのために、おれと一緒に出演するテレビ番組かネット動画を作るっていう企画だろう、たぶん。でもそういう話なら、申し訳ないけど協力することはできないよ。おれはもうリンダリンダのドブネズミじゃない」
ドブネズミは目を伏せ、ドアを閉めようとした。その瞬間、うどんは再び強い力でドアを掴んだ。
「違うんです」うどんはドブネズミの顔をまっすぐ見つめた。「そんな話じゃありません。わたしはドブネズミさんを助けにきたんです。この場所からドブネズミさんを出すためにきたんです」
あらかじめうどんはドブネズミの経歴をネットで調べていた。
ドブネズミは最初、深夜ラジオ番組のパーソナリティとして登場した。三十分の放送枠でかつての下水道生活について話したり、リスナーから届いた相談に対してメッセージを送ったりする役を務めた。朴訥とした話し方でユーモアにやや欠けていたが、ドブネズミならではの独特なエピソードと切り口が評判になった。新宿でうどん屋を営む老夫婦がいて、夜になると夫の寝言を長年ノートに書きとめている妻の話。あるいは、くしゃくしゃになった大量の紙幣や人生を独白した手記や有名人同士の婚姻届、なかには人体の一部など実に様々なものが下水道に流れてくる話。流れているものに近づいて匂っていると、次第に腐敗と発酵の違いを判別できるようになってきたといった話だ。
リスナーからの相談にも真摯に答えた。若い自意識を持った相談者を冷たく突き放す答えでも、それはドブネズミの経験に裏打ちされた回答だった。「君にとって君自身はすべてかもしれないが、一方では大勢の中の一人にすぎない。まわりは誰も君に怯えていない。君が怯えているだけだ。君のほんの一部だけでもいいから、世の中にそっと解き放ってみるといい。実は怯えるほど価値のある世の中じゃないかもしれない」というふうに。
樫本による宣伝活動も功を奏した。樫本は裏方のスタッフたちにドブネズミのことを地道に触れ回ることで、間接的に彼の存在を広く世に知らしめた。
開始当初からラジオの新番組とは思えないほどの人気が集まった。アイドルのような性対象としてではなく、彼の作家性が認められたような人気だ。やがてラジオ番組での発言をまとめた本の販売部数が五十万部を超えると、彼の活動にさらに注目が集まった。雑誌社や新聞社から文章の連載依頼が舞いこんだ。日本各地の寂れた町を旅した紀行文や、絶版になった本だけを扱った書評などを任された。樫本が厳選した媒体にドブネズミは執筆し、それらの連載は単行本化され、何冊もの著作が全国の書店に並んだ。これから売り出そうとするミュージシャンの事務所から、楽曲の作詞を頼まれることもあった。かつて昭和の終わりを飾った大量消費時代とは違う新しい価値を、下水道で生きてきたドブネズミが提示してくれる、多くの若者たちはそう信じるようになった。
ドブネズミがテレビに出演したり、彼の写真が雑誌に掲載されたりすることに樫本は慎重になった。ドブネズミの人気は神格性に所以し、簡単に姿を見せない方が金になると考えた。しかしテレビコマーシャルの出演料は桁が違う。結果的に外国産高級車のコマーシャルの依頼を受けたのは成功だった。ドブネズミに台詞はなく、ただジャケットを着て遠くの虚空を睨みつけていれば良いだけだった。他のカットは夕暮れの地平線に向かって高級車が走り抜ける映像で編集された。このイメージコマーシャルによってドブネズミの孤高性は高まり、樫本の懐も札束で満たされた。
マネージャーとしての樫本は仕事のオファーを次々に受けた。ドブネズミには休日も睡眠時間もなく、仕事に追われる日々が数年続いた。せっかく新しく借りたマンションの部屋にも帰る暇がなかった。何かに追われる毎日は下水道で暮らしていたときと大して変わらないな、ドブネズミはそう苦笑した。
ドブネズミについて書かれたネット記事は、テレビ番組への出演歴を最後に記述が途切れていた。平成八年が最後の活動となっている。その記事はドブネズミも読んだことがあった。ただ彼の好物であるうどんについては一切書かれていない。彼はうどんについてどのメディアでも発言したことはないはずだった。だから今、自分の目の前に座っている少女のうどんという名前が、自分の好物に影響されたものではないだろうと思った。うどんは言った。このアパートから自分を出すためにきたのだと。確か同じようなことを三十五年前、樫本にも言われたことを彼は思い出した。
「わたしが音楽の道を志したきっかけは、ドブネズミさんです」
ドブネズミの部屋で、彼とうどんは食卓テーブルを挟んで向かい合っていた。うどんはニットキャップと伊達眼鏡を外し、マスクは付けたままにした。ドブネズミも新型コロナウイルスの感染に気を遣い、換気扇を回して玄関のドアを少し開けたままにした。ただ一瞬だけうどんにマスクを外してもらい、彼女の顔とスマホの画像を見比べた。確かに彼女はガールズバンドのボーカルとしてデビューした少女だった。
「ドブネズミさんの本は全部読ませてもらいました」うどんは力強い目で言った。「ドブネズミさんの文章を読むと、余計な考えが全部削ぎ落とされて、大事なことだけが心に残ります。そんな本は他にありません。わたしも自分のやりたいことをまっすぐやるぞって決心できました。リンダリンダがデビュー曲って聞いたときは、運命ってこういうことだと心の底から理解しました」
「おれ自身は何を書いたか憶えてないけど、役に立たったならうれしいよ」
「そうだな」うどんは指を顎に当てて、斜め上を見た。「おれにとって物事は二種類しかない。おもしろいか、おもしろくないか。馬鹿みたいに単純な視点だけど、それ以外の視点はどうしても思いつけない、とかです」
「ずいぶんと極端な意見に聞こえるね、自分じゃないみたいだ」ドブネズミは苦笑した。「あるいは当時、よっぽど複雑でつまらない状況を過ごしていたのかもしれない」
「わたし、こう見えても今すごく緊張しているんです」うどんは姿勢を正し、テーブルの上で両手を固く握りしめた。「ドブネズミさんを目の前にして二人きりで話をしてるなんて……。何のアポもなくご自宅まで押しかけたことは本当に申し訳ありません。でもそうしなければいけないことが起きようとしてるんです。わたしも緊張している暇なんてありません。あの……さっき玄関でドブネズミさんが言ってたテレビ番組の話、実はそういう企画が事務所のスタッフたちの間で動き始めてるのは事実です。でもわたしが今日来たのは、その企画に協力してほしいためじゃありません。逆なんです。関わらないでくださいという助言をしにきました」
うどんの口調は真剣だった。ドブネズミは小さく咳払いをした。
「すみません。助言というか、お願いです」うどんは訂正した。
「お願いか。企画内容がどういうものかは知らないけど、それがどんなものにせよ、もう昔みたいな仕事をするつもりはとっくにないんだ。さっきも言ったけれど。誰から何を提案されても、断ることに変わりはないさ」
「違います、ドブネズミさん」うどんは前のめりになった。「ドブネズミさんに企画の提案はされません。いつのまにか撮影は進行されることになります。ドブネズミさんの知らないうちに。つまりドブネズミさんを騙して驚かそうという内容です」
「いわゆるドッキリものか。昔からよくある企画だ」
「確かにそうです。わたしその話を聞いたとき、すごく戸惑いました。自分たちのバンドを話題に上げようと、何人ものスタッフが考えてくれた企画です。もちろん有難いことではあります。でも同時にわたしが憧れ、音楽の道に進む力をくれたドブネズミさんを騙すことになる。わたし、そんなことはやっぱりしたくないんです。もしそんなことをしたら、わたし自身が真っ二つに分裂してしまいます」
ドブネズミはうどんを落ち着かせようと微笑んだ。「ああいう番組の舞台裏って、実はみんなが演技していることが多い。騙される方も実は事前に打ち合わせ済みっていうことがね。まさに今、君がおれに話してくれたみたいに」
「たぶん」うどんは顎に手をやり、眉間に皺を寄せた。「たぶん、普通のドッキリ番組はそうなんだと思います。お茶の間に受け入れられる程度の騙しなんだと思います。穴に落ちたり、幽霊があらわれたりする程度。でも今回、ドブネズミさんに仕掛けようする騙しはそんな程度ではないです。わたしもスタッフから趣旨となるメモをちょっと見せられたぐらいですが、おそらくドブネズミさんの存在を根底から激しく傷つける内容だと思います。だからこそわたしはドブネズミさんに会いにきたんです。撮影スタッフに見つからないところへ逃げてもらうために」
時計の針は夜の七時を過ぎていた。いつもならNHKのニュースを見ながら缶ビールを飲んでいる時間だった。そういえばNHKの番組に出演したことは一度もないとドブネズミは思い返した。そしてドッキリ番組に出演したこともない。
ドブネズミの人気が陰りを見せたのは、彼が二十歳を過ぎた頃だった。かつてベストセラーとして世に広まった彼の著作は、そのときには古本屋のワゴンに安値で並べられていた。雑誌の連載も次々と終了し、長く続いたラジオ番組も打ち切りを告げられた。簡単にいうとドブネズミは世間から飽きられた。ちょうど日本でインターネットが爆発的に普及し始めた頃だ。表現方法が表現内容を変えていく、そういう時代に合わせて自分自身の売り出し方も変えていけるほどドブネズミは器用ではなかった。樫本が仕掛けたモンキービジネスもそろそろ潮時だった。最後はどんなに小さなテレビ番組でもできるだけドブネズミを出演させて、小銭を稼いでから引き上げようと樫本は考えていたようだった。
「騙す内容がどういうものか、君は知らない?」ドブネズミはうどんに訊ねた。
「詳しい内容はわかりません」うどんは神妙な表情で答えた。「わたしが聞かされたのは、ドブネズミさんがドブネズミさんでいられなくなったら一体どうなるのか、ということです。いくつものドッキリをドブネズミさんに仕掛けて、だんだんドブネズミさんがドブネズミさんでいられなくなる様子を隠しカメラで撮影するんだと言ってました。スタッフのメモにはここの住所も書かれていて、わたしはその記憶を頼りに今日お邪魔させてもらったんです」
ドブネズミはふと、クレームをつけてきたクライアントの担当者を思い出した。部長に間接的なメールを送ってきた男だ。打ち合わせの席についた担当者のネクタイは、あの有名なネズミ柄だった。
「おれがおれでいられなくなる」ドブネズミは落ち着いた声で言った。「それはこういうことかな。たとえば浦安のテーマパークにいるネズミのキャラクターがいるだろう。昔から活躍している人気者。あの彼の身ぐるみを剥がして、本当の彼自身を晒し者にするみたいなことだろうか」
うどんは視線をテーブルの上に落として首をひねった。「うん……はい……たぶんそういうことに近いかもしれません。わたしは大阪育ちで、あのテーマパークには行ったことがなくて、よくわからないんですが。ただスタッフの話の印象は、ドブネズミさんの存在そのものを、ものすごく脅かす感じでした」
ドブネズミは腕を組んで、天井の蛍光灯をしばらく見つめた。そしてふいに立ち上がり、冷蔵庫から缶ビールを取り出した。席に戻ると、マスクをずらしてビールを一口飲んだ。
「考えていることが二つある」ドブネズミはマスクを元の位置に戻した。「まず一つめ。そのドッキリ番組は、君のバンドに注目を集めるためのプロモーション番組だろう。番組内容はひとまず横に置いて、君のバンドが幸先よく活動していくためには、その番組がちゃんと撮影されることにかかってる。もしおれがカメラから逃げ回って番組が作れなかったら、君のバンドもうまくいかないかもしれない」
「わかっています」うどんは小さな声で返事をした。「自分のやりたい音楽の道を目指してきて、やっとデビューできたんです。だから何日もよく考えました。ずっとずっと考えてきました。そして考え抜いた今日、ドブネズミさんにこの話をしにきたのが、わたしの答えです」
ドブネズミはビールを飲みながら、うどんの言葉を聞いていた。「二つめ。おれが雑誌やテレビに出ていたのは二十年以上も前のことだ。まだ二十歳ぐらいのときで、それからはずっと広告代理店の会社員として働いている。毎日満員電車に乗って、マッチ箱ほどの広告スペースを売るためにクライアントに頭を下げ、接待ではポケットマネーを出すことも日常茶飯事だった。何度か転職を繰り返したから、給料もそれほど上がってない。そんなしがない生活を二十年以上続けてきた奴を、なぜ今さら追い回そうとするんだろう。世間はおれのことなんて憶えてないし、興味も失っているはずだ。おれにはよくわからない」
しばらく沈黙があった。うどんはドブネズミの胸元あたりをじっと見ていた。彼女の視線を感じながら、ドブネズミはときどきビールを口にした。
よくわからないけど一人だけいる、ドブネズミの頭の中でそうよぎった。樫本とは二十年以上会っていない。かつての仕事がなくなってドブネズミが就職するとき、樫本から知り合いの広告会社を紹介してもらったのが顔を合わせた最後だった。樫本なら何かを考えるかもしれない。
「ドブネズミさん」目を閉じていたドブネズミにうどんが話しかけた。「これは私の想像ですけど、たぶん撮影はすぐに始まると思います。あるいはすでに始まっているかもしれません。つまりスタッフによってすでに何かが仕掛けられている可能性があります」
ドブネズミはうどんの目を見た。バンドのボーカルとして人を惹きつけるために充分な、明るく魅力的な輝きを放っている目だ。だがその輝きの奥に、まだ二十歳前後の危うく移ろいやすい揺れのようなものをドブネズミは感じ取った。
「もしかしたらこの瞬間も撮られているかもしれない」ドブネズミは部屋を見回した。
「それはわかりません」うどんは立ち上がった。「わからないので、もうこの部屋は出た方がいいです。できるだけ早く」
ドブネズミは腹が減っていた。どんな騙しが仕掛けられようが腹は減るし、食事をする様子を撮られたとしても特にかまわない、彼はそう思った。うどんも一緒に食べると返事をしたので、彼らは近所の商店街にある定食屋に向かった。テーブル席が五つほどしかない、ドブネズミがよく利用している小さな店だ。最初に食券を買うシステムで、ドブネズミは財布から一万円札を出した。だが反応が悪いせいか、いくら券売機に投入してもそのたびエラーで一万円札が押し戻された。彼の財布には一万円札しかなく、店員に両替をしてもらった千円札を投入することで、ようやく券売機のランプが正常に点灯した。うどんは塩鮭定食のボタンを押し、ドブネズミは天ぷらうどんのボタンを押した。
「ドブネズミさんに聞きたいことがあったんです」うどんは鮭の小骨を外しながら言った。
ドブネズミはれんこんの天ぷらを齧りながら頷いた。
「ネットの記事を読んだだけですが、ドブネズミさんっていきなりラジオ番組のパーソナリティを務めたんですよね。大変じゃなかったですか?」
「下水道から出て、いきなり仕事を始めたわけじゃないさ」ドブネズミは水を一口飲んだ。「まずはいろんな音楽を聴いて、いろんな本や雑誌や新聞を読んで、いろんな芝居や映画を観るようにと言われた。国内もの海外ものは問わずにね。寝る時間を削って、空気を吸うように世の中のいろんなものに触れることが最初の作業だった。ラジオに出演したのは、そんな育成期間を一年以上続けてからだったな」
「やっぱりすごいですね。たった一年ほどなのにラジオで話せるまでになって。それで一気に人気まで出ちゃうんだから」
「有能なマネージャーが付いていたからね。彼の力が大きい」
「やっぱりモテました?」うどんは大きな目を見開いた。
「どうだろう」ドブネズミは彼女の視線を避けるようにうどんをすすった。「番組宛に手紙はたくさん届いていたと思うけど。個人的には、ふつうとそこそこの間ぐらいだったかもしれない」
「そこらへんはいろいろ言えないこともありますよね。わかります」うどんは箸で味噌汁を何度もかき混ぜてから口にした。「三十年以上前のことだから、あんまり憶えていないですよね。わたしなんてまだこの世に生まれてもいない」
うどんはしばらく食事に集中した。鮭の身をひとかけらも残さず平らげてから、鮭の皮を箸で器用にくるくる巻いてから食べた。それから小鉢に盛られたほうれん草のお浸しをぱくぱくと口に放りこみ、味噌汁をすべて飲み干した。白米だけは半分ほど残した。
「ごちそうさま」うどんは両手を合わせ、頭を下げた。「ドブネズミさんって食べ物の好き嫌いはありますか?」
「ないよ。何でも食べる。だって下水道で暮らしてたんだよ」ドブネズミも天ぷらうどんの器の上で箸を揃えた。
「でも生活がだんだん裕福になることで、昔と変わったこととか」
「そうだな」ドブネズミは天井を見上げた。「今でも公園のベンチで寝ようと思えば寝られる。でも牛乳を飲んだコップで麦茶は飲めない」
ドブネズミはリュックサックから小さなプラスチックのケースを取り出した。そして蓋を開けて手の平に錠剤を何粒か出し、水と一緒に飲みほした。
「薬ですか」うどんが訊ねた。
「ただのサプリメントさ。どうしても栄養が偏りがちになるからね」ドブネズミは反射的に嘘をついた。本当は病院から処方されている薬だった。「健康の定義って聞いたことある?」
「いえ、ないです」うどんは首をひねった。「わたし的には、健康ってよく食べてよく寝ることかな」
「最近ニュース番組でよく映るWHOってあるだろう。世界保健機構。あそこによると『健康とは、病気ではないとか、弱っていないということではなく、肉体的にも、精神的にも、そして社会的にも、すべてが満たされた状態にあることをいう』ことらしい」
「すべてが満たされた状態」うどんは繰り返した。
「そう。つまり健康な人間なんてこの世に一人もいないってことさ。みんなどこか病んでいる。コロナウイルスが消え去ったとしてもね。おかげでこういうサプリメント会社も広告を出し続けられる」
定食屋を出ると、くっきりとした輪郭の白い満月が夜空に浮かんでいた。ドブネズミはうどんを駅まで送ることにした。彼女は都心のマンションでバンドメンバーと共同生活を送っているということだった。
「わたしが今日言ったこと、ドブネズミさんはどう思いますか」うどんはドブネズミのとなりを歩きながら訊ねた。商店街の店はほとんどシャッターを下ろし、人どおりもまばらだった。
「正直まだよくわからないけれど、テレビ番組を作る人間についてはそこそこ知ってる。彼らの考えそうなことさ。まわりでおかしなことが起こったら、それなりに対処するよ」
「わたしのバンドって、ありあわせのメンバーなんです」うどんはうつむきながら呟いた。「わたし元々は一人で、高校の三年間はひたすら大阪の路上でギターの弾き語りをしていました。その間にいくつもオーディションを受けてたら、東京に来てみないかって声がかかったんです。両親には猛反対されましたけど、その引き止めを強引に振り切って、高校の卒業式の後すぐに上京しました。そしたらもうすでに何もかも準備済み。全国から集められた他のメンバーも同じ部屋に集められて『君たちには今日からバンドを組んでもらう。担当もすでに決まっている』ってプロデューサーに言われました。それからまだ半年しか経っていません」
「すべてが本意というわけではないんだね、今は」
「今の状況にありつけただけでもラッキーなのはよくわかっています。今はとりあえずそうだとしても、この先は良い方向に変わっていく可能性もあるだろうって。別にバンドが嫌ということじゃなく、今メンバーはお互いに親睦を深めようとしてますけど、まだあんまり思い入れがないというか……。個人的な思いとしては、今回のドブネズミさんのドッキリ番組はやりすぎだと感じるし、これでバンドの人気に勢いがつくのは絶対間違っているし、そもそもおもしろい番組ができるとも思えません」
駅が見えてきた。ちょうど改札口を出た人々がそれぞれの帰路へ分かれていくところだった。ドブネズミとうどんは人波を避けながら進んだ。
「ドブネズミさんの言葉で、ずっと胸に残っているものがあります」うどんは唐突に言った。「たとえクラスメイトに相手にされなくても、先生に馬鹿にされても、家族に冷たくされても、君のそばにはいつも自由がいる。自由がそばにいてくれる限り、君はいつも君自身でいることできる。わたし、その文章を読んで大阪を飛び出しました」
ドブネズミはうどんの横顔を見つめた。返す言葉に頭を巡らせた。
「そういえば大阪弁は使わないね」しばらくしてドブネズミは訊ねた。
「ほんまですね」うどんは笑った。「これもプロデューサーの指示です。まだ方言を使うタイミングじゃないからって、メンバーみんな制限されてるんです。そういえばドブネズミさんはなんで世に出ようと思ったんですか?」
ドブネズミは前方に目をやり「かけがえのない自由を切り売りして、たらふく飯を食うためだよ」と答えた。「そのときはそう思った。そしていろんな仕事をさせてもらった。それも多くの人が経験できないような仕事で、おもしろいこともあれば、おもしろくないこともあった。ただそのおかげで広告の仕事を続けることもできた。あれからずいぶん年月が経ったし、今となっては市井の一人として生活をする毎日にすっかり慣れた。これが自分の居場所なんだとも感じてるよ」
うどんの視線も前方に向けられていた。改札から溢れ出る人々を避けることに彼女は集中していて、ドブネズミの言葉がすべて聞こえたのかどうかわからない。
改札口に着くと、うどんはスマホを取り出して、メッセージのやりとりができるように互いのIDを交換した。
「何かあったら連絡しますから、ドブネズミさんも何かあったら連絡してください」
「何もないことを願うよ」
「あと今度、浦安のテーマパークに行ってみます。今日ちょっと興味がわきました」
「楽しめばいいよ。彼らも苦労人だから」
うどんは改札を抜けると何度か振り返って、ドブネズミに手を振った。そして新宿行きのホームへと消えていった。
翌朝、ドブネズミは仕事の電話をかけた。相手は一ヵ月前に久しぶりに訪れた得意先の担当者だった。
うどんの話が嘘だとは思えなかった。音楽デビューを果たした二十歳前の女の子が、見ず知らずの部屋にわざわざ一人で話をしにくるほど暇ではないだろう。うどんが番組の仕掛人の一人だとも思えなかった。彼女はまだ演技経験もないだろうし、おれがディレクターなら企画がばれるようなリスクの高いことはしない。実際、彼女が演技をしているようには見えなかった。うどんは自分の意志でおれに会いにきた、ドブネズミはそう感じ取っていた。
いずれにせよ、どこの誰だかわからない他人が考えたおかしなことにドブネズミは巻きこまれたくなかった。何もせずにふらふらと毎日を過ごしているから、おかしなものが隙を見て入りこんできたのかもしれない。そろそろ仕事を始めて、毎日人波に流れていく日常に戻った方がいいだろう。その取っかかりとして、ドブネズミはかつての担当者に電話をかけてみた。
かけた番号は担当者の携帯電話だったが、コール音は鳴りっぱなしだった。まだ朝の九時半だった。ドブネズミは部屋を片付けることにした。流しにたまっていた食器を洗い、ごみを大きな袋にまとめ、部屋中に掃除機をかけて、雑巾で拭き掃除をした。クリーニング店に行ってスーツとシャツを渡し、スーパーで三日分ほどの食材を調達して、コンビニで新聞と週刊誌をいくつか買った。部屋に帰って食材を冷蔵庫に詰めこんだ後は、新聞と週刊誌に目を通し、特に広告のページは時間をかけてチェックした。
時計の針が十一時半を過ぎた。ドブネズミは再び電話をかけたが、いくらコール音が鳴ってもやはり担当者は出なかった。ドブネズミは仕事用の手帳から名刺を取り出し、担当者の事務所の番号に電話をかけた。すぐに高い声の女が出たので、ドブネズミは担当者の名前を伝えた。
「ええと……申し訳ございません、そのような者は弊社には在籍しておりません」女は事務的な口調で言った。
「営業部の方ですよ」
「はい、営業部にもおりませんし、他の部署にもおりません」
「もしかして辞められたんでしょうか」ドブネズミは手に持っていた担当者の名刺に目をやった。「一ヵ月ほどの前に、そちらで打ち合わせをさせて頂いたんですが」
「いえ」女の声が固くなった。「以前からそのような者は社内におりません。何かの間違いではないでしょうか」
電話を切った後、ドブネズミはコップに麦茶を注いで飲んだ。麦茶を飲みながら、一ヵ月前の記憶をたぐりよせた。確かにおれは彼と直接顔を合わせて三十分ほど話をした。子供の受験で金がかかるんだと彼は苦笑していた。そのときあらためて名刺をもらった。今かけた電話番号も間違えていない。
ドブネズミの頭に昨日の話がよぎった。すでに何かが仕掛けられている可能性はあります、とうどんは言った。これが仕掛けなのだろうか。あるいは仕掛けの一つなのだろうか。いくつもの騙しを仕掛けるという話だった。だが今のところドブネズミには確かめようがない。うどんに確認のメッセージを送ったとしても、彼女は仕掛けの内容を知らない。
ドブネズミは椅子に座って雑誌をぱらぱらとめくりながら、折り返しの電話がかかってくるのを待った。しかしいくら待っても、目の前のスマホは何の反応も示さなかった。彼は諦めて、昼食の用意をするためにテーブルの上を片付け始めた。そのときコンビニで買った新聞が目に止まった。というより、折りたたまれた一面に印刷されている日付が、彼の意識を強引に引き止めた。そこには「二〇二二年(昭和九十七年)」とあった。彼は新聞を手に取った。彼の意識が混乱しているわけではなかった。そして新聞社の誤植のせいでもなかった。なぜなら、テーブルの上の新聞と雑誌に印刷されているすべての元号表記が令和四年ではなく、昭和九十七年になっていたからだ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
