
Vol.9「仏教」
仏教はなにを教えてるの?
日本で行われる葬儀の9割以上が、仏教の教えにのっとった仏式で執り行われます。宗派によって若干の違いはありますが、仏式の葬儀は故人を極楽浄土に送ることを目的とします。
仏教はキリスト教、イスラム教とともに「世界三大宗教」に数えられ、世界におよそ4億人の信者がいると言われています。日本における仏教系の信者数は8,433万6,539人(文化庁編『宗教年鑑』令和元年度版)、日本国民の67%にあたる人が信心されている計算です。
仏教って、誰がこんなに広めたのかご存知ですか?
仏教の開祖はもちろん知ってます、よね??
お釈迦様、爆誕
仏教を英語でBuddhism(ブディズム)、直訳すると「仏陀(ブッダ)の教え」になります。
仏教の開祖は、紀元前463年4月8日に現在のインドとネパールの国境付近に住む部族・釈迦族の王子として誕生したガウタマ・シッダールタ、のちのお釈迦様。
お釈迦様は生まれてすぐに7歩歩いて天を指し、「天上天下唯我独尊」とおっしゃいました。
てんじょうてんげ、ゆいがどくそん。
自分という存在は、この世に一人だけ。
だから、尊い。
その時、天から9頭の竜が現れて甘い水を吐き、その水を産湯にしたという伝説があります。今でも4月8日は灌仏会(かんぶつえ)、通称「花まつり」としてお釈迦様の誕生を祝います。この時に、誕生仏(たんじょうぶつ)と呼ばれる仏像に甘茶をかけてお祝いします。

お釈迦様、成道
王子として何不自由なく育ったお釈迦様でしたが、成長していくにつれ、あることに悩みます。
「この世に生きている限り避けられない苦しみがある。老い。病。死。どうしたら乗り越えられるのだろう」
29歳の冬、お釈迦様は妻子を置いて出家します。死と隣り合わせの苦しい修行を繰り返しましたが、やがて苦行では悟りを得られないと気付きます。
お釈迦様は菩提樹の下で座禅を組み、瞑想に入ります。あらゆる苦しみは自分自身の心が生み出していたのだと、お釈迦様は35歳の時に、ついに悟りを開かれました。
お釈迦様が悟りを開かれた12月8日には、成道会(じょうどうえ)と呼ばれる法要を行います。
お釈迦様、覚醒
諸行無常…あらゆるものは常に変化をしている。
諸法無我…すべてはつながりの中で変化している。
これらの真理を理解し、迷いがなくなる。煩悩から解放されて苦しみがなくなるのが悟りです。悟りを開くことこそ、仏教の究極の最終目標なのです。
仏教では悟りを開いた者を「仏陀(ブッダ)」と呼びます。悟りをひらいた仏陀の教え、あるいは仏陀になるための教えが「仏教」です。
お釈迦様、説く
悟りをひらいたお釈迦様は「人々を幸せにしたい」と思い、その方法を教えるために説いてまわります。お釈迦様の教えは「八万四千の法門」と言われるほど多くその教えは方便(ほうべん)で説かれていました。
方便とは、相手にわかりやすいように、時と場合に応じて説くことを意味します。それゆえ、同じ内容の教えであっても人によって解釈が異なりました。
お釈迦様の死後、信徒たちによって形成された教団が、お釈迦様の教えの解釈をめぐり分派しました。その解釈の違いが、のちにたくさんの「宗派」を生みました。
お釈迦様、永遠に
お釈迦様の死後に弟子たちが集まり、お釈迦様の説法をまとめ、それを書き記したものが「お経」です。
仏教はインドから中国に伝わります。インドの言葉だったお経は中国語に訳されます。
お釈迦様が亡くなってから約1,000年の時を超え、日本にはじめて仏教が伝わったのは、538年(ご参拝に来た仏さん)と学校で習いました(『日本書紀』では552年)。この年、百済(今の朝鮮)より欽明天皇の元へ仏像と経典等が献上されれたそうです(『仏教公伝』)。
欽明天皇の孫にあたる人物が厩戸皇子(うまやどのおうじ)。馬小屋で生まれたとか、10人の話を一度に聴き分けたとか、はたまた日本のお札に最も多く登場した人物として「ミスター銀行券」と称される、「聖徳太子」です。
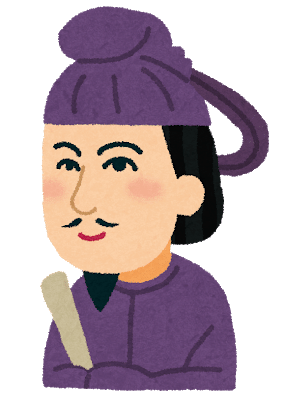
聖徳太子と仏教
聖徳太子は、日本に仏教を広めました。
聖徳太子が制定したとされる日本初の憲法、「十七条憲法」。その第二条に「篤く三宝を敬え」とあります。
三宝とは、仏・法・僧の3つと太子は教えます。仏とはお釈迦様。法とは仏の説いた真実の教え。僧とは仏教を正しく伝える人のことです。聖徳太子は、「日本人は仏教徒になりなさい」と、法律で定めたのです。
四天王寺と法隆寺
聖徳太子が建立したとされる有名な寺院が、大阪にある四天王寺と、奈良県斑鳩町にある法隆寺。
四天王寺は今から1400年以上前に建立された日本で最初の国立の寺院です。創建の経緯が『日本書紀』にも記されています。戦前までは天台宗の寺院でしたが、戦後に独立し、宗派にこだわらない『和宗』総本山を名乗ります。
法隆寺は「世界最古の木造建築物群」として日本ではじめて世界遺産に登録されました。明治時代は法相宗(ほっそうしゅう)の大本山でしたが、戦後に聖徳太子を宗祖とする聖徳宗として独立しました。
法隆寺の正式名称は「聖徳宗総本山法隆学問寺」です。
十三宗五十六派
宗教団体法が施行される昭和15(1940)年以前に認知されていた宗派は、十三宗五十六派と言われます。
現在は13宗派が日本仏教の主要宗派とされています。
系統別に整理すると、次の5つに分かれます。
⒈奈良仏教系(法相宗、華厳宗、律宗)
⒉密教系(天台宗、真言宗)
⒊浄土系(浄土宗、浄土真宗、融通念仏宗、時宗)
⒋禅宗系(臨済宗、曹洞宗、黄檗宗)
⒌日蓮系(日蓮宗)
次回から、宗派別に解説してまいります。
まとめ
・仏教の開祖はお釈迦様
・悟りを開いた者、悟りを開くための教えが仏教
・日本で仏教を広めたのは聖徳太子

表紙イラスト きむら
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
