
◆読書日記.《なだいなだ『権威と権力―いうことをきかせる原理・きく原理―』》
※本稿は某SNSに2019年9月30日に投稿したものを加筆修正のうえで掲載しています。
なだいなだ『権威と権力―いうことをきかせる原理・きく原理―』読了。
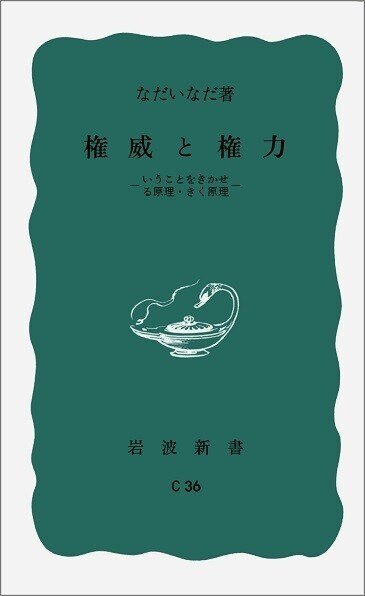
なださんお得意の対話篇にして、本書は先日もご紹介した『民族という名の宗教』の姉妹編。
『民族~』でも出て来るA君が高校生の時のお話。A君はなださんの所に「クラス委員としてクラスを纏めたいのだが、全く纏まりがない」と相談しにくる。
確かに、となださんは頷く。
日本の社会についても企業についてもばらばらで酷く纏まりがない。
では、と「なぜまとまりがなくなったか、考えてみようよ」とA君に提案。
何故人々にまとまりがないのか?
「みんなが勝手気ままになったからではありませんか」とA君。
何故みんなが勝手気ままになってしまったのだろう?
「きまりがあっても、それを皆が守ろうとしなくなったのです」とA君。
では、決まりや決まりを守らせていたものが失ったものは何なのだろう?
「様々な点で、これまであった権威が失われたことではないでしょうか」
――では、権威とは何なのだろうか。そして、それを取り戻せば人を纏まらせる事ができるのだろうか?
ここから、なださんとA君は「権威」とは何だろう? そして、それは「権力」と似た考え方だが、その両者はどう違うのだろう? という、この「権威と権力」に働いている「人にいうことをきかせる原理・きく原理」について徹底的に話し合う事となるのだった……というのが本書の「あらすじ」となる。
このように、なださんの対話編は、いつも小説の様な読み口で物事を考えるヒントを与えてくれる。
◆◆◆
本書は「対話篇」という事で、なださんとA君とが話し合うという形式で進められる思想書となっている。
なださんの話相手のA君が高校生という事もあるので、本書で展開する議論は非常に丁寧で分かり易く書かれており、学生でも楽に読めるだろう。
『民族という名の宗教』の時も言ったように、ぼくは学生時代になださんの対話篇『くるい きちがい考』を読んで「頭のいい人はこういう風に物事を考えていくのか!」と大変な刺激を受けた。
なださんの対話篇の議論はそれだけ丁寧で、学生でも分かるくらいの基礎的な部分から粘り強く考えを深めていくという魅力がある。
本書でもそういうなださんの姿勢は変わらない。
まず最初に「権威」について考えよう、となったら、改めて「では権威って何だろう?」という事を定義づけていく所から始める。
勿論、通常の一般語は定義しきれないから一般語なのだが、それをあえてある程度の補助線を引いてちょっとでも明確な意味を見つけようとする。
「権威」という言葉の定義を考えようとするなださんに向かってA君は「『広辞苑』でも引いてその言葉の定義を見たらどうでしょう。その方が、手っ取り早いですよ」と言う。
そこでなださんはA君に「おやおや、君は辞書を見れば、そこに正しい定義が見つかると思っているらしいね」と言う。
「そこ(広辞苑)にのせられている意味は、正しいかただしくないかの問題とは関係ないのさ」となださんは説明する。
人は言葉の意味をいちいち辞書を調べてから喋っているのではない。
辞書は、人の喋っている言葉の意味を、日本語学者などが後から考えて定義づけている言葉だ。
辞書もある意味「権威」なのである。
「ぼくたちは、一つ一つ定義もきめずに言葉をしゃべっていた。言葉に、自分達なりの意味を与えて、喋っているのだ。だから人によって、時代によって、地方によって、意味が違っている。東京で"てんぷら"と意味するものと、大阪の方のそれとは違っているそうだよ」
だからこそ、改めて定義を考えるのが重要なのだ。
「ぼくたちは外国語を勉強するみたいに、辞書を引き引き日本語を覚えたわけではないのさ。だから、ぼくたちが、今まで違和感を感じないで権力とか権威とかの言葉を使って議論をしてきたのなら、そこでぼくたちがこの言葉にどんな意味を与えて使っていたかを調べればいいのさ」
本書ではそこから「権威」という言葉を使う場合、どのような場面で使うのか、どんな時に使うのか、そして逆にどんな場面で使うと違和感が出るのか――そういった事を言い合いながら、だんたんと「権威とは何か」という問題を掘り下げていく。
重要なのは、このようにテーマを掘り下げる時のプロセスというのは、その他の様々なテーマを考えるときにも応用が効く汎用性のあるやり方だという事だ。
その他にも本書には「権威と権力」というテーマを考えるにあたって様々なアプローチを試みているが、全て学生でも使える思考方法だというのが優れている点だろう。
特にこの「定義づけ」というのは、なださんの対話篇ではしばしば出て来る得意技だ。ぼく自身もこれで随分と思考能力を鍛えられた。
なださんは本書の冒頭でA君に「ここで少し視野を広げて、思い切って大きな問題をとりあげてみようじゃないか。そして折に触れて君のクラスの問題を考える事にしよう」と提案する。
これも実に面白いアプローチだと思う。
とにかく問題がどこにあるのか、それを大枠でとらえて、問題の輪郭線をハッキリとさせようというのだ。
A君が「権威が失われた」と言っているという事は、以前は「権威」はあったのだろうか? それは具体的に何の「権威」なのだろう? 権威のあるものとないものとの違いは?
そうやって考えていく事で、問題の輪郭を徐々にはっきりさせていく。
「具体化」「比較」「例示」……思考のための様々な方法論が出て来るが、全てが高校生となださんとの対話によって丁寧に分かり易く進行する。
驚くべきは、それによって導き出される様々な考え方というのが、大人の鑑賞にも耐え得るレベルがだという事だ。
本書に書かれている結論のようなものや、途中で出て来る議論についてなど、所々に「ああ、なるほど!」と膝を打ちたくなるような優れた考え方が出て来る。
全く専門的な高度な知識を使わなくとも、これだけの結論を導き出すことができるというだけで、学生時代のぼくにはなださんの対話篇は尊敬の対象だった。
紀元前4~5世紀に著されたプラトンの対話篇は、例え結論が古びたものになっていても未だに読み継がれる名著でもある。
何故か。
それは、プラトンの対話篇は結論よりもその「考えるプロセス」の方法論が重要だという面があるからだ。
なださんの対話篇もプラトンの対話篇と同じような側面があるのだ。
本書で出て来る結論はこれはこれで一つの非常に面白い「権威/権力論」にはなっているのだが、それよりも更に優れているのは、本書が「高校生にも分かる、物事を考えるにあたっての考え方の訓練本」でもあるというところにある。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
