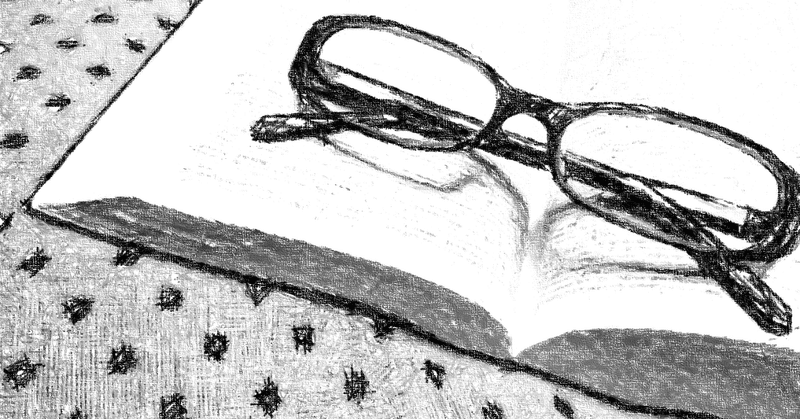
生活様式に合わせた眼鏡
「生活様式に合わせた眼鏡」と言うと眼鏡を作る側としては当たり前の事ではあるんですが一般ユーザーの方は新しく感じるかもしれません。
そもそも「物を見る」という事には眼の体力?力が必要です。
下の図でイメージイラストを描きましたが、上段屈折異常がない場合は眼が力を使っていない時に(無調節)遠くが見える人が自分の調節力を使って近くを見る際に近視状態に力めば近くも見えるようになります。
しかしこの調節力と言うのは年齢と共に変化し実は調節力自体の衰退は20代から始まっていると言われています。

え?じゃぁ20代から老眼が始まってるの!?
違います。老眼とは
老視(ろうし)は、目の障害の一つ。老眼(ろうがん)とも呼ばれるが、老視が正式名称。
加齢により水晶体の弾性が失われて調節力が弱まり、近くのものに焦点を合わせることが遅くなったり、できなくなってくる。(Wikipediaより抜粋)
明確なようで明確じゃない表現が一つありますが「近く」一般的には35cm~40cm位と言われていますが新聞を読む距離位です。
ただ新聞を読む距離と言うのもテーブルに広げて読む人、もって広げて読む人、折りたたんで文庫本の様に読む人さまざまでそのスタイルによっても35~40cmには収まりあません。
ここら辺のあいまいさも残しつつも兎に角35~40cm位が見えづらくなったor見えなくなった事を老視と言いますので「調節力の低下」があっても「老視」ではありません。
じゃぁスマホ老眼って何?
最近この言葉を聞いたことある方もいらっしゃると思いますが新たな造語?的なものだと思ってください。
私の認識ではスマホなど極端に眼にストレスが掛かる状況の積み重ねによって一時的に老眼のような症状になる事だと認識してます。
所謂「スマホ老眼」≒「老眼」なのでお間違えの無いように!!
もともとの屈折状態が重要
さて上に書いたことはすべて屈折状態が正視状態の時のお話です。
眼鏡や見えることの説明を不特定多数の方にすることの難しさは屈折異常が正視以外の場合(近視遠視乱視)にはそれを含めて考えなければいけないという事です。
実際にここら辺が混同して都市伝説的なものが生まれてるのも事実です(笑)
例えば老視の話をしても、近視の方の場合「いや俺は60歳だけど新聞読めるから老眼じゃない」と言っている方がいらっしゃるとします。

最初に見て頂いた表と比べると今回は調節できる幅が狭くなっている老視のイメージです。
正視の方は遠くが見える分だけ近くが見えづらいのに対して近視の方は近くは見えるけどそもそも遠くが見えないという状態です。
「いや遠くは眼鏡を掛ければ見える!」と反論されることがごく稀にありますが、逆に正視の方は「眼鏡を掛ければ近くが見えます」
眼鏡を作るうえで屈折状態を知る検査も重要ですが
眼鏡を作るうえで屈折状態を知る検査ももちろん重要ですが、眼鏡屋はお客様の眼の状態を含めて使用環境を知ることが重要。
眼鏡を作ったことがある方はご存知かと思いますが最初に機械を覗いて道路の先に気球が浮かんでる写真がぼやけたりしてるのを見るのありますよね?


これはオートレフラクトメーターといってどのような屈折状態があるのか簡易的に測る機械です
あくまで「簡易的に」測るものです
画面がぼやけたりはっきり見えたりするのは調節力を使わない状態にするためで機械は頑張って遠くを見ている時の状態を測ろうとしていますが、「人間は箱の中を見てる」「近くの写真を見てる」と言う感覚から機械の思惑通りに検査できないこともざらにあります。
この機械で出た数値は信用してはダメなんです。
いや確かに検出精度は上がってはいると思いますがどんなに機械が正確に測れたとしても人間の調節力がどのくらい入っているかまでは機械は検出できないのでやはりレンズをカチャカチャと変えて検査することは重要です。
そうすると5分くらいで検査を完了することは不可能なのでそれなりの時間がかかります。
そして慎重に測ったデータをもとにお客様の生活環境や生活サイクル、時には見る時の癖なども見極めながら見え方の提案をし出来上がるのが眼鏡なんです。
生活様式の変化で見えてきたもの
今回のコロナ禍は想像を超えるダメージを皆さんも私も受けていると思いますが、この「生活様式の変化」によって今まで見えなかったものが見えてきている事実もあるかと思います。
業種によってはわざわざ毎日会社に出社しなくても良いんじゃないか?とか逆に社内でのコミュニケーションが仕事を進めるうえで重要だったとか
物を見るという事に対しても本質に気づくきっかけになってくれたらいいなぁと眼鏡屋的には思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
