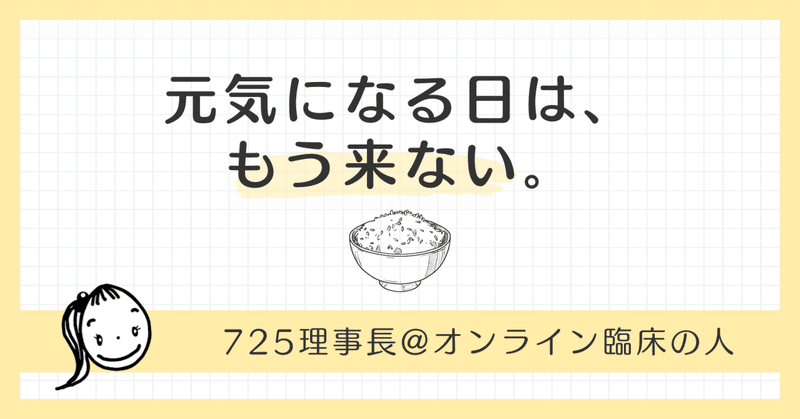
元気になる日は、もう来ない。
人はもちろん亡くなる。必ず、亡くなる。
「いつ」かは選べないし、避けられない。
忘れられない患者さんがいる。
病院と訪問看護ステーションの経験の中で数多くの患者さんと出会ってきたけれど、とても後悔していることがある。
とてもとても、後悔していることがある。
ある夏の日、市内でもかなり遠い地域の在宅医の先生から、勤務先の訪問看護ステーションに電話がかかってきた。
「お宅の訪問看護にはST(言語聴覚士)がいるんだよね?ちょっとうちの患者さんを見てほしいんだ。」
そう言って、訪問が決まったのが杉田さん(仮名)だった。
末期の肺がんだという。
そのときまで私はターミナルの患者さんを担当したことが無かった。けれど主治医の先生からも「昔からの知り合いでね。奥さんも最後まで食べさせてあげたいと言っている。よろしく。」と言われ、不安を隠しながら訪問したのを覚えている。
「初めまして。」
市内でも古い住宅の多いエリアで、駐車スペースもないお家だった。近隣の駐車スペースを借りて訪問した。
杉田さんの家もとても古く、築何十年だろうかと思いながら室内に上がった。介護生活のため、一部改修していたということで、室内はリフォームのあとがあり、フローリングも新しかった。
ベッドに横たわる杉田さんは、細身で優しそうな顔をしていた。肺がんということもあり、息苦しいのだろう。酸素のチューブを鼻につけていた。
奥様もとても優しく「やっと食事の先生が来た。食べさせてあげられる。」と喜ばれ、台所にある様々な調理道具を私に見せてくれた。
お粥の作り方から始まり、食べやすいものの調整。本人の体調を確認しながら、食欲に応じたメニューなど、家族と相談しながら毎週訪問した。
ある日のこと、普段通り訪問し、喉の状態、口腔ケアなどを行いながら奥様と献立の確認などを行っていた。
何がきっかけだったかは覚えていないが、ふと話題の流れで私は杉田さんにこう聞いた
「元気になったら何食べたいですか?」
末期の肺がんとはいえ、本人は余命宣告を受けていなかった。だからこそ、未来への活力をと思って、ふとそんな質問をした。
その瞬間、杉田さんの表情が曇った。
なんとも形容しがたいが、明らかに自分の人生の終わりが近いことを知っている表情だった。
あのときのなんとも言えな杉田さんの表情が、未だに脳裏に焼き付いている。
言ってはいけないことを言った。
私がそう感じた直後、杉田さんはすぐに表情が戻り、普段どおり穏やかに会話を続けた。温かい人だな、と思った。
会話の中では時に、癌になった悔しさを口にすることもあったが、奥様の料理をしっかりと食べ、その後も毎週の訪問を受け入れてくれた。
「今週はこれやっておいたよ」
自主トレーニングもやってくれていた。息苦しいはずなのに、自分にできることはしようと努力されているのが日々感じられた。
ある朝、職場に着くと杉田さんのご家族から電話があった。
夜、眠るように息を引き取ったという。
往診がない時間帯に
訪問スタッフが来ない時間帯に
家族しかいない時間帯に
すっと家族に見守られて眠りについたとのことだった。
杉田さんへの仕事で、私は何もできなかったと思っていたし、いまでも情けない訪問だったなと、思い出すたびに恥ずかしくなる。
けれど、いまもこうして私の記憶に色濃く残っているということは、私に専門職としての「何か」を教え続けてくれているのだと思う。
そしてそのとき指示書をいただいた在宅医の先生には、その後も大変お世話になったし、独立後も私を応援してくれていることからも、杉田さんのつないでくれたご縁で、いまも走れているのだなと思う。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
