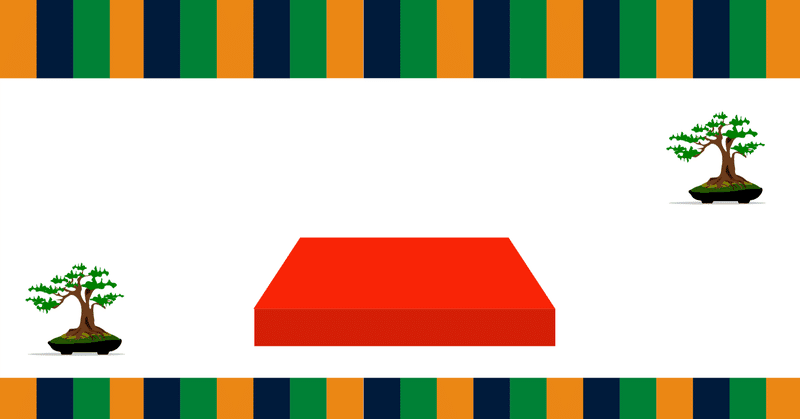
米津「死神」MVに思うこと/落語ファンのヒトリゴト
先日、『米津玄師「死神」にちょっと驚くw』なんて記事を書いたんですが、日を置かずにミュージックビデオが公開されましたね。
<米津玄師「死神」オフィシャルMV>
これがまたシャレてんだ。
誰やらわからぬ男のおぼつかない足取りの映像から暗転。
「新宿末廣亭」の高座にふらりと現れた噺家は、米津ならぬ「幻師」なのでしょう。枕もなしに冒頭から本ネタぶっこみの風情で羽織をさらりと脱いでしまう。これだけでも落語ファンにとっては尋常じゃない出来事です。
羽織を纏って高座に上がれるのは「二つ目」以上と決まっています。その上「死神」というネタは、主人公が死んでしまうサゲのため前のめりに倒れるしぐさで終わることが多く、演じ終えた後には幕が下りるのが普通。つまりはその日の演目の最後の大トリでやらないと格好がつかないネタなのです。
それを客の数もそろっていない状態で、何の前触れもなく本ネタで演じるのは狂気の沙汰。百歩譲っても、相当なケンカ腰というよりありません。
気にする風もなく演じ続ける「幻師」が見せるのは右手を頬に当てる特徴的なしぐさ。往年の立川談志師匠を思わせる部分でもあり、この「死神」が談志流のサゲを迎えることへの予兆とも取れます。
耐えかねて次々出てゆく客たち。その一方、引き戸ガラリで現れたのはフラミンゴよろしく、千鳥足でふらついていた冒頭の男。
よれよれシャツに黒ネクタイ。ヌっと高座に歩み寄ると「幻師」の右手の炎をフッと吹き消し、世界は暗転。
うーむ。粋ですね。尺が短いのがスッキリしててまたいい。
でもってこのMVを見ながらいろいろ考えました。
米津さんは自分の楽曲の解釈についてあまり明言しないように思います。あれこれ言ってしまうことでその解釈が固定化するのを恐れている、というか、聞く人に自分流の解釈の余地を残してくれている。あるいは、隠したメッセージを埋め込んでいる、などいろいろ受け止めができますね。
ちなみに「Flamingo」のときはインタビューで「都都逸や島唄などを参考にした」などと言っているのですが、都都逸をちょっぴり知っているだけの私でもこの説明はインタビュー用のフェイクであることは容易にわかります。
都都逸は、愛し恋しを唄った小粋な「江戸のラブソング」。「Flamingo」のようなシニカルで自虐的な嘆き歌とはテイストを異にする楽曲です。歌詞を見て、「ステージ」という言葉が気になりました。なぜ「舞台」ではなく「ステージ」という言葉をカタカナのまま残したのか。そのあたりに隠されたメッセージのヒントがあるような気がします。
おっと「死神」の話に戻ります。
私が思うこの曲のヒントは「最後に炎を吹き消す死神」の存在かなと。ひょんなことからチート的な力を得た誰かが、死神の逆鱗に触れ、命の炎を吹き消される。・・・面白くなるところだったのに。
思い浮かんだのは芸能界でまだまだこれから、という矢先に鬼籍に入ってしまったあんな方やそんな方の顔ですが・・・ま、どなたの顔かはご想像にお任せします。
そういえば、直近では「文春砲」という名の死神に、炎を吹き消されそうな人がいるとかいないとか。
有名人も楽じゃありませんね。くわばらくわばら・・・。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
