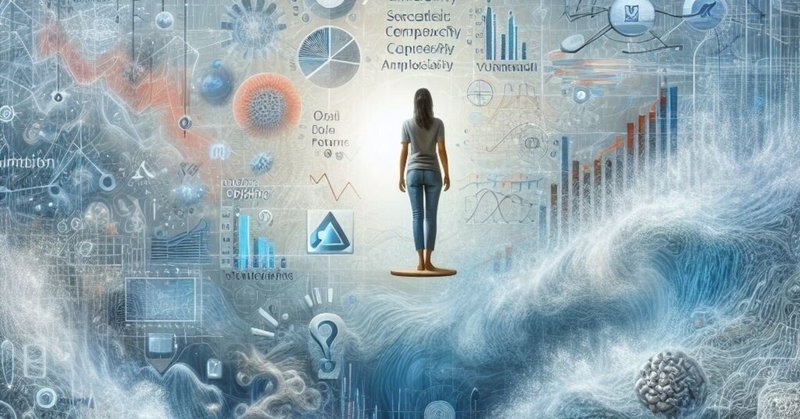
「立地」は変わる、「立地の見方」は変わらない
ㅤ
今の時代は「VUCA」の時代と呼ばれています。
ㅤ
「VUCA」とは、
ㅤ
・不安定で
・不確実で
・複雑で
・不明確
ㅤ
ということです。
ㅤ
ㅤ
そんな時代にあると、様々な物事が変化していくわけなんですが・・・・だからよく、「時代遅れ」として、それまで注目されていたものが急速に価値を失うようなことがよくあります。
ㅤ
ㅤ
ㅤ
ショップビジネスの世界でも・・・・
ㅤ
そうやって社会のニーズが高速で移り変わっていくため、風潮として、「立地を吟味したところで社会は変化していくんだから、その変化に対応する業態を考える方が大事」みたいなところがあります。
ㅤ
ㅤ
立地を分析して、その時は売上げが取れると思って出店しても、状況が変わったら売れなくなってしまう。
だったら、立地分析に時間をかけるのはナンセンスなのではないか、ということですね。
ㅤ
確かに。
その気持ちは分からなくはないのです。
ㅤ
ㅤ
ㅤ
ㅤ
ただ・・・・
ㅤ
「変化の激しい時代だから立地を考えるよりも業態(中身)を考えよう」
ㅤ
というようなことを言っている人たちは、きっと元々、大して立地のことを真剣に考えていなかったんだと思います。
ㅤ
ㅤ
元々、大して精度の高くない売上予測をやっていたり、立地についての知見が浅かったりしたから、「その程度の精度だったら時間をかける価値はない」っていうのは、それはそうでしょうね。
ㅤ
ㅤ
ㅤ
ㅤ
ㅤ
ㅤ
ㅤ
ㅤ
ㅤ
社会の変化によって、「立地の状況」は変わります。
ㅤ
でも、本質的なところ、原理原則は、変わらないのです。
ㅤ
ㅤ
人は、「なるべく便利な(アクセスしやすい)場所」に多く集まる習性がありますし、目につかない店より目につきやすい店に入るのは自明の理ですから。
ㅤ
ㅤ
社会の変化によって、「人が集まる場所」や「集まる度合い」みたいなものは、変わるかもしれません。
けれども、「人が集まる場所に近い方が売上げが高くなる」という原理原則は、変化することがありません。
ㅤ
ㅤ
駅とか、商業施設とか交差点とか、そういう人が集まるポイントのこと、立地用語で「TG」って言うんですけどね。
ㅤ
TGの規模や位置、質は変化するんですけれども、「TGに近い方が売れる」っていうのは、コロナ禍になろうとも変わること無い現象でした。
ㅤ
ㅤ
しかしながら、企業がこの変化の時代に立地を見ようとしなくなるのは・・・・
ㅤ
そもそも、例えばこの「TGの捉え方」などのような知識を知らないから、だと思います。
ㅤ
ㅤ
所詮、「駅前が売れる」というレベルでしかTGを捉えてこなかった企業は、駅から人が減ったら、「立地なんてアテにならない!」って言い出すんでしょう。
ㅤ
人々が駅を使わなくなっても、それは単に「TGが変化した」というだけですので、じゃあ他にどんなTGがあるかを考えればいいわけです。
ㅤ
電車を使うのをやめてバスを使う人が増えたなら、バス停が新たなTGになっているかもしれない。
自転車を使う人が増えたなら、自転車が通りやすい道路の大きな交差点がTGになっているかもしれない。
ㅤ
そんなふうに見ていけばいいだけの話です。
ㅤ
ㅤ
ㅤ
ㅤ
ㅤ
ㅤ
立地をしっかり考えてこなかった企業は、社内に、立地を分析できる人材を持っていません。
ㅤ
これね、数百店舗を展開しているチェーンでも、あるあるなんです。
ㅤ
社長の勘と経験で出店してきたとか、十何年も前の古いシステムを未だに使っているだとか、システムはあるけどその中身を理解できる人がいないだとか、そんなことばっかりです。
ㅤ
ㅤ
みんな、「なんとなく」で立地を見てるんですよね。
ㅤ
ㅤ
だから、社会の変化に耐えられないんです。
ㅤ
ㅤ
ㅤ
ㅤ
ㅤ
立地を分析するためのシステムって、ただでさえ生ものです。
“常に”メンテナンスして、ブラッシュアップし続けなければいけません。
ㅤ
僕らプロですら、一度作ったシステム(売上予測モデル)を、メンテナンスなしでずっと使い続けることなんかできません。
ㅤ
一昔前までなら、2年くらいは精度を保つことができましたが、おそらく今はもう無理でしょうね。
ㅤ
3~6ヶ月に1度は大幅メンテナンスしなければ、使い物になりません。
ㅤ
でも僕らは、立地のノウハウをしっかり持っているから、そのメンテナンスを難なく行うことができ、システムを時代の流れに対応させていくことができるのです。
ㅤ
ㅤ
ㅤ
ㅤ
ㅤ
ㅤ
先述のTGの話だけではなく・・・・
ㅤ
いっぱいある、立地の原理原則、これを理解していたら、そういうのはちゃんとできることです。
ㅤ
ㅤ
ㅤ
勿論、中身(業態)を考えることは、とても重要なことだと思います。
ㅤ
業態を時代に合わせて転換させていくことにより、お客さんのニーズをしっかり最先端で掴んでいこうとする努力自体は、素晴らしいことです。
ㅤ
ㅤ
けれども、結局それって、「やり方」「ソフトウェア」の問題なんですよね。
ㅤ
土台となる「在り方」「ハードウェア」の部分がしっかりしていなかったら、ただの付け焼き刃、苦肉の策、自転車操業的で終わりのない苦難になってしまいます。
ㅤ
ㅤ
ハウツーなんか時代が変われば変わります。
それに適応していくことは大事なわけですが、その前に自分自身の在り方を整えておかなかったら、人生迷子になっちゃいますよね。
ㅤ
個人で言えることは、それそのまま企業でも言えることです。
ㅤ
ㅤ
ㅤ
ㅤ
ㅤ
ㅤ
ㅤ
ㅤ
ㅤ
VUCAの時代と言っても・・・・
ㅤ
不安定なのは、
不確実なのは、
複雑なのは、
不明確なのは、
ㅤ
いつでも、「立地そのものの状況」の方です。
ㅤ
立地をどう読み解くかという、原理原則の方は、時代がどう変わっていこうとも変化することのない、
ㅤ
安定して、
確実で、
シンプルで、
明確で、
ㅤ
企業にとって重要な指針になるべきものです。
ㅤ
ㅤ
ㅤ
ㅤ
時代の変化に対応するために、立地を吟味している余裕がなくなった、わけではないのです。
ㅤ
今まで立地のことをしっかり考えてこなかったがために、「立地を考えるハードルが上がってしまった」だけなんですよね。
ㅤ
昔なら、一度システムを作れば2年くらい持ったものが、もしくは10数年メンテナンスなしでも大丈夫っぽく見えていたものが、崩壊してしまったわけですから。
ㅤ
数年に1度外注すれば良かったと考えていたような企業は、苦労するでしょうね。
同じクオリティを出すだけでも、3ヶ月に1度の外注をしなければならない・・・・って思ったら、それは現実的ではありません。
ㅤ
ㅤ
でも、立地を分析できる人材を1から社内に育てようと思っても、これはどうしても時間のかかるものですから・・・・
(毎日立地を考えている仕事に就いた僕ですら、素人からそれなりの知見を出せるようになるまで、1~2年かかったんですよw)
ㅤ
ピンチに陥ってから、それだけの時間と労力をかけることも適わない。
ㅤ
ㅤ
ㅤ
・・・・そういう企業の行く先は・・・・どうなることやら。
ㅤ
ㅤ
ㅤ
ㅤ
ㅤ
個人の間でも格差が開いて二極化していくように、企業もきっとそんなふうになっていきます。
ㅤ
「在り方」を整えて着実に歩を進められる企業や、そうでなければ元々圧倒的なパワーを持ってて在り方とか考える必要ない(ように見える)企業ばかりが台頭し、
ㅤ
目先の利益に踊らされたり、目の前の現実に対応することばかりに一杯一杯だったりする企業は、どんどん衰退していくことになると思います。
ㅤ
ㅤ
さぁ、ここが分水嶺。
ㅤ
ㅤ
生き残るべき企業が、生き残るべくして生き残る時代になっていく。
ㅤ
ㅤ
ㅤ
ㅤ
ㅤ
VUCAの時代、だからこそ、「在り方」が大切なのは、もはや個人レベルでは、飽きるほどに言われていること。
ㅤ
それでもあっちゃこっちゃの小手先のスキルやノウハウに溺れる人たちが後を絶たず、墜ちていくのは、もはや仕方のないこと。
ㅤ
ㅤ
変わらない原理原則をベースに、店舗展開をしていける企業こそが、生き残れる時代に変わっていくという、ただそれだけのこと。
ㅤ
ㅤ
ㅤ
#お店の立地
#お店の立地コンサル
ㅤ
#在り方の時代になったら
#結局はパワーがある人が強いよ
#在り方を整える余裕があるからね
ㅤ
#目の前のことに追われている人は
#いつまでも本当に重要なことに手を付けられない
#そんな感じでいる間に
#どんどん取り返しのつかないことになっていく
ㅤ
#個人も企業も
#勝負どころですよ今が
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
