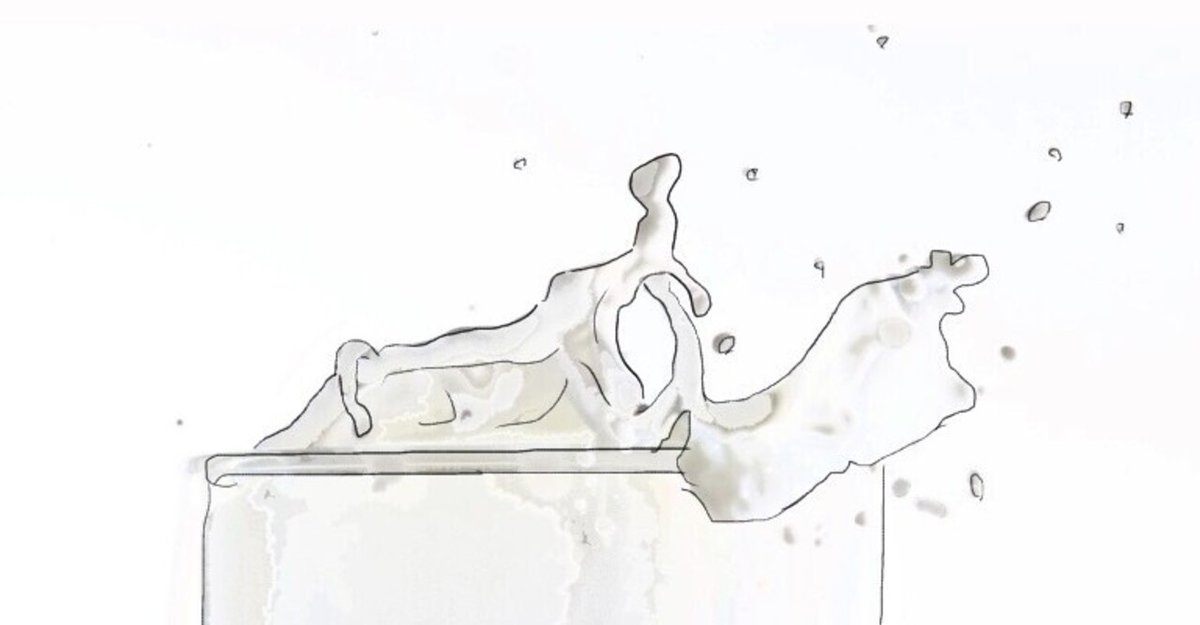
牛乳=カルシウムが嘘と言われている理由【失うもののほうが多い?!】
こんにちは。菜食トレーニーおまめです。
本日はタイトルにもある通り牛乳のカルシウムについて触れていこうと思います!
多くの人が牛乳には多くのカルシウムが含まれているからカルシウムのための選択肢として牛乳を摂取している人は多くいると思います。私も「カルシウムと言えば牛乳!」と思っていました。だって小学生の頃から牛乳を飲まないと身長が伸びない、牛乳を飲んでカルシウムを摂取しようと学校の先生から言われていましたからね。
しかし最近では牛乳について多くの人が疑問を持っているように感じます。その中でも牛乳と言えばカルシウムという言葉に疑問を持っている人は多いのではないでしょうか?
そこで今回は「牛乳=カルシウムがなんで嘘なんだろう」「牛乳を飲んでも骨を強くならないって聞くけどなんで?」「牛乳以外にどんな食材でカルシウムを摂取すればいいの?」
こういった疑問に答えます!
こちらの記事は論文や研究報告も参考にして書かせていただいてますので興味がある方は参考研究としてURLも貼っておくので見てみてください。
それでは解説をしていきます!
↓本記事はこちら↓
1⃣牛乳=カルシウムが嘘と言われている理由~牛乳を飲んでも骨は強くならない?!~
結論から言うと牛乳を飲んでも骨は強くならない、牛乳=カルシウムという考え方は古いです。牛乳を飲むことでカルシウムを摂取して骨を強くするといった理由やなんとなくカルシウムが摂れるから牛乳を飲むといった人は多くいると思いますが実は牛乳=カルシウムという考え方は少し古いのかもしれません。つまり牛乳を飲むことが効率よくカルシウムを摂取することではないということです。
⬇️理由その①⬇️
効率のいいカルシウムの吸収にはリンとの比率がとても重要です。(理想はカルシウム1.5~2.0:リン1)リンが多いと体内のカルシウムと結合してしまい、体内に吸収させるはずのカルシウムが吸収されずに体外に排出されてしまう又はカルシウムの体内への吸収を阻害されてしまうのです。結果的に理想的な比率のバランスが崩れててしまいカルシウムの吸収が減少したり吸収の妨げになってしまいます。
牛乳のカルシウムとリンの比率は1:1なので効率的なカルシウムの吸収が難しく、反対に牛乳にはリンが多く含まれるので体内のカルシウムを排出してしまう可能性があります。つまり牛乳のカルシウムで骨が強くなることもなければ牛乳で得られるものよりも失うもののほうが多くなる場合があるということです。
なかには牛乳のカルシウムとリンの比率は適切ではないのかという意見もあると思いますが、現代の人は加工食品やジュース、ジャンクフードなどの摂取によってリンを過剰摂取している傾向があります。そのためどちらにしてもカルシウムの効率的な摂取、吸収を望んでいるのであれば牛乳ではなくてもいいと思います。
⬇️理由その②⬇️
牛乳にはカルシウムだけではなく他の栄養素としてタンパク質も多く含まれています。実は乳中のタンパク質含有量が高いこともカルシウムバランスの乱れの一つの原因となっていて、乳中のタンパク質を多く摂取すると体内が酸性に傾き骨中のカルシウムを分解してしまいます。
リンやタンパク質といった他の栄養源と組み合わせて消費される乳製品が多いほど骨粗しょう症のリスクが高くなることが研究で報告されています。そのため普段から動物性たんぱく質を摂取している人は植物性たんぱく質のみを摂取している人よりも骨量減少率が有意に高いこともわかっています。(動物性たんぱく質にはリンやタンパク質が多く含まれているから)。
つまり骨を強くするため、骨粗しょう症を予防するために飲んでいた牛乳が予防されるのではなくリスクを高めてしまう可能性があるということも知っておかなければなりません。
私自身は牛乳=カルシウムというのはカルシウムを含む食材が牛乳しか知らなかったから牛乳を摂取していただけという経験があるのでほとんどの方もそうではないでしょうか?カルシウムを効率的に摂取、吸収したいという場合は牛乳ではなく他の食材から摂取するのもカルシウムを得るための一つの手段なのではないでしょうか。
この2つの理由が牛乳=カルシウムではない、そして決して牛乳を飲んでも骨を強くできるわけではないということです。
2⃣カルシウムが豊富な食材7選
~カルシウムの1日の目安量~
カルシウムは人間の身体の様々なところに存在しています。ミネラルの中でも最も人間の体内に多く存在していると言われていますのでやはり生命を維持するためにも必要不可欠な栄養ですね! では実際に必要な1日の目安量はこちらです。
▪️男性の場合:カルシウムの食事摂取基準推奨量 約800㎎(mg/日
▪️女性の場合:カルシウムの食事摂取基準推奨量 約700㎎(mg/日)
となっています。
日常的なカルシウムの排出を考えると700㎎~800㎎以上摂取しても問題ないと思います。厚生労働省がは公表しているカルシウムの許容上限摂取量は約2500㎎ですので取りすぎることはないと思います。
⬇️カルシウムが豊富な食材⬇️
①ケール
100g当たりの含有量:220㎎
ケールは青汁の原料にも使用されることが多いためスーパーフードとしても世間では知られています。
カルシウムだけでなくケールには多くの食物繊維が含まれており、 その量はレタスの約3.36倍と言われています。
②モロヘイヤ
100g当たりの含有量:260㎎
モロヘイヤには細胞老化のもととなる活性酸素の働きを抑える抗酸化作用のビタミンA、ビタミンC、ビタミンEも豊富に含まれています。高抗酸化ビタミンの含有量は野菜の中でもトップクラスだと思うのでアンチエイジング効果や代謝サポート、疲労物質の除去も期待できます。
③小松菜
100g当たりの含有量:170㎎
カルシウムだけでなく小松菜には鉄分も豊富な野菜としても知られていて、ゆでた葉の100g中の鉄分含有量は2.1mgです。
食物繊維も豊富に含まれているで水溶性食物繊維、不溶性食物繊維とどちらもバランスよく摂取できる優秀な野菜です。
④豆腐
100g当たりの含有量:120㎎
豆腐は皆さんも知っている通りタンパク質も豊富です。木綿で100g当たり6.6gで絹100g当たり4.9gなのでカルシウムだけでなくタンパク質も一緒に摂取できる点は嬉しいですよね。
➄ひよこ豆
100g当たりの含有量:100㎎
ひよこ豆は私自身おススメの食材です!カルシウムだけでなくタンパク質も豊富で100g当たり20gでその他栄養素ビタミンやカルシウム以外のミネラルである鉄やカリウムも豊富に含まれているので女性であれば貧血やむくみ改善にも効果的ですね。
⑥アーモンド
100g当たりの含有量:230㎎
他の食材と比べてカロリーは少し高めですが、アーモンドには良質な脂質と言われるオレイン酸やリノール酸も含まれています。これらは植物油や魚にも多く含まれる不飽和脂肪酸で体内で作り出すことができないので積極的な摂取が必要な栄養素です。ほかにも抗酸化力の高いビタミンEが含まれていて100gあたり29.8mgなのでトップクラスの含有量ですのでアンチエイジングにはとても効果的です。
⑦昆布
100g当たりの含有量:430㎎
昆布にもカルシウムだけでなく多くの栄養素が含まれています。その中でもでも海藻類と言えば食物繊維ですよね!昆布には普段摂取しづらい水溶性食物繊維が豊富に含まれているので野菜だけでカルシウムを摂取するのではなく昆布などの海藻類からもカルシウムを摂取することで普段取りずらい水溶性食物繊維も一緒に摂取できます。
3⃣明日から実践できるまとめ
本記事を簡単にまとめると「牛乳=カルシウムではない」「牛乳以外の食材でもカルシウムは摂れる」「牛乳で骨は強くならない、骨粗しょう症の予防にならない可能性がある」ということです。
そして明日からの簡単にできる実践の一つを紹介します!
ずばり【カルシウムが豊富な食材を調べて、普段の食事に早速取り入れる】です!
自分で調べて自分で実践をすればどんな食材にカルシウムが豊富なのかを知ることができ、普段の食事に取り入れることでカルシウムをより効率よく摂取できると思います。
結局は疑問に思って、調べて、実践することが大切ですよね。人間の体は食べたもので構成されているので、健康の維持も向上も普段の食事次第なので是非実践してみてください!
それではまた次回!!
↓参考研究はこちら↓
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9224182/ https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11124760/https://link.springer.com/article/10.1007/s12291-015-0524-y#:~:text=By%20contrast%2C%20human%20milk%20contains,%3A1%E2%80%931.7%3A1.
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
