
【年間ベスト】2020年の個人的な40枚
2020年ももうすぐ終わり(本当にあっという間だった)、今年も年間ベストをまとめたいと思います。昨年同様、お気に入り(20枚) + TOP20の構成です。
→【年間ベスト】2019年の個人的な40枚
毎度ながら、何かのシーンを追ったり、この1年を解釈する様なものではなく、単に自分の好みや見方、偶然の出会いをまとめた記録・日記です。読んでみて、もし「コレ聴いてみようか」「聴き直してみるか」ってなったりすればこれ幸い。
※アルバム画像を押すと、AmazonかBandcampのリンクにとべます。
……………………………………………………………………
お気に入り

「お気に入り」は順不同ですが、ジャンルでなく、個人のフィーリングで適当に分類しています。「この人はこの音楽についてこんな枠組みで聴く、並べるんだ」くらいのノリで捉えてもらえれば(コレはXではないという揶揄的な意図も一切ないです)。プレイリスト片手にどうぞ。
■Pops

Tame Impala 『The Slow Rush』
2010年代を彩ったオーストラリアのモダン・サイケの雄、グラミー受賞の前作から5年ぶり4th。
これまで上手くノれなかったのですが、本作はまずサウンドデザインの快楽がすさまじい。スピーカーから空間に広がる、このビートと音の空気感が最高。間違いなく当代最高峰のプロダクションのひとつだし、「On Track」「It Might Be Time」あたりのドラムの鳴りは往年のFlaming Lipsに並ぶ。ダンスフロアにドリームポップが降り注いでいるような陽光サイケデリア、新世代のディスコ。逃避というか避暑地。
Pickup:One More Year、Breathe Deeper、On Track、It Might Be Time

J Hus 『Big Conspiracy』
UKのラッパー、SSWの2nd。詳しくはこの記事が参考になります。
たしか宇多田ヒカル絡み、「低音の出が……」みたいな話題から知りました。この辺りは自分の耳がダブを通過したことで魅力が分かるようになってきたかも。多ジャンルを巻き込むことを美学とするUKのRapとして、グライム、アフロビート、ヒップホップ、ガレージ、ジャングル、そしてR&Bとまとめあげたのが本作の素晴らしさかと。
Pickup:Big Conspiracy、Helicopter、No Denying、One and Only
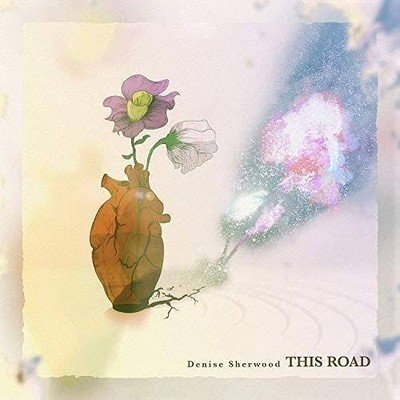
Denise Sherwood 『This Road』
ダブの語が出たところで、UKダブの長Adrian Sherwoodの娘さんのデビュー作。ビートと湿った曲感覚には「トリップ・ホップ」を思い出しますが、ヒップホップよりは「レゲエ」に忠実な楽曲が多い。そうしたジャンル間の系譜と、その間にあるものを浮かびだす作品としても聴ける。「ダブ」ひとつとっても、ジャマイカとUKでは感覚が異なるんですよね。
ベストトラックは「Ghost Heart」。低音の響かせ方、カットアップして構築したベースライン、スパイス的なダブ処理。物憂げな旋律の魅力もさることながら、多方面から豊かさを注いだ見事な3分ポップスです。
Pickup:Let Me In、Ghost Heart、Fairy Tales

Four tet 『Sixteen Oceans』
UKはエレクトロニカの雄(フォークトロニカの祖)、活動20年をこえついに10th。
最近のFour tetは「Pops」に括りたくなります(別に悪い意味じゃなく)。簡素に絞ったリズムトラックから、もはや"節"と化した音色とメロディがリフレインし、4~5分で収束するFour tet流ポップス。それはマンネリではなく、その人の達した境地と旨味を、あらゆる角度から照らす感じで……例えばLed Zeppelinのバンドとしての到達点の記録に『Presence』がありますが、そんな作品を毎回リリースしてくれています。ファン必携、入門ここから、20年こえ尚絶好調!な快作。
Pickup:School、Baby、Love Salad、Insect Near Piha Beach
■Groove
「グルーヴ」というと大げさですが、なんとなくリズム重視で聴いた作品たち。

Beynelmilan 『Yeralti Oyun Havalari』
Spotify「Global Funk」プレイリストより。謎の存在ですが、Facebookによると「ファンキーなグルーヴがトルコ民謡を蘇らせている。70年代アナトリアのロック/ポップスが好きなあなたのための作品」。ディスクユニオンのカテゴリによると「辺境」「アラブ」「ワールド」。なんなんだよ。
トルコ民謡を、往年のヒップホップ的なドラムループで無理やりこじつけた、どこか胡散臭い「似非ワールド」作として最高です。音もリズムも軽めなので余計そう感じる。ひょっとしたらSaultの横におけたり、Dos Monosのラップが聞こえてくる……かも。本作をクラブ仕様にしてフジの深夜で40分かければ伝説になれるよ多分。普段聴かないスケールのオンパレードにクラクラしてくる、酔っぱらってたれ流し推奨奴。
Pickup:Hey Onbesli、Kaslarin Karasina、Burcak Tarlasi

Hailu Mergia 『Yene Mircha』
これもプレイリスト「Global Funk」から。エチオピア・ジャズ界の重鎮らしい。たしかにジャケからして貫禄がすごそう(適当)。
内容はジャズ・ファンクで、ドラムの音が素晴らしいです。特に「Yene Mircha」のファンキーなリズム、ギターソロとベースラインの絡み、ハイハットとライドの16分3連のフィルの音の分離、最高。「Bayne Lay Yilhedal」はエチオピア流(?)レゲェ・ダブで、バンドメンバー各位のズレがたまらない。この辺の好み、完全にフジロックのHEAVENステージにハマってからだな。今年も行きたかった……。
Pickup:Yene Mircha、Bayne Lay Yilhedal、Shemendefer
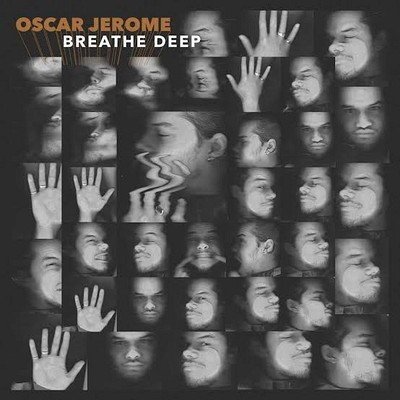
Oscar Jerome 『Breathe Deep』
南ロンドン・ジャズ・シーンの新星、ネクストTom Mischとも評される人物のデビューアルバム。 諸作にも登場している才人で、ユニオンの記事が詳しいです。ヒップホップとソウルが駆け落ちして「ネオソウル」になったころの感覚が、スタイリッシュに現在に再誕した感じがあります。tr2, 3だけでそのセンスは完全に理解る。Tom Mischがリゾートなら、こちらはストリートのクールさか。
Pickup:Sun For Someone、Give Back What U Stole From Me、Fkn Happy Days 'N' That
ほかには、低音への意識が心地よかったKan Sano『Susannna』、グローバルなリズムを楽しませてくれたKeleketla!『ST』、ブルーズに寄って、ft. Marcus Kingも絶品だったG. Love『The Juice』あたりも抜群でした。
■Indie Rock
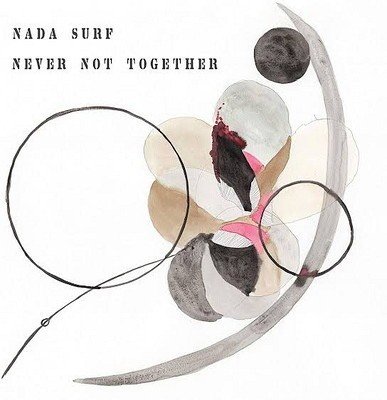
Nada Surf 『Never Not Together』
NYブルックリンの、Death Cab for Cutieとも関わりが深いインディロックバンド。活動30年弱の大ベテランにして9th。今年最もグッドソングが詰まってる1枚。風通しのいい録音、パワーポップとカントリー由来のタフなバンドサウンド、愛嬌あるシンセ。完璧だ……。アウトロでJ. Mascis(Dinosaur Jr)のギターソロが鳴り響いてきそうな「Come Get Me」は、つまりはパワーポップの時代を通過して生まれたNeil Youngの子供。
Pickup:So Much Love、Come Get Me、Something I Should Do 、Crowded Star

Wyatt Smith 『Maple』
カリフォルニア拠点のSSWデビュー作。「ポップ」の語の前に「ベッドルーム」や「ドリーム」がつきそうな霞がかった音。その頂点にElliott Smithがいるタイプの音楽。インディにありがちな量産型、いやいや取りこぼすべきでない実りある一作でした。こういう、好きな人からすれば聴いた瞬間「あぁ、良いやつ」で終わりがちな作品について、改めてちゃんと書きたいなと来年の抱負。なので今年はこの1枚にこの言葉を投げます、「聴けば分かる」。
Pickup:ぜんぶ
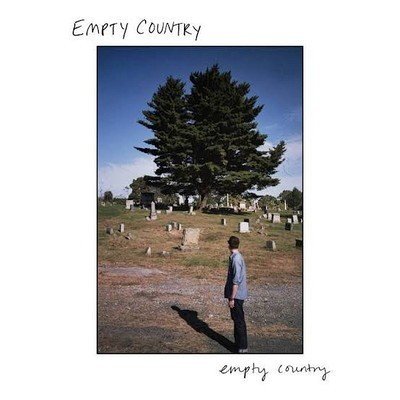
Empty Country 『Empty Country』
00年代末から10年代半ばに、あるバンドがいた。そのバンドは、Built to SpillやDeath Cab for Cutieに連なる方向の「インディ・ロック」に根差しつつ、世代的にエモやシューゲイザーを通過した音の景色とスケールを持っていた。その名前はYuckらとともに一部リスナーに刻まれてるはず。Cymbals Eat Guitars。迷走していた解散作から4年、フロントマンのソロ作が到着しました。憑物が落ちたようにストレートなインディ・ロック(相変わらず細部はグシャグシャだけども)。静と動のエモ。全く変わってないマイナスのメンタリティと、その音への発露。すごく良い。カムバック!!
Pickup:Martin、Diamond、Ultrasound、Swim
ほかには、歪みの美しさを感じさせたPure X『ST』、今最も必要とされるパンクだったJeff Rosenstock『No Dream』、Bob Mould『Blue Hearts』、バンドの気持ち良さが詰まったRatboys『Printer’s Devil』も良かった……あとはそう、Ratboysに対してインディの面倒くささが詰まったCar Seat Headrest『Making a Door Less Open』も忘れ難い。
■Club / Electronic

Andrea 『Ritorno』
イタリア出身、テクノ・レーベル<Ilian Tape>からのデビューアルバム。IDMやブレイクビーツを思い起こさせる硬質なリズムトラックが魅力的な1枚。詳しくはこちらの記事を。
こういう音楽、人によって「打ち込みの感じ」「メロウとリズムの比重」とか観点がありますが、本作がピッタシ自分にハマった。メロに寄りすぎずビートで歌ってくれる感覚……(Bonoboまでいくと完全にコード進行があってメロウすぎるとか……いや半周してポストロックだなと結局好き……)。Floating Pointsも照らすUKダブステップ「LS September」がベストトラック。Skee Mask『Compro』といい、毎年良作が出ますね。
Pickup:SKYLN、LS September、Drumzzy

Speaker Music 『Black Nationalist Sonic Weaponry』
Andreaに対して、「リズム」に全振りしてるのが本作。
ハードコアと言ってもいい電子のプロテスト・ミュージック、Bass MusicやDrum and bassに、Autechre的な音感覚でもって即興演奏を繰り広げたような鋭いリズムアプローチ。踊ることを拒否するリズム、情感を排した音の羅列、その上に乗せられたBlack Lives Matterに連なるメッセージは、ただならぬ切迫感をもってこちらの耳を捉える。本年度屈指の、聴き手の神経を尖らせる強烈な"ミュージック"。一聴推奨。詳しくはブログにて!
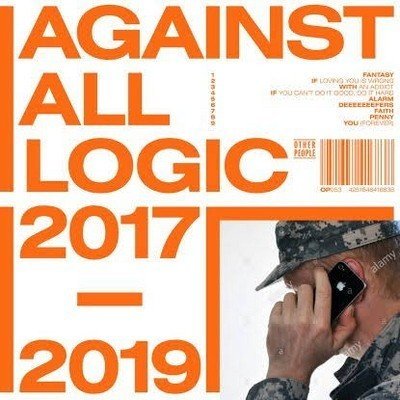
Against All Logic 『2017 – 2019』
Nicolas Jaarの変名2nd。変名とはいえ、Spotifyリスナーを見ると、Nicolas Jaarが96万、AALも56万と、すげぇなぁ。
『2012 - 2017』は往年のクラブアンセム的な傑作でしたが、これは何だろう……。前作よりベースミュージックに強く影響を受けた曲が多いのは分かる。ただ、クラブで踊らせるための音楽でなく、ポストロック方面との融合でもなく、総合的にジャンルで括れない。ジャンル的な「機能」でなく、AALの「美学」だけがある。その感覚はNicolas Jaar名義の『Telas』も同様で、その美学に上手く言葉は当てれないんですが、この人が見ている(だろう)景色には、やはり妙に惹かれてしまう。
Pickup:Fantasy、WInth an Adiict、Faith、Penny
■SSW

Matt Berninger 『Serpentine Prison』
The Nationalのボーカルによるソロ名義作。
バンドの音楽性の延長線にありますが、屋台骨のあのドラムが払われたことで、また違った魅力を引き出しています。Aaron Dessnerと違って、Booker T. Jonesプロデュースはいい意味でアレンジを作りこみすぎてなく、それが風通しの良さやしなやかさを生み、弾き語りみたいに声と歌詞が素直に響いてくる。改めて良いシンガーだなと。ストリングスやトランペット、ハーモニカが不意に零れてくるサウンドスケープはいわゆる「アメリカーナ」のど真ん中。適度にラフで、しかし締める所は締めた、渋いアダルトポップス好盤。TLで知りましたが、Booker T. Jonesの直近作も素晴らしかったので関連作としてぜひ。
Pickup:tr1 - 4

Ethan Gruska 『En Garde』
LA拠点のSSW、2nd。Phoebe Bridgers『Punisher』のSound Design、Perfume Geniusの作品参加、Matt BerningerのシングルをProduceと、ft. Moses Sumneyと、インディ界の重要人物になっていく人かと。
本作の目玉はとびっきりキャッチーなエレポップ「Enough for Now feat. Phoebe Bridgers」ですが、聴きどころは、ジャジーな質感と吸い込まれるコーラスを持つ「Event Horizon」あたりにある。Blake Millsとの共作曲(tr3)に象徴されるとおり、彼もまた、幾多のルーツを現代に鳴らしかえんとするひとり。
Pickup:Event Horizon、On the Outside、Enough for Now

Shohei Takagi Parallela Botanica 『Triptych』
すっかり独自の地位を築いたceroのvo. 髙城晶平のソロ1st。時代の知れないテープを再生しているような。非常に不可思議な手触りを持った一作です。その全景を掴むには、公式インタビューがひとつのカギになるでしょう。
ただこのローファイ、不思議なフィルターのかかった霞の先に見出すものはリスナーごとに違う気がします。そんな曖昧さからか、あまり反応は見かけませんでしたが、ゆえに「一概に言えない」面白さを感じました。この微ジャジーな曲想、ダイアトニックコードから外れた進行には、King Kruleらサウス・ロンドン勢に連なるものを感じました。並行世界のシティ・スケープとでもいうか。
Pickup:トワイライト・シーン、リデンプション・ソング、モーニング・プレイヤー
ほかには、5年分の音の洗練と変わらずの言語センスをみせた吉田一郎不可触世界『えぴせし』、The Nationalがらみでモダン・アコースティックな質感を聴かせたMina Tindle『Sister』、Ry Cooderの意思を継ぐ気満々なJoachim Cooder『Over That Road I’m Bound』も素晴らしかった。
■Bedroom
主に寝るとき聴いた音楽たち。

Gia Margaret 『Mia Gargaret』
シカゴを拠点とする”SSW”の2nd。わざわざ括ったのは本作の音楽性がフィールド・レコーディングに影響をうけたエレクトロニカ、アンビエントのためです。どうやらツアー中に声が出なくなってしまい、療養中に生まれた作品らしく。TURNに、そのままライナーノーツとして機能する尾野泰幸氏の素晴らしい解説がありました。
ノスタルジーを頼りに遠い何処かを描きだすように、1曲が構成もなく流れていく様子は寝る時にピッタリ。抽象的な作品ですが、そこには少しずつなにかを手繰り寄せる感覚があり、その終着点で彼女の歌声がこちらに届く。このエンディングも感動的でした。
Pickup:barely there、3 movements

Khotin 『Finds You Well』
カナダ拠点に活動しているプロデューサーのソロプロジェクト。ローファイ・チルアウトの文脈で評価されており、過去作はニューエイジ・ミュージック・ディスクガイドでもセレクトされた模様です。
このぼやけたアートワークで決まりですね。DowntempoやIDMの香り、そしてBoards of Canadaをみます。特に「Ivory Tower」「WEM Lagoon Jump」のリズムトラックには「そうこれ~」と唸る人が多いのでは。Skee Mask『Compro』につづくお気に入り作。
Pickup:Ivory Tower、Heavyball、WEM Lagoon Jump、My Toan
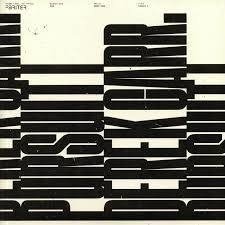
Derek Carr 『Pursuit』
王道をゆく絶品デトロイト流ディープハウス。どう考えても「Club / Electronic」枠にいれるべきですが、自分は入眠時にテクノを聴くことが多いので……(ループが退屈で眠くなるなんて意味じゃ勿論ないですよ)。睡眠時の脳内フロアミュージックとして愛聴しました。

Yo La Tengo 『We Have Amnesia Sometime』
USインディ永遠の良心、今回はインスト5曲37分のEP。バンドセッションを基にしたドローン、もといヨラテンゴ流ニューエイジか。ロックダウン中の企画作と見逃すところだった。このひとたちの音感覚で全編インスト作、悪いはずがない流石の聴きごたえでした。飲み込まれるというよりは、音の波、フィルターを体に浴びる感じ。ほんとうにワンコード、ミニマルなコード進行で曲作る匠ですよね。歌ものが恋しくもありますが。
Pickup:tr1, 3, 5
……………………………………………………………………
年間ベスト

ここで半分。ここからは年間ベストとして順位をつけてます。プレイリストとともにどうぞ。
■TOP20
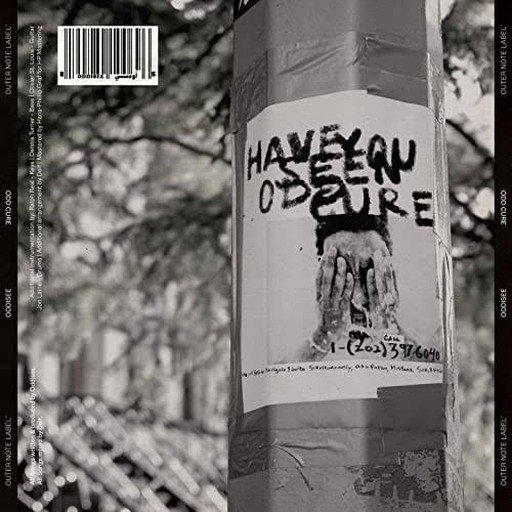
20. Oddisse 『Odd Cure』
ワシントンD.C.出身のラッパー兼プロデューサー。都会的でジャジーなトラックで、理知的なヒップホップを展開しています。
本作の核となる「The Cure」は、トランプ政権、BLM、ウィルスの蔓延といった事象を俯瞰でとらえつつ、Curtis Mayfieldの声をサンプリングし、「I'm the pro's, I'm the con's / I'm the hope and the harm / I'm relief or belief(私はプロであり、詐欺師 / 希望であり害悪 / 気晴らしであり信念)」から「Rest assure, it's the cure(安心して、それが治療法)」と、混沌とした状況にある個々人を鋭く多角的に切り抜いてみせる。フロアライクなハイハットから、ラップの核心に入るところで踏み込むキックのトラック構成も抜群で、本年度屈指の1曲です。KEXPでは、カーティスの名曲「Pusherman」をバンド演奏しラップしており、これもシビれました。
Pickup:The Cure、Go to Mars
今年は、「Cure」および「Care」の概念が、例年以上にいろんな音楽に現れていた(あるいは自分が感じとった)気がしていて、ランキング上位(TOP 6)もそんな感じになっています。後でまた。

19. Baths 『Pop Music (False B-Side 2)』
Anticon出のビートメイカー、エレクトロニカ系ミュージシャン。Hypnagogic Popとして10年代の瑞々しい楽曲感性を示した1st『Cerulean』('10)、よりダークにRadioheadやポスト・ロックに通じる美意識を携えた2nd『Obsidian』('13)。両傑作群から、レイドバックしつつ歌に寄ったのが前作で、本作もその延長線にあります。
未収録曲をまとめた編集盤ながら、Bathsの「エレクトロニカ(フォークトロニカ )を携えたSSW」という魅力を存分に味わえる逸品です。旋律の美しさとビートメイキングが共存し、非常にハイブリッドな「歌もの」として成立している。ゼロ年代ニカ周辺の空気感が好きなひとにもたまらないはず。ベストトラックは「Sex」。カットアップした危ういリズムの上で、愛へ渦巻く疑問をそのまま聖歌として昇華する感覚、繊細で凛とした感触はBathsならでは。
Pickup:Immerse、Sex、Wistful(Fata Morgana)
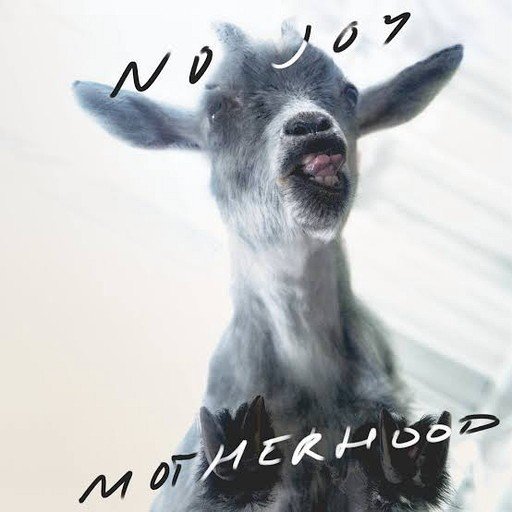
18. No Joy 『Motherhood』
カナダのシューゲイザーバンド、5年ぶり4th(本年間ベスト入りは7年ぶり)。
「シューゲイザー」が、いかに拡張性を持っているか、あるいは何にでも被せられるものか、を改めて知らしめる意欲作。さまざまなジャンルの表層的なクリシェ――ダブステップ、デスボイス、ちょっとしたメタルギター、クラブサウンド――が、ものの見事にシューゲの流儀で包まれていく。その成立には思わず死語「ニューゲイザー」を再考したくなる。また、ボーカル処理が絶品で、これはシューゲの親である「ドリームポップ」の経験値ですね。音の層に吸い込まれそうなサウンドスケープは至福。
Pickup:Birthmark、Nothing Will Hurt、Four、Primal Curse
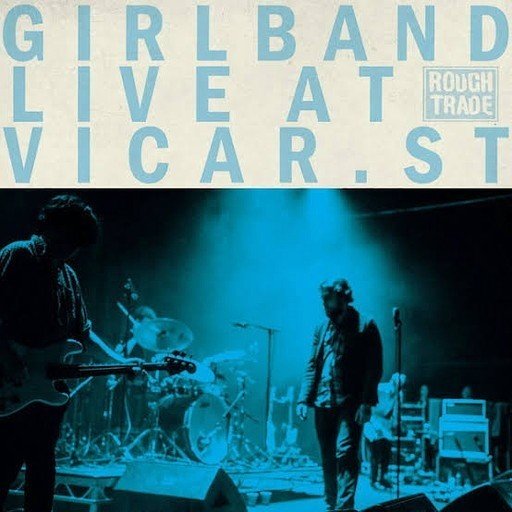
17. Girl Band 『Live at Vicar Street』
Rough Trade所属、現行最強ランクのポスト・パンクバンド、初のライブ音源。
年々「優しいね……」「あったけぇよ……」みたいなインディを愛する傾向が強まってるんですが、その中で本作には頭を打たれた。スタジオワークなしの生演奏によって、曲の異常性と暴力性が剥き出しに響いている。ちょうどSonic Youthの特集記事を書いていて、ポスト・パンクやノーウェーヴを聴き返していた中でもドンピシャでした。
ここ数年、ポスト・パンクと呼べそうな若手注目バンドが増えていますが、素直に良いと思う一方で「真面目そうだな」とも感じていて。例えばJohn Lydon、Mark Stewert、James Chanceとか、歌ってるときにナイフ持った観客がステージに上がってきても、逆に殴りかかっていきそうな音楽や声のすごみやキレがあるじゃないですか(?)。音のヤクザみたいな(??)。The FallのMark E. Smithなら間違いなくそのクソ野郎にビールをぶっかけますよ[要出典]。Girl Bandにはそうしたヤバさの気配を感じる。
battlesがノーウェーヴに雪崩れ込んだような「Fucking Butter」ポスト・パンクがハードコアへの分岐を辿る瞬間をとらえた「Heckle the Frames」。「The Last Riddler」のブラストビートからのシャウトも鳥肌もの。カッケェ!
Pickup:Fucking Better、Heckle the Frames、The Last Riddler、Laggard

16. Shabaka & the Ancestors 『We Are Sent Here By History』
UKジャズの雄、Shabaka Hutchingsのプロジェクト。彼のキャリアは国内盤ライナーノーツ(柳樂光隆)に詳しいです。前作は「UKからのカマシ・ワシントンへの返答」なんて乱暴なコピーがついたスピリチュアル・ジャズの傑作でした。本作も、「グリオ」(言葉を持たず歌で歴史を継いできた人々)としてイギリス、カリブ、アメリカ、アフリカを結ぶ、壮大なコンセプトは圧巻です。詳しくはこの記事を。
ただ自分は、唸りをあげて渦巻くグルーヴにまずやられた。前作は音響的な要素もつよくてテクスチャーも印象に残る作風でした。対して本作はフレージングがハッキリした曲が多く、複数奏者で旋律とリズムが濃厚に絡みあっていく展開が多い。だから、かなりロックリスナー的な耳で捉えられた。来日予定だったのが本当に無念。いつか……いつか?うぅ……。

15. Blake Mills 『Mutable Set』
昨今の音楽制作の重要人物のひとり。ギタリスト・プロデューサー・ミキサーとして、Alabama Shakes、Fiona Apple、Perfume Genius、Phoebe Bridgers、Bob Dylanと、様々な重要作にかかわってきた彼のソロ4th。
ジャンル分けするなら「インディ・フォーク」あたりで、一聴して芳醇であることは分かる。好きです。ただ、何に惹かれていて、この作品が何に焦点を当てているのか?そこが掴めない印象が強く残った。例えば岡田拓郎氏は「ギター・サウンドの更新」という観点で立ち会っている。そしてPitchforkの記事がライナーノーツ的な内容でよく整理されています。
自分は音楽性の組みかえに面白さを感じた気がしています。ベストトラックは「Money is The One True God」。詩曲のスタイルは「ブルース」(コード進行でなく、歌とギターとして)と言えますが、そのアレンジは全く「ブルース」的ではない。特に後半のクラシカルな音感覚はまるでRadiohead『A MOON SHAPED POOL』です。本作がこの順位なのは自分じゃ位置づけられなかったからで。間違いなく今年有数の、豊かさと示唆に富む濃密な一作。
Pickup:Never Forever、Money is The One True God、Vanishing Twin
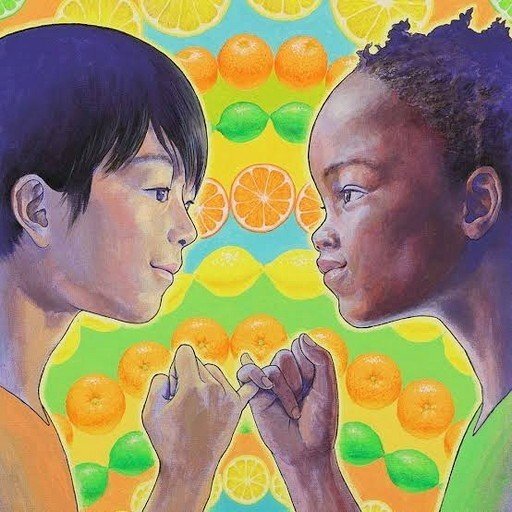
14. 岡村靖幸 『操』
日本の奇才Funk・J-POP・SSW、8th。昔Princeにハマった所から出会ったんですが、そんな視座は『靖幸』('89)でぶっ飛ばされました。ファンクの音楽言語である英語を、なぜか日本語で再調理できる才気。そして歌詞と声とリズムの強烈な"アク"。今聴いても鮮烈ですが、そこから30年!
まず1曲目「栄光と挫折」が最強。Corneliusの無機質なギターソロふくめ本年度屈指のトラックです。より粘っこくなった発声の変化、くわえて出音の現代化と、全体として物凄くパワフルで、現役をバリバリに感じる仕上がり。開幕4曲の流れが強すぎる。
話を戻して。00年以降のPrinceは、自身のルーツを真摯に見つめなおす方向に向かいましたが、そのアップデートも聴いてみたかった。そこでコレ。Princeの種から、また違う異形(オリジナル)として芽吹いた岡村靖幸の本作は、まさに"現在形"を提示していて、滅茶苦茶グッときました。「J-POP」という音楽性の闇鍋を開ける、強烈な一作。
Pickup:栄光と挫折、インテリア、ステップアップLOVE、マクガフィン

13. Metz 『Atlas Vending』
レーベルはSub Pop、カナダ産ガレージ・ノイズ・ハードコア・パンクバンド4th。The Jesus LizardやDrive Like Jehuら90sポスト・ハードコアに端を発し、現在ではIDLESなどにも共鳴するだろう、殴りつける、切り刻むバンドサウンドの系譜。
このバンドは基本的に"出音"が勝負なので、1曲目の人を殺すようなキックだけで勝負はきまる。前作はアルビニ録音でしたが、今回はSeth Manchesterによって過去最大のドラム快楽指数をたたき出しています。こだわりの録音に関しては変遷をプレイリストにしてみたので良ければどうぞ。「この場所を離れる必要があるんだ 今ならわかる」とカオスを踏み鳴らしていく最終曲アウトロのカッコよさったらない。
また、国内盤の天井潤之介さんのライナーノーツが、作品背景、重要人物の列挙、楽曲への具体的な言及と素晴らしい内容だったことを記しておきます。
Pickup:Pulse、Blind Youth Indastrial Park、Draw Us In、A Boat to Drown In

12. 君島大空 『縫層』
1995年生まれ気鋭の若手音楽家2nd EP。吉田ヨウヘイgroupで腕をふるっていたギタリスト西田修大さんが好きで、彼が参加している所から入りました。
「花曇」がとにかく好きです。この、空中泥棒などに連なる、何かを淡いまま飽和させた音感覚。いくつもの漠然がひたすら折り重なっている抽象画のような、散らばった記憶の断片を音の写真(曲)で捉えたような。ひどく感情が乱される。これを形容する言葉を持ちませんが、この音楽が、安易に名付けられる前の「何か」、表現なのは間違いないです。名曲。他の曲は予想よりJ-POP的な展開によせていて少し驚きましたが、一貫した美学を感じます。フルアルバムはどんな風になるんだろう。
Pickup:散瞳、火傷に雨、花曇

11. BUCK-TICK 『ABRACADABRA』
大ベテランロックバンドの33年目22th。昨年いきなりズブッとハマったんですね。ファンになって初めての新譜だったので緊張しながら臨みました(?)。意気揚々と書きだしたら、2000字を超えてったのでココではザックリ。
B-Tは『アトム 未来派 No.9』('16)から何度目かの全盛期を迎えてます。過密・重厚だった前2作と比べ、本作はいい意味での軽薄さを携えたポップな一作。作詩曲には手癖が目立つも、サウンドコーディングの現代化によって新たな息吹を吹き込んでます(tr2, 3あたりのシンセにはギョッとしつつ)。ハイライトは最終3曲。幅広い音楽性で存分に遊びまわった所で、「ESCAPE」とまとめ、おまじないとして「LOVE & PEACE」を掲げてみせる。よくある帰結ですが、そうした存在であると自覚し30年ロックバンドをやってきた彼らの説得力は追随をゆるしません。「忘却」の超然したスケールには平伏するほかない。年季が違う。
ここで1年の日記として記しておきたいのが、2020年を彩ってくれた「配信ライブ」のこと。どれも素晴らしかったですが、特に感銘を受けたのがBUCK-TICKとB'zです。このような特殊な状況でも、既存の曲からしっかり「今語るべき言葉」を引き出し提示できる、強さ、貫禄。改めて唸りました。今年1年精力的に活動してくれたことにまず感謝の気持ちがあって、やっぱり自分の生活には音楽、ライブが必要です。
Pickup:Villain、凍える(Crystal CUBE ver,)、tr11 - 14
……………………………………………………………………
ついにTOP 10!!

10. Happyness 『Floatr』
サウス・ロンドンのインディバンド3rd(他のロンドン勢とは全然別枠ですが)。本ブログでは3作全部年間TOP10入りで、「スパークルホース、ヨラテンゴらを飲み込んだ……」「洗練しきっていないElliott Smith的な魅力……」とか書いてます。つまり90年代的な空気を、タイムスリップしてきたんじゃないかってくらい本当に自然に携えている奇跡のバンド。
本作は過去最も"うた"に比重をおいた作風です。過剰なセンチメンタリズム、執拗なノスタルジア、ペタリと鼻につく自意識、すべてがメロディによって昇華されている。開幕曲と最終曲が名曲すぎる。この作品に対して、メジャーシーンと同じ価値観で「低音が弱い」という人がいたら鼻で笑います。
ロックバンドの評は大体「来日してほしい」で締めますが、Happynessに関しては別によくて(いや来てほしいけど)、アルバム1枚の中に存在してくれていればそれでいい。自分にとってこれは一種の箱庭です。
Pickup:title track、Milk Float、Vegitables、Seeing Eye Dog、ぜんぶ

9. THE NOVEMVERS 『At The Beginning』
4人組オルタナ系ロックバンド。本ブログで取り上げるのは初めてか。もう結成15年……最初知ったときの括りは「ART-SCHOOLに似ている」でしたが、隔世感がすごい。
本作の音楽性は、ニューウェーヴやインダストリアルの影響、ビジュアル系につらなる音楽解釈、J-POP的な曲展開の美学まで感じさせる。そこには自身が”良い”と確信する音楽を集めて、バンドとして真摯にその音を獲得しようとしてきた、試行錯誤を感じます(ラルクのyukihiroプロデュースもまさに)。ここはひとつ記事を。
作曲って、ある種その人(たち)の「頭のなかの理想郷を描写せんとする」行為だと思うんですが、本作からはバンドの提示する「青写真」、メッセージの先に描いてるものや価値観が鮮明に伝わってくる。一方、長い試行錯誤から完成したであろう本作の音楽性が、その説得力を高めている。だって、バンド初期は刃物みたいだった音が、今ではいい意味での「柔らかさ」を備えているわけで、そのキャリアには「変わることができる」ことを物凄く納得させられる。そこから歌われる「君はいつもここが始まりさ」ですよ。
観念的な話はともかく、単純に「洋楽に影響をうけているが、洋楽からは出てこないだろう」曲想もとても面白かった。次をワクワクさせる稀有なロックバンドとして認識しました。
Pickup:Rainbow、理解者、消失点、Hamletmachine、開け放たれた窓
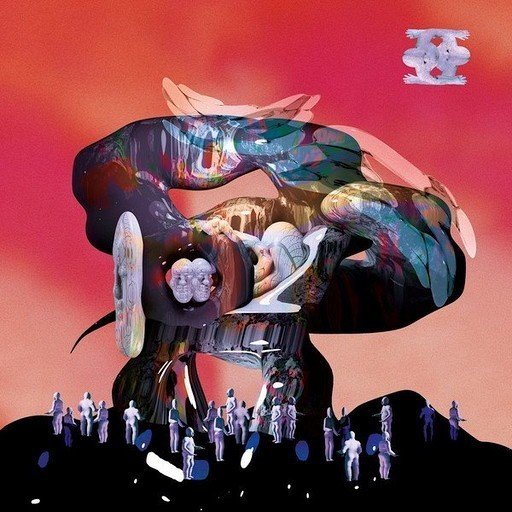
8. Pet Shimmers 『Trash Earthers』
今年1st、続けて2ndを発表したイングランド出身のインディバンド。どっちもマジで素晴らしかった。(SANDY) ALEX Gのツアーに同行、ウィルスが収まったら先に登場のHappynessとツアー予定と、この対バンがそのまま彼らの音楽性、ストライクゾーンを示してます。
トイ・シューゲイザーみたいな、Grandaddyのドリーム・ポップ化みたいな。ローファイ・ポップの傑作です。イタズラ心でトラップを魔改造した「All Time Glow」もいいし、「Madona's People」ではハイファイなアコギにチープな打ち込みとシンセベースが加わり、子供のスケッチのような世界が展開される。この楽曲をメジャー的な感性で捉えることは出来ないです。Sparklehorseの諸作と並べることにすら躊躇はない。今年最も素敵な作品。1番好きです。つまりこの作品より上のは「好き」より「すごい」寄りのやつになります(どれも好きですが)。
Pickup:マジでぜんぶ

7. SAULT 『Untitiled (Rise)』
去年『5』『7』で閃光のごとく話題をさらった匿名プロジェクト。Wikiでは「R&B、ハウス、ディスコ」、一方でその音感覚に「ポスト・パンク」の語も挙がる、UKらしいバイブリッドな音楽性。関連作はLittle Simz『GREY Area』、主犯はDean “Inflo 1st” Josiah。
「Untitiled」としてリリースされた2作は、おおきく問題提起の"Black Is"、再興を祈る"RIse"に分かれてます。本作については、bandcampの記事がオススメ。今年は野田努『ブラック・マシン・ミュージック』を読了したので、「ディスコ」という存在を映しての"Rise"の宣誓の意味には感じ入ります。
「Strong」の、往年のディスコサウンドとストリングスから始まり、間奏で突如太鼓だけが鳴り渡るシーケンスの異常な説得力に、いきなりグイッと引き込まれる。クラブから過去の大陸へとリズムを渡って見せる「I Just Wanna Dance」など全編がハイライト。過去最もスペクタクルな作風にひたすら圧倒され、たしかに最後に希望を見る。傑作。
Pickup:Strong、Fearless、I Just Wanna Dance、The Beginning & the End、Free
■TOP6
ここからは、なんとなくテーマとして「ケア」がある作品が並びました。長い長い本記事ですが、あと6作おつきあいください。
(目次から飛んできた方は、興味あれば暇なときに他を読んでやってください)

6. The Microphones 『Microphones in 2020』
17年ぶり5th。1曲44分44秒、自伝から成る内省的で壮大なミニマルフォーク。ミニマルで壮大とは矛盾しているけれど、最小限の枠組みから、内側を最大限に広げた、そんな印象を与える傑作。これは回顧によるセルフケアで、人生を見つめなおす所作です。作品の構造は以下の記事に詳しい。
輪廻まで辿るような開幕7分間のギターストロークにまず引き込まれる。サッドコアを思いだすコードと音色。左右からの「・・カッ・・カッカッ」のリズムが1曲全体の瞑想的な感覚と緊張感を決定づけます。そこに自然発生のフレットノイズやバンドサウンドなどが加わりながら、楽曲は映像的に進行していく。26分ごろ、「一人、暗がりの中また目を覚まし、泳ぎだしていく、心の湖のなかで、その内へと」から導かれる、音響派を想起するパートが本当に素晴らしいです。
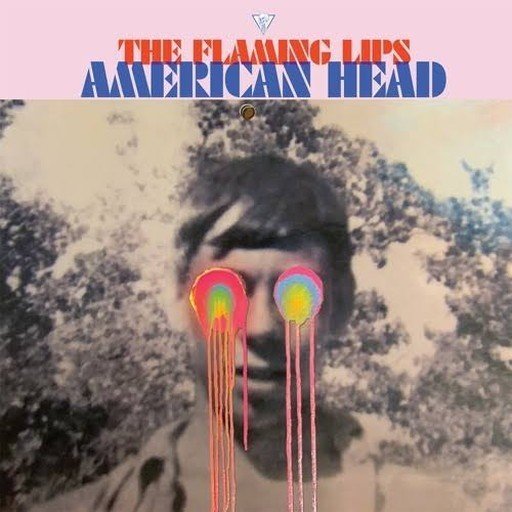
5. The Flaming Lips 『American Head』
「帰ってきた」と言いたくなるファンも多いんじゃないか。最も注目されていた時期の傑作群、『The Soft Bulletin』('99)~『At War with the Mystics』('06)と並べることになんの躊躇もない快作です。
リップスはよく「多幸感」みたいな言葉――よくない語なので言い換えると「確信をもって幸福に包まれている感覚」――で捉えられますが、本質的に"死"や"痛み"を抱えているバンドです。B級的な被り物やオカルティックな世界をどこまで広げても、あるいは初期作のようにアシッドとジャンクに逃避しても、逃れようのない何かが人生には纏わりついている。その背景が常に潜むからこそ「なぜか泣けてくる」んだと思いますが、本作はそうした情感に真正面から向き合った、過去最も実直で壮大な作品です。本作もまた回想によるセルフケア。
オーケストラルポップによるサイケ、毒を孕み幻覚剤を取り込んだドリームポップ、感傷としてのカントリー(ft. Kacey Musgraves!)。Microphonesが記憶をミニマルな構成でまとめあげたなら、リップスは綺麗な音のヴェールで包んでみせました。このバンドらしいです。マジで泣ける。
「アコースティック」という印象を与えない音にもこだわりを感じました。逆にアコースティックのオーケストラを強く印象づけたOwen Pallettの新作『Island』と並べても面白いかも。
Pickup:tr1、Flowers of Neptune 6、Mother I've Taken LSD、tr9 - 11

4. King Krule 『Man Alive!』
多くの注目すべきミュージシャンが登場しているロンドンシーンの先駆者。濁りや歪をうつす独特な音表現と、役者すら感じさせる声の魔力を持つ異端のSSW、変名込み4th。紹介やら音楽性の詳しくは記事に書きました。
ここではもう少し「何で惹かれたか」を書いてみます。なかなか掴みどころのない作品ですが、本作は確かにあるムードや気分を携えている。悲観的過ぎるものでもないけれど、明るいものでは決してなく、絶望や混乱に近い。それは今年の自分の肌感覚にものすごくマッチしていた。だけどその「ムード」を描いたこの男は、ただ、凛と立っている。ケアされて然るべき状況にあるが、癒される気はないし、破滅に向かう気もない。その佇まいが滅茶苦茶クールに感じた。
クオリティで見たとき、「傑作」の類ではないでしょう(ブログの無粋な点数評価は81。他のTOP5作なら86~89はつけます)。ただ、この佇まい、そして作品のムード。2020年の自分が選ぶとき、本作はこの順位までくる。
Pickup:Stoned Again、Alone, Omen 3、Underclass(ブログ参照)

3. Perfume Genius 『Set My Heart On Fire Immediately』
年々評価を高めているアメリカのSSW、5th。彼の歩みはMikikiの記事に詳しいです。ケア、ケアと書いてきましたが、正しくそうした段階から始まったのが彼の10年代の諸作で、2020年にたどり着いたのが、生を歌いあげた本作です。彼のことばが象徴的(国内盤ライナーノーツより)。
クイアーな僕は教会には入れないし、エルヴィスの歌も好きだったけど、彼の歌っている物語の中に僕のような存在は含まれていなかったから。でも僕はそういう音楽に共鳴したし、音楽を聴くたびに魔法にかけられたような感覚を味わっていた。
今までもそうだけれど、今回のアルバムでは特に、自分もそこに含まれているような物語を書いたり、僕と同じような人たちも共感できるような内容にして、そういう人にもその魔法のような感覚を味わってもらいたいと思ったんだ。
その魔法はまちがいなく2020年に一縷の光をあててくれた。そしてアメリカの往年のポップスをなぞりながら、単なるノスタルジーに留まらせなかったのが、先に登場したBlake Millsの真骨頂。その時代再現と再構築は、まさしく現在だから鳴らせた音の感触。幕開けとなるオープナーの「Whole Love」だけで名盤を確信させます。
僕の全人生の半分は終わった
漂い洗い流されればいい
優しい陽にあたれば影も柔らかくなる
ゆっくりと僕らはそれを置き去りにする
これは祈りのような宣言で、本作はその祈りが通じることを信じさせてくれる1枚です。
Pickup:Whole Love、Without You、On The Floor、Nothing at All、Some Dream

2. Mac Miller 『Circles』
2018年に26歳の若さで亡くなったアメリカのラッパー、生前に構想していたコンセプトを引き継ぎ完成に至った6th。今まで彼の音楽を聴いたことはほぼなかった。なんとなく聴き流していたらいつの間にか深く入りこんでいた音楽というのがあって、これがそれ。ソフト・ロック、R&B、にラップ。本作の佇まいはほとんどSSWです(tr6から聴き始めると分かりやすいかも)。だから個人的にも非常になじみ深く、一方で、2010年前の音楽をあさっても出会えないだろう質感に包まれている。
制作背景と歌詞を無視すれば、口溶けのよい音は「良い塩梅のメロウ・チル」ですが、もっとこう、エレガントで、いい映画を見終えたあとのスタッフロールみたいな「余韻」が音に宿っている。この感覚を作り出しているのが、古くはAimee Mann~Spoon、Frank Ocean、Kanye Westまでを手掛けた巨匠Jon Brionなんですね。
そうしたレイドバック加減と、無常のなかでひっそり幸福を願うようなすこし頼りない声。この組み合わせは間違いなく何かの境地にあります。『空中キャンプ』といった類の、ある種の気分(ムード)を完璧に捉えている作品で、本年度最も「名盤」に近いものじゃないでしょうか。
にしても歌詞をふまえて聴くほど、門外漢の自分ですら、本当にやり切れない感情になってしまう。寂しい。だけど同時に、確かに癒しに似た感覚も覚える。だって「Surf」の、「老いるまで花に水をやって育てよう」に連なるチープなシンセから「Let it go, let it be」の流れとか、意味も分からず本当に泣けてくるもん。不思議だな……。
この曲→tr2 - 4、tr6 - 7、Hand Me Downs、Surf
……………………………………………………………………

1. Phoebe Bridgers 『Punisher』
ロサンゼルスのSSW3年ぶり2nd。Rolling Stones誌は「Emo - Folk」と評していますが、彼女の言葉がその魅力を伝えてくれます。
「昔から悲惨な曲をポップソングのように奏でるザ・キュアーみたいなバンドが大好きだったんだけど、モリッシーとかね。だから自分でもああいうことをしてみたかった。」
マイナスを捉えて別の何かに変えてしまう感覚。音楽だけならMac Millerが1位かなと思ったんですが、何かしらの意図をもって今年の1位を選ぶとするなら、自分はこちらの感覚を上におきたいなと。
どの曲も語り口と音の組み合わせが素晴らしくて。「Kyoto」では彼女と父親のいかにも上手くいかなかった子供時代の関係が、80年代インディーポップを思い出させる軽やかなタッチで回想される。彼女が経験してきた様々な感情が、おなじく彼女が出会ってきた数多くの人物の鳴らす音ともに織重なっていく様は、まさにSSWの作品の醍醐味。特に「Graceland Too」でのJulien Bakerとともに掛けあう「I would do anything you want me to ~ Watever she wants」のシーンは最も美しい瞬間のひとつ。
「I Know The End」の、「行かなくちゃ、分かってる」から始まり「これで終わり」とリフレインし虚無への絶叫に至るシーケンスは、終末と始まりのカタルシスです。ただ、メッセージとしては、ひとつ前のフレーズ「終末は近いと書かれていた 振り返ってもそこには何もなかった」の方が真じゃないかと。そこで1曲目のタイトルが「DVD Menu」であることの距離感な訳で、本作の楽曲はあたかも映画のチャプターであり、当然こちらは何度でもこの「終わり」を繰り返し再生することが出来る。
「終わった」と言ってみても何一つ終わらないし、叫ぼうがどうしようが、全てはただ続いていく。でもそこに、何かしらを見出して――音や声をのせたりしてみる。そんな1枚だと思っていて、その感覚を今年の1位として置きます。
Pickup:Kyoto、Halloween、Graceland Too、I Know The End
次年度はこちら。
サポートがあると更新頻度が上がります。
