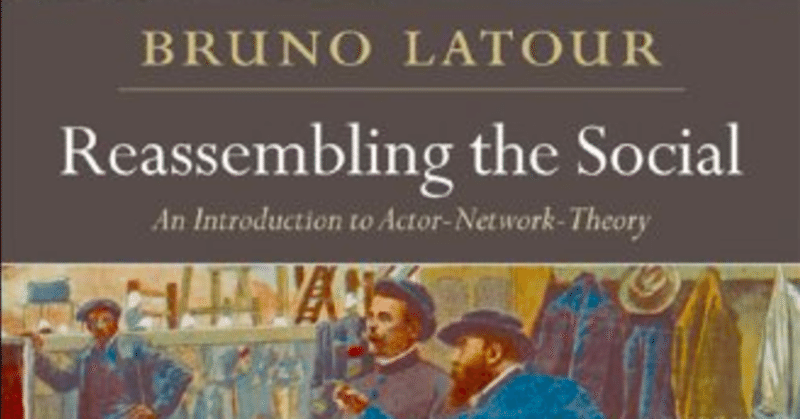
ラトゥール『社会的なものを組み直す』をわかるまで読む 全13回
第1回
初めに
大学で社会学を勉強すると、マックス・ウェーバーやエミール・デュルケムの名前が出てくる。社会には特有の形があり、その形が文化を形作るというのがウェーバーの考え方で、消費活動において禁欲をよしとする価値観をもつ人たちが結果として多額の貯蓄を積み上げて、それが資本主義を生み出す動力となった、という『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』(略してプロ倫)という本の名前は聞いたことがあるだろう。あるいはデュルケムはフランスのいくつかの村を調査して、カソリックを信じている人が少なくなればなるほど、その村の自殺率が高まる。それはよるべのない不安に駆られると、神を信じることが自助努力になっているプロテスタントの信者達は不安の重さに耐えられなくなって自殺をする」という仮説を統計的なデータで説明して見せた『自殺論』という本を書いている。これは『プロ倫』よりは知られていないかもしれないが、社会学的思考の古典である。
社会が資本主義の発達によって様々な面で大変動しているなかで、新しい世界を構築する過程にあった18世紀末から19世紀にかけて、新たに登場してきた「社会」がどのような性質をもっているのかを考えたのが社会学の始まりであり、ウェーバーやデュルケムの考えが生まれたとされる。大学に入り社会学を学ぶとゲマインシャフトからゲゼルシャフトへの変化として習うところだ。テンニエスの『ゲマインシャフトとゲゼルシャフト—純粋社会学の基本概念』で習ったね。慶應の社会学入門の授業だ。横山先生が教えていた。懐かしいね。
社会を実態のあるもの、統計的な調査で把握することが出来るものであるという考え方はその後も社会学の中核を占めており、イアン・ハッキングは1990年に出版した『偶然を飼いならす——統計学と第二次科学革命』において、19世紀の地方自治体が犯罪、飲酒、自殺などを調べて統計結果として印刷して発表していたと述べている。日常の世界での顔をつきあわせての付き合いのなかでは意識することの出来ない動きをあきらかにする方法として統計学がつかわれ、それが社会学という学問の確立へとつながっていったのである。たとえば現在でも、東京23区に住む人の特徴をそれぞれの区の人口の特性と平均収入でみて、分析して、これからの街のあり方、商品開発の方法などについて予測をする、という活動が研究者によって普通に行われており、またそのことについての書籍も大量に出版されている。港区民とか江戸川区区民とか、タワーマンション住人とか、公団生活高齢者とかいった集団が実態のある社会的存在として語られ、それに疑問を提示するどころか、こうした分析に基づいて地域開発が行われている。
だが、本当に社会的な実体というものは存在しているのだろうか?ウェーバーやデュルケムが社会を実在としてとらえていることは社会学者のなかで議論されてきた。だが、直感(ウェーバー)とカテゴリー(デュルケム)という否定しがたい思考の道具を使っているこの2人の社会学理論をくつがえすことはなかなか難しかった。この問題に対する批判は20世紀になって現象学的社会学としてようやく始まった。また人類学者の間では民族史的既述の「真実」を巡る議論などが戦わされ、客観的な社会の存在は証明することはできないが、その「社会」と現在我々が生きている状況を踏まえた上での「研究者」によるその社会の解釈の丁寧な既述は、対象とする社会のみならず、その社会を説明・解釈しようとしている我々のことも明らかにしていく、というクリフォード・ギアツの解釈学的民族誌の考え方が普及して、社会ではなくて、人間の行動の詳しい記述の方向に研究は大きく舵を切っていった。記念碑的な研究となる民族誌がいくつも書かれて、これらの民族誌は人間の存在のあり方に関して多くの示唆を我々に与えるようになった。こうした偉大なる現代の民族誌学者であるブルーノ・ラトゥールが2005年に著したのが『社会的なものを組み直す』である。
ラトゥールは数名の研究者仲間とActor-Network-Theoryという考え方を1990年代の半ばから提唱しており、活動をしてきたが、「社会的なるもの」と「社会的な説明」という言葉の定義が社会学で普通に使われている意味と大きく違ったため、混乱を招いていたという。この問題を丁寧に議論する間もなく、Actor-Network-Theory(以下ANT)の考え方は広まってしまった。どこかでしっかりとした学問的な導入をする必要性はずっと感じていたとラトゥールは述べている。
1999年からActor-Network-Theoryについての紹介を様々な大学で行う機会を得て、おおまかなドラフトを作り上げて、ANTの理論的入門書として『社会的なものを組み直す』が書かれたという。日本では2019年にしっかりとした翻訳が出版されて、ANT理論の概要がようやく日本語でアクセス可能になった。
だが、この本はよく出来ている翻訳で、訳者は慶應大学大学院社会学科の先輩のお弟子さんでもあり、信頼ができる仕事になっている。が、日本語で読んでもなかなか難しい。それは二つの意味においてである。一つは社会学のみならず社会科学一般の訓練をうけた人であれば社会的「実体」の存在について疑ったことはないはずである。社会科学はそもそもがそういう学問である。その実体にどのようにそまるか?抽象的な理念を歴史資料で説明するか、実体を構成する特性のいくつかを統計的手法で「実証」的に説明するか、が社会科学の普通のやり方である。だが社会学は違う、というのがラトゥールの主張だ。それは社会的なるものはないのだから、というわけ
だ。
この考え方を前面にだしたのがANTである。この考え方は社会的なるものの実在そのものを真っ正面から否定している。つまり社会学を学んだものであれば、自分が慣れ親しんできたものの見方、考え方を捨ててANTを再学習しなくてはいけない。とくに専門的に社会学などを学んでいなくても、われわれの普通の理性的な思考(データを論理的に整理して自分の主張の妥当性を述べる。これはこのエッセイの第二回のテーマである。)とはあらゆる点で異なった見方をしているのがANT理論だからだ。もう一つの難しさは方法論にある。ひとつは徹底した民族誌記述を行うという作業、もうひとつはプロセスを記録して分析するという実証の方法を活用するツールをつかうことが我々の思考スタイルとして身についていないことにある。ツールの使い方そのものもANT理論の一部であるため、話はさらに難しくなっていく。とはいうのもの、それは我々がすでにできあがっている方法で物事をみているために、新しいやり方になじみがないだけであって、実際に行われている作業が特に難しいというわけではない。考え方や方法になじみがないため戸惑うのである。
ANTでは社会ということばを安定した「社会的実体」を意味するとは考えない。あの人は「社交的だね」という意味でsocialという言葉を使う。すでにできあがってしまった社会に対しての議論をするのであれば実体としての社会を考えても悪いわけではないが、いま我々は21世紀の激動の時代にいきており、昔の(つまりは近代の)社会構造を分解して新しい組織をイノベーションしなくてはいけない時代に生きている。なので、socialとは既存の社会システムを指すのではなく、人間が他の人間と関係性をむすんでいくという意味でANTでは使う。この見方をすると、現在数多くある社会論、地域論だったり階層論だったりする研究においての社会的とは実体論であって、人と人が関係性をもって動いている、という視点がほぼ皆無なことがわかる。人が人と関係性を結びながらある程度の時間をかけて、社会を「組み立てていく (assemblageする)」プロセスの研究こそがほんらいの「社会学」が行うことであり、ANTはそれを目指すのである。つまり社会学とは「生活を共にする人たちについての科学」なのだ、と述べている。
さて、社会的ということばを通常我々が使っているような実体をあらわす意味ではなく使うとはどのようなことなのだろうか?これについて次に考えてみたい。ここにおいて、社会的とはことなるものを統合するということであり、これは、たとえば社会言語学において、言語学が統合できなかかったのこりを統合する「社会」という意味ではない。社会的に統合されたということは、経済学的に、言語学的に、あるいは心理学的に統合されているという状態のことなのだ。
どこが違うのだ?と思うだろう。ここからが難しい。social という言葉の語源にラトゥールは向かっていく。socialという言葉を聞くと、社会科学の研究者は同質のものの集合と考える。だが、異質なものの結合 associationとしてsocialという言葉を使うことが出来る。なぜなら、ラテン語でsocialのことをsociusというがこれは、組み合わせ(association)を追いかけていく、という意味なのだ。つまり、associationそのものではなくて、associationによって生まれてくる結合(connection )の種類を意味するのだ。異質なものが組み合わされて新しいものになっていくプロセスのことをsocialは意味することが出来る。assemblageによって新しいassociationが生まれているプロセスの記述をsocialと言うことが出来るのである。これをreassemblageと呼びたい。
新たにつなぎ合わされたものの背後には社会的実体は存在していない。「社会的説明」とはコネクションの背後に社会の存在があるとして、それを説明しようとするが、そもそもそのような「実体」は存在していないのだ。われわれが社会とおもっているのは、様々な異質な要素が試行錯誤をとおして組み合わさっって行くプロセスの痕跡 traceに過ぎない。こうしたことを研究する分野をラトゥールは 連関の社会学 sociology of associationsと呼ぶ。これをActor-Network Theoryと呼ぶべきなのかもしれないが、この名前が一人歩きして、ラトゥールは使う気がなくなっていたが、ANTと略せば蟻だから、目の前の事しか考えないでただひたすら周りの蟻の行動にあわせて動き回っているわけで、新しい理論にふさわしいのでは、とある人に言われて気に入ってこの言葉を使うことにしたという。
重要なまとめ 1: socialという言葉は社会学では実体を表す言葉として使われる。これをsociology of the social と呼ぶ。ここでは鉱物とか植物という意味で社会が存在するとする。だがANTではsocialとはつながっていくというプロセスを示す言葉としてつかっていく。これをsociology of associationと呼ぶ。
第二回 統計について
さて、Latour が関係性と痕跡の「社会学」と呼ぶ Actor-Network-Theory の現状と評価についての説明に入る前に、彼が批判するsociology of the social (社会実体論)の基本になる統計の考え方について話をしておきたい。
三浦展(あつし)という1958年生まれの社会学研究者がいる。パルコ入社後マーケティング誌『アクロス』編集長から三菱総研での研究を経ていまは自分の会社で日本の消費・都市・郊外を研究する。多作な人で魅力的なタイトルの本がたくさん出ている。僕は割と読んでいる。
さて、たくさん読んでいて、また参考にもしているのだが、三浦展氏の方向はラトゥールの批判する社会実態論の典型である。それを理解するには社会の見方、いってみれば哲学の問題が大きく関係する。その哲学とは、統計数字をつかいながらも、思考や論述がニュートン的な決定論の流れ、つまりはカントの定式化した世界を断ち切っておらず、それが「社会的なるものの社会学」に特筆であり、ラトゥールがいうところの「関係性の社会学」とは大きく違うところなのだ。
ではどこがちがうのか?統計的手法をつかいながらも偶然性 chanceを導入できない、というところが違うのだ。科学哲学者イアン・ハッキングの『偶然をかいならす』を参考に、すこし詳しく見てみたい。18世紀も終わりになると、啓蒙時代の整理整頓された世界観とそれを代表するカントの哲学、さらにはカントが前提としていたニュートン的機械論的決定論のものの見方だけでは説明が出来ないと感じる人々が出てくる。それは社会の統計化から始まる。統計とは数え上げる enumerationという作業に始まる。国税調査をあらわすCensusという言葉はラテン語でcensereといい、古代ローマ時代から市民を登録して、財産を評価して、徴税を課す、という作業がおこなわれていたことがわかる。豊臣秀吉もそうだが、ナポレオンも徴税のために人々の財産を数え上げた。時代が近代になると、徴税に加えて、徴兵が目的として加えられた。そしてその結果は秘密にしていたという。
ナポレオン時代の終わりに、統計データが印刷される。これをハッキングは「印刷された数字の洪水」と呼んでいる。調査結果が印刷物として出版され、人々はそれに「熱狂」した。犯罪や自殺など「悪い行い」が計測できるようになり、それが毎年規則正しく起こっていた。逸脱の数字があらわれてきて、それを正常に戻すための方法「社会工学」が構想された。18世紀の終わりの話である。
最初のセンサス(国勢調査)を行ったのはアメリカ合衆国で、1790年のことだ。アメリカ独立の少しあとだ。このときは人口統計がとられた。いま、この瞬間の人口を数え上げる簡単なものである。1792年にワシントン大統領にアメリカ13週の人口数3, 929, 214という数字が報告さえたという。(注 伊藤陽一論文)
その後ヨーロッパ諸国でもセンサスの調査がおこなわれ、データの分類と計量のための新しいテクノロジーが導入された。マルクスは公式統計の細目や工場視察報告書をつぶさに読んで研究していたという。階級意識をつくりあげるのは、統計の数字なのかマルクスの理論なのか?あるいは、統計の数字が階級意識を決定論的にきめるのか?
ハッキングはこの問題、つまり人間を作り上げるのはなにか、の問題は最初は階級意識ではなくて、自殺、犯罪、狂気、売春と行った「逸脱行為 deviancy」を改善することができるという発想から注目されたという。印刷した統計数字を見ながら、マルクスもデュルケムも何が人間の行動を決定しているのかについて議論を展開したのである。
だが面白いことに、データがあつまってみると、データにはデータ独自の性格があることがわかってきた。これを大数(large population)の法則という。これはギャンブラーの間で知られていた。博打に勝つという「偶然 chance」に法則性があるのでは、という議論だ。17世紀の事だとされる。哲学史的にはライプニッツの話となるが、この話はもっとあとで詳しく説明したい。偶然の問題はライプニッツの同時代人であるニュートンの決定論の世界ではあまり真剣に議論されていなかった。ところが、経済的自由主義、個人主義、個人の集合としての国家概念が広く行き渡っていた19世紀の西ヨーロッパの諸国は、自国のセンサスデータを読むことで、データと社会現象のあいだには「大数の法則」があることに気がついてくる。
確率とは統計的結果について議論しているのではない。統計はstatisticsで確率 はstochastic。つまり違う言葉だ。決定論ではなくて偶然を前に出すのが確率論である。我々は確率論で、つまり決定論の外で思考をする時代に生きている。実証的とは証拠を集めて、データを分析して、実験をデザインして、信頼性を評価することである。論述するとは 推論 inferenceをつかって論証 argumentする事である。論述の形は数学的にはトートロジーになり、それを「論理学」と考えるひねくれ者が論理学者にはおおいが、社会科学では統計学的推論つまり大数の法則が成立すれば良いとされる。また政策や戦略において何をするべきかは決定論的にではなく、確率論的につまり大数の法則によるデータの分析の結果によってなされている。これが20世紀前半の出来事であり、21世紀のわれわれもここに生きている。我々は、数字をあつめて仮説をつくったり、演繹をしたりする。計測する道具を工夫して実験をする。アナロジーをつかって仮説を作る。関数あるいはパラメーターをデータを比較したり整理したりして見つける。だがこうした作業を大数の法則にしたがっておこなっていることを忘れてはいけない。
大数とはlarge populationの訳であり、populationとは母集団とも訳されるが、まさにそうで、何をもってpopulationとするかの定義がないと始まらない。西ヨーロッパでは社会とは何かが問われるようになり、このpopulationの定義なしには議論は進まないのだ。そしてこの作業をおこなうなかで、偶然chanceというじゃじゃ馬をを飼い慣らし(taming)て決定論を紛れ込ませたのが19世紀から20世紀初頭に代表される思考である、というのがハッキングの主張である。つまり統計的資料がそろってきており、その分析のための大数の法則が整備されているにもかかわらず、その根幹の偶然の考え方を丸めてしまったのが19世紀なのである。これを打ち破ったのが20世紀初頭に登場したアブダクションを提案したC.S.パースなのだが、この話もまたライプニッツの話と同じで、もうすこし後で詳しく展開したい。
さて、話をもどすと、大量に印刷された統計データから偶然ではなくて必然性を、つまり偶然性を飼い慣らした思想家がいる。1人はマルクスであり、もう1人はデュルケムだ。
デュルケムの社会的実体the socialの社会学がどのように形成されていくのか、を次は見てみたい。ここはラトゥールは何をどのように乗り越えようとして関係性の社会学を提案しているのかを理解するために超えなければならないところだ。
重要なまとめ 2:統計 statistic と確率 stochasticは別の概念である。
Aという現象がBという現象を決定論的に生み出すのか、偶然にうみだすのか?では世の中の出来事や仕組みの成り立ちを説明する方法が決定的に異なる。19世紀に様々な活動の記録が統計としてまとめられたときに、その統計からAという現象がBという現象を「決定論的に」うみだすという考えがうまれた。これは統計データを決定論的に「飼い慣らした」ものであって、統計データを偶然の説明とみる確率論とは大きく違う哲学である。Aという現象がBという現象をうみだしたのは偶然であるとするのが確率論の哲学であり、17世紀のライプニッツから20世紀初頭のパースに続くもので、この考えを退けてきたのが19世紀から20世紀の哲学なのだ。sociology of associationはこの確率の世界を扱うものである。
第3回 Actor-Network-Theoryについて
Actor Network Theoryについてわかりやすく正確に説明したいとおもってwikiを見ていたら、なんとなく説明に悪意を感じた。またANT 理論をラツゥールとともに提唱したJohn Lawのサイトも20年くらいアップデートがない。そこで、本書が書かれた2005年の状態でANTをどのように説明しているのかをまず見てみたい。なにがANTでないか、というところから始まるのがフランスの学者らしい。
ANTという理論をラトゥールとその仲間が提唱したのは1981年ごろで、1980年代の後半に彼らの理論的な論文が発表される。ここではまだこのあたりの詳細には踏み込まないでおく。一番の肝は分析の対象にActorをおき、Actor同士のインタラクションを研究していくのだが、そのとき、Actorは人間だけではなく、人間ではないものも含むとされた。ただし、人間以外に拡張されたActorは、それ自体に意味が課せられていたり、物理的生物的な特性で記述されるだけではActorではないとされた。人間との相互関係でなにかを生み出す必要があるのである。ラトゥールがそのよい例としてあげているのが分散認知研究の民族誌の傑作といわれているEdwin Hutchings の Cognition in the Wild である。この本はデザイン思考の調査の大傑作であある。人間と道具とか共同して一つの世界、アメリカ海軍の水先案内人が船を無事に接岸させるまでを記述している。人と物がインタラクションをして目的を達成する仕組みであり、これがANTの世界だとラトゥールはいう。最後にANTが現状の社会学的な分析をことごとく否定する点に注目してポストモダンや脱構築の議論と一緒にしてくれるな、と述べる。新しい世界をみるために現状に世界認識を否定破壊しているのであって、大切なのはそのあと再構成 reassemblageすることであり、壊しっぱなしのポストモダン脱構築とは違う、さらには批判社会学とも違う、というわけである。
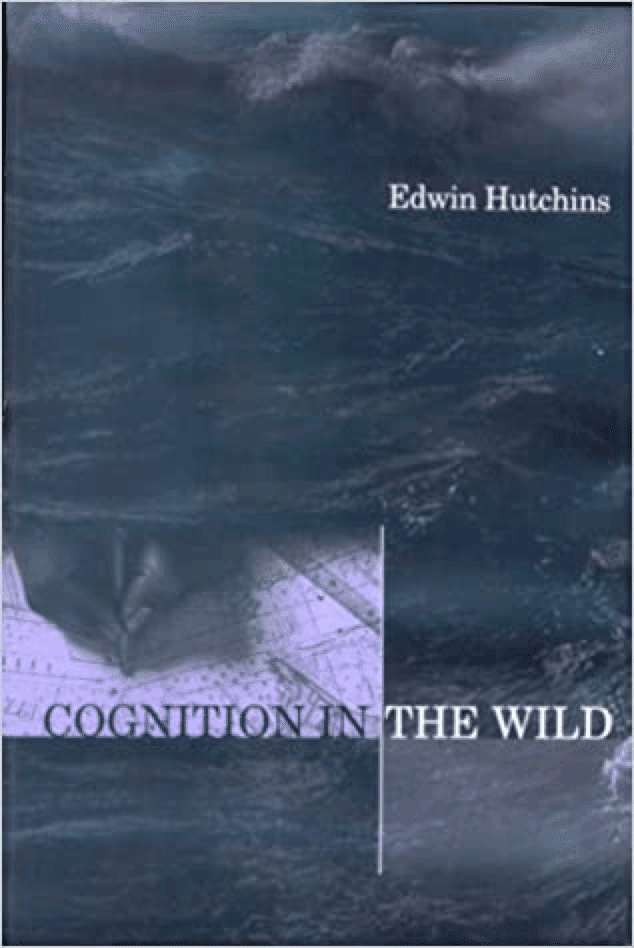
人間であるActorと非人間のActorが今までにない関係を結んでいくところにイノベーションが生まれている、というのが科学の実験室などを調査したラトゥール達の発見であり、それを体系化したのがANT理論である。何が起こるのかはわからないので、Actorの動きを追いかけていかなくてはいけないのだ。社会は体系として存在しているわけではなく、人間が他の人間と社会的な関係を結ぶ痕跡としてできあがっていく、というラトゥール達の見方はじつは社会学が始まる時代にデュルケムの主張に強く反対していたタルドという社会学者の研究に始まるという。タルドの話はまた後ほど詳しく行いたいが、ここでは社会が存在しているというデュルケムのかんがえが登場した時に、社会は作られ続けていて存在しているものは痕跡にすぎないという見方がデュルケムと同時代に存在していた、ということを覚えておこう。タルドの主著とラツゥールによるタルドとANT理論の紹介の書籍を紹介しておく。


このようにANTを定義すると、次の課題は
1)いかにしてANTを巡る論争をANT理論の展開に上手に活用していくか
2)ANTが自分にかかわる論争を解決していくプロセスをどのように追いかけて痕跡として描いていくか。
3)社会的なるものを社会的事実としてではなくて集合体として組み直す reassemble 効果がある手続きはどのようなものになるのか
となる。注目すべきは英語テキストでつかわれている
deploy render procedure
という言葉の使い方だ。コンピュータやシステムの分野で使われている言葉で、deploy はなにかを効率的に使う、という意味である。render は生成する描くという意味だ。procedure は使うと効果が確認できている手続きという意味になる。こうした動詞で描かれるのがANT理論であり、コンピュータネットワークの理論としても使われていくのが動詞に注目するとよく分かると思う。
さて、ラトゥールはこの本『社会的なものを組み直す』を旅行ガイドブックとして読んでもらいたいという。慣れ親しんだなんてことのない日常生活が、この旅行ガイドをとおしてみると、エキゾチックでわくわくしたものになるので、ゆっくりと旅をしてほしいと述べる。ありふれて日常がわくわくするために「どこを旅すれば良いのか」「何を見れば良いのか」を説明したのがこの本だという。日常世界をみる「方法」とか「方法論」という言葉ではなくて「旅行ガイドブック」と呼びたい。それはこの本が、新しい日常世界の見方をお勧めしているガイドであって、実際に旅をしない人が旅をした気になる豪華な旅行記ではない、ということだ。実際に退屈な日常をわくわくと旅をするためのハウツー本である。この本をガイドブックとしないで、社会的なものを組み直して、様々な社会的な事柄が組み合わさっていった痕跡たどることは難しいだろう、と言いながら、ラトゥールは我々を日常世界へのみたこともない旅へと誘っているのである。その旅については次回から順番にかたっていきたい。
第4回
第一の不確定性の発生源(53ページから71ページまで)を読んで見よう。
ANT の調査はすぐに始められる。調査の目的はアクターとアクターとのインタラクションによって残された痕跡の記述、それがネットワーク、であるのだからANTの調査をするときに、大切なことは調査をする集団をきめて調査をするのではなくて、集団の生成を調査するということを理解しておく必要がある。これは必ずと言って良いほど、初学者がまちがえるところで、調査対象やその定義から始めてはいけない。ラトゥールはこれをラテン語のin medias resという言葉を使って説明する。
in medias resと行っても聞き慣れないだろう。例によってWikiをひくと、古典ラテン語で、イン・メディアス・レースと発音する。物事の真ん中へ、という意味で、舞台や物語において、過去の出来事を語ったり、いきなり過去が現在にフラッシュバックしたりする状況だ。有名な例はシェイクスピアのハムレットの冒頭で、劇はハムレットの話であるが、ハムレットの父の死から始まり、その詳細に関しては飛ばして つまりin medias res して、訳すなら出来事の途中にいきなり介入して、物語が始まる。ハムレットとその父親との関係とか父親の話の詳細などを飛ばして本題にはいっているのだ。
この手法は背景の詳細について語ることなく物語を進めていくために用いられていて、ギリシャ時代の詩人のホーマーが使っていたとwikiでは説明されている。ようするに叙事詩を語るときに多用されていた方法だ。我々はこの手法に映画のなかで何度も出会っている。スターウォーズの映画などど、第一作から大きな複雑な物語の「途中」として始まっている。
wikiの言っていることをざくっと紹介したが、物語を語る手法として、途中から始める、というのは伝統ある普通の方法だ。ANTの調査も目の前のアクター同士のインターアクションの記述つまりやりとりの痕跡からはじめればいいのだ。なぜこのことを最初にいうのか? それは、なにかを決める、つまり定義をしないと観察に向かえないというのが、いまの学問で訓練された若い研究者の態度だからだ。ここを変えないと何も始まらない。
ANTをつかった研究をして良いのかどうかわからない不安(uncertainty)の最初がこの問題である。グループに注目するな、グループの組成をみろ、ということが信じられない。この教えはいわゆる社会科学や社会学の入門の本で最初に書いてあることとは全く違う。どの集団を調査するかを最初にきめるのが通常の方法だからだ。きちんとした集団を見つける、という作業が先行する。だが、調査を始めるときに、なにからでもいい、というのがラトゥールの立場だ。
僕は30年近く産業界での人々の行動を民族誌調査をしてきた。この経験からラトゥールの言っていることはよくわかる。新聞というアクターを「読む」つまりはインタラクションを起こすと、そこからいろいろなことが見えてくるし、こちらもなにかかんがえる。これが関係性の痕跡を残すということなのだ。政治記事や音楽などについての文化記事、あるいはコンピュータの使い方みたいな生活欄の記事。そのすべてが緩い痕跡をのこす。ここから出発するべきなのに、どのような集団を調査すべきか、とか偽りの集団ではなくて調査に値する本当の集団はなんであるか、とか調査するのはミクロレベルなのか、メゾレベルなのか、マクロレベルなのかを考える。だが、こんなことは関係ない。始めれば良いのだ。
ANT調査の妨げになるのは、集団が存在しているという思い込みなのだ。統計的な集合を安定して確立した集団とみなす、というのがこの考え方の出発点(つまりはデュルケムの社会認識)にあるというのがラトゥールの主張である。なぜデュルケムなのかは『偶然を飼い慣らす』の第20章、第21章、そして第22章を参考にしてもらいたい。

さて、議論を進めよう。まずアクター同士のやり取り(ネットワーク)を観察してその痕跡を記録する。すると痕跡があらわれてくる。グループというものが存在していれば、そのなかで物事がおこっていて、何も我々の目に触れることはない。だが我々が痕跡をみることができるということは、アクターが別のアクターとやり取りをおこなっていて、そのブレが記録されるので痕跡がのこるのである。やり取りをおこなうというのもラトゥールはperformという言葉を使っている。この言葉は重要になる。performativeというように使っていく。
痕跡をグループの形を示していないとすると、それは何なのか?が次の問題になる。グループが常に生成されている記録だというのがラトゥールの立場だ。これがperformative な定義ということになる。つまりグループを作り続ける行為(performance)をやめればグループはなくなってしまう。長期的な安定性がグループにあれば、むしろそれは異常なことなのだ。グループをつくるのはグループに備わっている、つまり共有されている特性だと考えるのが社会的なるものの社会学であり、関係性の社会学であるANTでは次のように考える。英文を書いておく。
Social links have to be traced by the circulation of different vehicles which cannot be substituted by one another.
つまり、アクター同士の結合は、(くねくねした道を)動き回っている自動車(actor)、それも他の自動車とはかわることのできない、独自の自動車達がつくりだす巡回行動によって描き出されるものなのだ。
ということになる。ごちゃごちゃした道を全然種類の違う車が行き来する様子が記録されてそこに描かれている痕跡が「社会的結合」つまりはANTすなわちActor-Network-Theoryの姿なのだ。ではこの世界はどのようなものなのか。この説明は次の回に譲りたい。
第5回
前回、第1の不確定性の発生源、つまりなぜANTの理解が難しいか、それは社会集団なるものはない、集団の組成だけだあるのだ、を論じた。難しかったと思う。ちなみにラトゥールはANT理解の難しさを5つあげており、またその説明が「難しい」ときている。なので、このノートではそれぞれをわかりやすく説明していく予定だ。
で、第4回では最初のわかりにくさのところで、社会というグループはなくて、グループを形成するという行為つまりパフォーマンスだけがある、ということを議論したが、第1の難しさを理解するためには、グループを形成するときにアクター同士でおこなわれる交換を記述する言葉の理解が必要となる。
ものとものとの交換では「市場」というものに交換が支配されているという考えに疑問は生まれない。アダム/スミスの「神の手」というやつだ。それは社会的であるとはシステムが平衡状態(equibirium) に到達するための活動ということだ。市場原理とはすべての交換が平衡に向かっていくと言うことである。ところがANTの交換あるいはサービスを提供するという動詞のサービスの交換ではこうした平衡状態を前提とすることはできない。社会的とは交換が成立したときに相手との間でだけ共有できるものである。現象学者はこれを間主観性(inter-subjectivity)として議論してきたが、それよりももっと動的な理解が必要だ。つまり、ある関係が次の関係に変化したときにおきるわずかな変化をとおして理解できるものをANTは扱うのである。ラトゥールはこれを次のように説明する。ちょっと長いが引用する。
It is only a movement that can be seized indirectly when there is a slight change in one older association mutating into a slightly newer or different one. Far from a stable and sure thing, it is no more than an occasional spark generated by the shift, the shock, the slight displacement of other non-social phenomena. Does this mean that we have to take seriously the real and sometimes exquisitely small difference between the many ways in which people ‘achieve the social’? I am afraid so.(p.37)
つまりいまあるグループ(組み合わせ)がつぎのあたらしいグループへと組み変わっていくときに、ちらっとスパークするときにのみ見えるような些細な変化、それまで社会的なるもの(グループ)に組み込まれていなかったものが組み込まれていく一瞬の動きあるいは前の状態からの差異についてしっかりと見ていかないと組み合わせとしてのグループあるいは社会とは何かを議論することはできない、というわけである。
ではそのささやかな差異に注目するとして、どうすればいいのか?ラトゥールの答えはアクターとアクターの結合の種類に二つあることに目を向けろということで、彼はそれをmediatorとintermediatoriesと呼ぶ。その説明に話を進めていきたい。
Mediator vs. intermediaries(2022/09/25修正)
人々が結合して新しい組織をつくる現象に「社会的なるものの社会学」(つまりはデュルケムに代表され、僕たちが大学で普通に学ぶ社会学)で扱ってこなかったわけではない。お祭りやトーテムが社会的な紐帯を強化するために必要となるとは社会的なるものの社会学でも議論されてきている。だが彼らにとって社会秩序が再生産される時のこうした現象は、「同じ」社会構造の表現に過ぎない。社会が再生産 repuroduce され同じ構造が祭礼やトーテムとして示される。この示されるという言葉は’represent’であり、ラトゥールの英語のテキストでは括弧にはいっている。また「同じ」はsameであり、こちらはイタリックである。そして再生産は括弧にはいって’repuroduce’である。何を言っているかというと、ダイナミックな現象にみえる祭りやトーテムへの進行も、変わらない同じ社会構造そのものを代表・表現したり、同じものをもう一度作ったりしていると解釈するのだ。representというのはもうちょっと説明すると、選挙で代議士(represent )を選ぶということと同じ意味であり、多くの選挙民の代理として議会で活動するからrepresentなのだ。ある人たちの意見を一人で代弁するというのが議員である。その用法だ。ようするにデュルケーム社会学的には社会構造が安定して存在していることを示しているに過ぎないのだ。
ところが、アソシエーションの社会学では、人々のグループはなにか強烈な糊とかそういったもので強固に結びつけられてはいない、とする。集団をむすびつけているのは ostensiveな活動と performativeな活動がある。ostentiveとは何があっても存在している状態である。performativeとは「第4回」で説明したように、動いている状態である。ダンサーがダンスをしているときにダンスは存在する。ダンスが終わればそれは消え去る。これがperformativeということだ。このことがわからないとANTの理解は難しい。
さてANT理論はここがわかると、最初の難関(といってもあと4つあるが)を超えることができる。intermediariesとは社会的なものの社会学が考える交換を意味する。インプットが決まるとアウトプットがきまるような接続の事である。mediatorとはインプットからアウトプットを予測することができない。こう書くと、intermediaries の方がシンプルなプロセスに見えるかもしれないが、実際にはインプットとアウトプットを一致させるために複雑なプロセスが発生しており、intermediariesは見た目複雑でもインプットとアウトプットが違うので、ただそれだけ、というわけだ。コンピュータシステムはうまく動いているときは複雑なintermediariesと見えるが、ひとたび動かなくなると、複雑でどうしようもないmediatorである。一方かろやかに進む学会のパネルディスカッションは複雑なmediatorによって行われている作業のように見えるが、実際は別のところで意思決定がおこなわれていることをうまくわかりやすいようにつないでいるintermediariesである、とラトゥールは述べる。社会現象を観察するときに目の前で行われている交換がmediatorなのかintermediariesなのかを判断することが非常に大切になってくる。
さて、目の前の交換がmediatorなのかintermediariesなのかを決めることができると、研究する社会は社会構造の「再生産されている reproducted」のか「作り上げられたのか constructed」を決めることができる。再生産に使われている道具や方法と作り上げるときに使われる道具や方法を区別することができるからだ。ラトゥールはこの違いを次のように説明する。絹とナイロンがintermediariesを通じて関係しているとする。すると絹とナイロンの違いはいつも決まった方法で説明される。つまり、手触り、色合い、輝きが絹とナイロンは異なるという物質的な違いに話は終始する。ところが絹とナイロンがで関係付けられていると、高級な人は絹をみにつけて、低級な人はナイロンを身につける、というmediator的な言い方が生まれる。すでに存在している高級な人と低級な人の違いが、その社会的な仕組みとは関係ない化学的な絹とナイロンの違いに ’express in’され、’project upon’ されるのだ。例によって引用符はラトゥール自身による。つまり彼独自で強調したい表現なのだ。
従来の社会学では社会をすでに存在しているグループのどれかに分けようとする。その作業は「社会工学」として社会学が19世紀半ばに始まった事による。社会を構成する要素はなにか、つまり化学や物理学のような科学者が問いかける問題、さらには同じ意識で政治学が問いかけたような問題を社会学者は提示するべきだと考えられていた。革命の時代が続き、何が正しいのかわからなくなっていた19世紀において、もっとも妥当だと思える社会とはなにか、について社会学者は考えたのである。intermediaries な考え方である。その結果として、観察した人がどのような行動をしているのか、に考えを及ぼさなかった。これはこの時代に勃興したもう一つの社会科学である人類学と大きく違っていた。人類学者は西洋社会とは違う社会に直面して、彼らの行動を民族誌として記述し、それを解釈して人間が集まって活動をする様子を研究した。社会学者はいまこそ社会を研究するのではなく、人々(アクター)がどのように行動するかの民族誌を描き、そこから解釈をして人々が集団を形成するプロセスに注目すべきなのだ。これがmediator的な学問である。
このような行動をするために、mediatorとintermediariesという二つの簡単な道具は役に立つ。ANTで社会を研究するときに社会という全体を見ようとするのではなく、アクターがネットワークを(交換を)通してグループを形成する仕組みを見ることができるのだ。人々の行動は社会の形を示す言葉に翻訳することはできない。社会工学のように人々の集団を本来あるべき社会へと変えることはできない。人々の行動を観察して「解釈 interpret」する事しかできない。また次に第二の問題でみるように、アクターは人間だけではなく、アクターとアクターの関係がmediatorなのだintermediariesなのかを判断しながら記述する作業は社会的なるものの社会学(デュルケム社会学)つまりintermediariesが示す世界とは大きく変わっているmediatorの社会学となるのである。
第六回
さて、ANT理論を理解するときの第1の障害は社会を存在しているものとみることであって、社会は人々をつなぎ合わせることで生成されていて、つねにその生成作業はおこなわれていて、我々が観察できるのはそのプロセスの痕跡だ、ということである。安定した社会の形はなく、そのような形にみえるような揺らいでいる痕跡だけが我々は観察できる。その痕跡を痕跡としてみていくことでANT理論は理解できる、というものであった。痕跡を生み続ける活動をperformativeと呼び、それは活動が終わるとともに観察できなくなる、とするのも非常に大切な見識である。
ANTをわからなくしている我々のものの見方は5つあり、第二のものの見方の説明に移っていきたい。それは行為はそれ自体で起こっているのではなくて、他者とのやり取りが行為なので、そこまで視野を広げなくてはいけない、ということである。それをAction is overtakenと表現している。これはまたわかりにくい表現だ。overtakeとは遅い車を追い抜くときの動詞だ。Action つまりあるactorのactionが、別のactorのactionに追い抜かれる、というのが言葉の意味だ。だが、もうすこし考えてみると、あるactionは何らかのものに突き動かされている(overtaken)と考えることもできる。感情に負けたとか突き動かされたといったような意味である。ANT理論では社会的なものをみとめていないのだから、あるactorのactionがたとえば資本主義の精神によって突き動かされた、という普通の社会学的な表現は表現はANTにはなじまない。ANTでは人間のアクションはなにかに突き動かされているとは見ない。では、その「何か」はなにか?ということである。
我々は様々な要因がくみあわさった「社会的な」ものによって行動をしている。この表現には問題ないとラトゥールは言う。だが、「社会的なもの」が生物学的、物理的、経済的と同じような意味での社会的だとすると、「社会的」なるものにアクションが突き動かされているという見方は問題となる。ここが混同されるのでANT議論は展開しない、とラトゥールは述べる。なぜ、あの人の行動は、あの人行動はその人の環境の中にある物理的、生物的、経済的要因が混ぜ合わされて起こっているのだ、という説明をしないのだろうか?
さて、ここでANT理論はaction, actorにくわえてagentという概念を登場させる。またそれにあわせてagencyという概念も登場させる。このあたりわかりにくいのだが、agentはなんらかのactionを行うあるいは行うことを許可されたactorであり、agneyはactor あるいはagentに何らかのactionを起こさせる力と理解しておこう。
私たちが何か行動をしようとしているときに、それを押しとどめる、つまりはagentになれない、何らかの要因がある。この直感が社会学者を虜にした。いままで見てきた例をあげるなら。デュルケムやマルクスは社会統計が示す特徴を社会的な実体としてみて、それがactorに何らかの活動をさせる力つまりagencyとなったと考えたのだ。その要因は群衆
(crowds)、大衆(masses)、統計的資料 (statistical means)、(神の)見えない手(invivisible hands)、だったり無意識の衝動( unconscious drives)、といった広く人々にもとめられた直感的概念だった。我々のactionはこうした「実体」に突き動かされている、つまりaction is overtakenと考えたのだ。これが社会を実態とみた第一の誤りに次ぐ、第二の誤りである。なんらかの原因が直接わかりやすく(transparent)actionを説明することはな
い。Actionとはさまざまなagencyがつながり、からまり、その結果うまれるのであって、actionについてしりたければ、このこんがらがった状態を丁寧に解きほぐしていく必要があるのだ。それをおこなうのがANT理論なのである。(続く)
第7回
actionについての議論を続けたい。我々つまりはactorがactionをしているとき、それは一人で行っているわけではなく、他のactorとのインタラクションをしているのだ、というのがラトゥールの主張だが、これはどういうことだろうか。ここでラトゥールは階級に関する議論を巧みに持ち出す。ひとつはブルデューのいう「ハビタス」である。これはある集団は特定の文化資本をもっており、そのなか(つまりはハビタスのなか)で育たないとその文化資本は継承できない、とする考えである。つまりクラッシック音楽を楽しむ教養はそれを文化資本とするハビタスで育たないと身につかないので、そうした文化資本のない下層階級に生まれた若者は勉強して社会階級を上昇するというアクションをしようとしても、文化資本がないので、上層階級にはなれない、とする考え方だ。あるいは誰かを好きになったとする。これもアクションだ。その誰かは結婚パターンの統計的調査からすると、身長、学歴、収入、住んでいる街などがほぼ統計的に自分と同じようなひとであることが多い。こうしたactionを引き起こしているもの(エージェンシー agency)はいったいなんなのか?これが問題となる。
社会的なるものの社会学者であれば、エージェンシーとして社会的なるもの、つまり文化、構造、ハビタスなどをあげるだろう。だが、そのような短絡的な説明方法をやめるべきだ、とラトゥールは言う。アクションはアクションとしてそのままにしておけ、なにか社会的なことからアクションがおこされた、と考えるのをやめよう、というわけだ。このラトゥールの、つまりアクターネットワーク理論のアプローチをとると、ほとんどの社会学的説明のみならず、マーケティングのセグメントの考えなども成立しなくなる。我々がアクションするのは「社会的なるもの」によってではないとする。では我々はなにによってアクションするのか?
ラトゥールはそれは他のアクターとの関係性によってであるとする。ただし、「アクター」の定義が問題だ。アクターは人間だけではないと最初のANT理解のアプローチとして説明される。説明の例として舞台での演劇が用いられる。アクターネットワークにおけるアクターは舞台の言葉から来ている。我々がアクターとして舞台の上で演技をしているとき、アクター(役者)一人で演技をしているわけではない。舞台で演技がはじめるとアクターは複雑な筋のもつれ(imbroglio)に取り込まれ 理解不可(unfathormable)な状態になる。社会学者のアービン・ゴフマンが『行為と演技』で述べたように、舞台の上でアクションしているアクターにとって、確かなことはなにもなくなるのだ。アクションをうみだしているのは、観客なのか、照明なのか、脚本家なのか、どれなのか?つまり舞台の上のアクションはアクターネットワークの産物であり、アクターは自分のアクションを何が生み出しているのかわからない状態で演技をつまりパフォーマンスを行っている。
このようなときに、社会学者はアクターのアクションについて、それを動かす社会的なるものを設定するのではなく、関係性の社会学者としてアクションは痕跡に過ぎない、と見るべきなのだ。集団がつねに組み直されているとき、アクターのアクションもまた多様に揺れ動いていく。アクターの多様な行動、とりまとめようのないインタビュー、複雑な表現などすべてが貴重な痕跡の記録であり、それを無視してはいけないのだ。調査をしたときに、インフォーマントの言葉そのものに調査者が感動する事が大事なのだ。つまり、はっとするような表現に「社会的な説明」を加えてはいけないのである。現象学的社会学者であるガーフィンケルが言っているように、アクターがいっていることに社会的説明を加えてはいけないのだ。
ここでラトゥールは政治学的な目的をもつ社会学の言い方を批判する。インフォーマントのものの言い方が正しい社会のあり方から逸脱しているのでそれをただして政治的に正しい社会にする、というのが政治的な社会学者の言い方である。また批判的社会学者にたいしてもラトゥールは異を唱える。批判的社会学者は観察からえられるデータを無視して、すでに想定した社会的な力で人々の行動を説明する。さらにそれに反発する反応がインフォーマントから出てきたときには、それは説明が正しくて耐えがたいからだとする。この段階で批判的社会学は経験的であることをやめてしまうのである。アクションを生み出すエージェンシーにかんしての経験的な議論がなされなくなる。ではどうするのか?
それはアクターの声に耳を傾けることである。アクターをうごかすエージェンシーとはなにか?これは哲学的に非常に大きな問題であって、社会的なるものの社会学者が述べているような簡単な話ではない。ヘーゲル、アリストテレス、ニーチェ、デューイ、ホワイトヘッドなどの哲学者がエージェンシーとは何かについて深い哲学的な思弁を展開している。社会学者がこうした哲学者の考察を理解すること無しに、フィールドワークにおいて出会った、
「主婦、従業員、巡礼者、犯罪者、ソプラノ歌手、CEO」の話を聞くことができるのか?哲学のこうしたインフラから社会調査を切り離すことはできない。アージェンシーの研究はそれほど慎重に行わなくてはいけないのである。次回はエージンシーの詳細について議論が展開する。
まとめ actor action agencyは哲学において大問題なのであるが、社会的なるものの社会学者は、特定のagencyが固有のactionをうみ、それを我々actorが演じていると単純化してみている。だがこの三者の関係は複雑で動いており、この複雑な動きの痕跡しか我々は見ることはできない。
第8回
Actorのactionを引き起こすagencyは複雑であって、それは丹念に解きほぐさなくてはいけない。ラトゥールはこれを実践的形而上学 practical metaphysicsと呼んでいる。これは面倒な作業に思えるかもしれないが、我々が知らない街を旅するときに、決められた道をとおって観光するという限定的なagency(能力と知識)に従う行動actionと、自由に移動してその場その場で旅そのものを楽しむような都市漂流という複数agencyのよって生み出される行動との質の差を考えてみると言い。明らかに後者の方が意味に満ち溢れたものになっているはずだ。
さて、ではこのような複雑なエージェンシーの集合とどのようにつきあっていけばいいのか。ラトゥールは観察から複雑なエージェンシーを見つけていく方法を4つ提示している。
1)agencyの存在はactionの活動報告あるいは痕跡として記述され報告(account)されなくてはならない。これはギアツの解釈学的民族誌あるいはガーフィンケルのエスノメソドロジーでも強調されていることだが、あるアクションが、あるエージェンシーによって別のアクションへの変化していく動きの中にのみ、エージェンシーの存在が説明できるのである。ここに証拠を報告できなくてはいけない。(これはaccountabilityという事である。現在やっていえることが報告可能であるという考え方だ。これは大切な概念だが、この問題には現在論じている5つの問題の5番目で議論する。いまは2番目の問題を議論している。)
2)agencyとfigurationは別物である。これは非常に大事でちょっと難しい表現だ。報告accountはかならず、なんらかのfigurationをもって行われる。この言葉は非常に捉えにくい。意味は形や姿であるが、figureというのは数字の事でもある。統計的数字による表現もfigurationだ。一方姿という意味もfigureにある。民族誌や人類学が報告するのは人々の生活であって、これは人の行動の報告そのものである。統計データをしめされたとして、その
データの周りにどれだけ多様な行動があるのかはわからない。逆に個別のアクターの記述が、社会におけるさまざまなアクターとどう関係しているのかもわからない。抽象的な数字と詳細な記述の間で何が社会でおこっているのかの理解が止まってしまう。ラトゥールはこの両方ともfigurative sociologyであって、社会の研究には使えない、と述べている。このあたりは、僕はよくわかるね。社会の関係性の研究の統計的妥当性をもとめる、という批判がまあ大半なんだけど、一方で、全く個別の事例で押し通そうとする研究も辟易する。
ではANT理論ではどうするか?この問題を解決するために新しい理論的概念アクタン(Acton)を導入する。ラトゥールはactionが一人のactorによってなしえるものではない、ということを説明するためにactonという言葉を使っている。文学では登場人物は自由にさまざまな役割をもって動き回る。なのでその活動を記述するために文学研究者がつかっているactonという概念を社会の分析に借用したのである。関係性の社会学者はactonの行動を選別するのではなく記録(record)し、規律をあてはめるのではなく、叙述(describe)する。
3) 研究者は研究対象の人々による世界制作の活動(world-making activities)に付き合う必要がある。いまある世界をそのまま記述する。グループが形成されていくパフォーマンス(group perfomation)はあたらしいエージェンシーを付け加えるだけではなくて、特定のエージェンシーの排除でもある。こうして生まれてくる世界を記述することがたいせつなのだ。
4) actorは特定のagencyがいかに有効かを自分の行為の理論(theories of action)として示してくる。そしてagencyをmediatorとしてつかうかintermediariesとして使うかの選択がうまれ、それによって結果は全く違ってしまう。どのagencyを選択するか、ではなくて、選択したagencyをmediatorとして扱うか、intermediariesとして扱うか、が問題なのだ。
大分難しくなってきた。actorのactionを観察するときに、その行動をきちんと記録して報告することが大切であるという。そのときに統計的数字(figure)や典型的登場人物actor(これもfigure)という二つのfigureに観察したことをまとめ上げてはいけない。agencyはfigurationで説明できることではない。むしろ、actionの背後にある様々なactonであり、それがactorと結びついて様々なことが起きてくる。actonとは文学理論で作られた概念であり、物語の中で様々な活動を行う。物語のエージェンシーは、「魔法の杖、こびと、妖精の内心の思い、二十数匹のドラゴンを退治する騎士」などさまざまなものがあり、それが同じactonを動かす。社会においてもactorをactonと見れば、様々なagencyによって動かされる(action)のであって、特定のagencyがactorの背後にあって、決定的にactionが行われているわけではない、と見ることができるのだ。ここを理解すると、社会のなかで活躍しているactorがどのようにagencyを選んだり排除したりしながら、自分の世界をつくっているかの様を記録して記述することができる。その記述をもとに、どのagencyがmediatorでどのagencyがintermediariesであるかが見えてくる。関係性の社会学にとってはmediatorとしてのagencyが重要になる。すなわち、インプットからアウトプットが予測できないactorのつながりに注目することが大切になるのだ。
次回はmediatorとしてagencyを扱うことができれば、何ができるのか?について議論を展開していきたい。
第9回
さて、ANT理論を勉強するときに混乱する第二のポイント、行為(アクション)は複数のエージェンシーが媒介項で連結されたなかで行われる、の結論である。ここまでアクター(アクタン)、エージェント、エージェンシーという言葉について勉強してきた。アクターが連携(ネットワーク)して、集団を生み出していく動き(相関 association)を研究するべきであって、その動きの痕跡しか我々は見ることができない。それを実体と思ってはいけない、というのだ第1のポイントであった。連携するのはアクターだけではなくてエージェンシーもである。これが第二のポイントとなる。
エージェンシーとはアクションを生み出す(現状を変えていく)力のことである。ある行為があるエージェンシーと中間項 intermediariesでつながっていれば、エージェンシーが原因となってアクションが結果となる。だが媒介項 mediator でつながるとそうではない。予測不可能なことがいろいろおこる。原因から結果を演繹することはできない。ANTではある行為を生み出す活動に関係しているエージェンシーを媒介項を介して記述するという方法をとる。可能な限りの多くの原因をアクターの連携とあわせて記録していく。
ここの理解はactorがものでもあるということを忘れると非常に難しい。ラトゥールはここの説明に操り人形遣いの例を挙げる。人形遣いは人形を操っているが、「操り人形が、思いもよらない動き方を教えてくれる」という言い方もすると言う。操る manipulateのラテン語には手を意味するmanusが入っており、manipulateの意味は 手で物理的にものを取り扱う技術(skill in physically handling objects by hand)である。つまりアクションは複数のエージェンシーの連結のなかに分散しており、アクターも他のアクターと集合したり離散したりしている。この状態を記録することが大切なのだ。ものである人形は操られるだけではなくて、物理的物体として動く。その動きが人形遣いに新しい動きを生み出す、というわけだ。
ここでラトゥールは注でこの考えを説明していくが、僕が教えているデザイン思考では「濃い記述」がここに相当する。人も物もアクターとしてあつかって記述分析を続ける。これはギアーツの解釈学的民族誌の方法であり、さらにはインタラクションの民族誌の基本でもある。ラトゥールがあげる3冊の本は、デザイン思考の方法を考えるときに基本書なので、ここで紹介しておく。分散認知の民族誌と言われている。
Edwin Hutchins(1995) Cognition in the Wild

Jean Lave(1988) Cognition in Practice: Mind, Mathematics and Culture in Everyday Life

Lucy Suchman(1987) Plans and Situated Actions

この3冊は今後のANT理論の展開においても基本となる。上記のうちCognition in the Wild 以外の2冊は翻訳されているが、現在はこの2冊は加筆改訂されている。いずれも名著であり、しっかりとした理解が必要だと考える。
もう一つ大切な方向は現象学だ。アクターを複数かんがえて、そのネットワークを動かすエージェンシーは分散された状態で存在している(つまり複数のエージェンシーが媒介子で連結されている)という視点は現象学が持ち込んだものであるが、現象学にはものという視点がまだない。ハイデガーは「道具」である。また批判社会学も、エージェンシーとして、人や、意図、感情、対面といった要素をだしてきているが、これもまたものは存在しておらず、こうしたエージェンシーがあれば自動的にアクションが決まってくるとしている。
では今後どのように研究を進めていけば良いのか。ラトゥールは次の4つの方法でANTの報告(民族誌)はかれるべきだとする。
1)どのようなエージェンシーが引き合いにだされているか
2)どんな形象figureがそのエージェンシーに与ええられているか
3)エージェンシーはどのようなアクションに関わっているのか
4)議論しているのは中間項によるエージェンシー連結(意味がない)なのか媒介項によるエージェンシー連結(意味がある)のか
この視点でたとえば組織マネージメントの民族誌を記録することがANT理論を構築するためには必要となってくるのである。
(続く)
第10回
ANTを理解するための第3の障害についての説明に入りたい。それは「ものobjects」にもagencyがあるということを我々は社会を研究するときに忘れてしまう、という問題である。action 行為は複数のagencyによって個別のactorを超えてなされるということを理解することが大切だ、というのがANT理解の第二のポイントであった。このときに社会的なるものの社会学者は社会に非対称が存在するとき、それはそれを引き起こすagency(時に複数)があり、それはニュートンがものの落下における重力の存在を示したように、社会のシステムがひとつの独立したシステム(sui generis)であって、その構造を決定している重力の力のようなものとして、社会的なるものの社会学者は疑ってこなかった、とするのだ。
ところが、アクター同士が関係して、複数のエージェンシーが関係して動き回るものとして社会をみて、なおかつ観察できるものはその動きの痕跡だけだとする関係性の社会学であるANTの視点からすると、この説明は受け入れられない。社会関係あるいは格差ですら、安定したシステムがあるのではなく、関係性がうみだす痕跡なのだ。その痕跡を見るために、ラトゥールがつかっている英語でみると、a movement, a displacement, a transportation, a translation, and enrollmentに注目することとなる。もので考えると、お店にものが配置されるときに、パッケージが変わったり、値段が変わったり、値札がかわたりする動きの痕跡にものともの、ものと人の関係が痕跡として見えるのである。そして物も人も同じactorとして見る必要がある。
ではその痕跡はどのようにうみだされるのか。ここでANT理論は我々に認識の大きな変化を要求する。それは人と人との対面的な動きの痕跡(社交的スキルとも認識される)だけではなく、弱々しくしか認識されない社会的な関係をより強いものへと変える仕組みも存在しているという認識だ。つまり社会的関係はうつろいやすいので、より持続性をもつ堅牢な性格を持つものによわよわしい社会的関係性を置き換えている。それは社交的スキルだけでは生み出せないものである。そこにactorとしての「もの」が登場する。
関係性の社会学者は人間以外のActor、つまり釘を「打つとき」はハンマーに注目すべきだし、お湯を「沸かす」ときにはヤカンに、肉を「切る」ときはナイフに、食料品を「積み入れる」ときにはカゴに、など、動作を行うときには人間も道具もactorとして注目するべきなのだ。つまり動詞に注目する。だが、こうした当たり前の行動を記述することにどのような意味があるのであろうか。
ものは物理的な世界にあるとしてしまうと、人間が他の人間と関係するときにreflectiveでsymboicな関係が見えなくなる、とラトゥールは述べる。わかりにくいところろだが、人と人の関係に何らかの意味が生まれているときに、その関係に参加しているものの役割を考える必要がある、ということである。関係性に参画するという役割をラトゥールはparticipantsと呼ぶ。ものはparticipants(翻訳では参与子)となるのだ。participantとしてのものが社会関係を決定しているわけではない。そうであればものは中間項intermediariesである。そうではなくて、参与子として関係性構築に関与していくのである。ものがこのようなエージェンシーを持つということに関してはギブソンのアフォーダンスの概念を参考にする必要がある。
関係性においてものをactorとして観察して記録するとそこにみえてくるのは人と物がactorとして関係性を結びながら全体性を生み出している様子である。社会の特質がアクターの行動に表れているのでもなく、ものに社会的ヒエラルキーが「象徴」されており、社会的不平等が「強められており」、不平等を「具体的に目に見えるようにしており(objectify)、ジェンダーの関係を「物象化(reify)」していることがわかるのである。
さて、ここまでANT理論を読んできて、かなり本質的な問題にぶつかってくる。それはマーケティングではブランド論で語られてきた問題であり、デザインの社会的な役割についても議論される問題である。プロダクトやブランドロゴは人間のアクターAからアクターBに何かメッセージを伝える中間項ではなくて、関係異性に参与子として介入し、媒介項として、つまり何が起こるかわからない関係性を生み出していく。このダイナミズムに何らかの形で関与して痕跡を作っていく、という活動ができる。つまりもの、オブジェクト、の社会学がANTなのだ。もっと言うなら、これは僕の考えだがものをデザインする理論でもあるのだ。
この考え方は社会性の社会学とは全く考え方が違ってお互いがお互いを理解できない。これをラトゥールは科学哲学者クーンの有名な概念incommensurability(共約不可能)だと述べる。お互いがお互いを理解できないのだ。だが、人間社会とものの世界が共約不可能であるからこそ、社会関係を表現する仕組みとして使われてきたのである。ここはANT理論の根幹であり、理解が難しいところだ。次回に詳しくここを検討したい。
今回のまとめ:
組織マネージメントを考えるときに、ものをアクターとして考えることはあまり強調されていない。だが、会社のロゴやオフィスのデザイン、利用する道具など様々なものをつかって我々は社会をまとめ上げている(assemble)。それは社会の性質(階級があるとか女性の地位が低い)といったことをものが表しているのではなくてものと人間が両方ともactorとしてさまざまな関係性をこころみていて、その痕跡がもののなかに固定されて残されているので、社会をまとめ上げることに役立っているのだ。デザインとANT理論の結びつき、つまりデザインされたものは関係性に参与子としてかかわり、関係を媒介項として動かし、その痕跡をもののなかに固定する(つまり中間項となる)役割をもつ。この視点はANT理論の活用として非常に大切である。
第11回
ものをactorとして組み込んだANT理論の続きである。人間のActor同士のネットワークは絶え間なく動き回り、一見するとネットワークの仕組みにみえるものは実は痕跡に過ぎない、というのがANT理論の第一歩である。ここを実体とみると社会的なるものの社会学となり、これが痕跡にすぎないとみると関係性の社会学、つまりANTとなる。ここがわからないとANT理論は先に進まない。ここまでが第1と第2のANT理論理解への障害である。次の障害はactorは人だけではなくてobjectも含む、ということである。人間は身体を介してものと関わり世界を作っていく。この仕組みはギブソンなどのアフォーダンスの心理学者によってかなり研究されている。また分散認知などの民族誌で詳細に記述されてきた。
ラトゥールは次の3冊をもののANT理論の基本としてあげている。こうした民族誌は1970年代後半に登場しつつあったパーソナルコンピュータ(もの)と人間の関係性の結び方を考える基本ともなり、のちにデザイン思考となるあたらしいデザイン手法の基本ともなった。動詞でかんがえるというのもIDEOがデザイン思考の本をだしたときの中心課題であった。このあと、時代はユビキタスをへてIoTとクラウドに入っていくが、ものと環境と人間のあり方の調査方法は同じである。HutchinsとSuchmanの本はすでに紹介したが、Jean Laveの本は初めてである。翻訳がある。
Jean Lave Situated Learning: Legitimate Peripheral Participation (1991)

人もものもActorとして扱う、というところはいい。だが、ものは人と違って関係性の痕跡をわずかしか残さない。これが前回の議論の結論だ。ANTの記述において、人と物が何かをつくっているときにはものの痕跡は記録できる。「労働者達の一団がレンガの壁をきずいているとき」などであるとラトゥールは言う。だがひとたび壁ができてしまうとそれは壁そのものであって、人のActorとは関係性をつまりネットワークを構成していない。
ANT理論の理解を阻むのはここにある。壁を作るという活動においては人と物つまりは主体と客体の二分法はなりたたないのだが、できてしまうと壁は壁つまりものになり、人と物が共同で活動していた痕跡を理解することは難しくなる。ANTの理論を使う研究者は、人と物がかかわっていたわずかな痕跡を探して記録していかなくてはいけないのだ。そのための方法として上記のような民族誌を記述する能力が求められるのである。
ANT学者が人と物とが共同で活動をおこなっている状況、たとえばレンガの壁を積み上げているときに、作業中のレンガをきちんと取り扱うのは難しい。つまり壁を作っているときにレンガは媒介子なのだが、ひとたび壁ができあがってしまうと、それは中間項となり、レンガの壁以外のなにものでもなくなる。ものが人と関係性をもち壁になるまでの記録、これをラトゥールはscriptと呼ぶが、これを可能にする方法が必要になる。
ここで方法論的な問題を整理しておこう。performativeという話を第1と第2の問題を議論するときにおこなった。話している行為speech act、書いている行為 writing (エクリチュールとよばれる)、やインタラクション(interaction)という行為は行われると消えてしまう。これがperformativeの意味だ。何度でも繰り返されるのでその痕跡を記録(account)することは難しくない。だが、ものと人のインタラクションは一瞬であり継続することはない。痕跡を記録することが難しい。したがって、その一瞬をつかまえて記録することが必要になる。
とはいうものの、人と物が関係性をもつわずかな痕跡を記録するにはどうすればいいのか。グループとしてのactorの活動の調査をおぼえることがANT理論の第1の課題であり、agencyの調査をおぼえることがANT理論の第2の課題であった。第3の課題はactorとしてのものの調査である。どうやるのかについてラトゥールは A list of situations where an object’s activity is made easy visibleのセクションで詳しく説明しているのでみてみたい。英語版では79ページ、翻訳では148ページである。
ラトゥールはこうした記録が比較的易しいのは第1にイノベーションが行われているときだとする。これはなかなかうまい着眼点だと思う。職人の仕事場、技術者の設計室、科学者の実験室を思い出してもらいたい。作業があり、道具があり、素材にあふれている。そこでは人と物がおたがいにactorとして複雑な行動を行っている。ここでラトゥールは非常に上手な表現をする。英語では
Here, they(men and objects) appear fully mixed with other more traditional social agencies. It is only once in place that they disappear from view. This is why the study of innovations and controversies has been one of the first privileged places where objects can be maintained longer as visible, distributed, accounted mediators before becoming invisible, asocial intermediaries.
となる。つまりものをつかってあたらしいもの(innovation)を生み出そうとしている仕事場やアトリエでは物も人も視界から消えてしまう時が一瞬ある。その瞬間がものが媒介子として人間と関わり合って、予想されないことを生み出している時なのだ、というような意味の文章である。この瞬間がすぎると、ものは中間項になってしまう。実際民族誌を記述して、分析をしてIdeationをおこなって、ものをつかってコンセプトをデザインして、できたなという瞬間にいたるまで、つまりinnovationが行われたまでの流れはこの通りであり、デザイン思考でもこのプロセスをしっかりと記録することで新しいコンセプトがプロトタイプになっていくわけであり、この話は非常によくわかる。現象学で世界の中に自分が組み込まれた状態をdisappear from viewと表現する。まさにその状態がものと人の関係性の痕跡を記録できる瞬間なのだ。
ラトゥールが紹介する第2の例はたとえ単なる日常の世界であり、そこに生活する人にとってはあたりまえであっても、その世界に対して距離のある人がそれに遭遇したときに、中間項となってしまったものと人の関わりの姿がふたたび媒介子であった状態を生み出して、関係性の痕跡が記録可能になるという。これは日常性の民族誌の問題を考えるとよくわかる。
調査者は調査対象の世界に出会う。そしてインフォーマントと社会関係を結ぶ。インフォーマントにとっては当然の世界 take for grantedであっても調査者はその世界を知らない。民族誌調査ではなくても、新しい技術習得の状況を考えてもおなじようなものだろう。そこには技能の隔たりがあるからだ。見知らぬ道具、古めかしい道具は調査者にとって媒介子である。使い方のノウハウや習慣が当然のものになって視界から消える disappear from view までは時間がかかる。取扱説明書や組み立て図を読めるまで時間がかかるのだ。ここがものと人間の関係性の痕跡の記録がとれるところとなる。
さらに、このような記録が可能となる第3の事例がある。それは事故が起こったときである。これを現象学ではbreakdownという。Heideggerの現象学で使われる言葉で、我々が日常に使っているもの(道具)に我々は日常生活では注意をはらわない。disappear from viewな状態である。だが、道具がこわれると、その時道具の透明性( "transparency of equipment”)が消えて、ものを意識する。現在リスクのあるものが増えてきており、事故や伝染病や地震で、技術が張り巡らせた仕組みが突然記録可能になるようなことはままある状況にある。
第4の例としては、ひとたびものが我々の視界から消え去ってしまったときに、歴史の資料を掘り起こしてものがactorとして人間と関わっていた状況を再現する方法である。電力、電話、コンピュータチップ、コンピュータネットワークなどの「技術史」は多くの事を教えてくれる。中間項として当然のものとされているこうした技術がかつて媒介子だった時代の記録は多くのことを教えてくれるのである。
最後にラトゥールがあげているのは、フィクションを使って物理的な中間項になってしまったものを人間との結びつきが深い媒介子へと変換する作業だ。
いずれにしても、ANT研究者はものをactorとして記録する努力が必要だ。そうすることによって権力や支配がどのように行われているのかを明らかにすることができるようになるのである。(この項、続く)
その12
さて、モノをactorとして社会関係を考える社会学つまりはANT理論で社会を見るとは、社会の権力関係を組み替えていく方法でもあることをここで考えていきたい。そもそも社会を考えるときになぜ社会性の社会学者は人間とモノの関係を検討の対象からはずしてきたのか。人間のモノとの関係はデザインの問題として、たとえばドナルド・ノーマンの『誰のためのデザイン』とか『人を賢くする道具』においてかなり詳しく調べられている。社会にある権力関係はモノと人の関係に明確に表れている。モノをactorとして見るやいなや社会の中にある不平等や支配関係は明確ではないか?なぜ19世紀の社会学者はモノの研究をエンジニアや科学者に任せた。社会性の社会学者はモノそのものを議論しないで、モノの持つ「意味」「象徴」「意図」「言語」を研究してきたのである。デザイナーが何かモノをデザインするときには、どのように使うのか、何のために使うのかといった「人間的な側面」を考える必要がある。だが、それは社会学の領域に越境した行為となる。したがって、ノーマンが批判したように人間的な側面に踏み込まないデザイナーが多く生まれてしまう。一方でものが作り出す社会的関係にかんして、モノの作用(エージェンシー)の側面から議論をしないのが社会性の社会学の仕事となってしまうのだ。モノが媒介項として社会関係に影響を与える側面への研究は社会学者もデザイナー・エンジニア・科学者も行わない、ということになる。これはデカルトが思惟実体(re cogitants)をいわゆる物質である延長実体(res extensa)から分離した考えをそのまま踏襲してるのだ。
この結果、参与子としてのモノの役割は次の3つに限られてしまう。
1)マルクス流に社会諸関係を規定する「物質的下部構造」とする
2)ブルデューなどの批判社会学のしてんからエージェントとしてのモノを「社会的な階級的相違を他のグループからちがうものとして識別する「鏡」とする、か
3)ゴッフマンの考える社会的アクターがしような役を演じるときの舞台の背景とするかになってしまう。
これでは社会構造がどのように生まれてくるのかをモノと人間の相関から説明することはできない。
ところが、実際過去の社会学者がのこした記録のなかにはモノが人間と関係をもって社会を変えていく記録が残されているときもある。マルクスの『資本論』で語られている物神崇拝の記録は、ラトゥールの英語の文章を引用するなら、こうだ。
Even as textural entities, objects overflow their makers, intermediaries become mediators.
つまり、マルクスが『資本論』で描いたことは、工場で生み出されたモノが作り手をはなれて、actorである人間とモノのactorとして関係性を持ち、中間項から媒介子となっていったのである。このあたり割と研究が最近ではすすんでいる。


支配がどのようにうみだされていくのか。ANTはモノが媒介子であった状態を記録することで、権力や支配と戦うことができる。支配の状況とりわけ支配されている人を批判するような社会学ではなく、モノが媒介子であった状況を暴き出すことでANTは社会の仕組みを変えていくことができる。そのためにはANT理論理解の第4の障害を乗り越えなくてはいけない。次回からはこの問題について検討していくことにする。
第13回
いままでANT理論の理解の障害について3つのことをみてきた。それは
1) groups are made グループは社会をあらわしているものではなくて、いつもactor同士が組み合わされて作られている。
2) agencies are explored actor達を動かしている力agencyがどのようなものであるのかは、調べてみないとわからない。複数の対立するagencyが共同することがある。
3) objects play a role actorにはモノもふくまれていて、人はモノと関係を結びながら世界を作っている。社会的次元と技術的次元の区別をすてて、活動の現場を見て記録することが大切である。
以上の3つである。社会は固形物として存在しているのではなくて流動的に動いていて、それを痕跡としてしかそれを我々は認識できない。実体としての社会の存在を信じる社会学者でもここまでは理解できるだろう。だが、ANT理論はこの先をいくのだ。このことを理解することはこれから展開するANT理論理解の第4の障害の理解無しにはなかなか難しい。
この難しさは、ANT理論がそもそも科学研究として始まったことによる。科学研究(science studies)とはギリシャ語のepistemologyの翻訳であり、この分野の研究をして言える研究者達は、科学の社会学をしていたつもりだったのだが、研究が進むにつれて、社会socioのみならず学logyへの疑問も持ち始めたのである。この疑問をせいりすることがANT理解の第4の障害を越えることとなる。
Constructivism vs. social constructivism
ANT理論は「科学的事実は社会的な構築物である」というまったく間違った議論からはじまった学問であるという。社会的という言葉を実態としてみるか、様様なものが集合していくプロセスとしてみるか、という立場の違いを不用意にsocialという言葉を使ったことで混乱させてしまったが、初めは科学の問題を事実fact、科学 scinece, 構成 construction,そして社会(social)という側面から見てみようというつもりだったのだとラトゥールは言う。「なかなかいいアプローチではないか!」というわけだ。
ところで、英語でのconstructionは工事現場という意味がある。実際工事現場を訪ねてみるとモノが参与子として人と共同して何かを生み出している状況を観察することができる。それは建築科や建築研究者によって記述されてきたことだ。ラトゥールは次の2冊をあげている。1冊目はTracy KidderのHouse(1985)である。

2冊目はRem KoolhasとBruce Mau のSmall, Medium, Large, Extra-Large(1995)である。

両方とも僕の古い愛読書である。僕自身もモノが作られる現場の研究書を出している。『アメリカンホームの文化史』(1988)だ。

この本を出版したのは30年以上まえだが、当時は日本女子大学で教えていた。あるとき住居学科のパーティで、学科長だった小川信子先生が僕のことをある建築史家に紹介した。アメリカの住宅の研究をみたいなことだったが、その建築史の研究者は「ああ、住宅の社会学ですか」と答えたら、小川先生が「違うのよ、この方は実際の建物を調べて計測をしたりして研究しているの」と説明したことをよく覚えている。まさにそうで、モノと人がであう現場の民族誌がこの本なのだ。
閑話休題。こうした現場は建築だとわかりやすいが、科学の実験室の「現場」でも同じだとラトゥールは述べる。映画であれ、建築であれ、料理であれ、ファッションであれ、ものがつくられている(making)現場では材料がくみあわされて一つの全体となっていく様子が観察できるのが現場であり、うまくいくかいかないか、失敗におわってしまうか、の緊張があるのがものを作り出す現場なのだ。
さて、建設の現場がこれだけ魅力的であるなら、高層ビルや自動車などが機能的にも耐久力においても、デザインにおいても魅力的に構成されるのでり、我々はこうした構築物に次のような質問を投げかけている。どのようにデザインされているのか、どれほどしっかりと作られているのか、耐用年数はどのくらいなのか、素材の値段はどのくらいなのか、こうした質問の答えが構築物の善し悪しに直接結びつくと思っているからだ。ANT研究者は研究をはじめたころ、おなじような質問を実験室という現場になげかけた。
藝術や映画や建築よりも、科学の研究室という現場ではものの加工・組み立てを行って人工的に実験を行って事実の「構築」を行っていた。実験室で使われる「粒子加速器、望遠鏡、国民統計、衛星群、巨大コンピュータ、検体標本」といったものが高層ビルやコンピュータチップ、機関車などを作る現場を構成している道具と同じものだとの確信を持って初期のANTの研究が進められた。摩天楼のかわりに事実が構築された(construction of facts)。またANT研究者は「科学は構築される」というときに「高層ビルは構築される」というときとおなじようなスリルを感じそれを楽しんでいたのである。そこはリスクに満ちたいノベーションの現場であった。人間の活動と非人間(object)の活動が出会うところであり、研究室はハリウッド映画をつくるようにドキドキする現場であった。そこで、実践者practionerである科学者は成功するかしないかわからない risky な制作 productionに関わっているのだ。
このような興奮は長くは続かなかった。constructionの意味が変遷していったのだ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
