
New York Review of Booksを読む(1)
ニューヨーク・レビュー・オブ・ブックスは隔週刊のタブロイド批評紙で、以下のウェブサイトもある。
このウェブサイトはかなり包括的で、過去の記事も必要に応じて検索して読むことができる。理解や決着が容易でなく、理解するのに長い時間を要する問題に対して、良い解決策を提示してくれる。政治的にはリベラルからやや左翼的、文化的にはモダニストであり古典主義者でもある。40年以上前、アメリカの大学院生だった頃、書店でたまたま手に取り、定期購読していた。記事をじっくり読むこともあれば、広告を見て気に入った本を買うこともある。
著者にとって嬉しかった出来事は、個人的に敬愛する人類学者グレーバーがこの書評委員会のメンバーに選ばれたことであり、悲しかった出来事は彼の突然の死であった。
さて、思いつくままに本誌の記事を紹介し、新刊本の広告の中から興味深いものを選んで解説したい。
さて、今号は2023年8月17日号から。
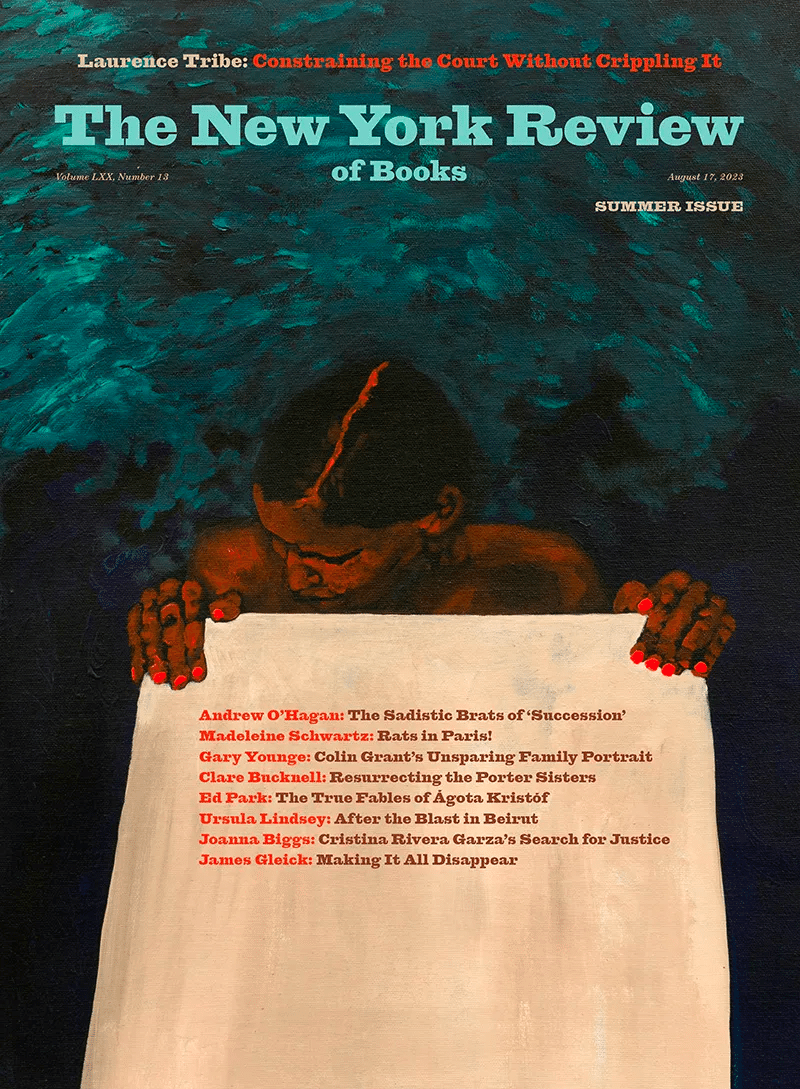
表紙を開くと、シカゴ大学出版局の興味深い本の広告が目に飛び込んできた。3冊紹介しよう。
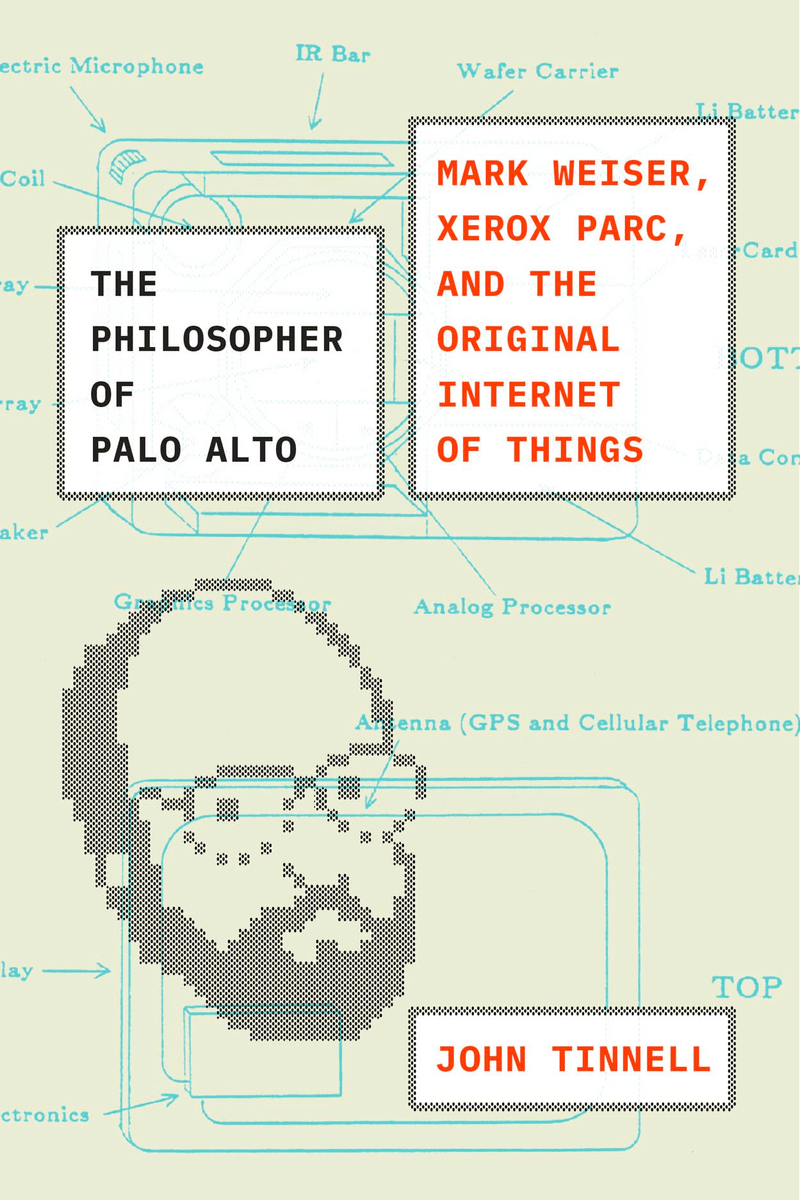
パロアルトの哲学者:マーク・ワイザー、ゼロックス・パルク、そしてモノのインターネットの元祖
ジョン・ティネル
ユビキタス・コンピューティングは、現象学とインタラクション・デザイン、そしてその発明者であるマーク・ワイザーの研究を結びつけた並外れた研究であった。なくてはならない研究書のようなものだ。読むのが楽しみだ。注文する
次もぐっとくる。
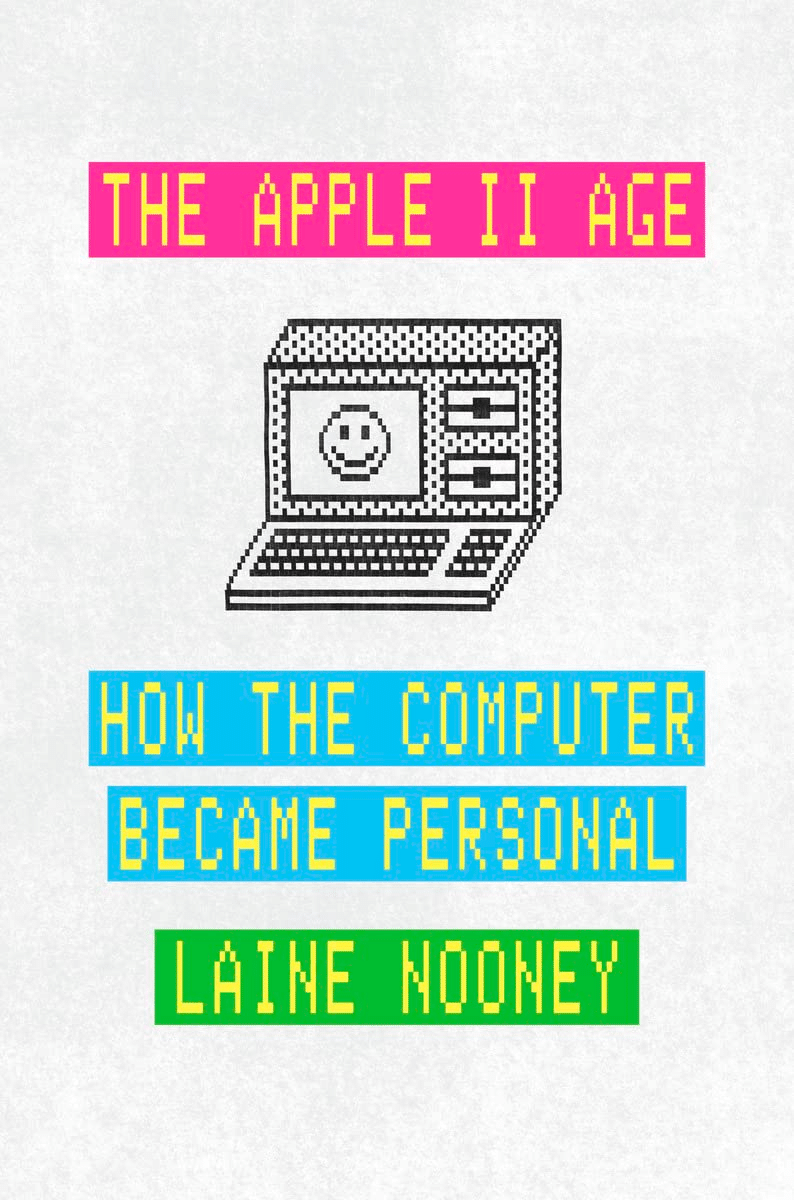
次のタイトルは「Apple II Era」。これはすでに翻訳権を日本の出版社がとっていると思うが、興味深い。コンピューターが自分のものになるというのは衝撃的で、アメリカに留学した最初の年にアップルIIを買ってすべてが変わった。個人的な体験ですが。
シカゴ大学の広告の最後はこれだ。
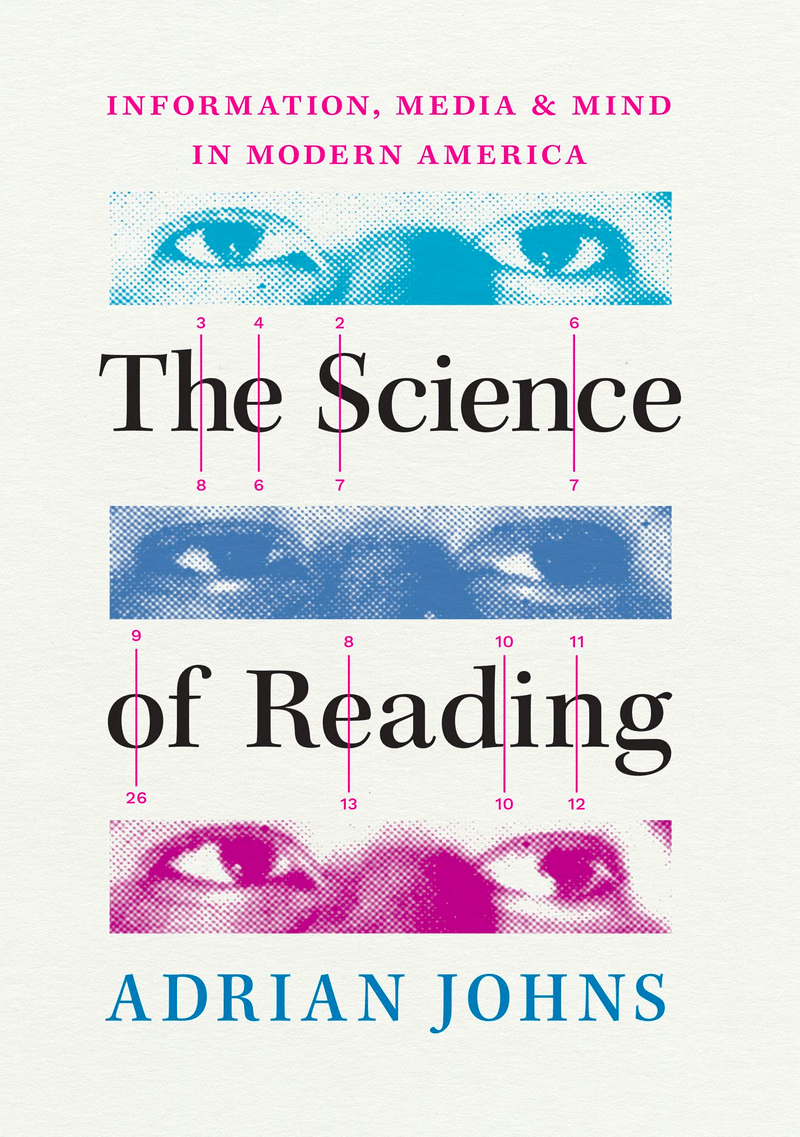
『読書の科学』などというタイトルの本が時折登場する。本書もその一冊だが、すべての読者が読書する際に行っていることを科学した本である。
この本は、人間の読書を科学しようとした研究者たちの話をまとめたものである。科学であるがゆえに、彼らはそれを研究するための機器や実験を繰り返す。彼らは、読者の目が印刷されたページをどのように横断し、心がそれをどのように理解するかを「心理学」しているのだ。つまり、人間に質問しているのである。全米の学校に通う何百万人ものアメリカ人が、この読書科学にさらされている。彼らはアメリカ全土を調査し、社会的、経済的、政治的問題のほとんどが、さまざまな人々の読書による情報格差に根ざしていることを発見した。では、どうすればいいのか?その答えはこの本には書かれていないようだ。それはいまだにアメリカ社会を苦しめている、と彼は言う。注文終了。
次にプリンストン大学出版局の広告を見てみよう。私が注目したのは次の2冊である。
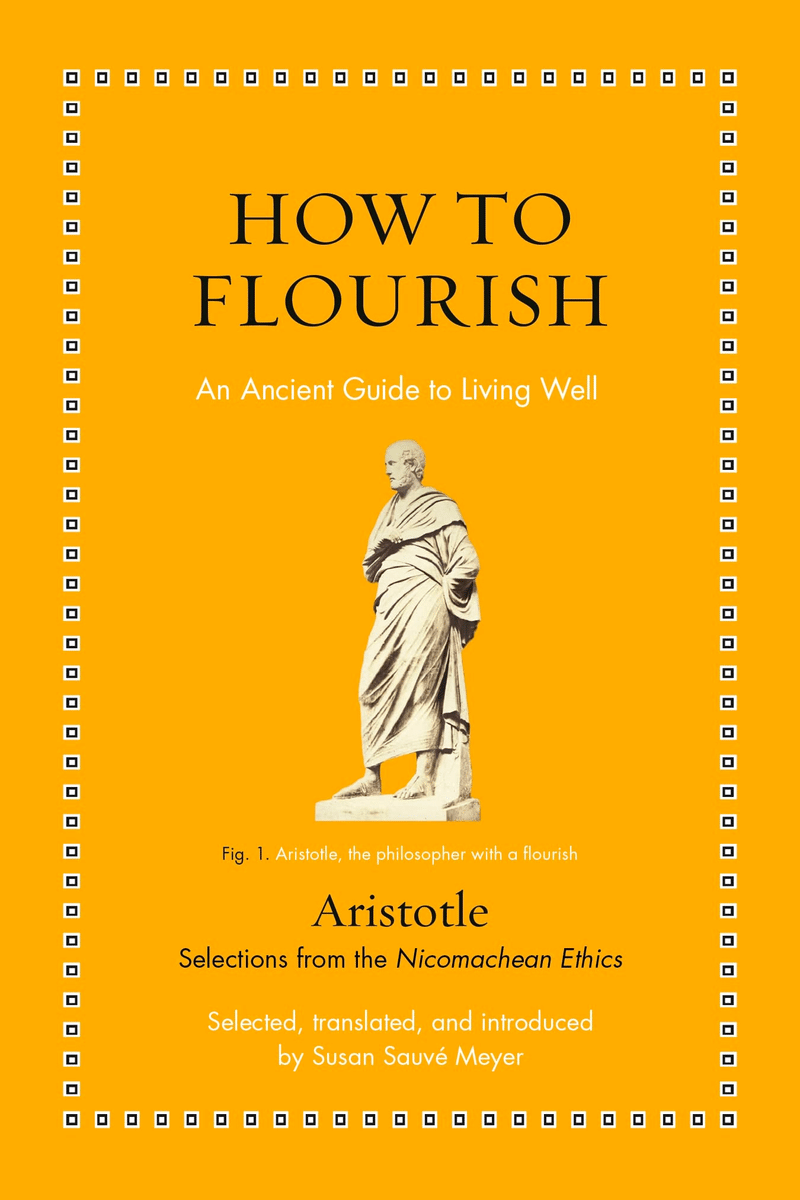
How to Flourish:よく生きるための古代のガイド(現代の読者のための古代の知恵)
プリンストン大学出版局からこのシリーズ、日本でも翻訳が出ているが、はっきり言ってあまり出来が良くない。日本の新書でいうところの「アリストテレスとは何か」のようなもので、表面的でどうでもいい話題や、難しい概念を意味不明な形で説明している。まあ、今回もそんな感じだろうと思いつつも、アリストテレスの倫理学を解説しようとしているということで注文してみた。ギリシア語で読んで、重要だと思うところを選んで訳し、解説を書いたと書いてある。
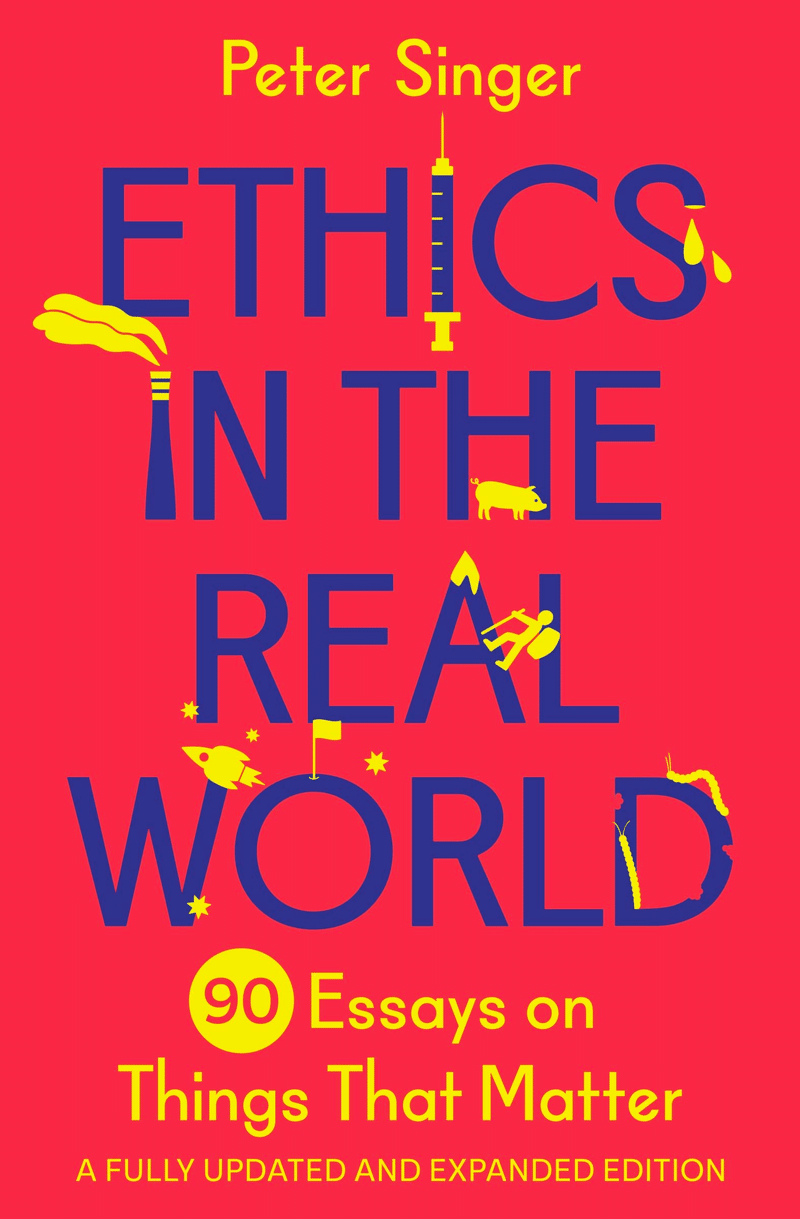
ウィキによると、ピーター・シンガーはオーストラリアのメルボルン出身の哲学者、倫理学者。モナシュ大学教授を経て、現在はプリンストン大学教授。専門は応用倫理学。功利主義の立場から倫理の問題を探求している。著書『動物の解放』は動物愛護や菜食主義の思想的根拠として広く用いられている。
現在、ピーター・シンガーは世界で最も影響力のある哲学者の一人とみなされているが、彼はまた、まやかしの倫理的主張をすることでも知られている。気候変動、極度の貧困、動物、人工妊娠中絶、安楽死、ヒトの遺伝子選択、スポーツドーピング、腎臓売買、高価な芸術の倫理、幸福度を高める方法などの問題に、物議を醸す彼の考えを適用している。しかし私は、倫理学が論理的な観点から発展し、私たちの常識や解決不可能な難問に答えを与える学問だとは思っていない。答えを提供するのが倫理学ではないのです。今の世の中は、このような倫理学者に依存しすぎていると思います。アリストテレスの倫理学とはまったく異なる倫理学なのだ。
トロッコ問題は、この観点から現代世界が直面している問題の優れたモデルである。トロッコ問題は次のようなものである。あなたは、線路に横たわる5人の縛られた人々に向かって暴走トロッコが走っている線路のそばに立っている。あなたの横にも1人の人が線路に横たわっており、あなたは5人の命が助かり、1人だけが死ぬようにトロッコの方向を変えることができるレバーの近くにいる。この問題は倫理の授業でよく使われる。
あなたは何もせず、トロッコが線路にいる5人を死なせてしまうだろうか?
あなたはレバーを引き、トロッコを1人しか乗っていない側線に迂回させますか?
ピーター・シンガーは功利主義的倫理学者とされ、この倫理学者グループは次のように答えている。 功利主義の下では、すべての合理的主体は効用を最大化しようと努めなければならない。功利主義における効用とは、幸福や快楽を意味する。私たちの行動を通じて幸福や快楽が生み出され、それが効用として測定される。例えば、私がホームレスに食事を与えることに時間を費やせば、より多くの人々が幸せになり、より大きな善が創造され、より多くの効用が生まれる。一方、もし私が自分自身に食事を与えることに時間を費やすなら、その結果、私はより幸せになり、より大きな善が生み出されるが、効用は少なくなる。多くのホームレスの人々に食事を与えることは、自分自身に食事を与えることよりも多くの善を生み出す。この論理では、一人よりも多くの人が救われるべきである。一人よりも多くの人が生み出す善の方が、たった一人のために生み出される善を上回るからだ。しかし、もし一人の個人がその行動を通じて、長期的には他の5人の合計よりもはるかに多くの善、すなわち効用を生み出すとしたらどうだろうか。
しかし、その一人の個人が他の5人の合計よりも多くの善を将来生み出すことができるかどうかは未知数である。この例では、5人の命が助かり、1人の命が絶たれるか、5人が死ぬかのどちらかしかわからない。私たちが知っていることに基づけば、明晰で理性的な頭脳があれば、トロッコを1人しか乗っていない線路に迂回させ、5人を救うことを選ぶだろう。
言い換えれば、5人の命は1人よりましだということだ。これが功利主義倫理の考え方である。
この質問は、アメリカの大学では多くの倫理の授業で出題される。もし功利主義的な立場をとらないのであれば、多くの解決策が考えられる。
同じような議論が続くのだろうと思い、この本は買わないことにした。功利主義倫理学はかなり難しい問題で、功利主義の解は一つなのか二つなのかということが問題になることがある。一つの考え方として、このような問題が起きないように、このような問題が起きると想定されるアルゴリズムや環境を設定することが考えられる。これは今後の大きな課題だが、功利主義的倫理学者には、パラドックスで遊ぶ論理学者のように、社会的・環境的に問題を解決するという発想がないように思える。
さて、ひとつの記事を読んでみよう。訳ではなくて概略をまとめた形で紹介をする。
裁判所を機能不全に陥れることなく拘束する
以下の書評は「自信過剰な最高裁判所が自らの行き過ぎによって弱体化し、ファシズムの勢力を封じ込められなくなる」という主張をいくつかの重要な書籍の書評の形で論述したものである。ローレンス・H・トライブは
カール・M・ローブ大学名誉教授であり、ハーバード大学名誉教授(憲法学)である。ハーバード大学ロースクールの憲法学の教授らしくリベラリズムに準拠した主張と、最高裁判所判事たちが最高裁の意味を理解しないで適当に判断を繰り返し、アメリカをファシズムへと向かわせようと批判している。アメリカ憲法の批判的保護者である。(2023年8月)
以下の文章はDeepLで訳して、最初のうちは文章を筆者が要約しながら整理していたが、だんだん翻訳の調子が良くなっていって、後半部はほとんどそのまま訳文をつかっている。
明晰に自分の主張を複数の本をデータとして論述していくトライブの文章は、憲法学の専門家でなくてもよくわかり、また内容を希薄にしてわかりやすく整理をしているわけではない。このような書評を読むことによって、憲法学者でなくても最高裁の判断にもの申すことが出来る。
あと、こうした分析をおこなわずに「アメリカの分断が」とアメリカ大統領選挙のコメントをしたりしている日本のアメリカ研究の専門家の状況理解力の低さが感じられるすばらしく具体的で高度なアメリカ最高裁判所への批判であり、一読に値する文章である。楽しんで読んでもらえると嬉しい。
ーーーーーーーーーーーーー
最高裁を批判する人々は、最高裁がその正当性と独立性を失ったと考えている。
アメリカ憲法とはどのようなものなのか?アメリカの最高裁判所が理解する憲法や裁判官の仕事についての考え方と、アメリカ人の大多数が共有する最高裁判所と裁判官と憲法への考え方には大きな違いがあり、リベラル派だけではなく保守派も最高裁はもはや、正当に機能していないと考えている。その正当性への主張を失ったというコンセンサスが高まっている。
米国は、法の下の政府を守る独立した司法法廷に権力を委ねる一方で、その権力が基本的人権や代議制政府、マイノリティの保護に対する脅威とならないようにしてきた。だが、現状ではアメリカの最高裁の判決は基本的人権や代議制政府、マイノリティの保護に脅威となってきている。ジョーン・ビスクピックのNine Black Robes: Inside the Supreme Court's Drive to the Right and Its Historic Consequencesはこの状況を説明している。
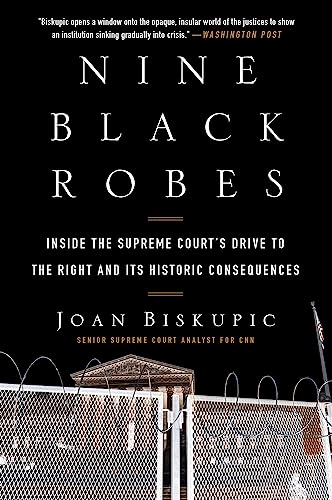
たしかに、現在の最高裁の判決を見てみると、中絶、アファーマティブ・アクション、同性愛者の権利、銃、行政府や独立機関に権限を委譲する議会の権限、宗教に対する政府の支援などにたいして、時代に逆行する判決がでている。これは強硬派団体「連邦議会主義者協会」から3人の判事をドナルド・トランプが任命したことによる。
ジョン・J・ロバーツ・ジュニア最高裁長官、アントニン・スカリア、サンドラ・デイ・オコナー、ソニア・ソトマイヨール各判事の伝記で受賞歴のある著者であるビスキュピックは、トランプ大統領の誕生が、歴史的データと保守的ドグマに基づいた判断を下し、非判断的、党派的、積極的反自由主義的な最高裁を形成する一助となったと主張する。「トランプ効果は、特に選ばれた人物とその結果としてのパワーバランスの変化という点で、比類なきものである。彼(トランプ)は去り、彼ら(トランプが任命した保守派の判事たち)は生涯ここにいる。
ビスキュピックが最も痛烈に批判しているのは、中絶の権利を根底から覆したドッブス対ジャクソン・ウィメンズ・ヘルス事件(2022年)である。彼女は、ドッブスがロー(Roe)対ウェイド裁判(1973年)を覆す6ヶ月前に下された、ホール・ウーマンズ・ヘルス対ジャクソン裁判における最高裁の驚くべき判決についての序章で、ドッブスに焦点を当てることを予感させる。Whole Woman's Health事件では、Roe判決がまだすべての立法府を拘束しており、全国的な基準のもとでは人工妊娠中絶の禁止が明白に違法であるにもかかわらず、テキサス州では6週間を超える人工妊娠中絶の禁止が、裁判官の賛成多数で施行された。Roe判決とは、妊娠中の女性の権利を保護するために制定された法律であり、州の立法府が法律を制定する際に考慮すべき重要な要素の1つとされている。これが無視されたのだ。さらに悪いことに、テキサス州の禁止令は、この法律の執行を国家公務員から懸賞金目当ての民間人=自警団に移し、いかなる法廷でも人工妊娠中絶の禁止に異議を申し立てることが困難になるように=巧妙に設計されていた。
ドッブス判決は予想できたことではあったが、多数派が前任者たちの憲法理解は自分たちの憲法理解より明らかに劣っていると主張したことが、判例そのものよりも衝撃的であった。サミュエル・アリト判事の多数意見は、次のようなものだったとビスクピックは指摘する。
半世紀近く前に認められた基本的権利を大胆にも否定した。[彼の)歴史的出典は奇妙なもの(中絶を引き受けた女性を「殺人者」として扱った英国法にまでさかのぼる)であり、また限定的なものであった。
ビスクーピックにとって最も不安なのは、裁判所の新しい多数派が、プライバシー、平等、身体的完全性、個人の自律性といった基本的権利を定着させた長年の判例を破棄し、Roeとそれに先行・後続する判決に対する不同意とする判決を下したことである。
そう考えると、ドッブス判決の党派性は紛れもないものであり、裁判所の歴史上、間違いなく前例がない。Roe判決を覆すことを可能にした3人の判事(ニール・ゴーサッチ、ブレット・カバノー、エイミー・コニー・バレット)は、そのために選んだと公言する大統領によって任命された: 「本法廷が本日方針を転換する理由はただひとつ、本法廷の構成が変わったからである。今日、個人の性癖が最高裁を支配している。
ビスクーピックは、このように最高裁の判決を批判しているが、その方法に問題が無いわけでは無い。彼女は、避妊具へのアクセスに関する2020年の裁判におけるトーマス判事とルース・バーダー・ギンズバーグ判事の見解を冷静に記述しているが、正確に解剖しているわけではない。また、ロバーツ最高裁判事がどのように考えを変え、トランプ政権が国勢調査に市民権に関する質問を設けるのを阻止するために決定的な5票目を提供したかにページを割いている。彼女の "奥の院 "での逸話は手に汗握るものであり、しばしば愉快である。がビスクーピックの情報源はしっかりとしたものであるとは言いがたい。
また、ビスクピックの本には、最高裁の歴史の中で、今日、衝撃的な反動的判決や抑圧的判決にさえ見えるものがいかに多かったかについての認識が欠けている。ドレッド・スコット対サンドフォード事件(1857年)のように、黒人は決して市民にはなれず、白人が尊重すべき権利もないとした判決や、ジャイルズ対ハリス事件(1903年)のように、憲法修正第15条にもかかわらず、州が黒人の市民権を完全に剥奪したことに対する異議申し立てを裁判所が受理する権限すらないとした判決や、ロッヒナー対ニューヨーク事件(1905年)のように、最高裁の悪名高い判決については何も書かれていない。ロッホナー対ニューヨーク裁判(1905年)では、州が労働搾取工場の労働条件を規制する権限を剥奪し、ハマー対ダーゲンハート裁判(1918年)では、連邦議会が児童労働の産物の州間販売を禁止する権限を剥奪し、バック対ベル裁判(1927年)では、標準以下の知能を持つとされる女性に対する外科的不妊手術の強制を支持し、コレマツ対アメリカ合衆国裁判(1944年)では、真珠湾攻撃の後、忠実な日系アメリカ人の強制退去を支持した。
私たちの歴史における裁判所の位置づけを、大部分は良心的で時に英雄的な機関というイメージで捉えている人なら、ビスクピックの副題にある「最高裁の右傾化」は比較的新しい現象だと結論づけても許されるだろう。善意から、彼女はつい最近まで多くのアメリカ人が抱いていた、裁判所に対する時代遅れの観念を利用している。マイケル・ウォルドマンが『The Supermajority』の中で言うところの「世代的ノスタルジア」は、法廷と多くの判事個人が、ジャーナリストとして法廷をよく観察している人々を含む法曹エリートや、広くアメリカ国民から、長年にわたって崇拝されてきたことに起因している。
このような敬意(最高裁に対する崇拝)がいかに見当違いなものであったとしても、そしてウォルドマンの著書は、それが法廷の歴史が始まった当初から大きく見当違いなものであったことを破壊的に証明している。
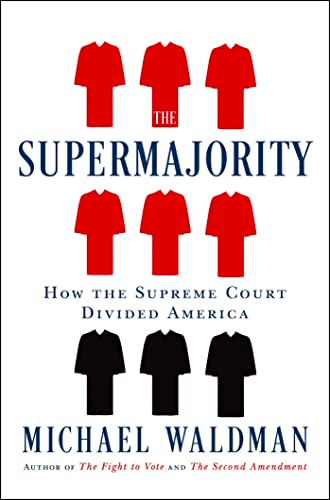
ビスクピックがトランプ政権時代をミクロの視点で検証することの弊害は、政治的平等と人権を損なうという、トランプ政権よりずっと以前からの裁判所の厄介な歴史を覆い隠してしまう可能性があることだ。ウォルドマンがよりバランスよく、より事実に基づいて語るなら、その歴史は、司法至上主義がいかに個人の権利の向上と相容れないものであったかを説明することになる。
憲法を教えていた頃、 私(Laurence H. Tribe)は学生たちに、最高裁が政治制度や法制度の設計においてその歴史的な機能を果たすとき、しばしば機会均等やインクルージョン、個人の自主性の尊重、プライバシーの擁護者であったことを、かなり詳細に説明したものである。その広く理解され、広く尊敬される権威は、議会、大統領、連邦政府機関、そして州や地方の立法、行政、司法の数多くの役人が、私たちの権利を蹂躙することを抑止するために、しばしば役立ってきたと、私は学生たちに断言する。
私の世代の弁護士は、アール・ウォーレンが最高裁長官であった頃に成人した。しかしその後、ウォーレン判事の時代(1953年から1969年まで)は、普通というよりはむしろ例外であったことが次第に明らかになってきた。今日、ウォーレン・E・バーガーとウィリアム・H・レーンクイストの両判事時代における法廷の保守主義を基盤として、ロバーツ最高裁長官の下での法廷は、憲法修正第2条と、憲法修正第1条の言論の自由および宗教の自由行使条項の一部において発見したと称する権利以外のすべての権利を、極度のためらいと、しばしば嘲笑をもって扱っている。
同時に、ビスクピックの著書とウォルドマンの著書が示すように、現在の裁判所は、身体的完全性から選挙権、州議会や下院の選挙区割りの引き方まで、法の下の平等に対する萎縮したとしか言いようのない見解に基づいて行動している。憲法上の権利についてこれほど偏狭で本質的に逆行した見解を持つ法廷が、憲法の約束を定義する上で誇り高い地位を占め続けることを許すことは、この文書とその上に成り立つ民主主義を、憲法を最も必要とする人々のために、そして私が何世代にもわたって学生たちに称賛してきた共和国の憲章として、機能しなくなってしまう危険をはらんでいる。
明瞭に言っておくと、司法至上主義は憲法の条文や構造に織り込まれているわけでもなければ、憲法誕生の歴史から発見できるものでもない。その代わりに、ハーバード・ロー・スクールのニコラス・ボウイ教授とダフナ・レナン教授が雄弁に語っているように、司法至上主義は「南北戦争後、憲法が公民権法や投票法を要求しているという議会の判断を裁判所が覆したときに初めてアメリカ政治に定着した」のである。私が委員を務めた大統領最高裁判所委員会における2021年の証言の中で、ボウイは、その歴史の大半において、法廷に座っていた判事たちが、正当化しようとする試みもなく、その役割を自分たちのものとし、平等主義的ビジョン以外のものを推進するためにその役割を利用してきたことを、エレガントに詳しく説明した。ボウイの言葉を借りれば、「歴史的な慣行として、裁判所はアメリカ法に反民主主義的な影響力を行使してきた。」
よく言われるブラウン対教育委員会事件(1954年)が司法至上主義の必要性を物語っているという訴えは、まったく説得力がない。ブラウンは、プレッシー対ファーガソン事件(1896年)を覆し、黒人と白人の公共宿泊施設は別々だが平等である(とされた)ことの合法性を肯定した。しかし、1954年にブラウンで裁判所が行ったことは、少なくとも、マイノリティの権利の議会による保護と、それらの権利の裁判所による執行を示すものであった。同裁判所は、連邦憲法と連邦法の規定を州当局者に適用するための手段を提供する、再建期に連邦議会が可決した連邦法、合衆国法典第42編第1983条を適用したのである。同性婚の基本的権利を確立したローやオベルゲフェル対ホッジス裁判(2015年)のような自律性、尊厳、プライバシーを拡大する裁判もまた、不寛容な州法を取り締まるために1983条に全面的に依存していた。ボウイとレナンが指摘するように、これらの判決は「司法至上主義を示すものではなく、むしろ連邦議会が国家憲法上の公約を作成し、執行する能力を示すもの」である。
権利の保護者、特に富と権力を持たない人々の権利の保護者としての司法について、満足のいくように修正された概念は、最高裁に焦点を当てるだけでは満足できず、国家公務員による濫用に関して1983条がそうであるように、連邦公務員による濫用から権利を保護するための新たな連邦司法の道を提供する法律を制定することによって、議会に介入することを求めなければならない。連邦議会はまた、平等主義的規範に反するような曖昧な連邦法を解釈する最高裁判決を覆すことによっても介入することができる。
連邦法の保護を強化するために、国民に選ばれた代表者がより積極的に参加することは、当然ながら、憲法の保護や連邦法で成文化された保護さえも定義する、伝統的に明らかに反主流主義的なプロセスに、「多数派の専制」に対する恐れを再投入することになる。しかし、基本的権利の定義と擁護に議会や州議会議員、州裁判所選出の裁判官や判事がもっと関与するよう促すことは、連邦司法全般、特に最高裁判所が、政治家が越えてはならない限界を定義することをやめることを意味するものではない。また、立法府の責任強化を主張する人々は、議会と裁判所が常に対立する必要があることを認めなければならない。むしろ、ウォルドマンが説明するように、重要なのは、アメリカの民主主義を支える上で議会が果たすべき役割がより大きいということだけである。
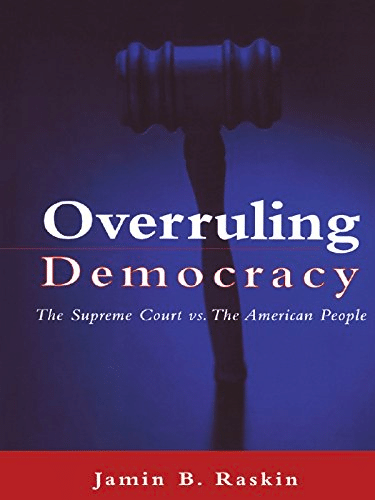
議会がその挑戦に踏み出さない限り、私たちは、民主主義の進歩を促進するどころか、むしろ妨害してきた機関によって支配される運命にあるようだ。『民主主義を覆す: 最高裁判所vs.アメリカ国民』(2003年)で、法学教授のジェイミー・ラスキンは、現在、議会民主党の進歩的だが現実的な翼の著名なメンバーとして、民主主義を拡大する事実上あらゆる手段に対するレーンキストの反対Rehnquist Court’s oppositionを記録している。
ウィリアム・ハブス・レーンキストは、アメリカの弁護士、法学者で、1972年から1986年まで判事補、1986年から2005年に死去するまで第16代最高裁長官として33年間連邦最高裁の要職を務めた。厳格な保守派とされるレーンキストは、連邦憲法修正第10条の州への権限留保を重視する連邦主義の考え方を支持した。この連邦制の考え方に基づき、連邦裁判所は1930年代以来初めて、通商条項の下で、連邦議会がその権限を超えているとして連邦法を破棄した。彼は、有色人種の票を希薄化させる州法を認可し、南部の黒人有権者が直面した歴史的な選挙権剥奪を克服しようとする試みを拒否し、首都に居住する人々が進めた代表者不在の課税に対する挑戦を退けた一連の判決を鋭く解剖した。ラスキンは、「現代の緊急課題は、民衆の民主政治を裁判所の束縛から解放することである」と主張した。ラスキンは、ブッシュ対ゴア(2000年)の多数派による「ずさんな解釈」に対して最も厳しい批評を留保した。この解釈は、憲法の条文やその狭間に広範な「連邦憲法上の選挙権」らしきものを見出そうとしない裁判所の歴史的姿勢を反映したものであった。
ラスキンは先見の明があった。彼がこの本を書いてから20年、最高裁は民主主義への参加に敵対的な姿勢を強めるばかりである。ビスクピックとウォルドマンが詳細に論じているように、この10年間で、最高裁は南部での有権者弾圧を可能にするために投票権法を改悪し、有権者の写真付き身分証明書に関する法律を支持し、有権者名簿の粛清を容認し、党派的ゲリマンダリングを可能にし、選挙資金制度改革を抹殺した。過去3年間の判決は、この傾向を加速させた。裁判所は、パンデミック(世界的大流行)の間、期限延長やその他の投票便宜措置に反対し、投票に意図的な人種差別的影響を及ぼすことがほぼ確実な州法を支持した。
今年、限定的な猶予が2つの判決という形でもたらされた: アレン対ミリガン事件は、アラバマ州にマイノリティが過半数を占める連邦議会選挙区を追加設定するよう求める投票権法の適用を支持する5対4の判決であり(この事件では、人種を明白に利用しているにもかかわらず、同法の合憲性が支持された)、ムーア対ハーパー事件は、選挙区割りを引き、大統領選挙人を選出する際の州議会の決定に対して、州裁判所や憲法は管轄権を持たないという、危険かつ全くあり得ない理論を、最高裁の多数決で否定した判決である。悲しいことに、この2つの判決を、最高裁の反民主的な態度が長期的に再調整された証拠だと解釈する観察者は、自分自身を愚弄している可能性が高い。私の強い感覚では、ここ数十年の判決の傾向は、一時的に中断されただけで、断ち切られたわけではない。この戦争は、自分たちは受動的に伝達される法理論の単なる器に過ぎないという神話の真の信奉者である彼らが自分たち自身から隠しているか、あるいは、誰が "われわれ人民 "に属するに値するかという原則的信念の論理的反映であるとして自分たち自身に正当化しているかのどちらかであると推測される。
司法至上主義の現在と歴史的な行き過ぎ、そしてこの至上主義が時を経るにつれ、持たざる者に権力を与えるよりも、持つ者の権力を強固なものにしてきたという認識が広まり、進歩的な憲法学者たちの間で、われわれの統治における最高裁判所の中心性を再考する声が高まっている。彼らの基本的なメッセージは、アメリカの長い歴史の中で、最高裁が弱者のために立ち上がり、恐れや好意なしに正義を行使する原則の模範であると神話化してはならないということである。そんなことはほとんど無かった。
しかし、最高裁の責任を再考する際に、現在の裁判所の忌まわしく、明らかに非判断的で、腐敗しきった無原則な行動を、前任の裁判所の慣行と同一視することは、それに劣らず間違いであろう。これほど露骨に、法律や論理に少しも縛られることなく、イデオロギー的に決められた方向に国家を動かそうとする裁判所を、私たちは見たことがないと思う。
ケーガン判事のように精通した判事が、2010年に最高裁判事に就任して以来、法廷から口頭で反対意見を述べるのは4度目だが、バイデン対ネブラスカ訴訟で政権による学生債務救済プログラムを却下したことで、6人の同僚判事が誤りを犯しただけでなく、「憲法違反」の行動を取ったと非難するのは、何かがひどく間違っている。裁判所は、「4300万人のアメリカ人に対するローン免除」を廃止するために、「立法府と行政府の総合的判断」を覆すために、「前学期と今学期、大問題の剣を振り回し」、「裁判所が裁判所らしく振る舞うことを意図した憲法上のガードレールを吹き飛ばしている」と彼女は述べた。彼女は、多数派が無意味な返答をすることなく、同僚たちが「事件ではない」ケースでこのようなことをしていると指摘した。大統領を訴えた当事者は、ローン免除プランに「個人的な利害関係はない」6つの州であったが、たまたま「このプランを非常に悪いアイデアだと考えている」「典型的なイデオロギーに基づく原告」であり、現在構成されている最高裁がそのような政策的嗜好を共有し、「政治的・政策的論争」を仲裁するよう憲法が指定している部門にそれを熱心に押し付けるだろうと賭けたのである。
ロバーツ最高裁判事は多数派を代表して、「最近のいくつかの意見に見られる不穏な特徴」として、反対意見が「自分たちが反対する判決は司法の適切な役割を超えている」と述べていることを批判した。しかし、主席判事の不満は的外れだった。問題は、ケイガン判事が静かな部分を大声で言ったことではなかった。問題は、彼女が明らかに正しかったことだ。ローン返済免除の判決でも、同じ日に下された差別撤廃の判決でも、裁判所は自らの政治的・社会的見解を国民に押し付けようとする熱意をまざまざと見せつけ、自ら作り出した「事件」の解決に手を差し伸べたのである。
ローン事件では、当事者の少なくともひとりに法的な「地位」、つまり結果に対する真の利害関係があるかのように装ったが、実際にはそのような当事者はいなかった。また、303クリエイティブ
LLC対エレニス事件では、結婚式のウェブサイトを運営するデザイナーに対し、「彼女の権利を明確にする」ための勧告的意見を提示し、結婚を望む同性カップルを差別すればコロラド州の差別禁止法に抵触するかもしれないという「心配」を解消した。ケーガン判事がローン事件で書いたように、「伝統的な司法判断の手段」を採用する裁判所がそのような行動をとるはずがない。
前期の最後の数件の判決を読むと、「学生財政支援」を「免除または変更」する権限を行政府に与えた議会行為について、明らかに自分たちが出したかった結論に到達するために、裁判所が通常の法令表現を分解している毛が分かれる音が聞こえてきそうだ。ソトマイヨール判事は、自身とケイガン判事、ケタンジ・ブラウン・ジャクソン判事のために反対意見を書き、LGBTQの人々の権利を低下させる判決を下した: 一部のサービスは同性カップルには提供されない可能性がある。
そして、『公正な入学を求める学生たち』対『ハーバード大学学長とフェローたち』裁判と『公正な入学を求める学生たち』対『ノースカロライナ大学』裁判では、奴隷であれ自由人であれ、何世代にもわたるアメリカ人の抗議が聞こえてくる。そして、ジャクソン判事が自身とソトマイヨール判事、ケーガン判事の反対意見の中で書いているように、「法律において人種を無関係とみなす」ことは「人生において人種を無関係にする」ことになると、「彼らにケーキを食べさせるような忘却の彼方」で主張するのである。
そのため、ボウイやレナンのような学者たちが主張する制度改革や構造改革は、現在私たちが目の当たりにしていることが正常なことでも、私たちの政治構造に固有のことでもないという冷ややかな現実を反映するよう、微調整されなければならない。しかし、これらの学者たちは、政治的に持続可能であり、50州にまたがる連邦法の安定性と統一性を脅かしかねない予期せぬ結果を最小限に抑えるよう設計された、改革のための詳細な計画らしきものをまだ示していない。
ボウイとレナンが、憲法の意味について司法が最終的な決定権を持つ形式主義的な三権分立に反対し、「議会と大統領は、枝葉間の立法プロセスを通じて、特定の制度的配置が適切かどうかを決定すべきである、 また、エール大学ロースクールのサミュエル・モイン教授が、2021年の最高裁判所に関する大統領委員会での証言で、同様に司法至上主義の危険性を強調した。モイン教授の「長期的に憲法上の司法の権限を奪うことは、改革者がつかむべき機会である」という見解を受け入れることは、まったく別のことである。
連邦裁判官の終身在職権を更新不可能な任期制に置き換えるという提案とは異なり、この提案は広く大衆の支持を得ており、憲法を改正することなく立法的に実現できるかもしれない; また、1869年に制定され、それ以来変更されていない9議席から13議席に拡大するという提案とは異なり、これは立法だけで間違いなく達成可能であり、また、無原則な現在の超党派の凝り固まった性格に照らして、正当かつ必要な動きであると私は考えるが、モインや、程度の差こそあれボウイやレナンが支持していると思われる、より急進的な種類の治療法は、病気よりも悪い結果をもたらす可能性がある。モインは、ある種の裁判を審理する権限を司法から剥奪したり、憲法上の理由で法令を無効とするための超党派の閾値を設けたり、連邦法に対する最高裁の無効判決を議会が批准することを義務付けたりすることで、議会が「憲法秩序の中で良識ある地位を回復する」ことを提案している。
アメリカ生活に対する最高裁の肥大化し、見識のない支配に対抗しようとする提案の背後にある衝動は理解できる。一般市民の感性、科学の進歩、競合する視点に対する非公式な説明責任からさえも隔離されている最高裁は、平等主義的で包括的な価値観とは大きくかけ離れた、強いイデオロギーや宗教的なコミットメントさえ持ちうる個人の手に、巨大な権力が握られてしまう危険性をはらんでいる。しかし、法の支配を維持し、腐敗しかねない政治家や利己的な政治家、派閥主導の政治家の手に野放図な権力を握らせないためには、世論の風向きや近視眼的な政治的情熱から隔離された、ある種の個人に独立したチェック機能を委ねなければならないと、私は信じ続けている。彼らは、しばしば法律と政治が混在することになる争点の原則的解決に尽力し、潜在的な報復の圧力から解放され、そしておそらく何よりも、自らの誤りを敏感に察知しなければならない。
右翼的で介入主義的な裁判所の危険性ばかりに目を向けると、権力を掌握して手放そうとしない独裁的な大統領の、間違いなくさらに大きなリスクも無視することになる。独立した強力な司法のチェックを受けず、行政府、特に軍を掌握したままにしておくことがもたらす脅威を理解するのに、想像力を働かせる必要はほとんどない。ロバート・ジャクソン判事が朝鮮戦争中に観察したように、「包括的で未定義の大統領権限」は法の支配に「重大な危険」をもたらす可能性がある。
1880年代と1890年代の中国系移民の排除、1940年代の日系アメリカ人の強制移住と抑留、そしてトランプ大統領就任中のイスラム系移民の排除に関わるような事件は、最高裁が不人気なマイノリティの苦境に無関心であること、そして言論の自由の名の下に性的指向に基づく差別を容認しているのと同様に、国家の安全保障の名の下に人種差別や宗教差別を容認していることを浮き彫りにしている。しかし、これらの訴訟で争点となっている外国人排斥、イスラム嫌悪、同性愛嫌悪の政策は、行政府がいかに市民の自由にとって致命的な存在になりうるか、また、マイノリティの独立した保護者という考えを放棄するよりも、マイノリティにより良い対応をするために十分な理念のある最高裁判所を目指す方がはるかに良い道であると思われる理由も示している。
1943年、ウェストバージニア州教育委員会対バーネット事件で、エホバの証人の子供たちがアメリカ国旗に忠誠を誓わなかったために公立学校から追放されるのを防ぐために方針を転換したときのように、最高裁はそのような保護者であることもある。トランプ政権時代にも、裁判所は商務省が国勢調査に市民権に関する質問を載せることを阻止し、国土安全保障省がオバマ政権の「幼年期到着者のための延期措置」プログラムを、適切な行政手続きに従わなかったとして取り消すことを阻止した。司法省の元職員マイケル・ドリーベンがイスラエルの司法危機に関する最近の記事で述べているように、「民主主義が一本の糸にぶら下がっているとき、司法の独立へのあまりに深い侵食はその糸を断ち切るかもしれない」。行き過ぎた是正は、同様に危険な代替案を招く。
最高裁判所が無力化されれば、現在の裁判所が恥ずかしながら支持してきたこと以上に、あからさまな違憲国家行動を引き起こす可能性もある。連邦法の執行を拒否する州を防ぐことができなくなれば、憲法第6条に記された唯一の「国の最高法規」が適用されなくなる。だからこそ、テキサス州は同州の強権的な妊娠中絶禁止令を執行する自警団として民間人を派遣することによって憲法を回避することができるとする2021年の判例は、ソトマイヨール判事が反対意見の中で書いたように、「州が憲法上の権利の行使を阻害し、司法審査を回避することを目的とする法律を制定した場合、連邦裁判所は救済を出すことができ、また出すべきである」という考えからの「危険な逸脱」として非難に値するのである。
もし最高裁が州裁判所で起きた事件で連邦憲法上の権利を擁護できないのであれば、州裁判所は、前世紀に奴隷所有者が主張したように、日常的にそのような権利を意のままに無効にすることができる。オリバー・ウェンデル・ホームズが、連邦法を執行する州裁判所の判決に対する連邦司法審査を支持する際に主張したように:
連邦法を執行する州裁判所の判決に対する連邦司法審査を支持したオリバー・ウェンデル・ホームズは、次のように述べている。「議会法の無効を宣言する権限を失ったとしても、合衆国が終わるとは思わない。しかし、複数の州の法律についてそのような宣言ができなくなれば、連邦は危うくなると思う。
また、連邦議会法や連邦政府機関の規制の意味や合憲性について、最高裁(そしておそらく下級連邦裁判所も)が、全体的または特定のカテゴリーにおいて決定的な判断を下すことを制限することは、50州の最高裁判所にこれらの問題についての最後の言葉を委ねることになり、国家全体として明らかに単一の答えを必要とする問題に対する答えが、パッチワークのようなキルトのような、どうしようもないものになってしまう。ボウイもレナンもモインも、少なくとも公の場ではまだこうした問題に焦点を当てていないが、こうした問題が十分に解決されるまでは、最高裁の権限を奪うという考えは、あまりに雲行きが怪しく、大きな意味を持たない。
従って、アメリカ生活における最高裁の中心的地位を低下させようとする衝動は、せいぜい広範かつ複雑な政治的プロジェクトの出発点として受け止められなければならない。また、政府全体を縛るのと同様に裁判官を縛るべき倫理規範の改革を含め、裁判所の運営方法の細部に手を加えるだけでは、本来政治的でありながら政治的に説明責任を果たさない機関にこれほど広範な権力を与えることの問題の核心に迫ることはできない。他の立憲民主主義国家の最高裁判所でも、民主的な手段で変更することが困難な法体系の意味について、これほど大きな権力をこれほど少数の人間に与えているところはない。
例えば、憲法第5条の改正発議要件を議会の3分の2から5分の3に、改正批准要件を州の4分の3から3分の2に引き下げるなどである。あるいは、修正条項を提案するための新たな大会を招集するための第5条の要件を、現在の州議会の3分の2から5分の3に引き下げる。おそらく、このような劇的な改革を求める政治的機運は、裁判所が投票権を保護できなかったこと、あるいは女性の権利、人種的少数者の権利、身体の自律と個人のプライバシーに関する権利の保護において半世紀にわたる進歩を覆したことを背景に、差別撤廃を単なる願望に終わらせないという目標を中心に構築されるであろう。
連邦法や憲法解釈のあらゆる問題について最後の一言を持つことに慣れた司法機関に、手綱を多少緩めることを期待するのは、大変なことを要求しているように見えるかもしれない。制度が自発的に自らの権力を縮小することに消極的であることは別として、このような自己犠牲の要請が、米国の法制度と政治制度の民主化の名の下に発せられるという点が難しいのである。単刀直入に言えば、現在の共和党の多数派を占める判事たちが、反民主主義的な目的を追求するために、いかに自信に満ち、しばしば怒りを露わにしているかが憂慮される。この傲慢さは2世紀以上前にさかのぼり、イデオロギーのスペクトルを横断しているが、反民主的なプロジェクトを支援するために武器化されたものは、厳密に右翼的であり、明らかに斬新である。
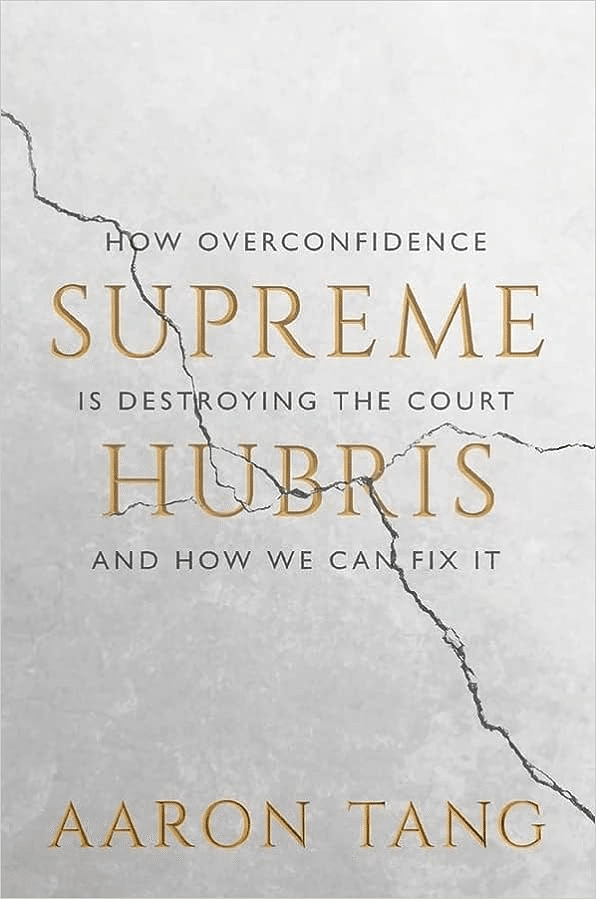
この自信過剰の問題は、アーロン・タンの『Supreme Hubris: How Overconfidence Is Destroying the Court-and How We Can Fix It』の中心テーマとなっている。タンは、裁判所の自信過剰がその中心的な問題であると述べている。今日の裁判所は、例えばミランダ警告が必ずしも憲法で義務付けられていないことを認めたウォーレン裁判所とは異なり、判断を下す際に謙虚さをほとんど見せず、中絶、アファーマティブ・アクション、銃規制、行政国家の将来といった分野における根深い論争は、原典主義のような好ましい解釈方法を用いれば、すべて「法律で解決できる」と自信たっぷりに示唆している。このような過信から生まれる意見には、現実の結果や反対論に対する最低限の配慮すら欠けていることが多く、判決に反対する人々は、裁判所という組織そのものに敬意を抱くことはほとんどない。
任期制限、超党派要件、その他の構造改革が司法の慎み深さを向上させることに懐疑的であることを含め、タンの記述や彼の診断に反対することは難しいが、そのような向上がどのようにして確保されるのかについて述べている部分を見逃してしまったようだ。タンは、裁判所の自業自得を懸念する人々が、裁判官を説得することができると確信しているようだが、それはおそらく、裁判官の裁判権を剥奪すると脅すことで、より謙虚に、より漸進的に行動できるようにするためだろう。私はそうは思わない。
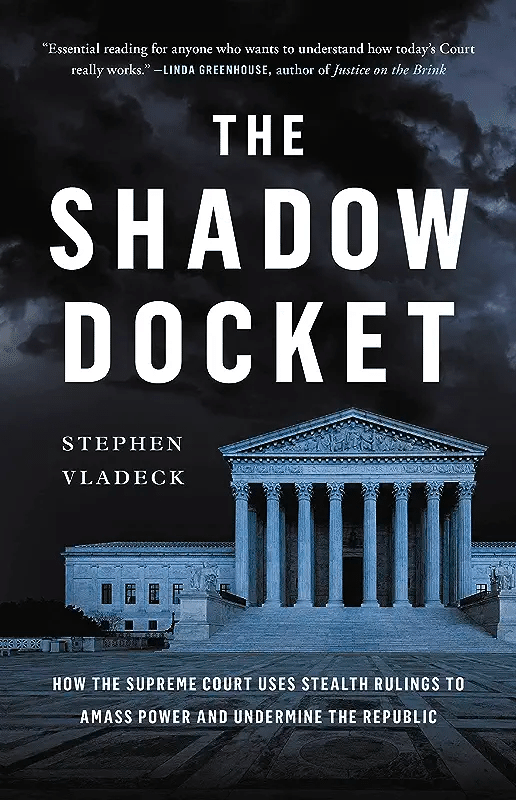
イデオロギー的に好ましくないと判断したプログラムや政策を廃止するために、裁判所が近道としか言いようのない手段を取るとき、現在の右派の超党派の不遜さ、そして思慮深く幅広い情報に基づいた審議を保証するために設計された伝統的な手続き上の仕組みに対する価値の低さは、特に際立つ。『The Shadow Docket』の中でスティーブン・ブラデックが認めているように、裁判所は歴史的に、説明のない一行だけの裁量審査(法律用語で言うところの「上申書」)の却下から、誰が連邦裁判所の意思決定権を行使できるのか(誰が「原告適格」を有するのか)を決定するための比較的難解なテストまで、簡略化されたフィルター機構を採用しており、十分なブリーフィングや弁論を行うことはおろか、問題となっている法的問題の本位についてどちらがより優れた主張を行っているのかを検討することもなく、大多数の申立人の訴訟を退けてきた。
このような非決定による決定の反対側には、ほとんど説明のない下級審判決の略式破棄による決定がある。下級審判決は、年間数千件にのぼる突然の再審理請求の中から、自分の事件が数十件の中に含まれるかもしれないことを知らされていない当事者に、青天の霹靂のように下される。このような処分は、半ダース余り前に急増し、ウィリアム・ボード法学教授がテキサスの控訴弁護士パメラ・バロンから「シャドー・ドケット」という言葉を借用するきっかけとなったが、ヴラデックにとって不愉快なのは、「裁判所の通常のプロセスを短絡させる」ためであり、それによって配慮に欠けたものになる危険性があるためであり、また、弁護士や一般市民にほとんど指針を示さない傾向があるためである。
ヴラデックが憤慨しているのが、裁判所のアジェンダの多くが、不作為や、ほとんど説明されず、確かに公然たる理由付けもない行動によって実行される方法につきまとう、不透明さや説明責任の欠如、あるいは慎重な審議の欠如なのか、あるいは、この透明性の欠如が最近展開されている右派のアジェンダなのか、あるいは、ほとんど陰に隠れている教義が展開される偽善がますます見え隠れしていることなのかは不明である。上記のすべて」というのが妥当な答えだろう。いずれにせよ、最高裁の高度に専門的で、極めて不透明で、容易に操作可能な存立権法理は、主に右寄りの多数派、そしてしばしばその多数派の中でも最も極端な層のイデオロギー的性向を助長するために展開されてきたという非難に対しては、特に脆弱であるように思われる。
しかし、ヴラデックが語りたいのは、現在の裁判所の手続きが、裁判所がどのような理由でそのような結果に至ったのかについて、いかに透明性を欠いているかということである。代表的な判決には、コヴィド19のパンデミック時に裁判所が下した緊急救済の決定(および司法審査の基準の変更)、トランプ時代の事務総長による緊急救済要請の「積極的な」利用を受け入れる姿勢、2006年の判例パーセル対ゴンザレス(裁判所が緊急選挙の異議を判断する際の基準を定めたもの)を利用した重要な選挙争議への土壇場での干渉などがある。ヴラデックの研究は、3年前にバレット判事が加わって以来、法廷がいかに一貫して積極的に、望ましい結果を得るために手続きを踏み外してきたかを浮き彫りにしている。このような話は以前にもあったが、ヴラデックは、この法廷の行動が、求める結果に到達するための手続きだけでなく、そのスピードと頻度においても、それ以前の法廷とは一線を画していることを示す貴重な証拠を提供している。
このような裁判所の明らかに非司法的な行動に対抗するため、ブラデック氏は、裁判所の重要な独立性を危険にさらすことなく、またその能力を損なうことなく、議会がシャドー・ドケット(shadow docket),の使用を大幅に抑制できるような、ささやかな一連の立法措置を提案している。
シャドウ・ドケット(またはノン・メリト・ドケット)wikiより。
合衆国最高裁判所において、まだ最終判決、控訴審判決、口頭弁論に至っていない事件の動議や命令をシャドウ・ドケットという。特にステーや差止命令(予備的救済)を指す。
ステーとは、執行停止(ラテン語: cesset executio、「執行を停止する」)のことで、裁判所の判決やその他の裁判所命令の執行を一時的に停止する裁判所の命令である。(wikiより)これには、略式判決や付与・破棄・差し戻し(GVR)命令も含まれる。「シャドー・ドケット」という言葉は、2015年にシカゴ大学のウィリアム・ボード教授がこの文脈で初めて使用した。
シャドー・ドケットは、通常の手続きとは一線を画している。このような案件は非常に限定的なブリーフィングを受け、通常、申請から1週間以内に決定される。この手続きでは一般的に、短くて署名のない裁定が下される。一方、本案訴訟の場合は数ヶ月を要し、口頭弁論を含み、多数決の理由や、賛成・反対判事がいる場合はその理由を詳述した長い意見書が作成される。
シャドー・ドケットは、申請者の要求が即座に認められなければ「回復不可能な損害」を被ると裁判所が判断した場合に使用される。歴史的に、シャドー・ドケットは重大な法的または政治的意義を持つ判決に使われることはほとんどなかった。しかし2017年以降、特に司法省による下級審判決の緊急停止要請など、重大な判決に使われることが増えている。この慣行は、偏見、透明性の欠如、説明責任の欠如など、さまざまな理由で批判されてきた。
ウィリアム・ハワード・タフト最高裁長官は1925年、増え続ける控訴審の山からの救済を懇願し、「ラテン語の大法官という不明瞭な用語で知られる司法慣行を拡大することで、最高裁が審理する事件をはるかにコントロールできるように議会を説得した」。ヴラデックが辛辣に指摘するように、大法院は「裁判所の訴訟事件が制御不能に膨れ上がるのを防ぐ唯一の方法」ではない。他にも多くの改革案が考えられるが、仕事量を処理するために判事を増員することもできる」-私を含め、多くの改革派が別の理由で主張してきた改革案である-とか、「連邦中間控訴裁判所で一般的なように、ほとんどの事件を3人の判事で審理することもできる」とか、「連邦議会は、最高裁への負担をさらに軽減するために、控訴裁判所をもう1つ増やすことができる」といったものである。イデオロギーに関係なく擁護可能だが、多くの読者にとっては確かにイデオロギー的な理由で魅力的な、このような硬派な提案によって、ヴラデックは "手続き上の技術的・形式的なことが、いかに大規模な実質的結果を生むか "に注目することを正当化しているのである。
今日の裁判所の社会的評価の低さは、シャドー・ドケットの使用を減らすといった、手続きに焦点を当てたわずかな改革だけでは、現在共和国を不安定化させている、少数の、少数による、少数のための政府への流れを変えるには不十分であることを意味している。アメリカの脆弱な民主主義や、我々の歴史において常にせいぜい願望的であった人権の基盤に対する攻撃が高まる中、闇を食い止めるために司法の機械をいじることだけに頼っている余裕はない。今後数年のうちに専制的な行政府が権力を掌握し、そのような行政府の暴力的な追随者たちが権力の座をすぐに手放さない可能性が迫っていることと、自信過剰な最高裁判所が自らの行き過ぎによって弱体化し、ファシズムの勢力を封じ込められなくなるという皮肉な現実とが相まって、希望を捨てようとしない私たちは手一杯だ。たとえ最高裁が拡大され、その正当性が弱まっている現状を克服するためにバランスが調整されたとしても、これからの仕事を裁判官だけに任せることはできない。それはいつものように、私たち全員の仕事である。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
