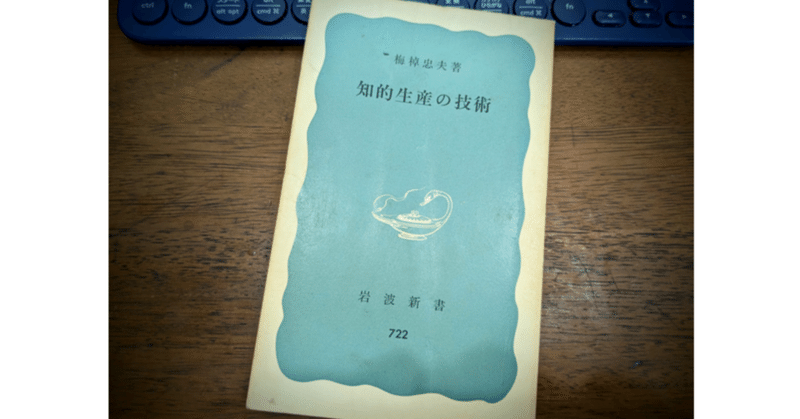
『知的生産の技術』の思い出
本棚を探してみたら、『知的生産の技術』が過酷な断捨離を耐えて生き残っていた。高木貞治の『解析概論』すら断捨離されてしまったことを考えると大したことだ。
奥付をみると初版1967年7月、第23刷 1976年8月10日とある。1976年、中学3年生の頃だ。
『知的生産の技術』と出会ったきっかけは中学の国語の授業だった。当時の私のクラスの国語を担当していた家崎さんは少し変わった人で、学校の夏休みにインドに出かけて行き、帰国後チフスだかコレラだかに罹患していることが判明、夏休みが終わったのに学校に来られなくなってしまった。馬鹿な中学生だった私たちは、「家崎マン、やっちまったぜ」と気楽に笑っていたが、1970年代にインドに行く人はまだそれほど多くなかった。そのことを考えても面白い人だったのだと思う。
実際、家崎さんの授業は面白くて、突然、黒板に『心中天網島』『女殺油地獄』『国性爺合戦』と書いて、「読めるかな? まぁ君たちにはまだ少し早い」とか言ってそのまま消してしまうような人だった。『女殺油地獄』が何なのか、一生気になる傷を子ども心に残したのだから、良い大人はそういうことをしてはいけないという教訓なのだろう。
最初に家崎さんが紹介したのは川喜田二郎の《KJ法》だった。ある日の授業でとつぜん紙の束を配って、「これに《赤》で思いつく言葉をできるだけたくさん書いてください」と家崎さんは言った。そんなの簡単!とばかりに、子どもだったので調子に乗ってたくさん書いていたら、「では、書いた言葉を全部使った作文を今日は書いて貰います。本当とか本当ではないかは問いません」とおっしゃる。最初からそう言ってくれたら5個ぐらいにしておいたのに・・・と後悔したが、後悔は後から悔やむから後悔というのだ。仕方がないので頑張って無理くり書いた。赤い服の少女が赤い風船で空を飛んで世界中でいろいろなことに出会う荒唐無稽な話ができた。
しばらくして職員室に用事があっていくと理科の担当の舟木さんに突然声をかけられた。「岡田、あの赤い風船の話、面白かったよ」。おいおい、教師は生徒の作文を回し読みするのか?とも思ったが、根が単純だったので、褒められたような気がして嬉しかった。
次の家崎さんの授業では、書いたものは特に褒められもせず、前回の授業の種明かしとしてKJ法の解説が行われた。連想記憶による強制発想法というよりは、もっときちんとした説明で、複数の事象に通底する共通点を、表面的に似ている部分だけでは本質的な点からも見出し、そこから一つの発見的な関係を導くという感じで、川喜田次郎が言っていることを的確に説明してくれていたと思う。《KJ法》について書かれた川喜田次郎の『発想法』の初版が1967年だから、10年ほどで公立の市立の中学の国語の授業で話されたことになる。そのときに家崎さんは合わせて『知的生産の技術』という本があることも説明した。理科の舟木さんに褒められた気がして調子に乗っていたので、『発想法』と『知的生産の技術』を読み、夢中になった。
《KJ法》はその後10年ほど、およそレポートと名のつくものを書くときにはほとんどかならず使うようになり、『知的生産の技術』の京大式カードは中学・高校とずっと使い続け、そして挫折した。《KJ法》について言えば、たとえば、高校の時の夏休みの公民の宿題では、ジョン・スタインベック『怒りの葡萄』×アーサー C クラーク『幼年期の終り』で《オーバーロード論》を書いたことがよい思い出だ。
ちなみに、学校をサボって国会図書館で本を読んでいたら、その公民の先生に見つかってしまい、彼は何もいわずにカレーを食堂で奢ってくれた。そして、「岡田の夏休みの宿題、最初Cにしようと思ったら、カミさんが「あら、結構、面白かったわ」というので、Aにしたんだ」というような話を笑いながらしてくれた。当時の国会図書館に食堂があったかどうか今となってはよくわからず、記憶修正された日比谷図書館か、また別の図書館だったのかもしれない。
そんな風に、《知的生産の技術》は、人との出会いで偶然に教えられたり、いろいろ試して挫折したり、奇妙な使い方をしても自分なりに満足のいく結果が得られたり、いろいろなのだろうと思う。
梅棹忠夫の『知的生産の技術』のまえがきにはこんなようなことが書いてある。少し長いけれど、適当に端折って引用しよう。
まえがき
この本ができあがるまでのいきさつを、かんたんにしるしておきたい。この本は、著者ひとりでできあがったものではない。たくさんの友人たちの、共同作業の結果のようなものである。
わたしは、わかいときから友だち運にめぐまれていたと、自分ではおもっている。学生時代から、たくさんのすぐれた友人たちにかこまれて、先生よりもむしろ、それらの友人たちから、さまざまな知恵を、どっさりまなびとった。研究生活にはいってからも、勉強の仕かた、研究のすすめかた、などについて、友人からおしえられたことがたいへんおおい。それぞれ専門はちがっていても、方法の点では共通の問題がおおかったのである。それも、ひらきなおって科学方法論と称するほどのことではなく、研究のすすめかたの、ちょっとしたコツみたいなものが、かえってほんとうの役にたったのである。そういうことは、本にはかいてないものだ。
友人たちのあいだに、べつに組織だった情報交換網があるわけではないが、ひとりが、なにかあたらしい技術を案出すると、それがほかの仲間にもすぐつたわるような仕くみが、いつのまにかできあがって、いまにつづいている。だんだんとあたらしい技法も開発されて、つけくわわり、また、ふるい技術は経験によって改良をうける。いまでは、これらの友人のあいだでの共有財産は、質的にも量的にも、かなりのものになっている。
その成果の一部を、あたらしい友人にはなしてみると、たいへん興味をしめすひとがおおい。具体的な技法についても、しばしばおしえてくれといわれる。そこで、そのような主題で、なにか執筆してみようかとおもいたったのは、一九六四年の秋のころだったと記憶する。
岩波書店の編集部のひとにあって、この話をしているうちに、これはなにも「研究」にかぎった問題ではなく、じつは、一般の「勉強」の方法にもつながることではないか、ということになった。なるほど、研究といっても、それをその構成要素となっている具体的な作業にまで分解してみると、けっきょくは、よむ、かく、かんがえる、などの動作に帰着するのであって、一般の「勉強」となにもかわらない。
そこで、予想される読者としては、研究者だけではなく、これから学問をやろうという学生諸君をもふくめ、また、ひろく一般に各種の知的活動を仕事にしている人たちをも対象に想定して、わたしたちの経験を、エッセイふうにかいてみようとおもいたった。まったく前例もないことなので、できあがった技術を解説するというよりは、いままでのなりゆきを中心にのべて、この種の論議におおいに関心をもってもらおう、というつもりだった。
もっともわたしは、いわゆる「ハウ・ツーもの」をかくつもりは、まったくなかった。わたしは、こういう問題についての関心をかきたて、刺激を提供することができれば、それでよいので、技術の解説書や教科書をつくろうという気は、はじめからなかった。「知的生産の技術」書ではなく、エッセイだという意味で、「について」としたのであった。
いま読むと、この文章自体が、漢字が開いてある(漢字をひらがなで書く)などの面白いギミックに満ちているが、このまえがきにはいま読んでも「そうだよなぁ」と共感する。
断捨離から生き残った新書は、紙質も悪く、印刷も薄く、老眼が進んだものには読みにくいことこのうえないのが残念だが、本文のところどころに赤線が引いてあったり、汚い字でメモが書いてあったりして、懐かしいといえば懐かしい。そして恥ずかしくもある。
『知的生産の技術』というタイトルには悩んだとも書いてあって、確かに《生産》とか《技術》とか、もっといえば《知的》という言葉の上昇志向的な前向きさも含め、高度成長時代が色濃くでているといえなくもない。
ひらがなタイプライターや京大式カードとか、そこに書かれている個別具体の方法論は、いまとなっては技術的に時代遅れにも見えかもしれないが、その底流にある本質はいまも生き生きと輝いている。普遍的というのはそういうことなのだと思う。
たとえば「日記と記録」という章には、こんな部分に恥ずかしい赤線が引いてある
技法や形式の研究なしに、意味のある日記がかきつづけられるほどには、「自分」というものは、えらくないのがふつうである。
どういうわけか、日記には心のなかのことをかくものだという、とほうもない迷信が、ひろくゆきわたっているようにおもわれる。
幼い私はこんな文章に出会ってびっくりしてしまったのだろう。肝心の梅棹忠夫のこの章での最終的な提案、《野帳の日常化》と《個人文書館》の部分の大切さにはそれほど思い至っていなかったようだ。
《知的生産の技術》という言葉遣いが最適かどうかはわからないが、独学の作法のいくつかは、日々の工夫と密接に関係しているのではないかと思う。
訪問していただきありがとうございます。これからもどうかよろしくお願い申し上げます。
