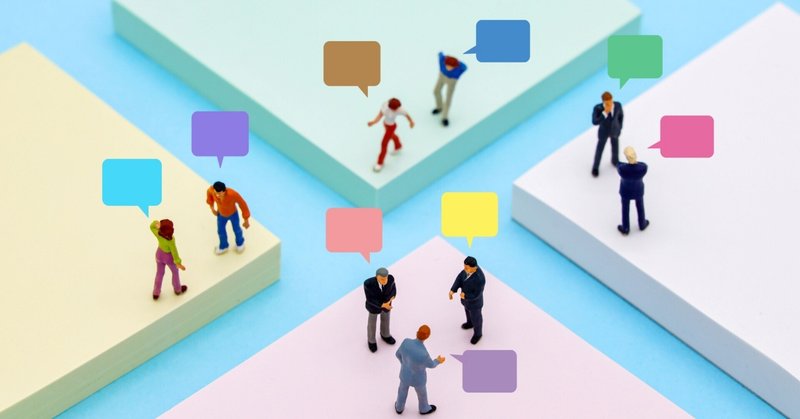
コミュニティで不動産に価値を込めるには
コミュニティって本当に便利な言葉だと思います。
コミュニティをその場所の特徴として打ち出していることを見かけることがよくあります。
地域活性化といったまちづくりの文脈はもちろん、商業施設やシェアオフィスなどの不動産ビジネスの文脈でもよく使われています。
一方で、当たり前ですが、コミュニティはそんなに簡単に作れません。
それでもこのコミュニティという便利な言葉は頼られ続けています。
職を変え、この仕事に向き合い続ける中で、行き着いた一つの答えがあります。
それは、コミュニティは結局人だということ。
何を当たり前のことを言っているのか、と思われるかもしれません。
でもそれがわかっていない人があまりに多いと、この仕事をする中で感じています。
だからこそ、今回はこのことをテーマに書きたいと思います。
コミュニティを謳い始める人達
コミュニティは結局人だということ。
これが分かっていない人が多いと感じるのは、仕掛けを作るフェーズでの議論をしているときです。
そこにいるのはデベロッパーや行政など、発注者側の立場の人たちです。
逆に、実際に現場で仕事をしている人たち(僕の会社ではコミュニティマネージャーと呼んでいます)と話しているときには、感じることはありません。
デベロッパーや行政といった発注者の人たちは、コミュニティマネージャーとして実際に働くことはないため、現場とは少し離れた立ち位置にいることになります。
この距離感がそうさせるのかもしれませんが、コミュニティをつくりたいと言って始まるわりに、彼らは人が大事なんだという本質に気づいていないのです。
もしくは、わかったつもりでいるのです。
ちなみに発注者という言葉があまり好きではないのと、発注者だけにあてはまる話ではないので、今回問題提起をする人たちのことをプロデューサーと呼ぶことにします。
プロデューサーとは、その場所をどんな場所にしたいか企画し、ビジョンを描き、そのプロジェクトを始める人のことを意図しています。
そして、その出来上がった場所を実際に日々動かし、魅力的に高めていく人をコミュニティーマネージャーと呼びたいと思います。
少し前置きが長くなりましたが、コミュニティを生み出していくには人が大事だということが分かっていないプロデューサーがあまりに多い、というのが今回伝えたい内容です。
プロデューサーがどんなにいいビジョンを描き、ブランドをつくり、素敵な空間をつくったとしても、同じ想いをコミュニティマネージャーと共有し、それを日々追いかけていく努力をしなければ、思い描いていた場所をつくることはできまぜん。
まさに絵に描いた餅です。
巷に溢れるコミュニティを謳った場所の数々で、実際に素敵なコミュニティが生まれているものが少ないと感じる原因はここにあると思っています。
コミュニティづくりは人材業だと思う
コミュニティマネージャー採用の募集をかけると、いつも多数の応募をいただきます。
飲食店で働いていた人、カメラマンやライター、会社員の人など、本当に多種多様なキャリアの方から応募をいただきます。
コミュニティマネージャーになりたいと思う人はたくさんいるんだなと実感しています。
多種多様なキャリアの人が集まるからこそ、その人たちが化学反応を起こしていくことで、コミュニティは生まれていくのだと思います。
一方で、培ってきた仕事の仕方や価値観はバラバラですし、この場所でやっていきたいことも一人一人もちろん違います。
いい意味で動物園みたいだなと思う瞬間がたくさんあります。
だからこそ、放っておいたら絶対にうまくいきません。
コミュニティをつくるには、場所を運営する事務的な仕事だけではなく、プラスアルファの仕事をすることが求められます。
そこに正解はなく、日々の小さな積み重ねによって実現されていくものです。
何を日々積み重ねていくのか、少しでもズレると時間の経過とともに、大きなズレになってしまいます。
だからこそ、マネジメントが重要なのです。
分かりやすい数字で結果を出すことが難しいうえに、キャリアも価値観もバラバラな人たちが集まる分、コミュニティマネージャーのマネジメントは、会社員のそれと比べると桁違いに難しいものです。
正解のないことに取り組んでいくからこそ、このマネジメントには、ビジョンをいかに共有できるか、いかにモチベートできるかが特に重要です。
全員で、向かっていきたい方向に進んでいけるかどうか。
つまり、いいチームを作ることができるかどうか。
要は組織論だと思います。
人材コンサルの方々の仕事領域かもしれません。
場所をつくり、そこにコミュニティを生み出していくということは、不動産業を行うことであると同時に、人材業を行うことだと僕は思います。
それが僕が行き着いた答えです。
プロデューサーは場所が完成したからと言って油断しちゃいけない。
そこから、いいチームをつくりあげるという長い戦いが始まるのです。
プロデューサーに伝えたいこと
企業によっては、コミュニティマネージャーを直接マネジメントしていくのは、プロデューサーの仕事ではないパターンもあるでしょう。
子会社に運営業務を外出ししている企業も多いかと思います。
でも、だからといって関わりを引いてはいけない。
あなたが作りたかったコミュニティのある場所は、開業したら完成ではない。
関わり続けて、作りたかったその熱量を、場所に込め続けなきゃいけない。
場所が出来上がったら顔が見えなくなるプロデューサーがあまりに多い。
だからコミュニティが絵に描いた餅になる。
そう僕は思います。
もし、これを読んでくださっている方にプロデューサーの方がいたら、いいチームを作れているかどうか振り返ってみていただきたいと思います。
それは現場がやることだから、と思ってしまう方がもしいたら、現場との関わり方を見つめなおしていただけたらと思います。
プロデューサーがこういった仕事をしなくても、うまくいっている場所もあると思います。
でもそれは、たまたま優秀なコミュニティマネージャーがいるからであって、属人的なものです。
作った人間には、それを完遂させる責任があります。
出来上がったから終わりではありません。
僕はありがたいことにありながら、コミュニティマネージャーをマネジメントする立場でもあります。
これは僕の学びであり、反省です。
どうか、1人でも多くのプロデューサーが、自分が想いを込めて作った場所に、火を灯し続けてくれますように。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
