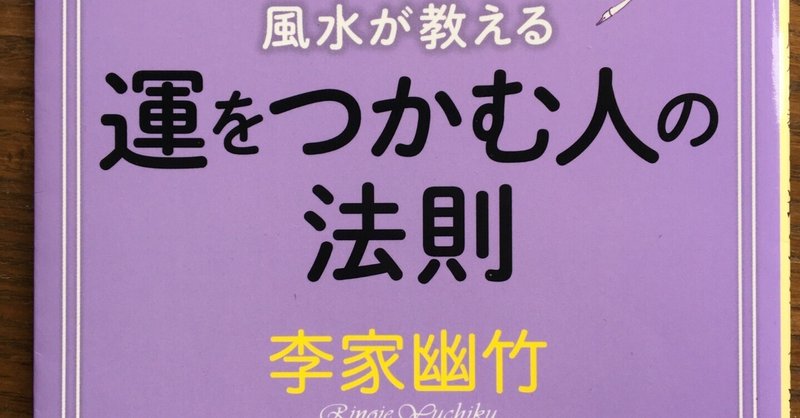
#95『風水が教える運をつかむ人の法則』李家幽竹
☆#94『おそうじ風水』李家幽竹に続いて読む。前著は主に家だったが、本書は身だしなみや小物などや生活スタイルなどを扱っている。
感想文は前著と同じになってしまうので、実行したこと・実行しつつあることを自分のために列挙する。
・風呂掃除(今まで洗剤を使っていなかったが使うようになった)
・毎朝トイレ掃除(むしろ楽しくなってきた)
・コンロの焦げ付きを落とす(奥までは出来ないが、不問)
・レンジフードの油汚れを落とす
・使う見込みのないものを捨てる
・玄関を水拭きする
・玄関のドアノブを拭く
・冷蔵庫の中身を隈なく掃除する
・水回り全般の汚れを落とす(落ちない黒カビ、断念)
・古くて汚れ切った布巾・雑巾を新しいのに変える
・クイックルワイパーを一度で使い切る(貧乏性だから次に取っておく修正有り)
今後の予定
・粗大ごみ処分(まだある…)
・下着、靴下、シーツ、財布、包丁を買い替える
・靴を買い足す
・スマホを新しくする
・車の中を綺麗にする
・アトリエに玄関マットを敷く
と言った所である。
性分の変化というものは面白いもので、面倒くさかった掃除が楽しくなってくる。毎朝トイレを掃除するのも気持ち良い。冷蔵庫の掃除も自分がどれだけ無自覚に黙殺していたか分かった。掃除すると「すまぬ、こんなに放っておいて」という気持ちが湧いてくる。
要するに、自分の住まいは全て自分の延長なのである。だから体をいたわるように家を労わらないといけない。しかし体をいたわる発想の無い人間の場合どうなるか? やはり家をいたわることもないだろう。
ここに根本的問題があると見る。
体をいたわるという発想の根っこには、「体は道具である」という考えがある。では何の道具か? 精神の道具なのである。もっと言えば、魂の道具である。こういうことを、ある親は難しい教えで無しに伝えている。
例えば「靴を大事にするということは足を大事にするということなんだよ、足を大事にするということは色々な場所に行けるという縁や可能性を有難がることなんだよ」…と言うまでもなく、靴をいつもきれいに保つ、子供の靴が壊れて来たら新しいのを買ってあげる、というふうに。
あいにく、そんなことは私の育った家では教わらなかったどころか、「体など壊れても問題ない」という教育がまかり通っていた。☆#9『子は親を救うために「心の病」になる』の言う所の「心理的ネグレクト」である。
住まいを大事にしない⇒体を大事にしない⇒魂を大事にしない、という潜在的教育(教えるつもりなく教えてしまうこと)がここに成り立つ。結局、私の離婚もそういう負の延長線上に必然的に起きた。
まあ、過去を悔いても仕方ない。大事なのはこれからである。気付けたのだから幸せである。
風水は簡単に言ってしまえば「こざっぱりと、身綺麗に」であり、理論は複雑だろうが、哲学の神髄は子供で分かる程度の内容である。例えば毎日トイレを使うのだから毎日トイレを掃除する…言われてみれば当たり前のこんなに簡単なことが出来ないのは、それだけ人間が精神的生き物だということだ。
精神の方にその習慣を得る準備が出来ていないと、まるで高い山を登るかのように、掃除ができない。だからその意味で「こんなことで良くなるなんて」と思いつつ、その「こんなこと」がたやすく出来るまで人生をまず進めなければならないということだ。
ついに私の人生も最終浄化に向かうだろうか?
結局、感想文が長くなってしまった。
この著者の本を、更に読んでみようと思う。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
