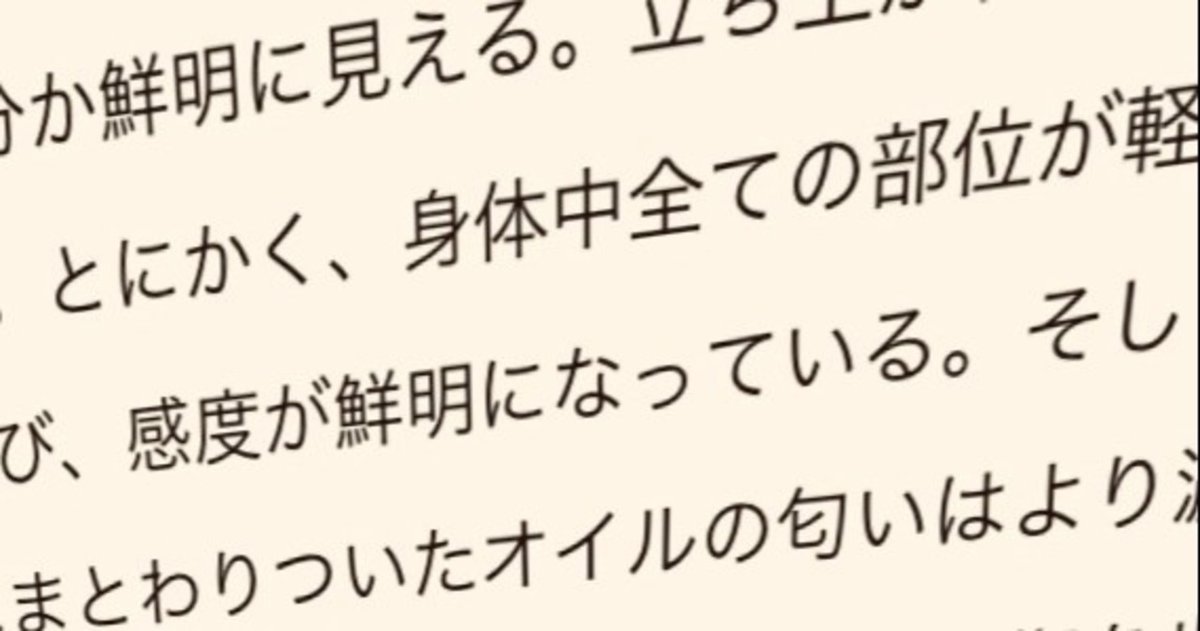
オイル
「ユカリちゃん、おいで」
ばあちゃんが呼ぶ声がしたので、「なにー?」と言って、横に近付く。ばあちゃんはベランダに腰掛けていた。
「ごらんよ、トマトがまた実をつけた」
ばあちゃんはいま、数ヶ月前から育てているトマトの苗に執心している。最近になって実が生り始めたようで、しばしばわたしに苗の様子を見せてくる。
「いい感じじゃん」
「まったくね。昔はいくら植物を育てようとしても、すぐ腐らせてしまったもんよ。こんな風に歳取って来ると、いろいろ丁寧に出来るようになるのね。見なさいよ、こんだけ育って」
「うん、食べ頃になったら食べよう」
「そうね。きっと美味しいはずよ」
まったく、たまの休日なのに、どこにも出掛ける気力が湧かない。会社では不慣れな上に内容のきつい事務仕事に回されているし、お金は繰り返す生活の中でいつの間にか無くなっている。これだけ自分自身がくたびれているのも、まあ当然なのだろう。築40年ぐらいのこの安アパートのベランダで、ばあちゃんと陽射しを浴びているだけで、世界は十分贅沢に思える。
「そろそろ、どう?」
ばあちゃんが、よっこらせ、と立ち上がり、わたしに目配せをする。
「しようか」わたしは言って、ばあちゃんを誘導する。「さあ、座って」
ばあちゃんはわたしの声を聞くと、部屋の隅にある鏡の前に腰掛けた。
「塗るね」わたしは瓶の中に収められた、薄紅色のオイルをトロトロと手の平に乗せる。ばあちゃんは上着を脱いだ。目の前に現れたばあちゃんの背中に、腕に、腹部に、肌一面にオイルを塗布する。ばあちゃんは心底ほっとしたような、嬉しがるような表情で、「ああ。いいわあ。すごくいい」と小声で呟き続ける。
塗り終えるとばあちゃんは、「あんたの番ね。塗りますかね」と言い、上着を着直して、わたしに再び目配せを送った。
「お願い」わたしは上着を脱ぎ、ばあちゃんに身体を任せた。ばあちゃんがわたしの肌にオイルを塗っていく。ばあちゃんの優しい手のひらからオイルが沁み込んで来るのを感じて、わたしは胎内に回帰していくような安らぎに浸る。
「今日も、いい感じ」わたしは呟いた。ばあちゃんは、「そりゃ、いいことね」と返してくれた。
オイルが身体に沁み渡るのを感じながら、ふと天井を見上げる。そうか、ばあちゃんとこのアパートに住み始めて、もう一年になるのか。
去年両親から、ばあちゃんと住んでくれないか、と言われた時は、まず、唐突過ぎだろ、と思ったものだ。
聞けば、40代にしてまだまだ働き盛りで忙しい両親に代わり、遂に80歳に突入し、そろそろ本格的に年老いてきたばあちゃんの介護役になれる人間が必要だという。老人ホームに入れるとか、デイサービスに通わせるとか方法あるでしょ、その道のプロに頼んだほうが絶対いいって。と言ってみたが、そんな金は無いとふたりは述べる。さらには、ばあちゃんはホームやデイサービスで子供扱いされて、幼稚なレクリエーションやらなんやらやるのはまっぴらごめんだ、今の今までこんだけ頑張ってきたんだから短い余生くらい好き勝手に暮らしたいのよ。と言って聞かず、しまいには家の神棚や食器を破壊し始め、家庭内暴力に手を染め始めている、と両親は伝えてきた。そこまで聞くとさすがに危機感を覚えてきたが、まだあの優しく、謙虚で、常に冷静沈着なばあちゃんが、そんなプリミティブな破壊衝動を発露するイメージは湧いてこなかった。
しかし、直後に両親からラインで、めちゃくちゃになった神棚と、半分壊れた食器棚の写真、それに、動かぬ証拠の、ばあちゃんが、キエエ、キエエ、とそこら中のカーテンを破っている様子の動画が送られてきた。
動画の中で、ばあさん!やめてくれ!やめてくれ!と父親が叫んでいる。ばあちゃんは、キエエキエエキエエとうるさく悲鳴を上げてカーテンを引き裂き続けている。母親はうわあ、うわあと泣いている。
その後、両親は必死にばあちゃんを説き伏せようと会話を重ねた。するとばあちゃんは、そんなに介護人がわたしに必要だというならユカリちゃんにお願いしたい、と言ったという。彼女はわたしの唯一の孫であり、昔からわたしを老人扱いも子供扱いもせず、常に若い心同士、対等に接してくれた人間だから、と。
混乱の中、ばあちゃんの御指名を受けたわたしは、なんとか去年の今頃になって、ばあちゃんをこの自分の住居に迎え入れた。
「ボロアパートで狭っ苦しくてごめんね、ユニットバスはあるよ、小さいけど」と言うと、
「なに言ってんの、ユートピアって感じよ。なにより、ここにはユカリちゃんがいるんだから。あんたは昔から変わらずにいるからいい。わたしを公平な立場で見てくれるから。そう、わたしの肉体は年老いているけど、精神はまだ全然若いの。みんな歳を取ったら人間、弱々しくなるもんだと思っているのよ」とまくし立ててきた。
「ばあちゃん、相当ストレス溜まってんねえ」と言ったら、
「まったく酷いもんよね、人生、ここからとも言えるのに」と呟いた。
ばあちゃんはしばらく見ないうちに体格が少し良くなって、目付きはだいぶ鋭くなっているように見えた。
「身体でも鍛えてるの」と言ったら、「自然に体格が変わったのよ。なにか本能的に、獣にでも生まれ変わろうとしてるような感じね」とばあちゃんは言った。
ばあちゃんとわたしは、まるでずっと前から一緒に住んでいたかのように、すんなりと暮らしに馴染んでいった。ばあちゃんがもし何かの拍子に暴れたらどうしようか、と内心怯えていたわたしだったが、別にそんな騒ぎもなく、平坦に、穏当に一年が過ぎたのだった。
ばあちゃんの肉体は確かに年老いて、結構ガタが来ていた。腰は曲がり始めていて歩きにくそうだし、老眼もだいぶ酷くなったのよね、と言う。しかし意識は明瞭らしく、口がよく回る。口が回るということは、無論頭がばっちり回っている、ということである。
わたしが仕事で理不尽な目に遭って愚痴をついつい述べると、
「どんな仕事も人間のやることよ。相手に完璧を望んじゃいけない。誰も完全にはなれない。ユカリちゃんも、あなたの上司も同僚たちも、みんな、完全にはなれないの。それを理解するのよ」と言って、わたしを諭す。
新しい仕事を回されたことの不安を言ってみると、
「不安は不安のままに、流れに任せて、自分をその場の空気に委ねればいいの。なにも焦ることはない。ユカリちゃんはユカリちゃんで、そこになにかを足すことも、引くこともしなくていいんだから」と言ってくれた。
ばあちゃんは別に家事も手伝わないし、基本そこにいるだけだ。しかし話してくれる相手がいるだけで、こうも意識が違う。ばあちゃんと過ごす日々は、わたしにとってとても快かった。
それで、オイルである。
ばあちゃんとわたしが週に一度、肌に塗布しているこのオイルの名称は「スーパー・シュリンプ・オイル」という。
このオイルの存在は、会社の同僚が休憩時間に教えてくれた。聞けばいま、同僚の両親が新しい健康用品を自家製造しているという。同僚はわたしと同い年くらい、つまり26歳くらいで、どちらかというと仕事の下手な、不器用な感じの女性だ。
なんでもスーパー・シュリンプ・オイルというのは、その名の通り海老の剥き身を擦り下ろして、オリーブオイルとニンニクと秘伝の複雑な製造工程を経たタレとともに混ぜ込んだエキスらしく、それを週に一回上半身に塗れば、日常的な身体の節々の痛みが消え、長いスパンで見れば癌になるリスクも半減するという。ただしその半永久的な健康と引き換えに、身体は海老とオリーブとニンニクと秘伝のタレの匂いになる、というのだ。そんな眉唾物の、得体の知れない臭みに溢れていそうなオイルなど、社員の誰も身体に取り入れようとはしなかった。言わば全身にアヒージョの汁を塗りたくるような行為である。狂気だ。健康への効果にしたって確証はないわけで、わたしは瞬間的に、そんなもん塗りたくない、絶対無理、と思った。
同僚は両親からの指示で、試供品を手に取って試してくれる人を探していた。要は実験台になってくれる人を求めていたわけだが、そんな物好きはもちろんいない。全員に断られた同僚は、最後にわたしのほうにやって来た。
「ユカリさん、どうかな…」
社内に友達もちょっとした話し相手すらもろくにいないわたしに声をかけるなんて、もうよっぽどだ。そんなに両親の発明が大事なのか。しかし実際には断るだけの度胸などわたしは持ち合わせていなかったし、ちょうどその頃ストレスで目が痛くなったり、目が治ったかと思えば今度は肩が痛くなったり、を繰り返していたこともあって、わたしは気が付いたら「分かった。わたしが試すよ」と申し出ていた。彼女は目から大粒の涙を流して「ありがとう…ありがとうね…ユカリさん大好き…」と、歓喜に打ち震えていた。
即座に彼女はわたしにスーパー・シュリンプ・オイルの試供品を渡した。二週間ほど試してみたら感想を出来るだけ早く教えて欲しい、という懇願を受けたわたしは、分かった、すぐ試すから、ばあちゃんにも塗ってみるよ、と返答しておいた。さて。
その日、スーパー・シュリンプ・オイルを手に帰宅したわたしは、言ったことはやらなければ、と、早速風呂場でオイルを上半身一面に塗ってやった。半ば自棄のような気持ちであった。
塗ったその日はなにも効き目を感じなかった。相変わらず肩も痛いし耳も痛いし、なんか歯も痛いような気がする。むしろ諸々痛くなってないか、これ。しかも身体には魚介類やニンニクの濃厚な香りがまとわりついている。これは失敗なんじゃないでしょうか、同僚よ。ばあちゃんが風呂場から上がったわたしを確認して、「あんた、なんか洒落た料理の香りがするわよ。なんか食ってきたのかい」と言った。どうすんのこれ。
しかし、その晩就寝して、夜中にふと目が覚めると、なにかが違う。肩が軽い。耳がすっきり通っている。歯が痛くない。目も幾分か鮮明に見える。立ち上がれば腰も軽い。とにかく、身体中全ての部位が軽みを帯び、感度が鮮明になっている。そして肌にまとわりついたオイルの匂いはより濃さを増している。これは朝目覚めて街を歩けば、通り過ぎる人々は顔をしかめるか、うまそうな香りだと喉を鳴らすかのどちらかに分かれるだろう。人を選ぶ匂いだなあ、と思いながら、また眠りに就いた。朝が訪れて再び起き上がる頃には、昨日の自分とまったく別人のように、肉体は痛みや重みから解き放たれて、朗々と躍動した。
出社すると、例の同僚が「もう塗った?」と、待ち構えていたように歩み寄り、そっと聞いて来た。
「塗ったよ。おかげで身体全体、めっちゃ元気。痛み重み、ゼロだよ」と伝えると、「えー、凄い!よかった!」と彼女は喜んだ。
「ばあちゃんにも塗ってみるよ」と伝えると、「ぜひぜひ。シュリンプ・オイルには年齢制限は無いよ。ただ塗るのは週一だけにしてね。塗り過ぎると、匂いがあまりにも強くなるし、逆に体調崩すみたいよ」と興奮気味に、事細かに彼女は教えてくれた。
その日も割りかしハードな仕事をきっちりこなしたが、身体はほんのりと怠くても、痛みや重みはあまり感じなかった。そして一週間経つ頃にはまた少しずつ身体が重くなって来たので、またオイルを塗った。塗ると、身体に蓄積された重みが凝縮されるように一時目立ち始め、そこからだんだん潮が引くように身体が軽くなっていく。かなり良く出来ているオイルではないだろうか。身体は完全に魚介、ニンニク、その他色々の芳香を放つようになったが、慣れてしまうと、普通にいい匂いだなと思ってしまうようになった。すれ違う人は大体顔をしかめて驚くが。
ばあちゃんの反応はというとやはり鋭く、ある夜帰宅すると、「あんた、匂いが変わってから、身体がぴんぴんしてるわね。なにが作用しているわけ?」と聞いてきた。わたしはシュリンプ・オイルを見せて、こういうのが同僚から渡されてさ、と事情を伝えた。
ばあちゃんは、わたしにも塗りな、と、すぐに言った。
「えっ、いいけど、もうちょっと躊躇とかない?」と聞くと、
「何年生きてきたと思ってんのよ。怖いものなんてないのよ、わたしには。塗ってみせな」とばあちゃんは言った。というわけで、その場でばあちゃんに服を脱いでもらって、わたしは彼女に、丁重にオイルを塗布した。
「なんか、逆に痛くなってきたわね、腰とか」とばあちゃんは呟いた。
「そういうものなの。ちょっと我慢して、寝たりとかして待ってみて」と言うと、「なるほどねえ」と、ばあちゃんは布団に入った。
次の朝、ばあちゃんの腰は真っ直ぐになって、格段にスムーズに歩行できるようになっていた。老眼はさすがに治っていなかったらしいが、「目がニチャニチャしないわね」と言っていた。一週間経つと、わたしと同じように効き目が切れてきたらしく、わたしはまたばあちゃんにオイルを塗った。
同僚に、ばあちゃんにオイルを塗り、こちらも健康促進に成功したことを話すと、「本当に!すごいなあ、うちの親。ありがとう...」と、例によって感激していた。
ばあちゃんとわたしは、休みの日にオイルを塗り合うことをルーティーンにした。大体日曜は休みなので、日曜の昼間にオイルを塗ってもらい、お返しにわたしもばあちゃんに塗る。ふたりがかりで塗ったほうが塗りやすく、ハードな業務の後に会社から帰宅して塗るのは地味にしんどい作業だったからである。余裕がある時に塗るのがやはり正しいようで、オイルの効きも休日のほうが心なしか良かった。試供品は一ヶ月ほどで使い切ってしまって、これは日常的に使いたいと思ったわたしは同僚にオイルを買い求めた。一本につき一万五千円なの、と聞いて、わたしはどうするか迷ったが、新たなる画期的な発明に対する支援の念も込めて購入した。同僚は、もうユカリちゃんは恩人だよ、ありがとうありがとう、とひたすらわたしに感謝した。社内では濃厚なこの匂いのせいでますます無視されたり、怪訝に扱われたりするようになったが、そんなことはどうでもよかった。実際に後腐れなく完全に近い健康さを維持できているのだから、なにを文句を付けることがあろうか。
わたしも確かに疑った時もあった。こんなうまい話があるのか、と。絶対なにか副作用とかヤバいなにかしらが降って来るんじゃないかと。しかし二ヶ月経っても、三ヶ月経ってもそういった悪い症状はなく、わたしは溌剌とした生活を享受していた。わたしはまずまずに上機嫌だった。
そうして健やかに過ごしていたある日、一本の電話があった。両親からである。
「もしもし」
「おう、ユカリ。父さんだ。うちのばあさんはどうかな?」
「元気だよ。喧嘩もしてないし、いつも機嫌良いよ」
「それはよかった。安心したよ。それで、今日なんで電話したかというとだね、実は、お見合いの話が来ているんだ」
「お見合い?」
「結婚相手にあぶれているという30代の息子さんを持った、会社の同僚の人がいてね。彼はすごくいい人で、仕事も優れて巧い人なんだよ。仕事でいつも彼の技術に助けてもらっているから、お返しだ。一度その息子さんと会うだけ会ってみて欲しいんだが」
「断る理由は、特にないけど…大丈夫かな」
「大丈夫だろう。きっと彼はおれたちを騙したりはしないさ」
「うん、分かった。会ってみよう。わたしも出会い無いし」
「ありがとう。では、スケジュールを調整しようか」
父が素早く調整した結果、わたしと父、父の同僚とその息子さん、の四人で、早くも次の日曜に会うこととなった。
ばあちゃん、お見合いだってさ、と隣にいたばあちゃんに言ってみた。
「ほう。なんでもやってみなさい。会社じゃ、あんたは周りにとって存在していないも同然なんだろう。チャンスね」と、穏やかに言った。
「パッと見、気に入らん男でも、なんかしらの魅力があったりするもんさ。まあ、気軽な気持ちで会ってきなさい」
そして日曜になった。今日はまずは実家へ。父と落ち合うのだ。
順当に実家に辿り着くと、わたしは父の車に乗り込んだ。父はわたしのオイルの匂いを嗅ぎ付け、「大丈夫か、なんか変なもん食ってないか」と言った。
「なに言ってるの?」
「いや、結構特徴的な匂いしてるぞ。知らないうちになにかあったのか、と思ったんだよ」
わたしは父親にオイルの話をした。
「そんなうまい話があるかね。変な副作用でもドカッと来たら、どうするんだ」
「わたしもそう思ったけど、週一に留めておけば大丈夫みたいよ、その同僚の子によれば」
「そうか。どうしようがお前の裁量だ。ただ、その同僚さんの言う通り、オイルを塗るのは週一にしなさい」
「当たり前よ。もう大人なんだから、他人の言うことくらいちゃんと聞くって」
「ちょっと魔が差したりすることもあるだろう、人間なんだから。油断するなよ」
「大丈夫、大丈夫」
そんなふうに話をしていると、一軒のレストランに辿り着いた。ここが今日の待ち合わせ場所である。都市部から少し離れたレストランで、外装から結構年季が入った建物に見える。
入ると、すでに父の同僚親子が奥の席に着座していた。息子さんはわたしたちを見るなり、すくっと立ち上がり、絞り出すような上ずった苦しい声で、「ああ、こんばんはっ…」と言った。いまは昼だ。
彼は極端なくらいにウエストが痩せ細っていて、目元のクマが凄いし、両目の小ささから眼鏡の度がめちゃくちゃ強いことが窺えて、社会経験が著しく不足していることを感じさせるような幼い顔つきをしていて、顎にはうまく剃り切れなかったと思われる、不揃いな髭の剃り残しがあった。
父が言う。「紹介するよ。同僚のミツルさんと、その息子さんの、ヒロミチさんだ」
「こ、こんにちは」わたしは言った。
ミツルさんは、「今日はありがとうございます」と丁寧にお辞儀をして、わたしたちを迎えた。
わたしたちはとりあえずメニューを注文した。このレストランはどうやらなんでもある感じだ。わたしは海老漬けになっているので魚介類以外のものが食べたかったため、ポークカレーとやらを注文した。わたしが注文すると、皆それぞれ色々と注文していった。ヒロミチさんは震えた声でいかにも辛そうに「う、う、あ、オム、オムムン、あ、オム、ライス...を、ひとつ」と言った。
ミツルさんは再度、「今日はありがとうございます」と謝辞を述べた。わたしと父は恐縮して、「いえいえ、いいんです」と言った。ふっと沈黙が降りる。
父が切り出す。「今日は、ユカリに息子さんを紹介して下さるということで」
ミツルさんが言う。「そうです。是非とも、まずはお友達から、ということでね、是非とも、ええ」ヒロミチさんは目にぎっしりと涙を溜めて、仏頂面を極め、口を真一文字に結んで、じっとしている。怖い。
父がまた切り出した。「ヒロミチさんは、お仕事は…」
ヒロミチさんは急に涙をシュッと目から引かせて、「いまは世界的に内在している思想の究明を急速に追求しております。世界現象の動向を伺い、数学的データにまとめ、いずれ論文という形で全世界に提出し、社会に満ちる病巣を解き明かすのです」と早口で述べた。怖いんだよもう。それにその追求とはちゃんとした仕事なのか。
父が、「な、なるほど。その事業は、調子のほうはどうですか」と問うた。するとヒロミチさんが述べる。
「極めて順調でございます、極めて、極めて順調であり、えー、凄まじい勢いで世界の病理は解き明かされております、えー、あの、わたしのデスクトップの中で。世界は現在肉体的なダークネスと精神的なダークネス、の両方を抱えており、そこに対応し切る神的な、コアな意志が未だ提示されていないことから、あらゆる方面に未曾有の混乱が」
ミツルさんが「もういいんだ、大丈夫だ」と制した。わたしはここにやってきたことを後悔し始めていた。父がわたしのほうを見つめて、おまえもなにか言葉を発しろ、という目線を送ってきた。
「あ、あの、ヒロミチさん、好きな食べ物とか、ありますか」わたしは声を出す。
するとヒロミチさんは、まるで三歳児くらいの子供のようなファルセットとイントネーションで、「ケーキが、好きです」と呟いた。突然に声が変わってしまった。言い方も。なんだこの人は。顔は依然真剣な仏頂面だし。早く帰してくれ頼むから。
「ケーキの、いちごのとこは、最後に食べます。そのほうが美味しいです」ヒロミチさんは、子供声になってそう答えた。「そ、そうですか。ありがとうございます」わたしはなんとか言った。
わたしは怖々としていたが、だんだんヒロミチさんに好奇心が出てきてもいたので、色々質問してみることにした。
「好きな芸能人の方は…」
「イエス・キリストが好きです。ブッダとは違う魅力があると思います」それ芸能人じゃないです。
「洋服とか、どちらで買いますか」
「全部、親のお下がりなんです!」急に大声に笑顔になるな。
「子供時代の一番いい思い出といえば」
「大きなパチンコ屋で、パチンコをしたことです。大当たりが出て、誰よりも儲けました。嘘ついてると思ってませんか、あなた、嘘と思ってるでしょ、本当ですよ」初対面でみだりに疑念を向けないでほしい。
その他色々質問するだけ質問したが、どれも歪な答えばかりが返ってきて、だんだん疲れてきてしまった。わたしは運ばれて来たポークカレーを丁寧に食す作業に移った。結構美味だったのが救いだった。
父がふと言った。「いい感じではないでしょうか」ミツルさんも、「そうですね」と笑った。どこがだ。両者ともなんとかしてそう思いたいのだろうか。
すべてを無難な会話に留めていたら、いつの間にか会は終わった。わたしたちは「この度はありがとうございました」「またよろしくお願いします」と言い合って、店を出た。ヒロミチさんの行動は結局、涙を溜めて黙っているか、違和感に溢れた声、言葉を発するかのどちらかに終始していた。
父の車に乗り込むと、父は「どうだった?」と聞くので、「分からない。全然分からない」とだけ言った。父は、「そうか」と言った。
夕刻、父と別れて帰宅したわたしは、ベランダに静かに座っていたばあちゃんの顔を見るなり「あー、もう大変だったんだよー」と言ってしまい、そこからひたすらばあちゃんに今日起きた出来事を聞いてもらった。
ばあちゃんは言った。「ヒロミチさんのような人の中には、なにかがあるはずよ。見つめてみなさい。想像できる範疇を越えたところにしか、喜びは無いのよ」
「でも、もうちょっと穏やかな、スムーズな出会いが欲しいよ。こんなの無茶苦茶過ぎる」
「まあ分かるわよ。でも、もうちょっと辛抱してみてもいいのかもしれない気もするわね。あんたが見ている景色や、感じていることは、無駄じゃないし、嘘偽りでもないわよ。もう少し注意深く眺めてみなさい」
「うーん、どうなんだろ」
「オイル、塗ったげるわよ」ばあちゃんはそう言ってくれた。わたしとばあちゃんは再びオイルを塗り合った。わたしの気持ちは幾分か静まったが、またヒロミチさんに時々会わなければならないのなら、めちゃくちゃ辛いな、とずっと思っていた。
さらにほどなくして、再び父とミツルさんのスケジュール調整により、今度はこの日に皆で会いましょうと、次の日曜に新たな会合の予定が押さえられていた。父はそれを電話越しに知らせ、「頼む。ミツルさんはおれの恩人なんだ。会社で何回も助けてもらったんだよ。辛いかもしれないが我慢してくれ」と懇願した。つくづく断れない性格のわたしは、ただただそれを受け入れた。
次の会合場所は、ミツルさんの家であった。もう家にわたしを連れ込むって、それ早くないですか。もうちょっと段階を踏んだほうがいいのではと思うのですが。
「映画を観ましょうか。いい映画があるんですよ」ミツルさんがテレビを点け、DVDをセットした。映画はざっくり言うと、戦時下で兄と妹が生き別れて、また出会うという話だった。劇中の音楽は気が利いているというか、お洒落な感じがしたが、話自体は淡白で、そこまで気は乗らなかった。もうちょっとドラマがあったほうが盛り上がるのだが。映画を観ている最中、ヒロミチさんはひたすら目に涙を溜めて、唇を真一文字にして、少し緊迫したシーンになる辺りでは小刻みに震えていた。
ミツルさんが「映画、どうでした?」と聞いてきたので、「あ、すごく面白かったですよ」とだけ答えた。
即座にヒロミチさんが、「映画の良さって、なんであるとお考えですか」と、やたら仰々しいバリトンの声色で聞いてきた。
わたしは少し答えに窮したが、「あ、あの、映画は風景が美しいですよね。美しい風景を見るといい気持ちになりますよね」と言っておいた。
するとヒロミチさんがわたしの返答を遮るように、「映画の役者たちの微細な動きというのは、人間の行動の機微を追求する上で非常に興味深いものでございまして、素晴らしい動き、鈍い動き、細かい動き、そういった様々な動きをわたしはデスクトップ上でモンタージュしながら日毎研究しているのです。そこには人間が持っている輝きの原理的部分に迫る手掛かりがあり、際限ない宇宙的事実の反響が」また始まった。
ミツルさんが、「もういいよ、ヒロミチ」と呟くと、ヒロミチさんは不気味にもすぐに静止してみせ、一瞬で彼の目に涙がギュッと溜まった。わたしはだんだん嫌になってきたが、それを表せる勇気も無く、父の顔に泥を塗るわけにもいかないので、努めて淡々と応対した。
ひとしきり歪なコミュニケーションをして、帰り際にヒロミチさんが「今度は、ユカリさんのお家で、ご一緒しても、いいですか?」と、三歳児みたいな例の気持ち悪い裏声と、わざとらしいイントネーションで言ってきた。可愛く言えば許されるとでも思っているのか、この野郎。しかしわたしはここまでアタックされても断れず、「い、いいですよ。またお話しましょう」と言ってしまった。どんだけ勇気が無いんだ、わたしは。ヒロミチさんはまた声色を異様に変え、やたらバリトンな声で「ありがとうございます…」と、深々お辞儀をした。嫌だなあ、こういう変な人。もう会いたくないなあ。でもそんなこと言えないんだよなあ。本当にこの意気地無したるや。嫌なものははっきり嫌だと言ってもよかろうに。
再び父に送迎してもらう。「どうだったか?」と父が聞く。「もう嫌。本当に嫌。こんなの…助けてよ」と、わたしは少し泣きそうになりながら言った。
「でも、もう断れないんだ。ミツルさんには本当に仕事でお世話になった。しかもそれを鼻にかけず、おれにいつも真摯に、親切に接してくれる。あんな素晴らしい同僚はいないよ。その…で、あるから…もしかしたら、ヒロミチさんとの結婚、も、あるかもしれない。視野に入れておいて欲しいんだ」父は言った。
わたしは限界を迎え、泣き崩れた。「なんでそんなことしなきゃいけないの」わたしは声を振り絞った。父は、「運命だと思ってくれ。きっと糧になる」と言った。なんだ、それ。
わたしは泣きながら家に帰った。魚介やニンニクの油の香りを漂わせて、泣きながら歩いている若い女なんて、これはこれで変人だ。ならばお互い様か。いいやあんな妖怪じみた奇人と結婚など。周りの大人の都合で、わたしの大切な人生の経路を決められてたまるものか。
ばあちゃんは、泣きながら帰ってきたわたしを見るなり、「まあ、どうしたの」と聞いて来た。今日あったことを全部話し尽くしても、どうせばあちゃんは中立めいた意見を言うだけだろう。「気にしないで。もう寝かせて」と言って、わたしは夕食も風呂もなしにして、布団に潜った。
ばあちゃんは、「大丈夫よ。なにがあっても、大丈夫だから」とだけ言って、わたしを好きにさせてくれた。ありがとう、と少し思った。でも、それも怒りと悔しさと悲しさで、すぐに分からなくなった。
そして父とミツルさんによって、ついにヒロミチさんが我が家にやって来る日が決定されてしまった。二週間後の日曜に決定付けられたその日が近付くごとに、わたしは憂鬱な気分になった。仕事場では相変わらず魚介臭い女として怪訝に扱われている。オイルを塗っているから、身体は重くも痛くもならないことだけが救いだ。だがオイルは肉体にはうまく作用しても、精神にはひとさじも効かない。わたしは次第に塞ぎがちになり、仕事もだんだん手に付かなくなった。ばあちゃんにもなにか話す気が起きない。家に帰ればすぐに眠ってしまって、夕食もあまり食べられなくなった。朝思い出したように風呂に入って、出社して、休日になるとばあちゃんに促されて、オイルを塗ってもらった。わたしはオイルを塗られながら、なにも言わずにいた。ばあちゃんはオイルを塗りながら、「大丈夫なのよ。結局は、何事も」と、誰に向けるでもなく、呟いていた。本当にそうなんだろうか、そんなわけがあるのか、と思った。
時間を止めることは不可能で、ついにその日が来てしまった。父によってばあちゃんは一旦実家に連れて行かれた。わたしたちをふたりきりにしておこうという算段のようだ。「しょうがないわね」と言ってばあちゃんは父の車に乗り込んで、実家へ運ばれていった。完全にあのヒロミチさんとふたりだけの空間が現れるのである。地獄であることは覚悟の上だ。こうなりゃなるようになっちまえばいい。わたしはもう、完璧に捨て鉢な気分だった。
そしてインターホンが鳴る。「はい」と言って、ドアを開ける。そこには目に涙を溜め、唇を硬く結んだヒロミチさんがいた。
「は、入りますか?」わたしは尋ねた。ヒロミチさんは、「よろしくお願いします」と仰々しくバリトンの声で言った。今日はバリトンのモードなんだろうか。下手なお芝居みたいで気持ちが悪い。
ヒロミチさんを部屋に案内して、わたしは「お茶、出しますね」と言って、お茶と菓子を少し出した。「サンキューベリーマッチ」とバリトンでヒロミチさんが言った。
わたしは思わず声を洩らした。「…すみません、正直なことを言うと、なにを話せばいいのか、分からないんです」
ヒロミチさんは狭い部屋を見渡して、「パソコンも、テレビも、無いのかい?」と、バリトンで言った。
「無いです。わたしもばあちゃんも、パソコンとかテレビに興味ないんです」と言うと、「なぜそういう生活で満足しているのですか?世界のコアに関心は無いのですか?」と彼は聞いてきた。
「無いです」わたしは言ってしまった。形だけでも、関心ありますよ、とか言えばよかったか。しかし無いものは無いんだから偽るのは逆効果だろうし。
ヒロミチさんは口を重たく開いた。
「満足するな」
「え?」
「それで満足するな。世界のコアを見て下さい。分かりますよね。見えますよね。嘘つきなんていないんです。みんな正直に生きている。誰もが正直に生きてきた結果が、この世界に凝縮されている。それを受け止めていくことでしか、平和への活路は見出せない。分かりますよね。見えますよね。見えますよね」
「分かりません。見えません。なにも、わたしには見えないです」
「見ろ!」ヒロミチさんはパッとズボンをずり下げて、ブリーフをさらけ出した。
「たとえば、このブリーフ。この物体はグレーの色をしている、ただの男性用の下着だと思ってしまうかもしれない。しかしこのフォルムにも、カラーにも、なにかしらの意味はあるのです。分かりますか。見えてますか。応えてくれますか。応答お願い致します」
わたしは、もうダメだ、と思った。
「帰って下さい!もう、あなたとは話さない!」大きな声が出てしまった。ヒロミチさんは、「なんでですか?教えて下さい、ねえ、なんでですか」と、三歳児の声色とイントネーションに変わって言った。
「もういい加減にして下さい!」わたしはもう止まらなかった。なんでですか、なんでですかと、ヒロミチさんがうるさく叫ぶ。
「早く!早く出て行って!もう知らない!あんたなんてもう知らない!」
「ぼくは、なにか変ですか」突然、冷静な男性の声とイントネーションで、ヒロミチさんは言った。彼のごく普通の受け答えを、わたしは初めて聞いた。
「…変ですよ」わたしは少し冷静になって言った。しかし口は止まらない。
「世界の思想や病巣を追求してるとかなんとか言ってましたけど、あなた、結局ただの無職でしょ。それはちゃんとした仕事じゃない気がするんですが」
「…自分の知りたい…ことを…解き明かそうとしているだけです」ヒロミチさんが静かに言った。
「声色とか、イントネーションとか、わざと変えているでしょ」
「わざとじゃなくて…本当に変わってしまう」
「そんなわけない。そんなことがあるわけない。あんた、どっかでふざけてるでしょう。真面目に話して下さい。そしたら、わたしもきちんと答えます」
ヒロミチさんは少し黙った。そして絞り出すように、バリトンと三歳児の声と普通の声をグラデーションさせるように移行させて、
「助けて ほしい だけだった」
と言った。
ヒロミチさんはズボンを履き直して、静々とドアのほうへ向かっていく。わたしは声を上げた。「待って。ちゃんと話しましょう。本当にふざけていないなら、わたしは話を聞くから」
ヒロミチさんはゆっくりとこちらに向き直って、「話して、くれますか」と言った。
「ええ。話します」と、わたしは答えた。
ヒロミチさんとわたしはベランダに座った。わたしが外の風を浴びて気を静めたかったので、ヒロミチさんをベランダに誘導したのだ。
「このベランダ、どうですか」わたしは尋ねた。
「いい場所だと、思う」ヒロミチさんは声色は安定しなかったが、だんだん普通に話せるようになってきていた。
「トマトですか」ばあちゃんの育てているあの苗を見て、ヒロミチさんが尋ねてきた。
「そうです。ばあちゃんが育ててるものです」
「…理解しました」
「…風、気持ちいいですか」
「…気持ちいい、です」
「あの、さっきは怒って、すみませんでした」
少しわたしたちは沈黙した。
「…僕が変に見えるのは、なぜなのか」ヒロミチさんは、沈黙から切り出し、わたしにそう聞いた。
「え?」
「それを、教えて欲しい」
「あの、他人に自分のことばかり早口で話したり、いきなりズボン降ろして、このブリーフに意味がある、なんて言うのは、それは、変ですよ」
「…僕が、そういう風にしかできないのは、なぜ?」
「…それはわたしも分からないです。でも、それが…」
「…それが?」
「それが、あなたの持っている個性なんです、多分。あなたの追求していることも、あなたが見ている景色も、無駄じゃないし、嘘じゃない。自分を信じていけばいいと、思いますよ」
全部、本当はいつかのばあちゃんの言葉の受け売りである。ばあちゃんはいつも中立的なことだけを言う。時々それが苛立つけど、こういう時にはばあちゃんが用いるような話法しか役に立たない。自分の負の感情をそのままぶつけてしまうのは不正解なのだろう。
ヒロミチさんは沈黙した。
「わたし、さっき酷く怒ってしまったけど、きっとわたしが理解できていないだけなのかもしれないんです。あなたの見ている世界の景色を」
「そう…かい…」
「きっと、そうなんです。おそらくは」
「…もう30になってしまった。もう30になってしまったんだ」ヒロミチさんは、鼻をすすって泣き始めた。
「年齢がですか」
「…そうです…もう、嫌だ」
「なにか、辛いことがあるんですか」
「辛いなんて…言いたくない…他人に比べてみれば...まったく苦しんでいない…おれは…おれは」
「そんなことはない。誰だって辛い思いをする。そこに上も下も無いです。ヒロミチさんはヒロミチさんのままでいいんです。そこになにも足さなくていいし、引かなくていいんです」
これもまた、ばあちゃんの受け売りでしかない。結局わたしは自分の言葉で話せていないじゃないか。わたしは他人の言葉を借りているだけの、空虚な存在。わたしはなんだか、笑ってしまった。
「あはは」
「…どうしました」
「わたし、こんな立派なこと言うけど、空っぽなんですよね。空虚ですよ」
「…そんなことは…」
「わたし、自分の言葉が無いんですよ。今まで話したこと、全部ばあちゃんが聞かせてくれた言葉なんですよね。あははは」
「…自分を嘲笑う…必要はないよ。君は…大丈夫なんだ…きっと…言葉なんて借り物でいい…ユカリさんは、ユカリさんだ」
「大丈夫…なんですかね」
「…そう言ってみるのも、悪くは…ない」ヒロミチさんの表情は、少しずつ穏やかになっていき、声もより普通に変わっていった。
街がだんだん日暮れていくのが、ベランダから見える。今日はやけに綺麗な夕暮れだ。
「いいムードじゃないですか?」わたしはまた、思い付きで言ってみた。
「え?」
「この夕暮れ。よくないですか?」
「…うん…きみのその、香水の香りも…」
「魚介類とか、オリーブじみてません?」
「…いい香りだ」
わたしは鏡のほうに向かって、オイルを取り出して、ヒロミチさんに見せてみた。
「これがわたしの香水なんです。香水っていうか、健康のための…」
「成分は…なに?」
「海老の擦り身とか、ニンニクとか、らしいです。同僚がくれて」
「…いい香りだと思う…好きな香りだ…ああ...昔父親が...こういう香りの料理を…振る舞ってくれた…それを…思い出す」
「アヒージョとか、ですか?」
「…そうだったのかもしれない…その料理は、よく分からないけど」
「…今度、一緒に作りますか?」わたしは、なぜか言ってしまっていた。
「…僕らの家で、みんなで、作ろうか」
「…いいですね」
わたしたちはそれからずっと黙りこくって、風を浴びていた。涼しく、優しい風を。もはやわたしたちはなにも言葉を交わす必要は無かった。心が通じ合っていた。
ふと携帯を見ると、ばあちゃんはもうすぐ帰ってくるよ、もう実家に縛り付けられるのは限界だ、ユカリちゃんのもとに帰してくれと喚いてる、と、父がラインを寄越していた。
「もうそろそろ、ばあちゃんが帰ってくるらしくて」わたしはヒロミチさんに言った。
「…わかった」
「今日は、ありがとうございました。楽しかったですよ」わたしは言った。
「ありがとうございました」ヒロミチさんは、はっきりとそう言って、振り向かずに部屋を出て行った。
ああ、ひとりになったな、と思った瞬間、
「やったぞお!やったぞお!おれ、やったぞお!」
と、部屋の外からヒロミチさんの大きな声がした。わたしと通じ合えたことがそんなに嬉しかったのか。わたしは笑って、お茶と菓子を片付けると、部屋の明かりを灯した。そしてばあちゃんが「ただいま」と帰ってきた時、わたしは久しぶりの満面の笑顔で、「おかえり」と言えた。
わたしはわたしの想像を越えた。そんな気がした。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
