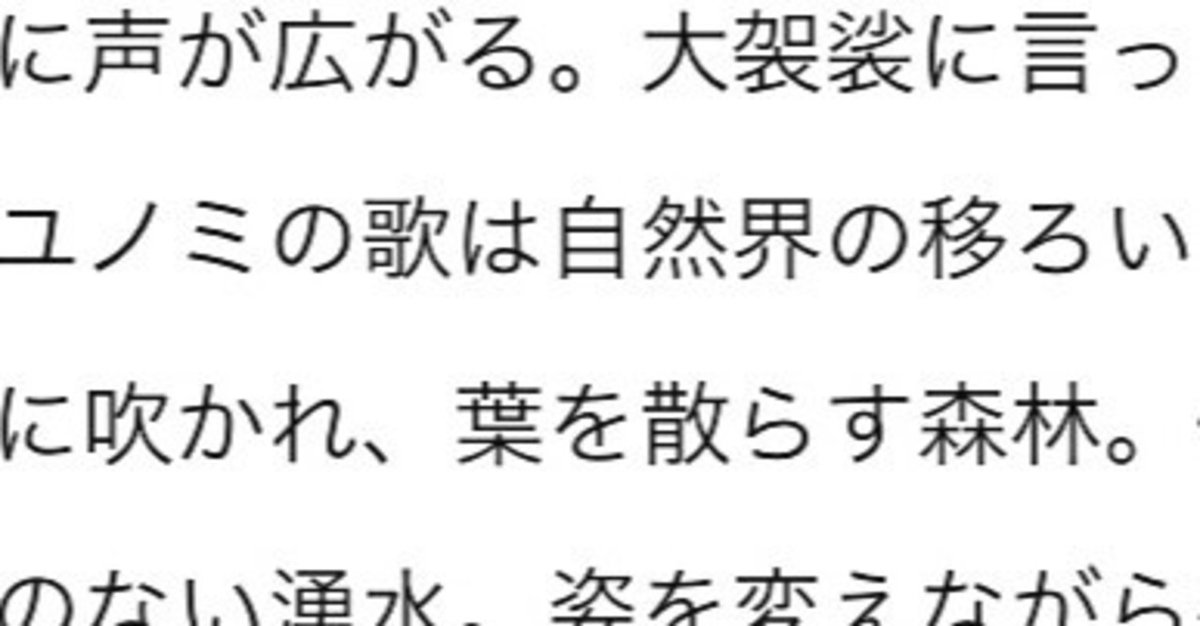
ぼくの醒めているところに
目を覚ますと、彼女の歌がスピーカーから流れている。ぼくはまた一晩中、彼女の歌に抱かれて眠っていたことになる。毎朝の光景。毎朝の感触。
彼女は「ユノミ」と名乗る若い女の子で、ピアノを奏でながら歌う。歌う内容は、恐らく彼女が実際に体験した恋愛の様子に集約されていて、言葉の端々からその恋愛はドラマティックなものではなく、傍目から見ても異常に淡々としたものであったことが想像された。
彼女は夜になると、一晩中ネット越しに歌を届ける。いわゆる生配信である。彼女は動画サイトに自分のチャンネルを持っているが、その動画サイトはまるで聞いたこともない、かなり知名度の低いサイトだ。その「パースペクト」というサイトで彼女は毎晩、生配信をしている。
昨夜もユノミは静かに歌っていた。硬質なピアノの音が心地好く、彼女の声が持つヒーリング作用の芳醇さに感じ入りながら、うつらうつらとして、眠る。4時頃にふと目覚めた時彼女が歌っていた、「親友にマニキュアを塗られて、わたしは彼のもとへ向かう」というリフレインだけで起承転結のすべてが構成された歌を聴いた時、ぼくはなぜか少し泣いてしまって、自分で驚いていた。そしてまた自然に眠り、朝に目が覚めると、いつの間にか配信は終了していた。
ユノミの存在を教えてくれたのは親戚のおばさんだった。おばさんはぼくが幼い頃から昔の洋楽をおれによく聴かせた。たとえばそれはアレサ・フランクリンであり、オーティス・レディングであり、ニック・ドレイクであった。
「世界はひとつじゃない。いくつもの面がある。わたしはその中の或る面に、レコードを聴くことで肉薄してんの。あんた、わかるよね」おばさんがぼくに昔そう言ったのを覚えている。でもぼくにはその意味が分からなかったし、そもそも音楽が別に好きじゃないし、古いレコードばかり漁って聴いているのは単なる野暮ったい懐古趣味にしか思えず、ぼくはおばさんに対して共感できなかった。
一ヶ月前、おばさんの家で行われた親戚の集まりで、久しぶりにおばさんに会った。しばらく見ないうちにおばさんはだいぶ老け込んで、おばあさんに片足突っ込みはじめているような顔立ちになっていた。
「まあ、来んね」と自室にぼくを誘い、その日もおばさんはぼくに昔の洋楽を聴かせた。はっきり言ってつまらない時間だ。ゲームでもしてたほうが楽しめる気すらしてしまう。外面の態度には出さないが。彼女は妙にぼくを気に入っている。ぼくがまだ17で、子供を作りたがらない親戚たちの中で唯一の若い人間だからだろうか。おばさんは言う。
「あんたも、いまは学生で、なにをしても苦しいでしょうよ。気を付けなさいね。学校には悪魔がたくさんいるの。学校を出ても、社会という下品な世界が待ってる。惑わされないよう、レコードを聴きなね。歌はあんたに多面性を教える。多面性はあんたを救う」
この退屈さを打開したくて、ふっと尋ねた。「おばさんは、いまの音楽は聴かないの?」
するとおばさんが言う。「ああ、いまの歌手なら、この子、なかなか芯があるわよ」
おばさんがレコードを取り出す。明朝体の黒字で、「ユノミ」とだけ小さく書かれた白いジャケット。そのジャケットが目の前に現れ、盤が取り出され、ゆっくりとおばさんが針を落とす、その瞬間からなにかが違っていた。まだ音も鳴っていないのに、ぼくには恐るべきものがやって来る予感がじわじわとあった。音楽を聴く時には、音が鳴っている間や、鳴った後だけでなく、音が鳴る前にも気配が漂うことがあることを知った。
そして緩やかに再生されたその歌は、いままでぼくが聴いてきたどの歌よりも、音の、低音から高音までの帯域が広大で、静寂に満ち、秘密がかっていた。淡々と歌われる恋の歌には、残酷な不幸せも、陽だまりのような幸せも紡がれない。切り取られる情景の数々は、歌にするほどのことでもないようなドラマティックでない事柄がほとんどで、でもだからこそ心に入って来てやまない。ピアノがゆっくりと動いていく。照り付ける真夏日の落陽のように。その、比喩でなく心が溶け行くような、厳然たる一曲を聴き終わったぼくは、おばさんに言った。
「この歌、いいよ」
「あんたがそう言うなんて、珍しいね。いままでなにをかけても無表情だったじゃない。雪でも降るんでない?」
「音がなんか、違くない?」
「いまの技術でしか録れない音かもね。耳を優しく覆うような音よね」
「このレコード、欲しいんだけど」
「聴きたいなら、うちに来なさい。今はプレミアよ。ネットオークションじゃ、最低でも20万の値が付いてる」
「へえ。なんでこのレコード、見つけたの」
「レコード屋に行くと、ジャケットから呼ばれる、って現象があんのよ。これもその、呼ばれたレコードのひとつね。まだ定価で売ってた。買ったのは去年の春だったわ。ラッキーよ」
「ネットで聴けたりしない?」
「"パースペクト"を知ってる?そこで毎晩、彼女、歌ってるわよ。聴いてみなさい」
そうしてぼくはユノミの歌にアクセスし始めた。一般的な動画配信と違い、パースペクトには閲覧者のチャットルームもないし、視聴者数なども特に出ない。ユノミの配信以外に投稿されている動画数も少なく、あらゆる情報が可視化され、都度都度拡散されていく今日のインターネットに、こんな孤島のようなサイトがあることが不思議でならない。
おばさんの言うように、学校は確かに悪魔だらけだ。教師も生徒もいわゆるマッチョ気質で、弱いより強いほうがいいよね、という価値観のもとでなんとなく暮らしているだけのやつらだ。いじめなんて日常過ぎて普通に感じてしまう。誰かが誰かを殴り、傷付け、後始末は誰もしない。教師たちも、大概の生徒も、みな雑務をこなしながら怠惰に、取り立てて思考もなく生きているのがぼくの目には瞭然だ。しかしぼくはぼくで勉強でもスポーツでもまったく思うように結果が出せない深刻な劣等生なので、なにかを成す気力もなく、正直なところ他人への愛情や興味もなく、目立たないように、なにがあっても主張せず、発言も動きもしないことで自分を守っている。
ユノミの配信はピアノを弾く手元しか映らないので、どんな顔で歌っているのか分からない。やけにシックな色の服を着ていることだけしか。喋らず、沈黙もせず、ただただ恋の平坦さ、自分と他人の所作の機微を歌い続けるユノミ。メロディーはいつもメジャー調だが、スローなテンポがやるせないから、悲しげに聴こえてしまう。ユノミはパースペクト以外のSNSをしないし、公式なウェブサイトすら持たないから、コンタクトを取る術もない。ただただ、歌を聴くだけの関係。それがむしろ良かった。触れられるより、触れられないほうがより切なくて、苦くて、良いのだ。日中に味わうあらゆる徒労感を、ユノミの歌を聴くことで癒した。
ユノミは毎晩、欠かさず配信をする。24時から、朝日が昇るまで毎晩だ。調子が悪そうな日は一日もなく、果たしてこの人はどのようにして生きているのか気になってしまう。普通に仕事とかしているんだろうか。もししているなら、どんな仕事か。しかし彼女の暮らしを知る術はない。ピアノと歌だけがそこにあり、それはどこまでも濃く煮詰まった謎だった。すべてが秘密がかっているからこそ余計聴きたくなるし、パースペクトのひっそりとした構造が、この歌はぼくしか聴いていないのではないか、という妄想をもたらしてもいた。実際、他のポピュラーなSNSでもユノミの歌が話題になることはなかった。そうしてユノミは一介の歌うたいとしての純潔を保っているように思えた。奇跡的だと思った。
ユノミの歌を聴き始めてから2ヶ月後のことだった。いつも通り憂鬱に学校に登校すると、なにか様子がおかしい。校舎が半壊しており、地面には大量の血痕が散らばっていて、警察が大勢動き回っている。なにか野蛮なことが起きている。教室に着くと、同じくして担任がやってきた。
「なにがあったんですか」誰か生徒が聞いている。
「爆発だ。うちの卒業生がやりやがった。詳しくはあとだ。席に座っておけ」担任は出て行った。
それから校内放送があった。校長の声。
「今朝我々の学校で、信じられないことが起こりました。
我が校に恨みがある、と主張する卒業生たちが徒党を組み、朝早くに校内に不法侵入し、登校する生徒に向けて手榴弾を投じ、校舎を爆破し、駆け付けた教師たちも彼らによって刃物で刺され、被害に遭った人々は先程、病院に搬送されました。皆命に別状はありませんが、しばらくの間入院し、医師の扶助が必要な状況です。
加害者の卒業生の集団は現在、警察に取り押さえられ、取り調べを受けております。彼らは、この学校が憎かった、この学校を壊したかった、わたしたちがここに通っていた頃にあなたがた教師らが行った、無知の露呈、過った教育を思い出してみろ、と繰り返し述べています。彼らは、明らかに正気ではないと思われます。
今日は休校です。現場は混乱しており、通常の生活は困難です。速やかに帰宅をお願い致します」
そうして、ぼくたちは帰宅させられた。
茫然と帰路を歩いていると、同じ学校の制服を着た人がいる。関わりたくないのでなるべく避けて通る。
「避けんな」
声をかけられてしまう。その顔を見る。女の子だ。見覚えがあるような、無いようなで、「誰ですか?」と聞いてしまった。
「とぼけんな。同じクラスのナミキだよ」
「ナミキ?ごめん、自分、クラスの人間の名前とか顔とか、覚えないから」
「あー、まああんたいつも存在消してるからね。でも大体の人は気付いてるよ」
「そうか」
「そろそろこの学校もおしまいかな。転校してく人も多いし」
「いじめばっかだもんな。殺伐としてる」
「そうそう。爆弾投げたやつらの言ってること、正直よく分かるんだよね。大きな声じゃ言えないけど、わたしも同じような気分かも」
なにも会話が浮かばない。ナミキが続ける。
「わたしもなんか壊したいからね。ま、わたしたちが曖昧にしてきたことのツケが、いよいよ回ってくるんじゃないの。今日はその始まり。わたしも早く逃げたいんだけどね」
「うん」
「あんたも早く逃げたらいいよ。じゃ、わたしこっちだから」
「おう」
ナミキは帰っていった。ぼくも家に帰った。
その夜のユノミの配信は、珍しく最初に本人の口から告知があった。
「明日から、レコード出すので、よかったら。東京のレコード屋さんで販売します。ホワイトムーン、っていうレコード屋さんです。詳しくはホワイトムーンにお尋ね下さい。では」
それだけ。初めて聞いた彼女の話し声は、実に低く、しかしシルキーだった。
あとはひたすら歌、歌、歌。今日は一段と歌うペースも速い。河川が絶え間なく満ちるようにピアノが奏でられ、呼応するように声が広がる。大袈裟に言ってしまうと、ユノミの歌は自然界の移ろいのようだ。風に吹かれ、葉を散らす森林。停止することのない湧水。姿を変えながら夜を照らす月。漂う雲の一片一片の色合い。
目を閉じて、うつらうつらとしてくるのを待つ。学校。生活。どうでもいい。人生が、この歌を聴くだけで済めばいいのに。たとえば大学行くとか就職するとかして、ぼくがなんとなく社会的に成熟して、どこか様変わったとしても、この歌だけはこのままで止まないで欲しい。
ぼくは天井に向かって、「ユノミさん、素敵です」と口に出した。レコード、買おう。
いつの間にか、街に冬が来ていた。
「ホワイトムーン」から通販で取り寄せたユノミのレコードには全部で8曲が収まり、ジャケットは彼女がいつも配信で着ているシックな服を捉えた写真で、盤は季節を越えてプレイヤーに乗り続けた。レコードを聴くために、ぼくは少ない小遣いを貯めてプレイヤーを買ったのだ。
学校では閉塞感に耐えかねて転校する生徒が続出し、残った生徒のほとんどはより醜い暴力の露出に没頭した。今日もひ弱なやつから何人もジョックスたちに服を脱がされて、校庭で叩きのめされている。そこら中に「学校おわれ」「ばか」「全員底辺」といった落書きがでかでかと書かれ、消されもしない。窓ガラスは割られて当然のものとして扱われているから、季節的に寒風が始終吹き抜けて寒い。校外で在校生によって覚醒剤がトレードされ、毎週乱交パーティーが行われている、という、下世話に過ぎる噂まで広まっている。
教師たちは誰もが塞ぎ込んでいて、怯えており、必要以上のメッセージは言わなくなっている。彼らは淡々と生活をこなしている。ぼくもまた傍観を決め込んでいる。なにも言いたくない。なにも成したくない。少なくともここでは。
ぼくはナミキとたまに話すようになった。たとえばこんな話を。
「あんた、進学すんの?就職すんの?」
「わからん」
「わたしは就職かな。もう勉強とかうんざり。わたし、意外と社会適応能力あるほうだから」
「ぼくは...そうだなあ。しばらくはバイトして食い繋ぐかな」
「それでもいいんじゃない、生き甲斐があれば。やりたいことがあるのが一番だってみんな言うじゃん。それは確かだと思うよ」
「ああ」
「なんか、やりたいことある?」
ぼくは切り出してみた。
「ユノミ、って人知ってる?」
「知らないな」
「歌を歌う人でさ。毎晩配信してる。レコードも出て、買った」
「最近レコードってまた流行ってるよね。その人、どこで配信してんの?」
「パースペクトっていう動画サイト」
「全然知らないな。調べてみよう」
「ユノミさんの歌が聴ければ、あとはどんなに辛くてもいいかもしれない」
「へえ。なら、自分でも歌、作ったらどう?」
一瞬たじろいだ。ぼくが歌を作る。考えたこともなかったことだ。現実的に思えない。
「いや、うちに楽器なんてないし」
「買いなよ。最近は安いのもいっぱいあるでしょ」
「うーん。やってみるかな」
「やれ!歌を作れるようになったらいいよ。芸は身を助く、じゃん」
ぼくは今夜もユノミの歌を聴いている。ナミキの言葉がずっと引っかかる。歌を作る。そんなことがぼくにできるんだろうか。でもなんか、そういうことでもしないと、自分が抜け殻になってしまいそうな気もしてきてはいる。
やってみるか。でもどうすれば。わけもわからずネットで「音楽 作り方」と検索してみた。なんか自分がひどくバカみたいに思えてしまった。ユノミは歌を作りたいと思った時に、こんな検索なんかしなかったはずだ。彼女は勝手に浮かんで来るメロディと言葉を、ピアノの前に座って、自動筆記のように捉え続けて来た人のはずだ。滑稽な気分を抱えながらそれでも調べると、無料で音楽を作れるアプリを発見したので、ダウンロードした。アプリを開くと、中にはピアノをあしらった画面があり、押すと音が出た。ドレミファソラシド。スマホのマイクから歌も録れるみたいだ。
息を深く吸い込む。努めてナチュラルに吐き出す。画面のピアノを見よう見まねで鳴らす。ひとつのコードだけを鳴らして、鼻歌を歌う。曖昧な鼻歌が、だんだん言葉に変わってきたのが分かる。
ぼくの醒めているところに
あなたが手を触れてきて
言葉はそこまでしか出て来なかった。その言葉がどういう状況、感情を示しているのかも、ぼくには判然としなかった。とりあえずそこまでを録っておいた。そしてユノミの配信に戻って、目を閉じれば、いつものように眠くなってきた。そういえばぼくはどれだけ悲しくても、現実が混乱していても、夜になれば眠れなかったことがないことにふと気付いた。なぜだろうか。わからない。なんか最近、わからないことばかりが増え過ぎている。わからない、という言葉以上に正直なことが、ぼくには言えない。ユノミがあの歌を歌っている。
親友にマニキュアを塗られて、わたしは彼のもとへ向かう。
親友にマニキュアを塗られて、わたしは彼のもとへ向かう。
親友にマニキュアを塗られて、わたしは彼のもとへ向かう。
ぼくはもう泣かなかった。窓越しに少しの雨音が聞こえ始めた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
