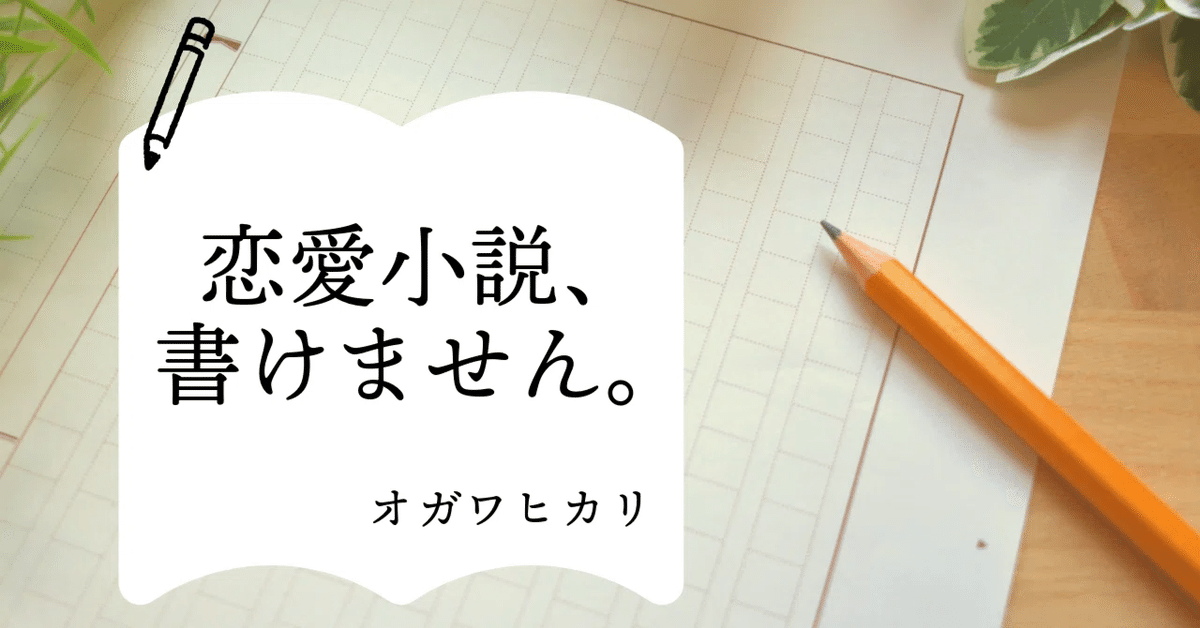
恋愛小説、書けません。/Lesson6:「悩める男の夜」
やってしまった、と肩を落としながら耀介は文華社を出た。自ら恋愛未経験をカミングアウトしてしまったことに対しての恥ずかしさも然ることながら、その後の木下の爆笑ぶりにもだ。
「初恋、まだ……って?」
妙な空気が流れた後、木下がうわ言のように呟く。そしてその後に
「冗談きついよ、菅原くん!!」と腹を抱えて笑い出したのだ。木下の声は良く通る為、女性社員が「編集長?」と応接室にまで現れる事態となってしまった。その辺りは上手い具合に木下が女性社員を追い払う。耀介は耳が熱くなっていくのを感じた。
ひとしきり笑うと、木下が耀介をじっと見据えて
「……その様子だと、冗談ではないんだろうね。笑って悪かったよ」
と詫びた。耀介は慌てて「やめてください! 多分僕がおかしいんです」とフォローに回る。
「でもね、ミステリー作家が人を殺さずに殺人事件を書くように、恋愛をしていなくても恋愛小説は書けるんだ。まずは色んな恋愛に纏わる物に触れることだね」
「はあ」
「私の初恋は小学生の頃かな、みっちゃんっていう女の子だったんだが……」
その後は、まずお手本としての『木下の初恋話』――勿論いつもの通り長い話になるのだが――を聞くことになった。参考になりそうなものがあればとメモを片手に話を聞くが完全に思い出話なので、正直参考になるかどうかは微妙だった。
「殺人と恋愛じゃ桁違いですよ……木下さん……」
文華社を後ろに、耀介は足を引き摺るような重たさを感じつつ自宅へと歩いた。
◆
『どう? 恋愛小説の調子は!』
お疲れ様という動くスタンプのあとに一言書かれたメッセージをスマートフォンが受信したのは深夜だった。
「絢乃か」
年齢の割に滅多矢鱈可愛らしいチョイスで「らしくないなあ」と呟く。耀介でも見たことがあるキャラクター。液晶画面内で忙しそうに動く様は正直今の耀介自身と重なる。
『どうもこうも、全然だ。でもお前のファイルには感謝してるよ、ありがとう』
それだけ文字を打ち送信する。我ながら味気ないメッセージだと耀介は思う。
今、作業用のデスクの上には絢乃がファイリングした記事のいくつかが取り出されて無造作に置かれている。そして耀介はそれをぼんやりと眺めている。女性心理は正直分からない。実に様々な意見があり、それこそ恋愛未経験の身としては『ついていけない』のだ。理解、とまではいかなくともある程度掴んでおかないと、書き手として大問題だ。
耀介のパソコンのディスプレイに浮かび上がるメモ帳は、真っ白なままだ。溜息を吐きながら勝手にスマートフォンに手が伸びていた。
『もしもし、どうしたの?』
いつもの声。聴き慣れた、少し甲高い声。
「起きてたか? 絢乃」
『起きてたからメッセージしたんじゃない』
「悪いな、遅くに……久々にやらかしてしまったんだ」
溜息交じりの電話の向こうの声に、絢乃は早々に勘付いた。
『自分が初恋もまだっていうのをカミングアウトしちゃったとか?』
「な、何で分かる!?」
耀介は酷く動揺して、デスクに置いていた飲みかけのエスプレッソが入ったカップを肘で倒してしまった。「うわー!?」と叫び耀介はスマートフォンを放り投げ、慌てて記事などを救出する。スマートフォンはラグでワンバウンド、そしてフローリングに着地した。しかし耀介はデスクの救出作業で全く気が付いていなかった。
『ちょっと耀介! 今の何の音よ!? 耳割れるかと思ったじゃない!』
放り投げた瞬間、偶然なのか、ハンズフリーになったスマートフォンから相当怒っていると分かる声色の絢乃が叫ぶ。
「わ、悪い! マグカップを倒してしまって……お前が集めてくれた記事を慌てて掻き集めていたんだ! その時にスマホを放り投げてしまった!」
ティッシュペーパーを握り締めた耀介がその場で叫ぶ。
『ドジねえ、もう』
「も、申し訳ない……」
明らかに呆れている絢乃の声が、小さな箱から聞こえる。
幸い飲みかけのエスプレッソは残り僅かで、デスクは最小限の被害で済み、肌触りが気に入ったベージュのラグに零れた形跡はなかった。ほっと胸を撫で下ろし、耀介はまたスマートフォンを握る。右耳からは『頼れる声』が聞こえて来た。
『耀介さ、本読むの好きなんだから、恋愛小説を買って読んでみたら?』
とてつもなく大きな声が耀介の左耳から脳へ到達する。漫画で表すとしたら、受話器から吹き出しが耀介の顔の数倍の大きさで描かれるような状態だろうか。ハンズフリーを解除していなかった為、耀介は一瞬スマートフォンから耳を離す。
耳鳴りが残る中、絢乃の声はある種爆弾のようではあったが、耀介にちゃんと届いていた。とりあえずはハンズフリーモードをオフにして、もう一度耳にあてがう。今度は右耳だ。
「俺が……恋愛小説を買う?」
『うん、今ベストセラーになってる小説も恋愛モノ。家の近くに大型書店あったでしょう? 多分相当な数揃ってるわよ。平積みだから目立つし、別に男性が恋愛小説買っても違和感ないって!』
絢乃は耀介の性分を知っている。
そう、図書館で借りる事は滅多にしないのだ、この男は。
図書館自体は大好きな男だが、借りる行為は余程の事がない限り、ない。それは中学生時代からしばしば見られる光景だった。大抵の書物は自分で購入し、資料として後生大事に自分の書棚に仕舞い込み、時にまた読み返したりする事を全て知っている。学生時代のアルバイト代の殆どが書籍代で消えると絢乃に話した時、聞いて呆れられたことがあったぐらいだ。あの当時もし耀介に彼女がいれば、超音速で破局していただろう。
『書物は財産だからな』
そう言い切っていた耀介を絢乃はちゃんと覚えている。そしてそのスタイルを変えない男は電話越しでこう話して来た。
「現代文学における恋愛の定義は良く分からないのだが、近代文学の作品とは大差ないのか? なるべく近代文学のものと近い小説であれば……」
『あのねえ……アンタだって現代文学の作家でしょう!? 食わず嫌い禁止! そんな事ばっかり考えるから彼女も、恋愛も出来ないんじゃない! それにね、時間は止まってくれないのよ。間違ってても歩く事を止めちゃいけないの。伊田滝大先生なら、そこ自覚してるんじゃないの? 曲がりながりにもプロなんだから、書けて当然よ』
色んな意味で絢乃は爆弾だ。最後の言葉は正直、耀介には堪えた。
「色々とお前の発言は、俺の内部にダメージを与えているぞ……」
正直な気持ちを述べると、絢乃が大笑いしながら言う。
『それでも乗り越えてるんだから、いいんじゃない? 百聞は一見に如かず、よ』
「何となく使い方を間違えている気がするのだが……しかし、絢乃の言い分はもっともだな。明日辺りに本屋に行って来る」
そうだ、俺は書かなければいけないんだ。俺を応援してくれる人の為にも、期待してくれる人の為にも。ようやく気合いが入るような気がしていた。絢乃の叱咤激励は、いつも耀介の背中を確実に押してくれるものなのだ。
『じゃあ今日のお礼は、イタリアンにデザート付きね』
ちゃっかりしてるな、お前は。
耀介はそう言いながら苦笑いを浮かべて、役割を終えたティッシュペーパーをゴミ箱へ捨てた。
Lesson7はこちらから↓
Lesson1はこちらから↓
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
