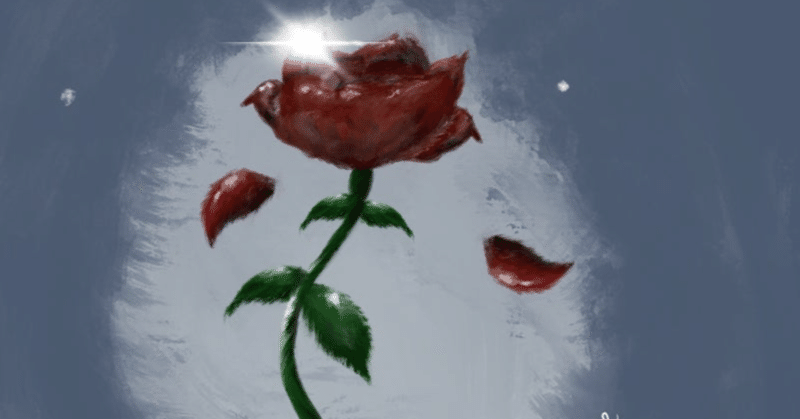
愛とはなによりも美しいエゴなのかもしれない
「ねぇ、あなたを愛してる」
百合子ははじめて僕を愛してくれた女性だった。
僕は百合子と出会い、はじめて女性から必要とされるのではなく、大切にされ愛されているという実感を得ることができた。
たとえば先に眠ろうとする僕に百合子は「あなたの寝顔を見てから眠りたい」と柔らかい笑顔を見せた。甘い言葉が漏れるその唇を塞ぐと眠気は覚めて、性欲さえ見失った僕は百合子を無垢に抱き締めた。
百合子は着飾った大人の僕も無防備な幼い僕も総てを受け入れてくれる一方で、極めて厳しい目で僕を見ていた。百合子の丸く温かい心には愛が宿りながらも、常に切れ味鋭い視線がはり巡らされていた。
愛に触れたことのなかった僕は、百合子の温かさにどうしようもなく惹かれながらも、その鋭さを恐れてもいた。愛に備えられた刃がいつか僕の奥底にある汚さを鋭く突くのではないかと。
その鋭い眼差しは「愛しているか」ということのみを見ていた。百合子は僕に深い愛を注ぎながらも、僕の些細な言動から感じる不安を見逃さなかった。
「あなたはわたしと会えるのが楽しみと言うけれど、わたしはあなたに会えなくて苦しいの」
僕が大好きな百合子と会えなくても苦しくなかったのは、離れていても満たされてしまうほどに百合子の愛が深く確かだったからだ。そんな感覚を味わったのは後にも先にもはじめてだった。
一方で百合子が僕と会えない期間を辛く感じたのは、僕が相応の愛を差し出すことができなかったからだろう。そもそも僕は百合子と出会うまで人から愛されたという実感を得たこともなければ、人を愛したこともなかったのだ。
僕という人間は長きに渡り自己愛で自分を守ってきたし、自由できらびやかな世界から得られる艷やかな刺激を得ることで、そのナルシシズムを保っていたのだ。そんな卑しい僕を百合子はただ愛してくれた。
百合子と出会うまでの僕は、恋愛における何度かの喪失感を通過する中で、もうこれ以上傷つきたくないと愛し愛されることから目を背けて、自由で刺激満ち溢れる世界に逃げていた。
僕が逃げ込んだその世界は日常に彩りと刺激を与えてくれたし、そこに生きる何人かの魅惑的で奥行き深い人たちは、僕に新たな価値を示してくれた。いわばその世界は僕という人間を外側から成熟させてくれたのだ。
そんな僕にとっての刺激に満ちた世界も百合子を前にしたら色褪せた。百合子の愛は僕が今まで価値を感じて止まなかった世界を遥かに凌駕したのだ。
僕の存在も百合子の生きた時間の中で特別な位置を占めていたはずだ。
百合子は長年恋愛をすることを忘れて、子どもを育てることに喜んで総てを捧げていた。百合子の幸せは子どもが幸せでいることそのものだったし、そこに恋愛が入り込む隙はなかった。
長年恋愛から遠ざかり、女性として男性を意識することを忘れかけていた百合子は、まだ冬の気配が残る春先の夜に僕と出会った。間もなく百合子の鋭い五感は僕の奥底の核心を見抜き、そこに抗いようもなく惹かれはじめた。
「あなたはとても成熟しているように見えるけれど、心の奥底にはあどけない少年がいるのね」
百合子は僕に深く惹かれながらも、恋愛に喜びを感じることを躊躇していたし、しばらくの間自身にそれを許さなかった。
「あなたを愛してしまったら、わたしはいずれあなたを壊してしまうほど傷つけてしまうかもしれない」
本当の愛に触れさせてくれるならばどこまでも傷つければいい、と僕は恐れながらも強がった。
いくつかの喪失を味わい愛を諦めかけていた僕の心は、百合子と出会い再び愛を強く欲しはじめた。
「愛してると言わせたらあなたの勝ち」
「愛は自由を凌駕するのか」
「あなた次第ね」
僕の目を覗き込んだ百合子は、こぼれそうなぐらい柔らかく微笑んだ。
やがて百合子は僕に恋することを自らに許して、僕を愛しはじめた。
「ねぇ、あたなを愛してる」
百合子から愛されることで、僕は束の間自由と愛を手に入れかけた。
それでも僕は長年身につけた自己愛を断ち切れずに、百合子に相応の愛を差し出すことができず、百合子の鋭い眼差しは両者の愛の乖離を悟った。加えて好きという気持ちだけでは追いつけないぐらいに百合子の愛は深かったし、互いの乖離を見過ごせるほどに僕らは若くはなかった。
「もうわたしには関わらないで。あなたはわたしから離れた方が幸せになれるから」
愛に僅かな陰りを見た百合子は僕以上に辛くとも、離れたくないとすがる僕を自ら断ち切った。
僕と百合子が愛し合い共に歩むいくつかの可能性を残したまま、僕ははじめて愛してくれた百合子を失い、百合子は最後に愛した僕を失った。
今の僕の目には自由できらびやかな世界は色褪せて、百合子と歩んだ記憶は残酷にも眩しく映っている。傷つくことを恐れ自分を守り続けた自己愛という盾が、百合子の愛を経て刃となり僕を内側から切り刻んだのは自業自得だ。
もはや僕には、百合子の愛を失うことで深い喪失感を得ることができたというナルシシズムに寄りかかる他、自分を保つ術がない。
そんな僕にとっての愛とは、なによりも美しいエゴなのかもしれない。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
