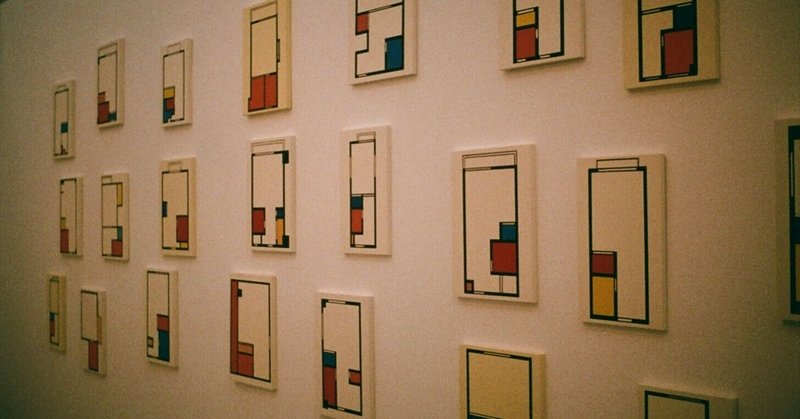
芸術作品を批評する芸術作品
それ自体が芸術作品でありつつ、芸術作品についての批評であることは可能なのか。可能である、というのが本稿の主張だ。
前に書いた通り、私がもっともらしいと思う批評の定義とは、鑑賞のガイドである。特定の芸術作品についての理解、知覚、情動を導き、強化する機能を担うアイテムはなんであれ芸術批評と呼ばれるのに十分であり、そのような機能を担うことは芸術批評と呼ばれるのに必要である。(必要条件のほうは今回のテーマとは関係ないが。)
鑑賞ガイドとしての批評、という考えを採用した場合、私たちがふだん「批評」と呼んでいないようなアイテムの多くが、実は批評なのだということになる。ロザリンド・クラウスやポーリン・ケイルが書いたような文章でなくても、作品の鑑賞をガイドするアイテムはあちこちにあるからだ。私はこれを部分的には理論の不備として捉えているが、部分的には理論の魅力として捉えている。以下では、どう魅力的なのかを紹介する。
とりわけ興味深いのは、あるアイテムがそれ自体として芸術作品でありつつ、別の芸術作品についての批評であるという可能性が認められる点だ。つまり、芸術作品であることと批評であることは排他的ではない。この事実は、それほど驚くべきことでもない。個別の芸術作品に関して「批評的[critical]」という形容詞が使われることは珍しくない。もっとも、この場合のcriticalは、具体的な社会的・政治的問題に切り込むという意味合いで用いられることが多いだろう。私の考えでは、しかし、芸術作品はロザリンド・クラウスやポーリン・ケイルが書いたような文章と同じ身分を持つ、という意味合いにおいてもcriticalでありうる。芸術作品は、別の芸術作品の鑑賞をガイドしうるのだ。
私が気に入っている例は、ふたりのピアニストによるエリック・サティの《グノシエンヌ》だ。
《グノシエンヌ》というのは、多くのサティ作品の例に漏れず、ずいぶんと変な作品である。小節線で区切られていない五線譜の上にミニマルな伴奏とメロディが配置されており、ところどころに意味不明な指示がメモされている(「舌に乗せて」「頭を開いて」など)。その謎めいた雰囲気は、ジョルジョーネの絵画《嵐》が持つそれときわめて似ている。
私がより模範的だとみなしているのは、例えば、パスカル・ロジェ[Pascal Rogé]の演奏する《グノシエンヌ》(1984)だ。ロジェの《グノシエンヌ》は音の粒がはっきりとしており、ときおり発作的に前のめりになりつつ、小気味よく進行する。「軽快な」「明瞭な」「いたずら好きな」といった美的用語にふさわしい演奏である。(アルバムのアートワークに使わているジョアン・ミロの絵画も、これらの美的性質にフィットしている。)
一方、ラインベルト・デ・レーウ[Reinbert de Leeuw]による《グノシエンヌ》(1995)は、呪術的なまでにスローかつ不明瞭であり、ほとんどアンビエント・ミュージックだ。ロジェとは対照的に、もたもたと遅れながら開示される音たちは、発作的な記憶喪失に襲われながらふらふらと前進している印象を与える。とりわけ強烈なのは左手の伴奏であり、かろうじて伴奏と呼べるギリギリのラインまでタメて奏でられている。こちらも、スキップするような右手のメロディが注意を集めるロジェの演奏とは対照的である。デ・レーウの《グノシエンヌ》は「軽快」からは程遠く、「シリアス」で「メランコリック」だ。
私の考えでは、どちらの演奏もそれ自体が芸術作品でありつつ、《グノシエンヌ》というミステリアスな作品の異なった側面に注意を向けさせ、鑑賞をガイドする批評となっている。私たちは彼らの演奏を通して《グノシエンヌ》のことをより深く理解し、より強化された聴取ができるようになる。同楽曲について考察する文章やスピーチとまったく同じ身分において、ロジェとデ・レーウの演奏は批評作品なのである。
実際、このような扱いは奇をてらったものでもない。クラシックの世界ではパフォーマーによる楽譜の読解と演奏を通した実現の作業を指して「解釈[interpretation]」という語が用いられている。パフォーマーは作品とそれが体現する意味や意義の間に立ち、分析し、仮説を立て、演奏という形でそれを提示する。鑑賞者は、その産物を通して、元の作品をより深く鑑賞できるようになる。こういった作業や最終産物の担う機能は、プロフェッショナルな批評家が文章やスピーチによって提示する解釈とまったく同じであるように思われる。違いはただ、一方が演奏された音楽であり他方が文章やスピーチである、というだけだ。
それらは、とりわけ理想的な批評であるとさえ言えるかもしれない。フランク・シブリー[Frank Sibley]は、美的判断の伝達を批評家の中心的な仕事とみなしていたが、その手段として論証が役に立たないことを絶えず気にかけていた。基礎となる低次の性質(「ここに細い曲線がある」などなど)をいくら指摘したところで、「美しい」「けばけばしい」といった美的性質を正当に適用できるとは限らない。実際に美しさやけばけばしさを見てもらったり聞いてもらう以外に、そうなのだとただ説得することは不可能である。したがって、シブリーは知覚的証明というのを批評家の重要な課題とみなしていた。批評家は、あの手この手を駆使して、読者を同じ美的知覚へと至らせることでのみ、自らの美的判断をシェアできる。ここで、実際に演奏してみせるというのは、もっとも手っ取り早く効果的な知覚的証明ではないだろうか。
もうひとつ例を挙げよう。私がたいそう好きで、ひとつだけ手に入るならこれにしたいと思っている絵画はエドゥアール・マネの《バルコニー》だ。

発表当時はともかく、今となっては珍しくもない解釈として、この絵の主題は現代における親密さの欠如、コミュニケーションの不可能性である。描かれている人物たちはそれぞれ異なる方向に目線を向けており、互いにまったく連関のない格好とポーズをしている。ある意味で、それは互いに対する無関心の現れとも解釈できるのだが、私にはむしろ、身体的・精神的に触れ合うことの本質的な困難が表出されているように思われる。好むと好まざるとにかかわらず、コミュニケーションというのは成立しようのないものであり、端的に言って無理、どうやったって無理なのである。《バルコニー》には、その根源的などうしようもなさに対するやるせなさ、気まずさ、諦観が、ひんやりとした無彩色と寒色で塗りたくられている。《オーギュスト・マネ夫妻の肖像》から《フォリー・ベルジェールのバー》に至るまで、同様の主題はマネの絵画に繰り返し現れており、また、エドワード・ホッパーを筆頭とする多くの画家たちに引き継がれていった。
これは、《バルコニー》のひとつの解釈であり、私はそれについて書かれた批評たちを読むなかで同様の解釈を形成した。しかし、おそらく同じ解釈をもっとも手っ取り早く明瞭かつユーモラスな仕方で提示し、それゆえ鑑賞者をガイドしているのは、ルネ・マグリットの絵画《マネのバルコニー》だろう。

《バルコニー》に描かれた人物たちは、マグリットのパロディ作品において、物言わぬ棺桶に置き換えられている。死んで箱詰めにされているという以上に、コミュニケーションの不可能性を端的に象徴する表現があるだろうか。それは、先立つ段落で私が言葉選んでどうにか表現しようとした《バルコニー》の主題を、軽やかに要約している。私たちはマグリットのパロディ作品と《バルコニー》を並べて見ることで、《バルコニー》についてもより深く強化された仕方で鑑賞できるようになる。この意味において、《マネのバルコニー》は、とりわけ理想的とすら言える仕方で《バルコニー》を批評した芸術作品なのである。
以上の話はもっと一般化できるだろう。一般的にカバーやパロディは元の作品の批評となりうるし、批評を目指すべきものなのである。批評たりえていない、すなわち元の作品の鑑賞をガイドする機能を担えていないカバーないしパロディは、自己満足であり、その意味において失敗している。(もちろん、模写には自らのスキルの養成と誇示の役割もあり、批評的であることが唯一の評価基準ではないのだが。)
P. D. マグナス[P. D. Magnus]の著作を皮切りに、カバーやパロディ、アプロプリエーションやオマージュといった主題は改めて関心を集めつつある。芸術作品を批評する芸術作品という観点は、カバーソングの本性や鑑賞を理解する上でも有益なものかもしれない。
芸術作品を批評する芸術作品という観点は、プロフェッショナルな批評家にとっても無視できないものである。ただでさえ、作らず奏でず、言葉をこねくり回すだけの職業批評家になんの意義があるのかとdisられがちだ。鑑賞をガイドするという役割はその仕事のコアにあるものだが、それでさえ芸術家が創作や演奏を通して(しばしばより上手に)担いうるのだとすれば、職業批評家にならではの仕事などないということになる。あくまでテキストを通して批評することになにか独特な利点があるのか。批評の哲学で博論を書き終えたいま、この点が改めて気になっている。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
