
#5 分子栄養学で使われるサプリメントと、海外サプリメントなど一般的なサプリメントとの違い
海外サプリメントなど一般的なサプリメントと分子栄養学実践専用サプリメントの具体的な違い④
違いその⑥製品中の栄養成分同士が反応しないよう、反応抑制のためのコーティングはされているか
続いて、栄養素同士が反応して効力を失ってしまわないよう、反応抑制のためのコーティングがされているかどうかです。
サプリメントでは、配合する栄養素の種類が多いほど成分同士が反応し合って栄養素が変性したり、一部の成分が酸化して製品全体が劣化したりする可能性が高くなります。
特に、前回記事のような栄養素同士が協力して働くものを複合体で配合したり、総合栄養補給食品として複数の栄養素を配合したりするほど、栄養素同士が反応し合って変性したり、劣化したりしてしまう可能性が高まります。
そのため、複合体での設計や配合をサプリメントで行う場合は、配合された栄養成分同士が反応しないよう、反応抑制のためのコーティングが必要です。
分子栄養学実践専用サプリメントでは、栄養成分同士が反応したり、酸化・劣化しないよう天然の酸化防止剤でコーティングするなど、1つの製品に数十段階もの工程を設けて製造されています。このような工程が増えるにつれて製造コストが上昇してしまうことから、分子栄養学実践専用サプリメントは総じて市販されているサプリメントよりも高額です。
対して、市販されているサプリメントや海外サプリメントなどの多くは、このようなコストと手間のかかる設計や工夫、製造工程は行われていません。そのため、配合されている栄養成分が反応して変性したり、効力を失ったりしてしまっている可能性があります。
このような酸化・劣化した栄養素が含まれているサプリメントを用いた場合、栄養素が本来持っている働きが失われてしまっていることから、体内の乱れた分子を整える目的で使用することは出来ません。逆に、酸化・劣化した栄養素を大量に摂取することによって体内に活性酸素が発生し、活性酸素が細胞やDNAなどを傷つけてしまうことも考えられます。
そのため、分子栄養学の実践を行う際は、成分同士が反応しないよう設計・製造された高品質なサプリメントを選ぶことが大切です。
違い⑦細菌・薬物など汚染物質のチェックは厳重に行われているか?
続いて、細菌・薬物など汚染物質が混入しないよう、厳重なチェックが行われているかどうかです。
「そんなチェックなんてどれも当たり前に行われているでしょ」と思うかも知れませんが、実は殆どのサプリメントではこのような薬物などの混入が無いかなどの厳しいチェックは行われていません。
何故かというと、サプリメントは「食品」という位置づけである事から、医薬品ほど厳密な製造体制やチェック体制が求められていないためです。医薬品は有効成分以外の成分が含まれていると薬物として認可されないことから、非常に厳しいチェックが行われています。対して市販されているサプリメントの多くは、このような医薬品と同レベルでのチェックはほぼ行われていません。
このため、信じられないかも知れませんが、実際にサプリメントによる医薬品成分の検出が相次いで発生しているのです。このようなサプリを摂取した結果、肝機能障害が引き起こされたなど健康被害を伴う事件も発生しており、厚生労働省や日本アンチドーピング機構などが注意を呼びかけています。
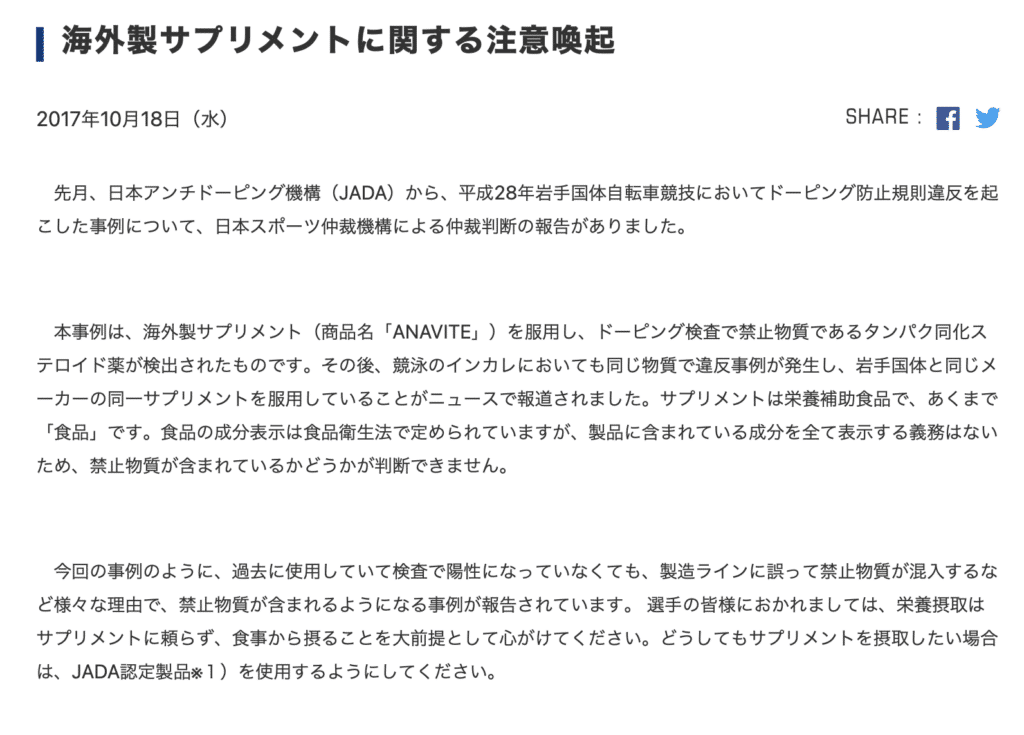

例えば、2017年には「ANAVITE」という海外製サプリメントに、ドーピングで禁止薬物であるタンパク質同化ステロイドが検出された当事件が発生しています。
この他にも、愛知県衛生研究所が平成18年4月1日から平成19年3月31日までの一年間で、国内で販売された健康食品の成分を調べた結果、66のサプリメントから医薬品成分が検出されたとの結果が出ました。
この情報からも分かるように、国内外問わずサプリメントに違法薬物が混入している事例が相次いでいます。基本的にサプリメントには成分をすべて表示する義務がないため、パッケージの栄養成分表示を見ても薬物が混入しているかどうかは分かりません。
もし、サプリメントに薬物が混入していることに気がつかずに摂取し続けてしまった場合、最も懸念されるのは健康被害です。薬物には必ず副作用があり、摂取量や他の薬との飲み合わせなどによっては、最悪の場合死に至る恐れもあります。
また、薬物の解毒は肝臓で行われていることから、肝臓にも大きな負担がかかります。特に分子栄養学では、一般的な栄養学で推奨されている量よりも遙かに多い量の栄養素を補給することが殆どです。この時に、もし薬物が混入しているサプリメントを使用した場合、その健康被害は相当なものになります。
では、なぜサプリメントなのに薬物が混ざるのでしょうか? 基本的にサプリメントの製造には食品由来の原材料が使われているため、このような薬物がついつい混入しちゃったなんてことは普通は起こりません。あなたも、家で料理をしていて「ついつい料理に薬物が混入しちゃった」なんてことは起こらないですよね。
では何故薬物が混ざるのかというと、これにはハッキリとした理由があります。それは「サプリメントに薬物を混入させた方が手っ取り早く安く効果を出せるため」です。
サプリメントに含まれるものは栄養素ですので、基本的に医薬品ほどの速効性や効果は期待出来ません。例えば、「痩せたい」「膝の痛みを改善したい」「病気を治したい」などといった場合、サプリメントだけでは改善出来ず、運動や食生活の改善など、生活習慣全般の見直しが必要になります。
これに対し、サプリメントに食欲を抑える作用のある薬を混ぜたり、痛み止めの成分を混ぜたりすれば、生活習慣の改善などせずとも手っ取り早く効果を出すことが出来ます。加えて、サプリメントは食品なので混ぜた薬を成分表示に表示する義務はありません。薬品成分が含まれていることを隠しておけば、副作用の説明も必要なく、安心安全に効果が期待出来るとアピールすることが出来るのです。
つまり、サプリメントに薬物が混入しているケースでは、「ついつい薬物が混入しちゃった」のでは無く、「わざと、あえてその薬物を混入させている」場合が殆どです。何かしらの効果を体感して貰えれば、その後のリピート購入にも繋がりやすくなります。その結果、安く手っ取り早く売り上げを上げることが出来るというわけです。
また、最近では小林製薬の紅麹使用サプリメントに想定外の成分が混入していたとして問題になりましたよね。この想定外の成分を含む小林製薬の紅麹使用サプリメントを摂取した人が、腎疾患で入院・死亡するなど大きな健康被害を引き起こして問題となりました。
このことから、市販されているサプリメントや海外サプリメントで分子栄養学を実践することは非常に危険です。この他、海外製サプリメントについては次のような問題点や危険性もあります。
海外製サプリメントの問題点と危険性
パッケージや商品説明には記載されていない薬物が含まれている可能性がある
アミノ酸キレート鉄など、自然界に存在しない分子構造の物や、本来人間が食品として口にしない成分が使われている
海外からの長期輸送、長期保管によって栄養成分が劣化、失われている可能性がある
栄養成分同士の反応が考慮されていないため、飲み合わせによっては栄養成分同士が反応して効力を失ってしまう
日本人に合わせた設計になっていないため、日本人が摂取すると過剰摂取になる恐れがある(ヨウ素など)
プロバイオティクスなども日本人の腸内環境や食事に合わせた設計になっておらず、日本人の腸には合わない可能性がある
殆どが健康維持やスポーツ用を目的とした商品であり、消化吸収能が低下した人や病人が摂取するような設計になっていない。
当方にも、このような海外サプリメントを使って分子栄養学を実践したいという方からご相談を受ける事がありますが、上記のような理由から海外サプリメントを用いた分子栄養学の実践は推奨していません。
やはり、サプリメントといえど安全が第一です。安全第一でサプリメントを作るためには、医薬品と同じレベルでのチェックが必要となります。この厳しいチェックを行うためには、厳しい管理体制と、コストのかかるチェック体制が欠かせません。
分子栄養学実践専用サプリメントでは、医薬品と同じレベルでの検査体制により、安心・安全な製品が作られています。対して市販されているサプリメントや海外製サプリメントの多くはこのようなチェック体制がないため、薬品成分や危険な成分などが混入しているリスクが高いです。
この事からも、分子栄養学を実践するときはかならず安心・安全な分子栄養学実践専用サプリメントを選ぶことが大切です。
※この記事は、下記記事から一部を抜粋・改編したものです。記事全文は下記記事をご覧下さい。元記事はこちら↓
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
