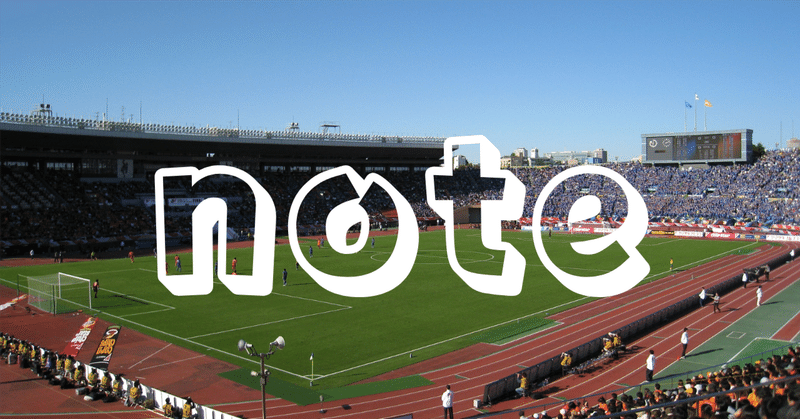
スタッツマッチレビュー:23-24 ラ・リーガ第1節 R.Madrid v A.Bilbao
はじめに
前提
スタッツマッチレビューを始めた経緯や、数字の定義などについては以下のnoteを参照してください。
とりあえず第一弾は個人的に好きなチームであるレアルマドリードの試合をやってみようということで、8/13に行われた23−24シーズン第1節のアスレティック・ビルバオ戦をやってみました。
この記事の読み方
まずスタッツを羅列して、それぞれのサマリーを記入し、最後に試合分析としてスタッツを横断的に参照した分析結果を記載していきます。
なので「あれとあれは関係あるだろ…?」というのは最後の試合分析に記載されています。
書かれている順番どおりに読んで、自分なりの考察をした上で私の試合分析を読んでもらうよし、最初に一番下の試合分析を読んでスタッツを参照するもよし、という構成にしています。
計測方法
目視で手打ちでスプレッドシートに記入。
第一弾ということもありめちゃめちゃアナログでやっているので精度が若干低い可能性が高いですがご了承ください。
とはいえ、前半30分ほどはパスの回数を計測していたのですが誤差は10回ほどで、リプレイ中でそもそも計測不可能なパス回数などを考えると許容範囲かなとは思っています。
(入力用ツール作りたいな…)
定番スタッツ
序盤はパス数や成功率を手打ちでやってたんですが、あまりに時間がかかるのでWhoscoredを参照しました。
ゴール数:2
パス回数:603
パス成功率:88%
ドリブル回数:19
ドリブル成功率:42%

結論、これだけだと本当に何も言えないですね
攻撃スタッツ
シュート

やはり上下隅にペナルティエリア内からシュートする、というのが意味ありそうですね。ヴィニシウスのシュート本数は多いですが、相手SBの対応が上手かったのものありほとんどが無理やり系のものだったのでなかなかゴールには結びついていません。
ファイナルサード

ファイナルサードへの侵入は左が一番多く、ボールを受けた回数も左が最も多い結果になっています。
ただ、ゴールに近ければ近いほど脅威を与えられているとすると…右側、右内側でのプレーに厚みがありますね。
ボールを受けたポジション

最もDFラインの背後でボールを受けているのはヴィニシウスでした。
一方で、両SBがライン間で受けていることが多く、逆に両WGがMFラインの間で受けている回数が多いですね。
そして両SBの違いとして言えるのは、カルバハルが相手DFラインの中で受けることが多いのに比較してフランガルシアはもう少し手前側で受けていることですね。
つまりレアルマドリードの戦術としてはSBがWGのような役割を担い、WGが中に落ちてくるようなものを採用していそうですね。
また、ロドリゴが非常に特徴的で、DFラインの中でのボールを受ける回数が多く連続性も高くなっています。
守備について
タックル

ベリンガム、フランガルシアのロスト直後のタックルの数字が高いですね。
とはいえ相手を前に進めないためのタックルの数に比べると全体的に少ないのでボールを取られた直後の奪取をそもそも是としていない可能性があります。
実際、ゴールを決めさせないためのタックルも非常に少ないのでロスト直後のタックルをしなくてもなんとかなるでしょ、体力削らないほうが良くない?という判断なのかもしれません。
試合分析
分析
まず面白いのは、DFラインの裏に多く抜けているヴィニシウスが一見脅威を与えているようで効果的なシュートを打てていないことですね。
フランガルシアが相手DFと相手MFの間でボールを受けることが多かったということは、2人の距離が遠いことも意味するので連携が疎になってしまっていたのかもしれません。
結果的に、やはりファイナルサードで内側に入れていないのがゴールに繋がっていない大きな要因だと思います。
更に、ベリンガムもかなり低めの位置でボールをもらうことが多かったのでヴィニシウスのフォローに行くのは難しかったようです。
逆に右サイドは、ロドリゴがDFラインの間で多く受けており、かつ連続性もある。
更にカルバハルもDFラインの間でボールを受ける回数が多いのでこの2人の関係性で相手の左サイドの選手を攻撃できていたことがわかります。
整理すると
右サイド:ロドリゴとカルバハルのプレーエリアが近く、かつロドリゴの連続性の多さによって密な連携で相手を攻撃できていた。
左サイド:ヴィニシウスが相手DFの裏に抜け出すプレーを行い左のファイナルサードまでは侵入できるが、フランガルシアが間に合わず連携が取れずに取られてしまっていた。
ということが言えると思います。
DFに関してはカルバハルのDF能力高すぎですね…という感じでした。
あまり何か言えるようなデータを取れていないですね。
自分だったら今後どう進めていくか?
やっぱり最も最初にケアしたいのはヴィニシウスですね。
卓越したフィジカルがある選手なのは間違いないで爆発力としてもっと活かして行きたい。
DFの裏のスペースに出されたボールを追いかけ、深いところで追いつきサポートが追いつかないうちに相手DFにはめられるというパターンが多いので、受ける場所自体は相手のDFラインの中で受けさせ、スピードを活かしてちぎってもらうのが良さそうですね。
結構ベイルが得意としていたイメージがあります。今だと三笘も結構近いことやりますよね。
フランガルシアも足は速い選手なので、もしチャレンジが失敗しそうなら追いついてきたガルシアと連携を取って崩し、チャレンジできるなら相手DFをちぎってもらう。
そのためにはスペースにボールを出すというよりも、相手DFに近いところだとしても、相手DFが反応できないタイミングでボールを渡し、ヴィニシウスの意思決定の幅を広げるのが良さそうかなと。
実際相手DFを外してボールを貰う動きが意外と少なかった(少なくとも自分でみつけにくかった)ので、相手を攻める”外す”TRを行うことでヴィニシウスの選択肢を増やすことで攻撃力は何倍にもなるような気がします!
やってみての感想
ただしいかはさておき、めっちゃ面白かったですね!!
と同時によく表示されるスタッツって使いにくくないですか?という疑問が生まれました。
普段試合を観る人たちはチームを強化するという文脈はないし、数字は混乱を招きがちなのでよくある感じの数字に落ち着いているのかなと言う感じなんでしょうか。
ここまでに書いたことは当然現場では数段質の高いことをやっているとは思うのですが、真似事なりにやってみるのは中々楽しいものでした。
サッカー指導者向けのオンラインスクールを開発していて、学ぶ内容だけを提供するのではなく、運営の負担軽減や客観理解のための雑事など、もっと全員が本質的な部分に集中できるような世界にしていきたいとも思うのでそのための訓練は今後もしていこうと思います。
今週末の試合もやろうとは思いますが、まだどの試合をやろうかとかは考えていません!
いろんなチームでやると戦術の違いやリーグの違い、対戦カードのレベル差といった変数のパターンが増えるので色んなところでやりたいとは思っています。
ではまた!!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
