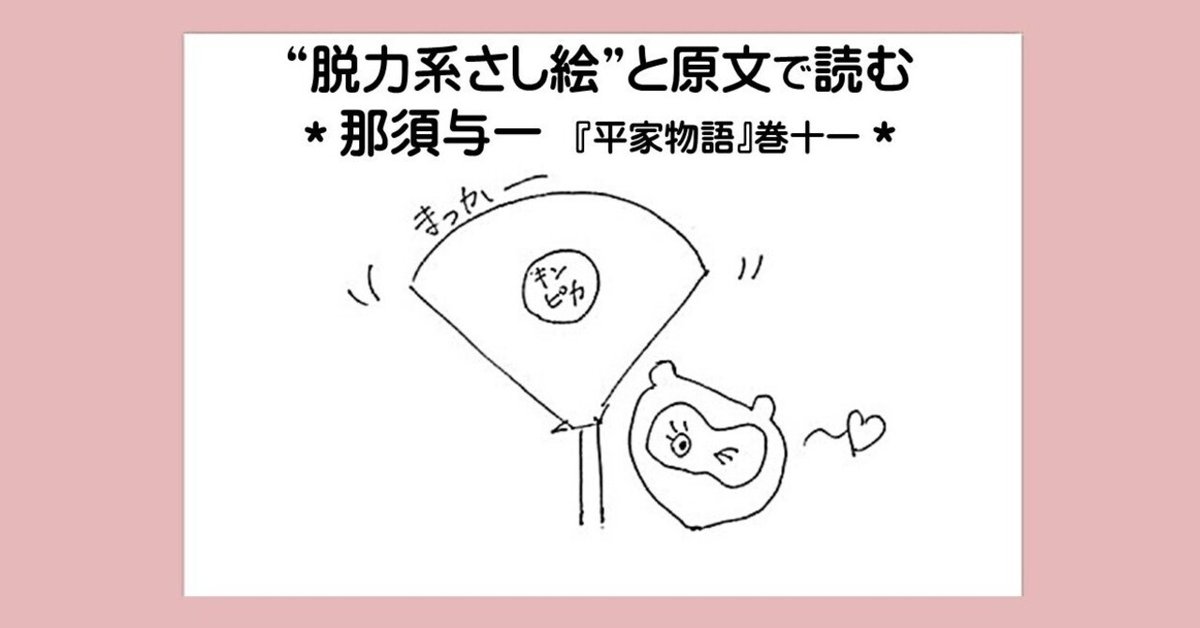
“脱力系さし絵”と原文で読む~那須与一『平家物語』巻十一
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
「脱力系さし絵」ってなんだ?と自分ツッコミ。それ以外に言葉がみつからないわ。過去のフアイルを探していると、『源氏物語』のさし絵なども出てきて、柏木が茄子(野菜)。すっかり忘れてたけど。そういえば、わりと好評だったので、アップしてみようかしら。まずは那須与一から。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
●『平家物語』那須与一を描いてみました。平家方はタヌキ、源氏方はキツネ。なんとなく、そんな感じイメージ。
◆夕刻、一日のいくさが終わろうとする時、平家方から一艘の舟が現れた。
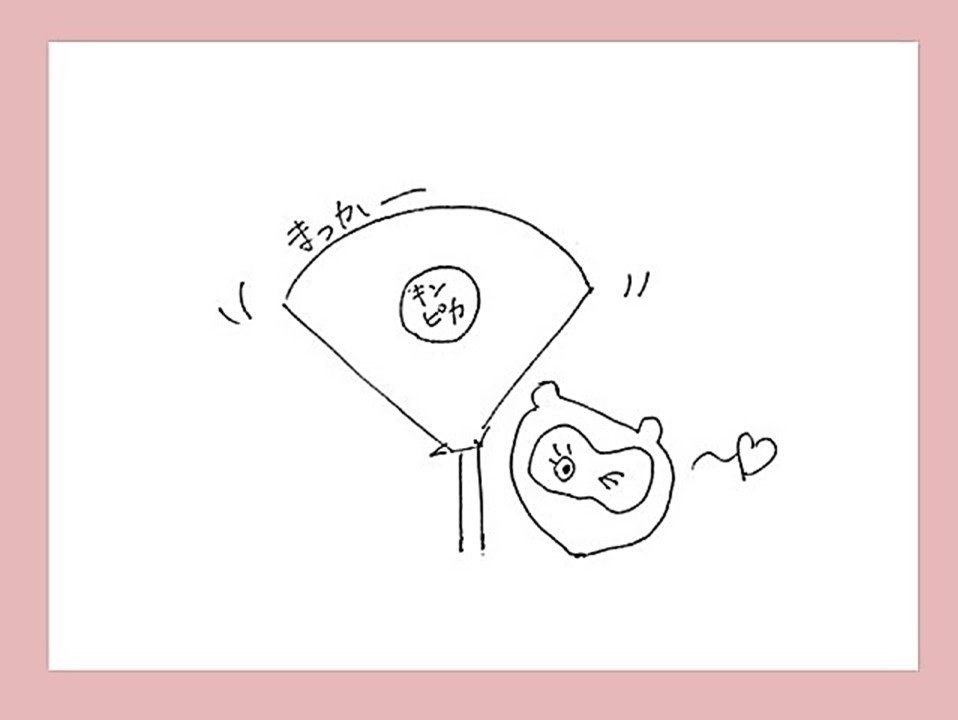
「今日は日が暮れた。勝負を決することはできない」といって兵を引き上げるところに、沖の方から立派に飾った小舟が一そう、水際にむかってこぎ寄った。磯まで八、九十メートルほどになったところで、舟を横向きにした。「あれはどうしたことだ」と見ているうちに、舟の中から十八、九歳ぐらいの女房で、とても優雅でかわいらしい人が、柳の五衣に紅の袴を着て、全体は紅で真ん中に太陽を描いている扇を、舟棚にはさんで立てて、陸にむかって手招きしている。
「今日は日暮れぬ。勝負を決すべからず」とて引き退くところに、沖の方より尋常にかざったる少舟一艘、水際へ向いて漕ぎ寄せけり。磯へ七、八段ばかりになりしかば、舟を横様になす。「あれはいかに」と見る程に、舟のうちより齢十八、九ばかりなる女房の、まことに優(いう)にうつくしきが、柳の五衣に紅の袴着て、みな紅の扇の日いだしたるを、舟のせがいにはさみたてて、陸へむいてぞまねいたる。
◆あれはどういうことだと尋ねる源義経に、知恵者の後藤兵衛実基が答える。

判官(義経)が後藤兵衛実基を呼んで、「あれはどうしたことだ」とおっしゃったので、〔実基〕「射よといっているようです。ただし大将軍(義経)がもし矢の正面に立って美女をご覧になるなら、弓の名手に狙わせて射落とそうというはかりごとだと思います。そうであっても、扇を射させるのがよいでしょう」と申しあげた。
判官、後藤兵衛実基を召して、「あれはいかに」とのたまへば、「射よとにこそ候ふめれ。ただし大将軍、矢おもてにすすんで傾城を御覧ぜば、手たれにねらうて射おとせとのはかり事とおぼえ候ふ。さも候へ、扇をば射させらるべうや候ふらん」と申す。
◆しかし平家の挑戦は受けなくてはならない。後藤兵衛実基が推薦したのは若武者の那須与一宗高だった。

〔義経〕「射ることができるのは味方では誰だ」とおっしゃったところ、〔実基〕「名手はたくさんおりますが、中でも下野国の住人、那須太郎資高の子で、与一宗高こそ身体は小さいですが腕前はたいしたものです」
〔義経〕「証拠はなんだ」
とおっしゃるので、
〔実基〕「飛ぶ鳥を射ることを競って、三つに二つは必ず射おとす者です」〔義経〕「それなら呼べ」
と言ってお呼びになった。
「射つべき仁はみかたに誰かある」とのたまへば、「上手どもいくらも候ふなかに、下野国の住人、那須太郎資高が子に与一宗高こそ小兵で候へども手ききで候へ」。「証拠はいかに」とのたまへば「かけ鳥なんどをあらがうて、三つに二つは必ず射おとす者で候ふ」。「さらば召せ」とて召されけり。
エビデンス(証拠)↓↓

与一はその時は二十歳ぐらいの若い男である。赤地の錦で前襟や袖ぐりを彩った濃い紺色の直垂に萌黄威の鎧を着て、銀の足金がついた太刀を腰にさし、その日のいくさで射て少し残った|切斑《きりふ》の矢を、頭の上に出すように背負い、薄い色の切斑に鷹の羽を混ぜた、鹿の角で作った鏑矢(ぬた目の鏑)もいっしょにさしていた。滋籐の弓を脇にはさみ甲を脱いで高紐にかけ、判官の御前にかしこまった。
〔義経〕「どうだ宗高、あの扇のまんなかを射て、平家に見物せさせてやれ」
与一がかしこまって申したことには
「うまく射ることができるか定かではありません。もし射ることを失敗すれば、長い間お味方の恥となりましょう。必ず射ることができる人に仰せつけるべきかと存じます」
と申した。
与一そのころは二十ばかりの男子なり。かちに赤地の錦をもっておほくび、はた袖いろへたる直垂に、萌黄威の鎧着て、足白の太刀をはき、切斑の矢の、その日のいくさに射て少々残ったりけるを、頭高に負ひなし、うす切斑に鷹の羽はぎまぜたるぬた目の鏑をぞさしそへたる。滋籐の弓、脇にはさみ、甲をば脱ぎ、高紐にかけ、判官の前にかしこまる。「いかに宗高、あの扇のまんなか射て、平家に見物せさせよかし」 与一かしこまって申しけるは、「射おほせ候はむこと、不定に候ふ。射損じ候ひなば、永き味方の御瑕にて候ふべし。一定仕らんずる仁に仰せ付けらるべうや候ふらん」と申す。
◆那須与一が、失敗すれば源氏の恥、私などではなく、絶対成功させる人にまかせてくださいと言ったら、義経が怒った。

義経はひどく怒って
「鎌倉を出発して西国へ行くような者どもは、わたしの命令をそむいてはならぬ。とっとと帰るがよい」
とおっしゃった。与一はこれ以上辞退するのはよくないと思ったのだろうか、
「はずれるかどうかはわかりません、お言葉ですからやってみましょう」
と言って、義経の前から下がって、黒い馬で太くたくましいのに、小房のついた鞦をかけ、まろぼやの紋様を擦りこんだ鞍をおいて乗った。弓を持ち直し、手綱を繰りながら、水際に向かって馬を進めたので、味方の軍兵たちはその後ろ姿をずっと見送って、
「この若者はきっと成功するだろうと思います」
と申し上げたので、義経も頼もしげに見ておられた。
判官大きに怒って、「鎌倉をたって西国へおもむかん殿ばらは、義経が命をそむくべからず。すこしも子細を存ぜん人は、とうとうこれよりかへらるべし」とぞのたまひける。与一かさねて辞せば悪しかりなんとや思ひけん、「はづれんは知り候はず、御定で候へば、仕ってこそみ候はめ」とて、御前をまかり立ち、黒き馬の太うたくましいに、小ぶさの鞦かけ、まろぼやすったる鞍おいてぞ乗ったりける。弓とりなほし、手綱かいくり、水際へ向いて歩ませければ、味方の兵ども うしろをはるかに見おくって、「この若者一定仕り候ひぬと おぼえ候ふ」と申しければ、判官もたのもしげにぞ見給ひける。
◆那須与一は決死の覚悟で挑戦することにした。

矢を射るには少し距離が離れていたので、海へ十メートルほど乗り入れたが、それでも扇までの距離は七、八十メートルぐらいあるように見えていた。頃は二月十八日の午後六時ごろだが、ちょうどその時は北風が激しく吹いて磯に打ち寄せる波も高かった。舟は波に揺られて上がり、揺られて下がり、一つ所に定まらないので、扇もはさんである串に定まらずひらめいている。沖では平家が舟を並べて見物している。陸では源氏が馬の口を並べてこれを見る。どちらもどちらもじつに晴れがましい。
与一は目をとじて、「南無八幡大菩薩、我が国の神明、日光の権現、宇都宮、那須の湯泉大明神、願わくはあの扇の真ん中を私に射させてください。もしこれを射損なうなら、弦を切り弓を折って自害し、人には二度と顔を見せないつもりです。もう一度故郷に私を迎えてやろうとお思いになるなら、この矢を外させないでください」と、心の中で祈って、目を開いたところ、風も少し弱くなり、扇も射やすくなっていた。
矢ごろすこし遠かりければ、海へ一段ばかりうちいれたれども、なほ扇のあはひ七段ばかりはあるらむとこそ見えたりけれ。ころは二月十八日の酉の刻ばかりのことなるに、をりふし北風激しくて、磯打つ波も高かりけり。舟は、揺り上げ揺りすゑ漂へば、扇も串に定まらずひらめいたり。沖には平家、舟を一面に並べて見物す。陸には源氏、くつばみを並べてこれを見る。いづれもいづれも晴れならずといふことぞなき。
与一目をふさいで、「南無八幡大菩薩、我が国の神明、日光の権現、宇都宮、那須の湯泉大明神、願はくは、あの扇の真ん中射させてたばせたまへ。これを射損ずるものならば、弓切り折り自害して、人にふたたび面を向かふべからず。いま一度本国へ迎へんとおぼしめさば、この矢はづさせたまふな」と心のうちに祈念して、目を見開いたれば、風も少し吹き弱り、扇も射よげにぞなったりける。
◆みごと命中!

与一は鏑矢をとって弓につがえ、引きしぼってヒュッと放った。身体は小柄だが、十二束三伏のりっぱな矢で、弓は強弓、浦に響くほど長鳴りして、ねらい違わず扇のかなめのあたりから三センチほど上を、ヒュウッと射切った。鏑矢は海に入り、扇は空に舞い上がった。しばらく空でひらめいていたが、春風に一もみ二もみもまれて、海へさっと散った。夕日が輝いている海面で、真ん中にお日さまを描いている紅の扇が、白波の上にただよい、浮いたり沈んだり揺られたので、沖では平家が、舟の端をたたいて感じいった。陸では源氏が、腰につけている弓を入れる箱(箙)をたたいて歓声をあげた。
与一、鏑を取ってつがひ、よっぴいてひやうど放つ。小兵といふぢやう十二束三伏、 弓は強し、浦ひびくほど長鳴りして、あやまたず扇の要ぎは一寸ばかりおいて、 ひぃふつとぞ射切ったる。鏑は海へ入りければ、扇は空へぞ上がりける。しばしは虚空にひらめきけるが、春風に一もみ二もみもまれて、海へさっとぞ散ったりける。夕日のかかやいたるに、みな紅の扇の、日出だしたるが、白波の上に漂ひ、浮きぬ沈みぬ揺られければ、沖には平家、船端をたたいて感じたり、陸には源氏、箙をたたいてどよめきけり。
この記事が参加している募集
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
