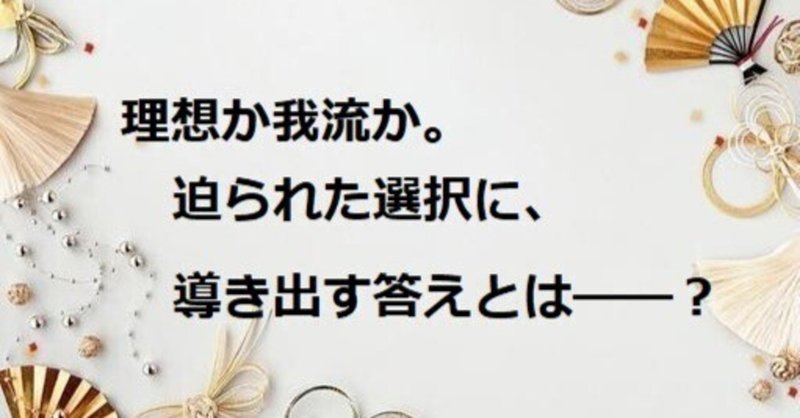
[短編小説]指先に宿るは
***
美しい、と問われて思い浮かぶ姿は、いつも師匠が舞う姿だった。
師匠の舞は、見る者の瞳を縛り、見る者の呼吸を奪い、見る者の心を掴んで離さない。
師匠が舞っている空間は、全て師匠の独壇場と化す。
それは、その場にいる誰もが、師匠の舞は唯一無二で美しいと本能で悟っているからだ。きっと師匠の舞を見た人は、この世の舞とは一線を画すものだと認めることだろう。
俺もそうだ。師匠の舞は、師匠にしか表現できない芸術だと心の中で分かっていた。
師匠のように舞うことは一生かかっても叶わない――。
幼心に分かっていながらも、気付いた時には俺は師匠の背中を追っていた。理想を消すことなんて、高校を卒業したばかりの青臭かった俺には到底出来なかった。
師匠が指南する個人流派に所属するようになり、師匠の舞を盗むようにがむしゃらに真似た。憧れだった。師匠の言うことは全て受け入れ、一つ一つ俺の挙動に落とし込んだ。荒かった俺の動きも少しずつ師匠のように繊細になっていく。たった少しの成長が、俺にとっての何よりの喜びだった。
しかし、次第に現実が俺を襲う。
どんなに頑張っても俺と師匠とでは立つステージの次元が異なることを、嫌というほど叩きつけられた。俺と師匠の年齢差は祖父と孫のように離れているのだが、たとえ師匠と同じ年齢に至っても、同等に動けるようになっているとは思えない。いや、絶対に無理だろう。
子供のように純粋だった心も、一度疑いの目を向けてしまえば、大人のような冷徹な心へと変わる。
自分の限界を悟ってしまった俺は、いつしか師匠の舞を目指すことを止め、典型的な面白味のない舞を舞うようになった。
師匠は寂しそうな顔をして俺のことを見ていたが、俺は気付かないふりをして、自分がやりやすいように舞った。
いつしか、師匠のような芸術性を俺の舞で表現できなくても、食えるくらいの舞を舞うことが出来るようになっていた。絶賛されるほどの評価を受けなくとも、後ろの方で舞い、師匠が舞う舞台を堅実的に支えた。
そして、個性を押し殺して、場に溶け込むような無難な舞をする俺に、別の流派から声が掛かるようになった。
師匠のそばにいると居心地の悪さを感じるようになっていた俺は、その流派からのオファーに素直に頷いた。
俺は新しい流派の中で、今まで学んだことを活かしながら堅実な舞を舞った。俺が参加したことによってか分からないが、その流派は少しずつ名を上げるようになり、俺の評価も上がった。
師匠の舞を追いかけることも少なくなり、俺の心も楽になっていた。
そこそこな充実感で、順風満帆な生活を送るようになって来た、とある日だった。
師匠が倒れた、と俺の耳に入って来たのは――。
***
「――どうぞ」
虚しいノックの後に響いた声は、かつての力強さは失われていて、今にも消え入りそうなほどに弱々しいものだった。
扉を引く手に一瞬躊躇いが生じたが、唇を噛み締めたと同時、扉を開く。
師匠が入院している個室は、広く、大きかった。その個室の大きさだけで、師匠が今までどれほど多くの功績を残して来たのか、痛いほどに感じられた。
「坊か、よく来たね。こちらにおいで」
師匠が俺のことを呼ぶ。子供の頃に師匠の舞に心を奪われ、高校卒業と同時期に師匠の元へ駆け込んだ俺を、いつまでも「坊」と子ども扱いするのだ。
俺は後ろ手に扉を閉めると、ベッドの脇に置かれている椅子にゆっくりと腰を掛けた。師匠は何を言うでもなく、優し気な目で俺のことを見つめている。
十年ぶりくらいに見る師匠の体は、やせ細っていた。なんて声を掛けていいか分からず、互いの呼吸する音だけが病室に満たされる。視線をどこに置くべきか迷い、ただただ自分の膝に乗せた両の拳に視線を落としていた。
そんな時だった。爽やかな風が開いた窓から入り込み、俺と師匠を優しく撫でた。流れる空気を追うように視線を上げると、俺の位置からでも窓の外に広がる桜景色が美しく見えた。師匠も同じように窓の外を見つめていた。
一時見る分なら美しいこの景色も、一日中ベッドに座る師匠は、どんな想いで窓の外を眺めているのだろうか。
きっと俺には師匠の想いを推し量ることは出来ない。
「私の流派は――、畳もうと思う」
「え?」
外の景色に意識を向けていたため、師匠の言葉の意味を呑み込むのに時間が掛かった。
言葉を返さない俺に、師匠は弱弱しく口角を上げ、
「今までたくさんの人に教えてみたけど、誰も私の舞を体現出来るものはいなかったからね。たとえ強く勇ましいライオンがいたとしても、その血を引き継ぐ者がいないなら、その強く勇猛な血統は断たれる――、それが自然の成り行きだよ」
体が弱っていることは置いておいても、師匠の声は寂し気なものだった。
師匠を慰めようと反論しようとしたが、何も言えなかった。師匠の言葉を一番痛感しているのは、俺自身だからだ。
過去に背中を追い続けた師匠の舞は、この世の言葉では表現できないほど、美しく気高い。私生活全て――、それこそ指先一つにさえも舞へと捧ぐ生活に、ついていける人間なんて誰もいないのだ。
師匠の舞は、まさしく神様の気まぐれだ。到底人間には至ることの出来ない芸術的な舞を、この地に落とし込んだのは師匠だけだった。
だからこそ、俺は師匠の元から逃げ出したのだ。
誰も舞うことの出来ない舞を舞った師匠の生き様は、この先伝説として語り継がれることだろう。
「ところで、坊よ」
新たな話題を切り出そうとする師匠の声が、やけに明るく耳に届いた。「何でしょう」と、俺は訊ねる。
「最後に、坊の舞を見せてはくれないかい?」
師匠はあっけらかんと笑いながら言った。その言葉と仕草は、俺の心臓を握りつぶすには十分だった。
「……最後にだなんて、言わないでくださいよ」
「すまない、言葉の綾でついね。でも、坊の舞が見たいのは本当だよ。今の坊がどのように舞うようになったのか、この目で確かめたいんだ」
師匠の優しい声に、一瞬躊躇したが、俺は椅子から腰を上げた。そして、まるで舞うために存在する舞台のように広いスペースへと足を運んだ。前を向くと、ベッドに腰かける師匠が、大好物を目の前にした子供のように嬉々としていた。
――そんな目で、見ないでくれ。
俺は俯きながら、扇子を握る手に更に力を籠める。
多分、今この瞬間に舞う舞が、最後に師匠に見せられる舞になるだろう。
俺はどのように舞うべきだろうか。
その場に溶け込むために個性を押し殺した現在の舞か、それとも、どこまで体現出来るかは分からないが師匠に教わった過去の舞か。
どちらの舞を舞ったら師匠が喜ぶのか、頭の中では取るべき答えを導き出していた。
しかし、俺の中の良心が、模範解答を演じることを許してくれない。
俺は師匠の期待を裏切って、他の流派に行った人間だ。しかも、裏切ることは疎か、その場所で師匠の教えをいいところ取りして、利用までした始末だ。そこには師匠の舞を体現しようなんて想いは一切なく、自分が楽して認められることだけを意識していた。
そんな俺に、どうして師匠の前で舞を舞う資格があるというのか。
究極の二者択一が、俺を襲う。扇子を持つ手が、いつの間にか自然と震えていた。この選択をどうするかによって、俺の将来は大きく変わる。いや、きっと何を選んでも、師匠を裏切った時点で後悔することは分かり切っていた。
重圧に耐え切れず、唇を噛み締めながら、俺は師匠に顔を向けた。
「……っ」
視線の先には、全てを受け止めるかのような達観した表情を浮かべる師匠がいた。
昔ながらの懐かしい想い出が、俺の脳を駆け巡る。
一つ一つ丁寧に教えてくれる師匠の姿、貧乏だった俺に自ら飯を振るう師匠の姿、舞を通じて人生をも教えてくれる師匠の姿、そして、当たり前のような教えを行なっただけでも大袈裟なくらいに喜ぶ師匠の姿――。
いつも師匠を思い浮かべると湧き出ていた苦々しい記憶ではなく、今まで忘れていたことが不思議なほど、優しく、温かい記憶だった。
扇子を握る手の震えは、自然と治まっていた。全身の力が、良い感じに抜けている。
俺は目を瞑った。呼吸を整え、爪先に至るまで意識を全神経に傾ける。まるで俺一人だけかのように研ぎ澄まされた世界が、一身に感じられる。
そして、目をゆっくりと開けると同時、
「――」
一挙手一投足、全てに全神経を捧げるように舞を舞い始めた。
止めるところは鳥が止まり木で身を休めるように穏やかに止め、動くところは水がとめどなく流れるように滑らかに動かす。
まるで自分自身を世界と化し、世界の美しさをその身に体現させる舞は、まさしく師匠が一人で築き上げた流派そのものだ。
俺はここまで育ててくれた師匠に、報いることにした。
師匠から教わった舞は、まさに自分という存在を芸術へと昇華させるような舞だ。たかが舞一つに、ここまで投資する人は、この地球でどれほどいるのだろうか。俺が知る中では、たった一人しかいない。
僅かな動きしかしていないにも関わらず、全身に嫌というほど汗が流れる。足も震え、指先も痺れ、脳も複雑な働きが出来ない。それでも、師匠から教わった舞を止めようなんて、思わない。
師匠から教わった舞は、一つのズレも許されないような細かく厳しい舞なのに、なんでこんなにも楽しいんだろう。辛いはずなのに、上がる口角が止まらなかった。
久し振りの感覚だった。
この感覚は、師匠の前から逃げ出して以来、一度も味わったことがなかった。
誰でも限界を越えることは、辛く、苦しい。実らない努力が虚しくなって、俺はいつしか無難な人生を歩むようになった。しかし、今は違う。乗り越えた先にある光を求め、俺は舞う。
舞を通じて、俺という存在を世界に認めてほしくて、ただ一心に舞う。いや、世界なんてどうでもいい。俺が認めて欲しいのは、唯一――。
「――」
舞いながら視線だけ器用に動かせば、師匠は真剣な表情で真っ直ぐに俺のことを見つめていた。昔からそうだ。弟子の舞を見る時、師匠は真剣な眼差しを惜しみなく注ぐ。そして、舞が終わった後、何が足りないのかを的確に言葉にしてくれるのだ。
「――坊」
一瞬、師匠の唇が動いた気がした。いや、きっと気のせいだろう。舞の途中で、師匠が口を開いたことはない。ましてや、全てを受け入れるかのような優しい声で、俺のことを呼びはしないだろう。
気のせいだと分かっていながら、俺の口元は自然と緩んだ。
――今この瞬間、師匠から教わった全てを表現しよう。
嘘偽りのない単純な想いが、指先の細胞にさえも力を与えくれる。
師匠と出会ってから、酸いも甘いも多々あったけれど、師匠と過ごした時間を後悔していないと――、こんなにたくさんのものを貰っていたのだと伝えるために、一心に舞い続ける。
言葉では足りないけれど、舞でなら十分過ぎるほどに、この胸から湧き出る想いを伝えられるから。
「――はぁッ」
一通り舞を終えると同時、息を押し殺して舞っていたことに気が付き、上を向く。汚れのない白い景色が、俺の視界を埋め尽くす。
空気を吸い、空気を吐く。
生きるためにする当たり前の行為が、やけにありがたく感じる。
呼吸を整えながら、心地よい疲労だけが俺を襲っていた。
師匠の教えを体現した時は、いつもそうだった。
指先一つに至るまで極限に集中しているから、舞の最中はとても神経をすり減らす。けれど、終わった後は言葉では表現できないほど爽快で、新しい自分になれたような気がするのだ。
懐かしい余韻に浸っていると、力強い拍手が舞台に鳴り響いた。
天井から師匠の方へと顔を向ける。
「久し振りに坊の舞を見たけど、やっぱり気持ちがいいなぁ」
「……師匠」
「私の元から離れても、ずっと一つ一つの行動を大事にして来たんだね」
師匠の指摘に、俺の頬に一筋の汗が伝った。
この十年間、たとえ離れていても、いつも俺の心の片隅には師匠がいた。
師匠の舞を追及しなくなり、場に溶け込むような舞を舞うようになっても、一つ一つの動作を無下にすることは出来なかった。師匠の教えを忘れ、全ての行動を雑にしようと何度も思ったが、その度に師匠がどこかで見ているような気がして、実践に移せなかった。
中途半端な想いは、全体を調和させつつ丁寧さを備えるような舞となり、いつしか俺の持ち味とまで呼ばれるようになっていたのだ。
だから、今のように周囲を意識することなく師匠の教えを舞に落とし込んだのは、本当に久し振りだった。どこまで師匠の流派を表現出来るか不安だったけれど、会心の出来で舞うことが出来たのは、小さいけれど日々の積み重ねがあったからだろう。
一目見ただけで空白の十年間を見透かす師匠に、俺は益々頭が上がらなくなる。
「さて」
枕元に置かれていた扇子を手にすると、師匠はベッドから足を下ろし始めた。
「師匠、動かないでください」
師匠の容体を心配して、俺は師匠のそばへと近付こうとした。しかし、師匠は近付く俺に向けて、その場に留まるようにと手を広げた。
「いいんだ、坊。今、とても体の調子がいいんだ。むしろ、寝てなんていられないくらいだよ」
「……師匠」
「それに、私は坊と一緒に舞を捧げたい気分なんだ。成長した可愛い坊と一緒に舞うなんて、これほど嬉しいことはないよ」
子供のように無邪気に言われてしまえば、もう止めることが出来なかった。
それに、不謹慎かもしれないけれど、俺も師匠と一緒に舞いたかった。
師匠が俺の隣に立つ。体が弱くなっているとは思えないほど洗練された立ち姿に、あの時のように心が奪われる。
そして、師匠が扇子を構え、優雅に舞い始めた。その動きに合わせて、俺も舞う。
一挙手一投足全てを、師匠に合わせようと神経を集中させる。しかし、一緒に舞うことで分かることは、やはり俺とは次元が違うということだ。一生かかっても、俺は師匠の域まで届かない。
そう目の前で痛感させられているのに、以前ほど嫌な感情は芽生えなかった。
師匠と舞うことが出来ている――、その喜びの方が勝っているからだ。
この世のものとは到底思えないほど、静かな時間の中、師匠と俺は二人だけの空間を築き上げる。
一生続けばいい、と願う中。
「うん。綺麗だね、坊の舞は」
永遠のような静寂を崩したのは、師匠だった。
憧れだった師匠にずっと言われたかった言葉を言われて、俺は流れそうになる涙を必死に留めて、舞う。
普段厳しいことを教えるくせに、いざ耐えられなくなった弟子が涙を流すと、優しい師匠はそれ以上舞を教えることをしなくなる。俺がここで涙を流したら、この夢のような時間が終わりを告げてしまう。
師匠と一緒に舞う内に、俺の中で一つの想いがふつふつと湧き出して来る。
「師匠、俺やっぱ……その……」
舞の途中で話すことは、師匠の教えではご法度だったが、既に師匠が話したのだから問題はないだろう。
湧き出た想いを素直に言葉へと転じられない俺に、師匠は優しく笑いかける。
「坊が連絡を返してくれた時から、全部分かっていたよ」
昔から師匠は、人の感情の機微を敏感に察していた。師匠の前で隠し事は、いつだって出来ない。
「……でも、俺は師匠の期待に応えられなかった」
「確かに、過程はそうかもしれないね。だけど、坊は結局戻って来てくれた。それも色々な経験をして、ね。先ほどの舞からも、今までの坊の全てが伝わって来たよ」
「……師匠」
「何も私は、私の後継機となるようなロボットを作ろうと思って、坊や弟子たちに教えて来た訳じゃないんだ。舞を通じて人間として成長を遂げ、その人にしか出来ない表現をして欲しいだけだ。その表現が舞を通してでも、それ以外のことでも、私にとっては可愛い弟子が成長してくれることが一番嬉しいんだよ」
「……」
それ以上は、もう何も言えなかった。「もちろん、私の伝えた舞で表現し、更に後世にも伝えてくれることが一番嬉しいけどね」とはにかみながら言うけれど、それにも答えられない。
「だからね、坊。何も心配することなく、坊のやりたいことをやっていいんだよ。――あとのことは私に任せなさい」
嬉しそうに言ったその言葉を、師匠がどのような表情で言ったのかは、視界が滲んでいて確認することは出来なかった。終わる気配のない舞に、ずっと神経を注ぐ。
もう言葉は要らなかった。
ただ二人で、至高の舞を舞う。
師匠の舞は、止まらない。その背中を、俺はずっと追い続ける。
今はただ、夢のような時間を、心ゆくまで憧れの師匠と共に過ごすだけだった。
<――終わり>
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
