
いかにして文章を読みやすくするか⑤ 読点・「て、」の回避・改善案
今回は送ってもらった実際の小説の文章に対し、「読みやすさ」という点での改善案を出していきたいと思います。
例文
送られたメッセージはこちらです。
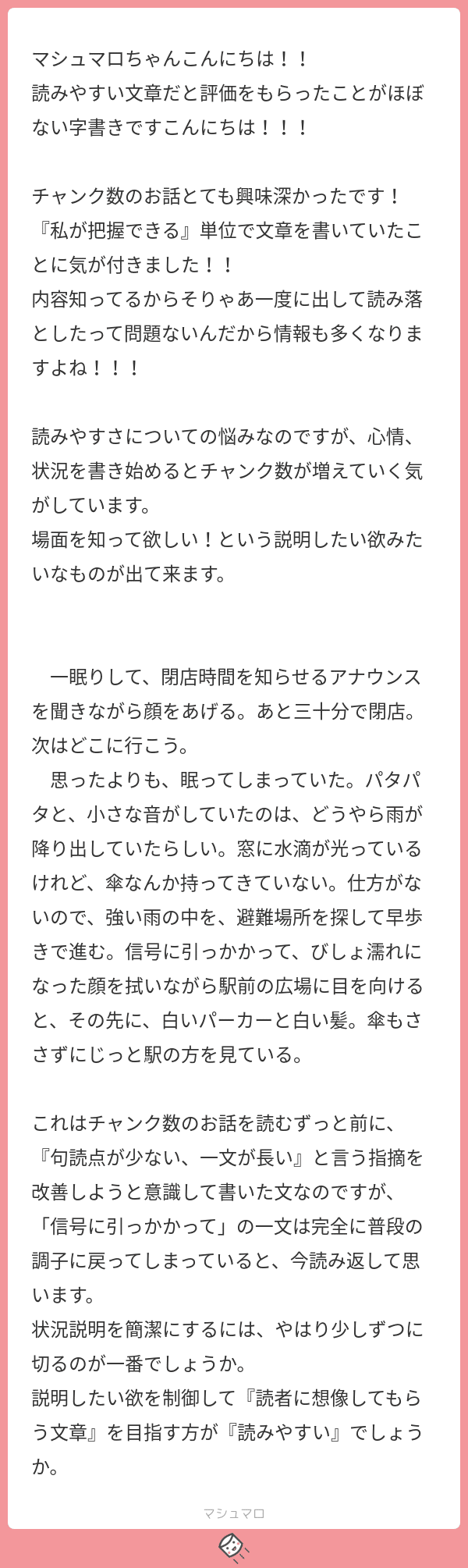
メッセージには2点の質問があるので、まずはそれについて答えていきます。
説明したい欲
説明したい欲を制御して『読者に想像してもらう文章』を目指す方が『読みやすい』でしょうか。
まずこちらから答えますが、これに関しては一概には言えません。作者のタイプ次第でしょう。
ではこのメッセージ送信者の方はどうなのかというと、説明したい欲を抑えすぎないほうがいいように思います。なぜなら状況を高い解像度でイメージする力に長けているように見えるからです。ですからまずは抑えるよりも、磨いて磨いて切れ味のいい武器にしていく目指すほうをおすすめしたいです。
一見すると物語が進まない部分なのに、読者をぐいぐいと作品世界に引き込んでしまう描写というものがあります。そんな描写を書くタイプに化けるポテンシャルをこの人に感じます。
状況説明を簡潔にするには
状況説明を簡潔にするには、やはり少しずつに切るのが一番でしょうか。
これに関しては、概ねその通りだと思います。一度に多くの情報を読者に投げると読者の負担が大きく、結果としてしっかり伝わらなくなってしまいます。しかしこの場合は、読点や「て」の問題も大きいように思います。それについて説明します。
読点の問題
「句読点が少ない、一文が長い」と言われたことで、読点を意識的に使っていると見受けられます。しかし一文が長いから読点が必要になってしまうわけで、一文が短ければ無駄に読点があるほうが読みづらいでしょう。
例文では一文が比較的短く保たれています。そのため、読点はさほど必要ないかと思います。つまり、無駄な読点で読みづらくなっていると感じます。
おそらく「句読点が少ない、一文が長い」が呪いのように効いてしまい、読点を打てるところ全てに打ってしまっているのだと思います。ですから「省いていい読点は全部省け」という新しい呪いで上書きしておきましょう。この呪いは知って損のない呪いかと思います。
試しに読点をすべてなくしてみましょう。
一眠りして閉店時間を知らせるアナウンスを聞きながら顔をあげる。あと三十分で閉店。次はどこに行こう。
思ったよりも眠ってしまっていた。パタパタと小さな音がしていたのはどうやら雨が降り出していたらしい。窓に水滴が光っているけれど傘なんか持ってきていない。仕方がないので強い雨の中を避難場所を探して早歩きで進む。信号に引っかかってびしょ濡れになった顔を拭いながら駅前の広場に目を向けるとその先に白いパーカーと白い髪。傘もささずにじっと駅の方を見ている。
後半部分は無理があるものの、前半部分はむしろ読みやすくなっているように思います。ならば前半部分の読点は基本的に不要だということです。実は小説の文章ならば、読点は意外と打たなくて大丈夫なんですよね。試しにプロの作品を何冊か手に取って読んでみてください。スタンダードな文体ならば、読点の頻度は一般的な文章よりもずっと低いかと思います。
「て」が多いと悪文
次に「『て』が多いと悪文」という呪いも紹介しましょう。これは「一眠りして」のような「動詞+て」が多用されるとリズムが悪くなり、読みづらくなる傾向があるというのを示した言葉です。昔から言われている伝統的な呪いですね。谷崎潤一郎か川端康成か三島由紀夫か遠藤周作かは忘れましたが、そのあたりの文豪も言っていたのを読んだことがある気がします。
ここで重要なのは、「て」が駄目ということじゃありません。実際マシュマロちゃんも「『て』が多いと悪文」は過激派すぎでしょ……と思います。この言葉が示す重要なポイントは、「て」が小休止の役割を持って文章のリズムに強く干渉することじゃないかと考えています。
この「て」と同様に小休止の役割を持ってしまうものとしては、読点です。そのため、「て、」となると小休止どころか大休止です。つまりリズムが止まってしまうんです。表現としてリズムを意図的に止めたのではなく止まったのなら、それはリズムが悪くなっていると判断されがちです。
ですから「動詞+て」だけならさほど問題ではないとしても、読点と組み合わせて「て、」と書くのは極力避けましょう。とはいえ口語的表現ならば、リズムが止まることも「息継ぎ感」の表現として成立します。ですから口語的な文体や台詞ではだいたいOKです。しかし例文のような標準的な簡潔文体だと、一部の例外を除いてだいたいNGだと思っていいでしょう。実際例文でも「て、」によってリズムが悪くなっています。
一眠りして、閉店時間を知らせるアナウンスを聞きながら顔をあげる。あと三十分で閉店。次はどこに行こう。
この書き出しのつっかかり感、非常にもったいないです。つっかかり感によって「あと三十分〜」以降の短文の畳み掛けを「気持ちいいテンポだ」と感じられなくなってしまっています。ここ、本当は気持ちいい文章のはずなんです。
「て、」の回避
「て、」で大休止になってしまうことを回避するために手っ取り早いのは、読点を省くことです。「〜して○○」と書いて問題ないなら、そう書いて小休止程度に留めましょう。
読点を使う場合は、代わりに連用中止法を使いましょう。「動詞(連用形)+て、」ではなく、「動詞(連用形)、」とするということです。「〜して、」ならば「〜し、」、「〜をやって、」なら「〜をやり、」と書きます。たったそれだけの違いですが、大休止になることを回避できるのでリズムがぐっと良くなります。
連用中止法の注意点としては、口語的な文体だと合わない場合があります。少し堅くなってしまうんですよね。とはいえ口語的な文体なら「て、」で息継ぎ感を出していけるので、そもそも「て、」を回避する必要性は薄れます。
一方で標準的な文体ならばほぼ問題なく連用中止法を使えます。「堅くなっちゃうかな?」とか「連用中止法を連発しすぎてないかな?」なんて不安になるかもしれません。しかし小説の地の文というのは特殊で、連用中止法を連発しても意外と問題ありません。これもプロの作品をいくつか読んでみるといいでしょう。比較的やわらかい文体でも連用中止法を連発しているものです。
ただ、「名詞+し、」だとさらに堅さが出てしまうので、簡潔文体でも違和感が生じる場合があります。この場合は文章ごとに判断するしかありません。
「て、」を回避する3つの書き方
「て、」を回避する方法を2つ紹介しましたが、これらは併用が可能です。ですからどちらか一方に加えて、両方という選択肢もあります。
1. 読点カット
2. 連用中止法
3. 連用中止法&読点カット
ということです。
ですからどちらか一方に加えて、両方という選択肢もあります。
で考えてみます。
1. 読点カットのみ
ですからどちらか一方に加えて両方という選択肢もあります。
2. 連用中止法のみ
ですからどちらか一方に加え、両方という選択肢もあります。
3. 連用中止法&読点カット
ですからどちらか一方に加え両方という選択肢もあります。
もちろん、この文章は小説ではないので「て、」でリズムが悪くなろうとさほど問題ではありません。強いてリズムを良くしようと思うなら、こんな風に考えるという例です。ちなみにマシュマロちゃんならば、この場合は2. 連用中止法のみを選択しますね。実はそもそも連用中止法だった箇所に後から「て」を足して例としました。
これを例文の冒頭でやってみます。まずは原文です。
一眠りして、閉店時間を知らせるアナウンスを聞きながら顔をあげる。あと三十分で閉店。次はどこに行こう。
読点カットのみだとこうです。
一眠りして閉店時間を知らせるアナウンスを聞きながら顔をあげる。あと三十分で閉店。次はどこに行こう。
連用中止法のみだとこうです。
一眠りし、閉店時間を知らせるアナウンスを聞きながら顔をあげる。あと三十分で閉店。次はどこに行こう。
連用中止法&読点カットだとこうです。
一眠りし閉店時間を知らせるアナウンスを聞きながら顔をあげる。あと三十分で閉店。次はどこに行こう。
マシュマロちゃんなら読点カットを選択します。書き出し直後のせいか、連用中止法のみだとまだ読点でのつっかかり感があります。文章としての違和感も少しあります。連用中止法&読点カットも違和感があります。
もし間を作りたいわけじゃないのに「て、」を書いてしまったら、こんな風にして回避できないか考えてみてください。
「いて、」問題
最も書きがちな「て、」は、「いて、」だと思います。例えば以下のような文です。
大粒の夕立が降ってきたというのに彼は依然としてそこに立っていて、じっと彼女を見つめていた。
この「いて、」というのは少し厄介なんです。「いる」の活用形の問題で、「て」を取るだけじゃ変な表現になりがちなんです。試しに「て」を取ってみます。
大粒の夕立が降ってきたというのに彼は依然としてそこに立ってい、じっと彼女を見つめていた。
これじゃ「脱字かな?」と思われますね。かといってこれくらいの長さだと、読点をカットしても読みづらくなってしまいます。
大粒の夕立が降ってきたというのに彼は依然としてそこに立っていてじっと彼女を見つめていた。
むしろ「て、」よりも読みづらいかもしれません。それに「じっと彼女を見つめていた」に文章のフォーカスを当てたいなら、直前に読点を打ちたいものです。
ではどうするのかというと、「いて、」の連用中止法である「おり、」を使うのが基本です。
大粒の夕立が降ってきたというのに彼は依然としてそこに立っており、じっと彼女を見つめていた。
標準的な簡潔文体ならば「いて、」は一切使わず「おり、」に統一するのがおすすめです。ライトな作品じゃないなら、商業作品でも基本的にそうなっています。そう書かなくても、校正で指摘されると思います。ですから「いて、」NG、「おり、」OKの基本セオリーだけは覚えておくといいでしょう。
しかしあくまで「基本」であり、基本から少し外れたらセオリー通りにやるかその都度考える必要があります。やはり口語的だったりやわらかめの文体だと、判断が難しいところです。連用中止法をどんどん使っても意外と堅くならないとはいえ、「おり、」だとさすがに堅さが出やすいのです。
これこそが「いて、」問題の厄介なポイントなんです。「いて、」と「おり、」の中間の堅さの表現が日本語にはないんです。ですからこのあたりをどうバランス取っていくかは作者が頭を悩ますしかありません。
「て、」の例外
また、先程もちらっと述べましたが例外もあります。通常「て、」は「〈(主語)(述語)〉して、〈(主語)(述語)〉」という2つの並列関係の文を接続するために使われます。しかし「あの美しい丘を上って、少し行ったところの一軒家に〜」のように、何らかの言葉にかかるために使われる場合は例外です。こういう書き方だとチャンクが肥大化しがちなので、「て、」で区切っておくほうがかえって読みやすくなったりします。
こんな風に例外はいくつもあるでしょう。「〜だとして、」など、「て、」という文字列自体は頻出するものです。ですから「て、」という文字列を厳密に回避するというよりも、簡潔文体なら基本的なパターンでの「て、」をなるべく回避するという程度で考えておくのがいいでしょう。繰り返しますが簡潔文体じゃないなら、そもそも「て、」を回避する必要性も薄いものです。また、間を作りたいなら休止ポイントを作るのは適切な行為でもあります。
そしてこれらのセオリーはあくまでセオリーなんです。守ると効率が良いとうだけで、守らないからといって駄目なわけじゃありません。ですからこだわりがない部分ではセオリーを守り、効率的に結果を出しちゃいましょう。こだわりがある部分ではセオリーを回避し、自分なりの表現を確立しましょう。
改善案
前置きが長くなりましたが、ここからが本番ですし、マシュマロちゃんが本気を出すのはここからです。
ここまでに述べた点を踏まえ、例文の改善案を考えてみます。まずは改めて例文を見ましょう。
一眠りして、閉店時間を知らせるアナウンスを聞きながら顔をあげる。あと三十分で閉店。次はどこに行こう。
思ったよりも、眠ってしまっていた。パタパタと、小さな音がしていたのは、どうやら雨が降り出していたらしい。窓に水滴が光っているけれど、傘なんか持ってきていない。仕方がないので、強い雨の中を、避難場所を探して早歩きで進む。信号に引っかかって、びしょ濡れになった顔を拭いながら駅前の広場に目を向けると、その先に、白いパーカーと白い髪。傘もささずにじっと駅の方を見ている。
まずはみなさんで書き換えてみてください。一回アウトプットしておくと記事の内容もより理解できるかと思います。
書き換えました? できた人は次に進みましょう。ここからはマシュマロちゃんの改善案を、過程も含めて書いていきます。

