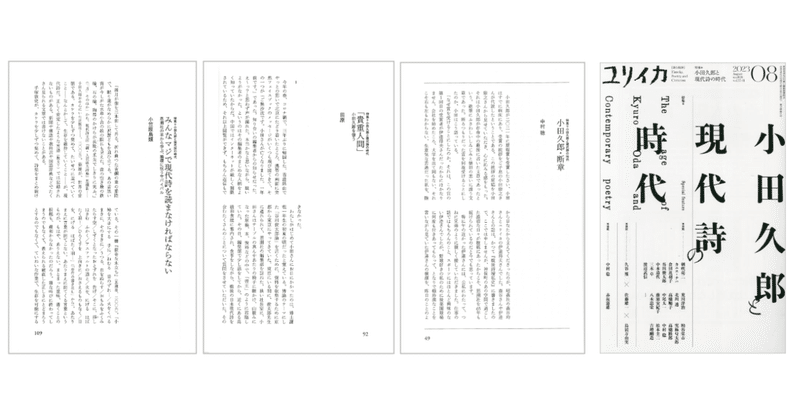
『ユリイカ 2023年8月号 特集=小田久郎と現代詩の時代』
☆mediopos-3182 2023.8.4
思潮社は小田久郎により一九五六年に設立され
一九五九年には『現代詩手帖』が創刊
一九六二年には「現代詩文庫」の刊行がはじまる
思潮社は同人誌を中心に発表された
戦後詩の展開を引き継ぐように
「現代詩」の主要なプラットフォームとして
その役割を担ってきた
『ユリイカ』八月号の特集はその小田久郎
『現代詩手帖』での特集ではなく
『ユリイカ』での特集である
小田久郎は
二〇二二年一月一八日に亡くなっているが
その訃報は一年以上経た
二〇二三年三月二八日まで伝えられることはなかった
その遺言には
「間違っても現代詩手帖で
小田久郎追悼特集など出すな」
という小田氏ならではのこだわりがあったらしく
それで現代詩手帖ではなく
小田氏とも深く関係した伊達得夫との関係もあり
『ユリイカ』での特集と相成った・・・
ということでもあるのだろう
「現代詩」というと
「現代音楽」のように
かつてはそれなりの前衛的な役割を
演じていたところがあるが
いまではどちらもかなり閉鎖的な世界で
限られたひとたちによって
作られ享受されるものとなっている感がある
特集記事のなかで中村稔が
「詩壇」が存在しているのかそうではないのか
といったことにこだわりをみせているのは
そうした閉鎖性を危惧しているからなのだろう
そしてそれはおそらく
「文壇」や「歌壇」「俳壇」といった世界とは
異なった可能性が開かれることを
詩人のひとりとして願っているからなのかもしれない
さて特集の記事のなかから
ほかにふたつほどとりあげてみた
ひとつは二〇〇六年に開かれた日中詩人会議において
中国の『新京報』の取材内容を
詩人であり谷川俊太郎の研究家でもある田原が
紹介しているもの
小田久郎の思潮社での率直な苦労話もあるが
「現代詩」についての次のような視点は興味深い
「敗戦後の日本の詩人、荒地派の詩の主題は
「わたしたち」であり、
それによって今までになかった集団意識を表現してい」たが
「谷川俊太郎の詩から始まって、
「わたしたち」が「わたし」に転化し、
さらに「わたし」と「他者」が生まれ」てきた
という小田氏のとらえ方である
もうひとつは小笠原鳥類による
「現代詩」の役割と読み方についてのもの
これは「詩壇」ということではないものの
「現代詩」がもっている閉鎖性とも関係してくるが
「現代詩」においては
「わかるかどうか」は問題にならない
「わかる」言葉は
「正しく安定したような言語(散文?)では
記録されないもの」であるからである
「「正しく安定したような言語(散文?)」は
「何もしないとのさばってしまう暴力と崩壊と消滅」へと
むかってしまうような言葉だから
それに抗う言葉が求められる
それは「知ることができない何かを予感させる」
そんな言葉でもある
詩的言語は基本的に
日常的な言語から離れた機能をもった言葉だが
そのなかでも「現代詩」は
そんな言語の未知の創造的機能を
活性化させる契機となる役割がある
小笠原鳥類が
「みんなマジで現代詩を読まなければならない」
というのは
そうでなければ言語は
人工知能的なルーティーンのなかで
崩壊し消滅してしまいかねないからだ
小田久郎によって開かれてきた「現代詩」が
これからも生き延びられるということは
たとえ今はそれが閉塞的な状況にあるとしても
言語の可能性と深く関わっている
昨今の「論理国語」や「チャットGPT」のような
言語の創造的な側面を死滅させようとする方向への
アンチテーゼとしても「現代詩」を「読まなければならない」
■『ユリイカ 2023年8月号 特集=小田久郎と現代詩の時代』
(青土社 2023/7)
(田原「「貴重人間」――小田久郎を憶う」より)
※二〇〇六年秋、日本と中国の詩人が一堂に会して交流する大規模な日中詩人会議が開かれた
「小田夫妻が帰国する前日に、当時の中国で最も読まれ、影響力のある『新京報』の取材を受けた。取材を通して、思潮社には三回存亡の危機があったことを聞いてたいへん驚いた。通訳が終わった跡、感動したというよりも、ただ小田さんに脱帽したい気持ちばかりが湧き上がってくるのだった。」
「新京報/一九五六年に思潮社を設立し、半世紀以上にわたって、現代詩と詩論だけを発表・出版されてきました。これまでどのようにして続けてきたのでしょう。
小田久郎/まず言っておきますが、わたしは政府からの助成金はほとんど受けていませんし、企業からの支援もほとんど受けていません。わたしはこの五〇年で、存亡の危機を少なくとも三度経験しました。一回目は一九五九年で、出版社を設立して三年のときですが。売れている詩集よりも売れない詩集を多く出しました。ある日、耐えきれなくなって出版社の扉を一人で閉めてしまい、胸を引き裂かれそうになりましたが、帰宅中に「日本の現代詩はどうなるのか」という思いが頭の中でぐるぐる回り、ついに再び扉を開け、勇気を出して月刊誌『現代詩手帖』を創刊し、出版社を救いました。二度目の一九六二年には、日本の詩に大きな影響を与えた「現代詩文庫」シリーズを開始し、出版社は再び財政難に陥りました。三回目は二〇世紀の八〇年代で、漫画やアニメーションやテレビなどが純文学に大きな衝撃を与えました。やむを得ず、出版社を簡素にして少数精鋭で行きました。わたしは生まれつきの楽天主義かもしれません。危機はチャンスの信号弾だと思っています。」
「新京報/日本ではあなたは「天才編集者」と呼ばれているようですが、詩は個人の思想の結晶であり、フランスのある詩人はネットだけに詩を掲載し、編集者の選択基準に抵抗したそうです。あなたはどうやって詩に対するあなたの的確な嗅覚をみんなに納得させているのでしょうか。
小田久郎/これはね、もしかしたらわたしが時代の空気に敏感になっていることと関係しているかもしれません。良い詩にははっきりした基準は存在しないと思います。しかし、少なくとも普遍的な時代感情と現在に対する鋭い配慮は必要です。たとえば谷川俊太郎さんも思潮社から出てきた重要な詩人の一人ですが、それ以前には、敗戦後の日本の詩人、荒地派の詩の主題は「わたしたち」であり、それによって今までになかった集団意識を表現していました。谷川俊太郎の詩から始まって、「わたしたち」が「わたし」に転化し、さらに「わたし」と「他者」が生まれるというように、物語の主題が変化していくことは、時代が転換することを暗示しています。」
(小笠原鳥類「みんなマジで現代詩を読まなければならない――思潮社の本から学ぶ、崩壊に抗うサバイバル」より)
「「満月が指を三本出して昇る。折れ曲がった青銅の葦の葉の葉陰で、眠り薬がなめらかに沢蟹どもを追ひたてる。あの青黒い背が今しがた水車小屋の娘の眼にも見えた。森の空き地の鉄輪、石の輪。陶器のかけらが長靴の爪先でしきりに笑ふ。」(「月」そのほか」から。現代詩文庫『続・入沢康夫詩集』思潮社————小田久郎が中心にいた出版社————、二〇〇五)。崩壊が、世界の常態である。カケラを少しずつ集めて、たいせつに並べていくこと————なんとかして、生存を維持していくこと————が、現代詩だ。正しく安定したような言語(散文?)では記録されないものがある。新聞や雑誌や教科書や国語辞典などでたくさん見られる文章では書けないことがある。」
「わかるかどうか、よりも、おもしろいかどうか。好きであるかどうかだ。〈わかるものが好きだ〉という狭さでは、予想を超えたこととともに生きる必要がある世の中でサバイバルできない。好きなことにとことんのめりこんで、次々に来る驚きの瞬間である。必ずしも説明ではない情報を詰め込んで書いた、読者の勉強になる詩————知ることができない何かを予感させる詩————が、もっと、あっていい。こんなものは詩ではないというのであれば、そうであるが詩だ。実際には、あっさりエッセイなのか、なんでもないものを軽く書いて、何も起こっていない静けさを雰囲気の良さであるように見せて誤魔化している、愛がない〈詩人〉たちが、『現代詩手帖』にも多いようである。何もしないとのさばってしまう暴力と崩壊と消滅に、ていねいに、何事かの出現で抗う必要がある。
私が自分の本の打ち合わせでお会いした小田久郎さんは活発で、話がおもしろくて、本の作り方についてのアイデアが、シャープだった。思潮社の本にはおそるべき迫力があった、少し過去形だが。何事かを起こす人がいなくなったあとで、どうするか。まず、読むこと。みんなマジで現代詩を読まなければならない。」
(中村稔「小田久郎・断章」より)
「小田の『戦後詩壇私史』に見られるとおり、小田は「詩壇」というものの存在を意識していた。わたしは「詩壇」というものが存在するとは考えていなかったので、小田のこの著書の題名にはかなり違和感を持った記憶がある。
詩壇があるとすれば、どこにあるのだろうか。『現代詩手帖』に寄稿する人々を中心として、『現代詩手帖』の毎年十二月号の「現代詩年鑑」の「詩人住所録」に掲載されている二千人か三千人の詩人たちで構成されているのであろうか。伊達得夫や森谷均は「詩壇」の一員という意識は持っていなかったと思うし、第二次『ユリイカ』を発行した清水康雄もその初代編集長をつとめた三浦雅士も、「詩壇」という意識は持っていなかったのではないか。谷川俊太郎も自分が「詩壇」に属するとは思っていないのではないか。これは亡き大岡信にしても、飯島耕一にしても同じではないか、と考え、ところが、おそらく小田は谷川俊太郎も大岡信も飯島耕一も、彼らはみな、「詩壇」に属する詩人と思っていたのではないか、と考え、それ故、小田が「詩壇」という発想をもつのを奇妙に感じるのである。
(・・・)
「詩壇」「歌壇」「俳壇」もそれぞれ存在するように思われてくる。そこで、詩論や詩人論は「詩壇」の中でのみ通用するようである。同じように、歌論や歌人論は「歌壇」という閉鎖社会の中でだけ有用しているように見える。そういう意味で『現代詩手帖』は小説家に門戸を開いていないし、文藝時評の類を採り上げることもなく、社会時評の類を採り上げることもない。採り上げるのはもっぱら詩と詩に関する評論やエッセイに限っているように見える。『現代詩手帖』と思潮社は、そうした閉鎖社会の中で君臨していたのではないか。という感じがしないでもない。そういう閉鎖社会を「詩壇」というのかもしれない、と考える。
(・・・)
現代詩の世界では「詩壇」があるのかどうか。「文壇」と同じく、たぶん、あるのだろうが、その存在が必ずしもはっきりしていないのに対し、短歌、俳句の世界では「歌壇」、「俳壇」というものが確実に存在しているように見える。そして、「歌壇」「俳壇」は「詩壇」以上に閉鎖的なように見える。日本の文学者の世界は、まことに風通しが悪いのではないか、という疑問を私はもっている。そういう意味では、「詩壇」というものが存在すると言われても、頷きたい気分が強くなるのである。」
「私が現代詩を読んでも興趣を覚えることが稀なのは、私が愚昧だからではなくて、「詩壇」の閉鎖性の結果、「詩壇」内部でだけ通用する、独善的な表現やイメージの氾濫によるものかもしれない。このことは現代詩の読者は「詩壇」に属する人々に限られているのではないか、という読者の不在ということにも関連するかもしれない。
(・・・)
このことは、また、あるいは閉鎖社会においては批評性が欠如することになるという問題と繋がるかもしれない。現代詩においては、かつて吉本隆明、大岡信に批評性のある評論があったように憶えているが、その後は現代詩の批評としてどんなものがあるか、魯鈍な私が知らないだけで、きっと現代詩が批評性を失っているということはないのであろう。ただ、遠くから眺めているという素人眼には、「歌壇」「俳壇」にはいかにも批評が欠如しているように見える。歌人や俳人はたがいに褒め合っているばかりのように私は感じている。また、現代短歌の読者は「歌壇」に属する人々に限られるように思われるのだが、どうだろうか。
(・・・)
「詩壇」の閉鎖性がつよくなると、どんな事態になるのか。危惧は尽きない。「詩壇」は決して閉鎖的ではないのだ、と小田は言うかもしれない。「詩壇」とは、多かれ少なかれ、閉鎖的な世界だと見るのは私の僻目なのだろうか。
このような感想はたぶん小田久郎とは関係ないことであろうが、『戦後詩壇詩史』という小田の著書の題名に対する私の違和感をつきつめて考えてみると、こんな感想にまで辿りつくのである。」
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
