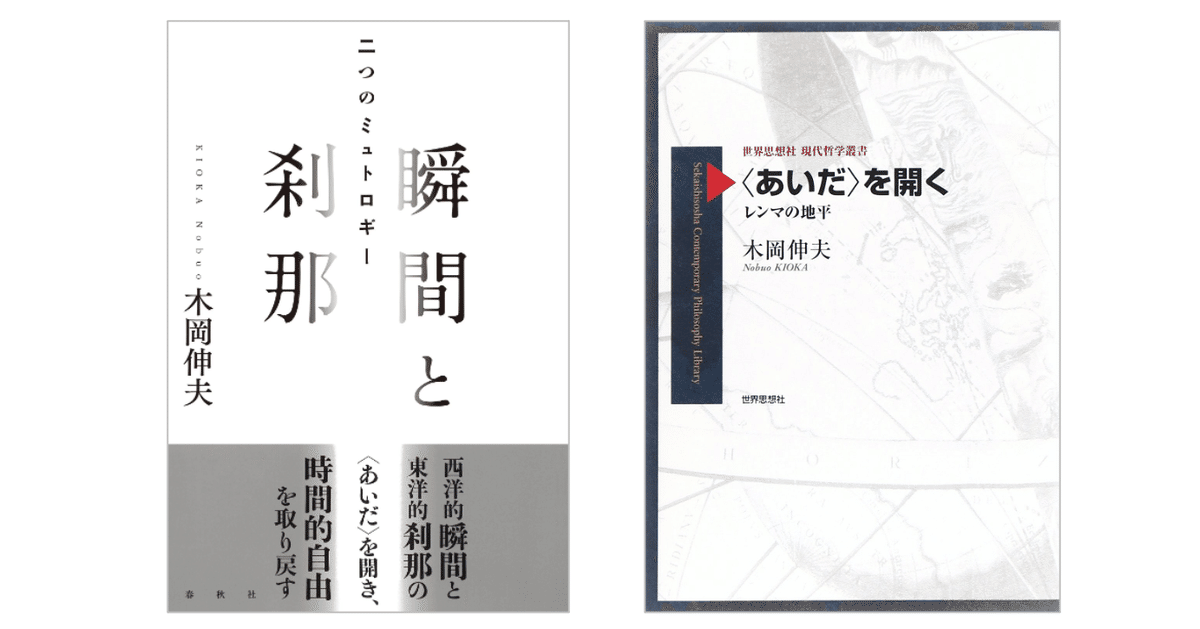
木岡 伸夫『瞬間と刹那/二つのミュトロギー』/『〈あいだ〉を開く/レンマの地平』
☆mediopos2668 2022.3.7
「瞬間」というと
現代では西洋近代のイデオロギーの影響で
過去と未来という「直線的時間上」にある
「均質無個性の時間点である「点時刻」」
として理解されているが
ほんらいの「瞬間性の根本体験」はそれだけではない
著者によれば「瞬間性の体験」は
共通の起源をもつにもかかわらず
「瞬間」と「刹那」という
異なるタイプのミュートス(神話)を生んだが
(仏教的にいえば「瞬間」は「常住」であり
それに対して「刹那」は「無常」である)
「そのいずれかではなく、いずれでもない中間地点に」
「〈あいだ〉を開く」ことが必要だという
「瞬間」と「刹那」の
「〈あいだ〉を開く」ために
著者は二元論である「ロゴスの二値論理」ではなく
山内得立の示唆している「中の論理」である
非二元論の「レンマ」の視点を導入する
(「レンマ」といえば
中沢新一の「レンマ学」も
山内得立の議論に基づいている)
二元論を排するのではなく
非二元論によって二元論を超えようとするのだ
ちなみに第一・第二のレンマは
肯定及び否定の二値論理であり
第三のレンマは〈両否〉
第四のレンマは〈両肯〉である
そして第三のレンマから
第四のレンマへの移行は「即」であり
この転換を山内得立は「即非の論理」と称した
「肯定でもなく否定でもない」絶対否定から
「肯定でもあり否定でもある」絶対肯定への転換が
即時的・無時間的に成立するというのである
「瞬間性の根本体験」が
根源的には共通しているにもかかわらず
それが「瞬間」と「刹那」として現れるのは
西洋の論理が「有」の論理であり
それに対して仏教的な論理は「無」であるからである
本書ではその違いの発している究極の地平に至るために
レンマの論理を使って
東洋的「刹那」と西洋的瞬間の〈あいだ〉を探る
その非二元論を著者は〈かたちの論理〉で説明している
〈型の文化〉における〈かた〉には
可視的不可視的の両面があって
その〈かた〉そのものは不可視だが
可視的な〈かたち〉のモデル(規範)となるように
〈かた〉は真の《存在》への手がかり・導きとなる
(「〈かたち〉の「ち」は「力、勢い」を示す接尾語で
〈かたち〉には〈かた〉にはない生命性・可変性が含まれる)
そして西洋においては〈かた〉の先には
《存在》としての「神」があるのに対し
レンマ的東洋では「非存在(無)」がその場所にある
それゆえに「瞬間性の体験」が「瞬間」と「刹那」という
異なったミュトロギーとして現れることになる
さてこうした短い記事では
こうしたことを説明するのは難しいので
本書で扱われている
九鬼周造・大森荘蔵・三木清らの時間論や
もっとも重要な山内得立のレンマ・即非の論理等について
項を改めて少し詳しくご紹介することにしたい
■木岡 伸夫『瞬間と刹那/二つのミュトロギー』
(春秋社 2022/2)
■木岡 伸夫『〈あいだ〉を開く/レンマの地平』
(世界思想社現代哲学叢書 世界思想社 2014/10)
(「第一章 「瞬間」と私−−−−失われた時」より)
「「因果」ではなく「縁起」の相の下に、世界を見つめ直すこと。それが、さしあたり「瞬間」の対極に「刹那」を位置付けることの意義である。」
「本書が主題として取り上げるのは、二種のミュトロギー、「瞬間」をめぐる西洋のミュトロギー、および「刹那」に関する東洋のミュトロギー、である。仏教の視点からは、それぞれを「常住」と「無常」に基づく二つのミュトロギー、と言い換えることができるかもしれない。(・・・)この二つは、二値論理的にいずれか一方が正しく、他方が誤っているというのではなく、たがいに否定し合い、かつ肯定し合うという、レンマ的な相のもとに、共存すると考えられなければならない。
ところで、現状はどうか。全世界を席巻した西洋近代のイデオロギーにより、「瞬間」の意味は、「直線的時間上の点時刻」へと切り詰められている。(・・・)本書が、あえて「二つのミュトロギー」を掲げる理由は、人が人であるかぎり、共通に体験する瞬間性の根本体験に溯り、そこから異なる言説が発生、分岐して、二つの流れを形づくる経緯を辿ってみることにある。瞬間性の体験は、「瞬間」と「刹那」という異なるタイプのミュートス(神話)を生んだ。二つのミュートスに、それぞれのロゴス(論理)が加わることで、二つの「ミュトロギー」(ミュートス的ロゴス)が成立し、展開する。現在の世界は、共通の起源をもつ二つのミュトロギーのうち、一方の全面的支配下にある。(・・・)言いたいことは、二つの方向が開かれているとき、そのいずれかではなく、いずれでもない中間地点に身を置いて考えよ、ということ。すなわち、〈あいだ〉を開くべしということ、ただそれだけである。」
(「第九章 瞬間と刹那の〈あいだ〉」より)
「「瞬間」と「刹那」は、二つの異なるミュトロギーがそこから展開する起点であり、それぞれが「ミュートス」であるものの、その様相を異にする。西洋世界における「瞬間」は、それ自体が「ミュートス」として屹立したというより、瞬間的なものをめぐる言説が、「ミュートス的ロゴス」として展開した。この点は、「刹那」のミュートスが、「刹那滅」というミュトロギーと不可分に結びついた、仏教のあり方とは対照的である。瞬間性をめぐる東西両世界のミュトロギーは、それぞれに固有な性格を表し出す。」
「西洋近代に成立した直線的時間は、「瞬間」の意味をどのように変えたのか。〈瞬間のミュトロギー〉の観点から言えば、第一に、ロゴス化の極に、均質無個性の時間点、「点時刻」の観念を生じさせたことが挙げられる。
(・・・)
第二に、〈瞬間のミュトロギー〉において、(・・・)脱神秘化・世俗化と並行し、かつそれに反発して、経験超越的な志向が発生する。これは、ロゴス化の進展に対する反動として、〈再ミューズ化〉の勢いが生じるという事態である。キルケゴールやニーチェ、さらにハイデガーなどに代表される、「実存」重視の哲学は、「瞬間」の体験によって、合理主義のロゴスに風穴を開け、親和的次元への通路を開こうとした、と言ってよいだろう。してみれば、全体としての「ミュトロギー」のうちに、〈ロゴス化〉と〈ミュートス化〉の両ベクトルが併存し、拮抗するというあり方が、〈瞬間のミュトロギー〉の実態であると考えられる。
とはいうものの、今日のわれわれは、以上の要約に盛り込まれたような「瞬間」の両義性を生きている、とはもはや言いがたい状況にある。(・・・)滔滔たる世俗化の流れは、自然と社会とをあわせた世界の全体を、直線が支配する因果的な時間によって覆いつくしている。そう言っても過言ではないだろう。もう一つのミュトロギーが要請されるのは、このような近代の終焉に際してのことである。
ミュートスはロゴス化を予想し、ロゴス化への途を拓くことにより、「ミュトロギー」を形づくる。形成されたミュトロギーは、一方でロゴス化合理化の極に、ミュートスとは一見無縁であるかのごとき抽象物、記号表現を産出する。直線としての時間、時刻点としての瞬間は、ロゴス的合理化の果てに成立した人工的記号にほかならない。」
「これとは対照的に、仏教的な「刹那」をめぐるミュトロギーは、部派仏教から大乗仏教に至る過程で、ロゴス的な理論整備が進行するものの、ミュートス本来の性格を失うことはなかった。」
「「瞬間」と「刹那」は、いずれも生の本質にかかわる瞬間性の体験である。体験を語るミュートスである点に関して、二つの語に違いはない。世に文明の型が複数あり、それぞれに特徴的な時間論が存在するとしても、時間観念の核をなす瞬間的なものの体験に、根本的な違いがあるということは想像しがたい。(・・・)とはいえ、かたや「瞬間」、かたや「刹那」、瞬間性の表現にこの二語が存在するという事実は、それぞれをめぐる言説としての「ミュトロギー」(ミュートス的ロゴス)に、重大な性格の異なりを生じさせるだけの事情があることを窺わせる。」
「仏教的な「刹那」のミュトロギーの特質を、西洋的な「瞬間」のミュトロギーとの対照において際立たせるとすれば、その手がかりとなるキーワードは、「即」および「即非」であると言いたい。(・・・)
山内得立は、『ロゴスとレンマ』(一九七四年)の中で、自身の創案したテトラレンマの定式について、その第三レンマ(両否)から第四レンマ(両是)への移行が、「即」であるとして、「即の論理」を提唱した。それは、「肯定でもなく否定でもない」絶対否定から、「肯定でもあり否定でもある」絶対肯定への転換が、即時的・無時間的に成立する、という理路を意味する。そのさい、たがいに対立し矛盾する二つの主語が、「分かたれたものとして同時にあり、分かたれてあるままに一である」ことが、「即」である。「世俗諦」である第一・第二レンマの関係−−−−ディレンマ−−−−とは対照的に、「勝義諦」とされる第三・第四レンマの関係が、「即」として見られるということは、般若の智慧とされる「空」の境地が、それ自体として無時間的であるということである。とすれば、仏教的な解脱の境地は、時間を超えた〈永遠〉である、ということになるのではないだろうか。」
「西洋の「ロゴスの論理」と東洋の「レンマの論理」−−−−この二つの「論理」を比較するとき、一方に存在するものが、他方には存在せず欠如する。一方において、「在りて在るもの」、すなわち創造する神と、「在らしめられて在る」被造物とに成立する、二元的で絶対的な対立は、東洋的なレンマの世界には存在しない。他方、存在の根拠たる「非」、つまり「絶対無」の思想は、西洋の有神論では考えられない。にもかかわらず、山内が「即非の論理」に導入したのは、計上額的な「存在の論理」であった。論理の形式としては西洋、内容としては東洋、という独自の〈総合〉が企てられたわけである。」
「「二つのミュトロギー」とは、西洋哲学における「瞬間」、仏教思想における「刹那」をめぐる二種の言説を表す。あえてそのように題したことの意図は、大きく見て、次の二点である。(一)西洋と東洋のいずれにおいても、「瞬間性」−−−−より一般的に「時間」というふうに拡張してもよい−−−−の経験が、ミュートス(神話)とロゴス(論理)による表現、「ミュートス的ロゴス」としての「ミュトロギー」を生み出した、という点。(二)西洋と東洋に成立した二種のミュトロギーは、それぞれの世界における存在理解。世界理解の型を表す、という点。つまり、瞬間性をめぐる言説が「ミュトロギー」である点は、東西に共通するが、その表現の〈型〉は異質であるという考えは副題には込められている。したがって、本書の意図は、瞬間的ないし時間的な経験が、東西それぞれの独自性をもつことを見きわめる「比較思想」にある。(・・・)しかし。その先に問題がある。なぜ、何のための「比較思想」なのか。
(・・・)
「比較思想」は、何のために行われるのか。それは、二つの思想が現に異なってある地点から溯って、その異なりが発源する究極の地平に至ること。思想A(西洋思想)、思想B(仏教)が、そこから発して現在にまで至りつく源泉の所在を突きとめること、それが「瞬間と刹那」を主題に掲げる本書の目標であり。それを実現する上で不可欠な理念が「ミュトロギー」である。」
「比較の対照は、「瞬間」を時間の要素とする西洋的な言説と、仏教用語「刹那」を核とする東洋的な言説、である。(・・・)時間は、「瞬間」「刹那」のミュートスを元に形成される「ミュトロギー」の〈型〉として、理解されなければならない。第一次的な瞬間性のミュートスが生まれ、それに第二自的なロゴスが加わることで、ミュトロギーとしての「時間」が形成される。ミュトロギーは、基本的に〈ミュートスからロゴスへ〉の移行である。」
「著者がなぜ、この二つの語(瞬間」と「刹那」)をめぐる言説を、それも「ミュトロギー」として、比較の俎上にのせようとしたのか。理由は、次の二点である。
第一に、西洋的「瞬間」の東洋的「刹那」に対する圧倒的優位は、そのまま受け容れ放置することができない、「異常」事態であり、その異常さに気づく必要がある、ということである。第二に、その状況を変えるためには、双方の〈あいだを開く〉態度変更が必要不可欠である。このことに、大方の注意を促したい、と考えるからである。」
「ロゴスの二値論理、つまり二元論ではなく、レンマの非二元論によってこそ、〈あいだを開く〉ことが可能になるのだ、と言いたい。とはいえ、非二元論によって二元論を超えるということが、二元論を排却することではない。(・・・)そういう非二元論を確立するための理論装置として、著者流の〈かたちの論理〉を紹介する。
「「形なき形」を追求する、東洋・日本の文化。そういう〈型の文化〉が、西洋文化と根本的に異なる意義をもつとすれば、それはどういう点だろうか。(・・・)〈かた〉には、①可視的、②不可視的、の両面がある。①の場合、〈かた〉は、それ自体が可視的な〈かたち〉、つまり実在するモデル(規範)となる。これとは対照的に、②は、不可視的な絶対者に接近する通路である。①は、文化形成の過程が生じるかぎり、どこにでも普遍的に成立する。問題は、②である。というのも、〈かたち〉をつうじて〈かた〉をめざす過程自体は、普遍的であるとしても、〈かた〉のめざす先の「絶対者」は、それをめざす世界によって異なることが、明らかだからである。その異なりを、端的に言えば、ロゴス的西洋における絶対者が、《存在》つまり「神」であるのに対して、レンマ的東洋では、非存在(無)すなわち「絶対無」が、その地位を占める。絶対者と絶対無、対極的なこの二つが、どうして考えられるのか。理由として、〈かた〉は、それ自体を顕すことのない根源の〈痕跡〉に過ぎない以上、その根源を「存在」とするか「非存在」とするかは、〈かたち〉を実践する主体の自由に委ねられるからである。
たとえば、宗教的実践の世界では、ふつう修行の目標は、不可視の「神」を見ることにある。それゆえ、〈かた〉には、真の《存在》への手がかり、導き、という意味が与えられなければならない。そうした到達目標を必要としない修行の場合、〈かた〉の先に《存在》を想定すべき理由はなく、ただ〈かた〉と〈かたち〉との行き来が保障される仕掛けがあれば、それでよい、ということになる。西田幾多郎が、禅の修行をつうじて体得した「無」の境地。それは、後者の意味における〈かた〉の一つのありようにほかならない。その境地において、〈かた〉から〈かたち〉が生まれるプロセスを、後期の西田は、「絶対無の自己限定」と言い表したのである。
(・・・)
本書の議論をここまで導いてきたんは、山内得立の「即の論理」「即非の論理」である。〈かた〉を介して窺われる〈絶対〉を、有と無のいずれかの決定しなければならない理由はない。このことに思い当たったのは、山内得立が、「即非の論理」における「非の地平」を「意味の世界」に見立てた、という事実を知ることによってである。「意味の世界」では、神も仏も、有神論あるいは無神論でさえも、すべてが「意味」として並び立つ。「瞬間」と「刹那」もまた、異なる世界における瞬間性の「意味」として、たがいに遜色のない位置に立つ。そのような「意味の世界」から、さまざまな〈かた〉が生まれ、それにもとづく無数の実践、〈かたち〉が展開する。いかなり〈かた〉に準拠すべきかは、異なる〈かた〉と〈かた〉の〈あいだ〉に身を置いて、一人一人が決定すべきテーマである。〈あいだを開く〉ということは、そういう意味の「自由」を行使することにほかならない。」
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
