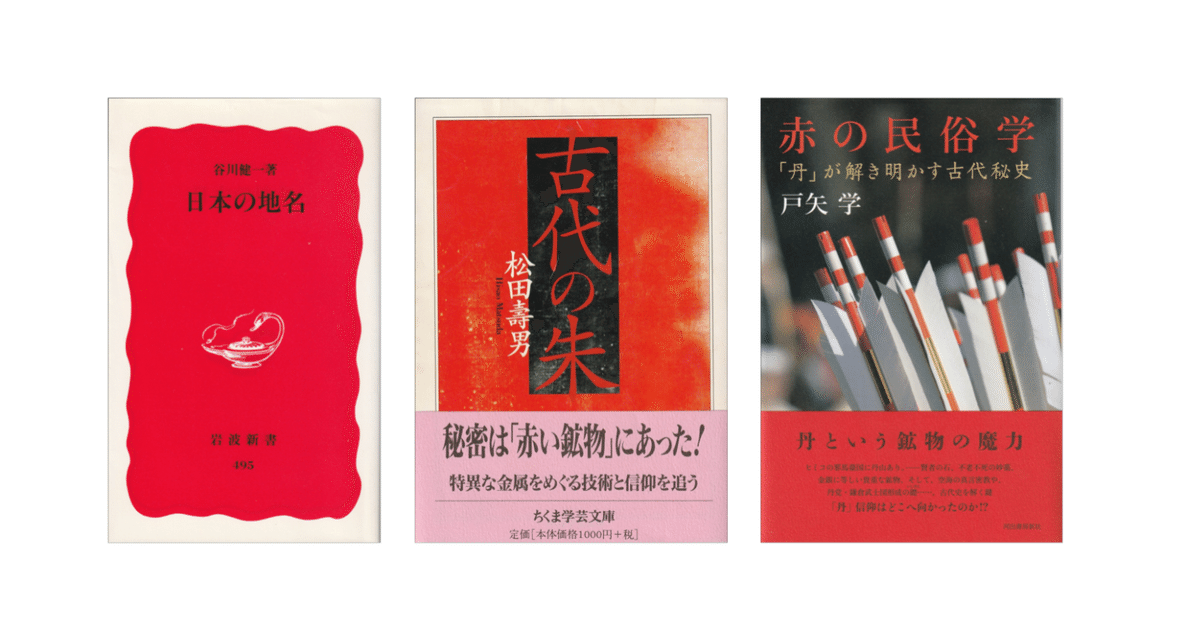
戸矢学『赤の民俗学 「丹」が解き明かす古代秘史』/松田壽男『古代の朱』/谷川健一『日本の地名』
☆mediopos3485 2024.6.2
「丹(に・たん)」とは
硫化水銀鉱物の「辰砂(しんしゃ)」であり
朱色の顔料としても珍重され
金属精錬・鍍金・医薬・顔料・化粧品などとしても
広く用いられてきた
「丹」を産出していたことから
丹波国(たんばのくに)・丹生神社(にうじんじゃ)のように
全国各地に社名や地名などとして「丹」が多く使われてきた
谷川健一は『日本の地名』のなかで
松田壽男の『丹生の研究』から
中央構造線と辰砂の関係という興味深いテーマを紹介している
(文庫化されている『古代の朱』は
『丹生の研究』をコンパクトにまとめた著作)
「戦前の日本では、北海道をのぞく本州で約三十の鉱山に、
水銀の産出が確認されたが、
その三分の二以上は中央構造線に沿って位置するものである」
そして「「伊勢の丹生から西に、
数々の丹生をつらねて豊後の丹生まで、地質学での中央構造線は、
まさしく「丹生通り」を形成している」とし
「黒潮が海上の大動脈として
日本文化に大きな役割を果たしてきた時代があったように、
中央構造線が陸における日本文化の大動脈として
寄与した時代があったことを忘れるわけにはいかない。」
というのである
そうした「朱」をめぐる縄文時代からの古代史が
戸矢学『赤の民俗学/「丹」が解き明かす古代秘史』
として刊行されている
辰砂は縄文時代以来きわめて重要な産物であり
「縄文の遺物には赤い彩色のほどこされたもの」の多いことが
最近の研究で明らかになっていて
あの無彩色のようにイメージされていた縄文土器や土偶も
丹の朱で彩色されていたというのである
しかも「「丹」を身体にも塗っていた」とも考えられている
戸矢学・説ではあるが
国旗の日の丸の赤も
「日本が丹の国であることを標榜するものであったとも言える」
とさえいえるほど
「古代において丹の産出がすなわち実質的な国力を
体現するものという時代があった」のである
かつて盛んであった辰砂の採掘も枯渇してきたことから
その実態はよくわからなくなってきているが
その辰砂の産地では「丹生都比売」(にうつひめ)」を
氏神として祀る丹生都比売神社
そして辰砂の産出に関わった丹生氏の一族の存在があった
「丹生都比売命」は『古事記』『日本書紀』にはでてこないが
それはヤマトの文化とは別の系統の
文化が存在していたことを示している
さて水銀・辰砂といえば
高野山を開いた空海も
丹生・高野の二柱の神を迎えて寺の守り神としている
高野山の開山にも「丹」が深く関わっているのである
空海は「中国の道士が水銀の薬物としての性能を
巧みに応用して不老長寿の薬としていた「丹薬」の製法」
(「煉丹術(錬丹術)」)を伝えているともいわれている
実際のところかつてそれを飲用することで
中国の皇帝が中毒死を遂げてもいたりするように
水銀は飲用すると毒物になる
これはほんらいの錬金術の基本的な考え方である
塩プロセス・燐(硫黄)プロセス・水銀プロセスにおいて
実際の水銀を服用すれば水銀プロセスとして働くものと
誤解され誤用された結果ではないかと思われる
空海が実際にどのように水銀と関わったかはよくわからないが
空海が「即身成仏」を果たして
高野山の奥の院に祀(まつ)られ今なお生き続けている
とされているのもなにがしか関係しているのかもしれない
■戸矢学『赤の民俗学 「丹」が解き明かす古代秘史』(河出書房新社 2024/4)
■松田壽男『古代の朱』 (ちくま学芸文庫 2005/1)
■谷川健一『日本の地名』(岩波新書 1997/4)
**(戸矢学『赤の民俗学』〜「まえがき————「丹山を、探せ。」より)
*「日本の古代を解き明かすキーワードは「丹」である。」
「丹波国(たんばのくに)、丹生神社(にうじんじゃ)などのように全国各地に地名や遺跡名として遍在しているが、そのほとんどは「丹(たん・に)」を産出していたところから名付けられたものであるだろう。
「丹」は学術的には辰砂(しんしゃ、cinnabar)と称し、硫化水銀(HgS)からなる赤褐色で半透明の鉱物で、別名「賢者の石」「朱砂」「丹砂」などとも呼ばれる。古代品においては丹は薬であり(日本の民間薬「仁丹」もこれにあやかっている)、また朱肉や朱墨のように朱色の顔料としても珍重された(これを「水銀朱」ともいう)。当時は金銀に等しい貴重な鉱物であった。なお「辰砂」の呼び名が、古代シナの辰州(かつて実在した地名)で多く産出したことから付いた。
その貴重な「丹」が、邪馬壹国の山で多く産出したと『三国志』魏書の烏丸鮮卑東夷伝倭人条(通称「魏志倭人伝」に記されている。つまり邪馬壹国には丹の山があり、朱色の顔料が贅沢に使われていたことが推測される。(・・・)
古代シナでは産出地を神仙郷と考える思想が浸透しており、とくに秦始皇帝以来、歴代の皇帝は丹から抽出される水銀に金を溶かし込んだ液体を「不老不死の妙薬」とする方術士たちの欺瞞により、飲用することで複数の皇帝が中毒死を遂げてもいる。
たとえば神社の鳥居は、「丹」の造形との説もあるほどで、だから朱色でなければならず、「丹」を支配する者の証であった。」
「丹生都比売神社に始まると考えられる「丹」信仰は、その神域の一部を空海に与えることで真言密教をも取り込み、紀伊に独自の信仰圏を創り上げた。そしてその影響力の広がりは西は四国全域かた九州北部、東は関東の鎌倉武士団の形成に至るまで広がるが、ある時期から突然「丹」の産出が激減し(もしくは代用品が安価に出回ったため)、丹生神社の消滅とともに歴史の闇へと消えてゆく。」
**(戸矢学『赤の民俗学』〜「第一章 縄文を彩る赤き信仰・・・・・・べに(紅)と共に」より)
・赤の発見
*「縄文の土器や木器は「真っ赤」であった、と言ったら、きっと多くのひとが驚くだろう。」
「縄文の遺物には赤い彩色のほどこされたものが思いのほか多いことが判明したのは近年になってからのことである。二千年以上経てば、いかなる色彩も褪色するのは当然で、長年泥土にうずもれていた発掘品であれ、放置されて風雨に晒されていたものであれ、数千年も経てば否応なく劣化は進む。そのためつい最近まで、私たちは縄文土器の多くは無彩色だと思い込んでいた。
しかし考古学の研究手法の進歩のおかげで、わずかな色彩の痕跡かた、縄文人が「赤色」にひときわこだわっていたことが明らかになった。」
・「赤色=縄文赤」の正体
*「「縄文赤」の実態は何かというと、主に次の三種であったとされる。
1【丹 HgS】赤色硫化水銀(丹=辰砂)
2【紅殻 Fe2O3】酸化第二鉄(紅殻・弁柄=赤鉄鉱)
3【鉛丹 Pb3O4】四酸化三鉛(光明丹=赤鉛)」
「縄文人は(弥生人も)「丹」を身体にも塗っていたと考えられている。丹朱は、縄文後期に使われ始め、弥生時代や古墳時代にはかなり広まっていたようで、入れ墨や、装飾古墳の内装などにもふんだんに使われていり、丹朱をふんだんに使えることは権力の証でもあったようだ。」
「丹波などの地名は、かつて丹を産出していたことから称されたものだろう。
丹生や丹羽などの苗字氏名は、丹の採掘や精製に関わる一族が名乗ったものであるだろう。丹生都比売神社の世襲宮司家は、もとは大丹生氏と称したもので、丹生氏はその子孫である。
鎌倉時代に武士のさきがけとなった武蔵七党の一つである丹党は、武蔵国北西部に産出した丹を古くから管掌していたことから称したのので、氏神として秩父郡から児玉郡にかけて丹生神社を創建している。」
*「わが国の国旗である日章旗(日の丸)とは、日本が丹の国であることを標榜するものであったとも言えるだろう。古代において丹の産出がすなわち実質的な国力を体現するものという時代があったことからも、そのように考えることは可能であろう。したがって、本来「日の丸」は「朱色」である。」
「「水銀朱(辰砂)」こそは、縄文時代以来、日本および日本人にとってきわめて重要な産物であった。」
**(戸矢学『赤の民俗学』〜「第二章 煉丹術と化学・・・・・・たん(丹)を求めて」より)
*「錬金術は、実は古代シナの「煉丹術(錬丹術)」に由来している。(・・・)「丹」を主原料として(*厳密には辰砂から抽出した水銀が主原料)、様々なものとの加熱化合を繰り返して「不老不死の仙薬」を作り出そうというものである。」
「煉丹術には外丹と内丹とがあって、化学的に仙丹(仙薬)を作り出すことを外丹、それを服用して仙人となるための修行法を内丹と称して区別している(後に服用は前提条件ではなくなる)。
いずれにしても丹薬の主原料は水銀である。」
*「日本(ヤマト)における丹の採掘は一時期盛んであったが、やがて資源の枯渇によって変貌し、実態はよくわからなくなっている。ただ、どうやらその入り口は丹生都比売信仰にあるようだ。紀伊地方以外ではあまり馴染みのない神名であるが、きわめて古くから信仰されている神であって、おそらくは関東の武士・上野あたりにおいてもそうだろう。しかし丹生都比売命は『古事記』にも『日本書紀』にも登場しない。つまり、ヤマトの神ではないということである。記紀以前に、異質な文化が存在したことの証左の一つかもしれない。
かつて「丹生神社」であった少なからぬものが、なぜ社名変更されているのか解明されるとすれば、古代史の闇のある部分が明るみに晒されることになるだろう。そこには、「丹(辰砂・朱)」という資産と、それを活用する渡来の知識や技術が関わっているはずである。紀伊の丹生都比売神社や丹生川上神社、また武蔵・秩父の金鑚神社(元・金砂神社)や。両神神社(元・丹生神社)は、その重要な手がかりの一つである。」
**(戸矢学『赤の民俗学』〜「第三章 丹神からの贈り物・・・・・・に(丹)の発見」より)
*「ニウツヒメを祭神とする神社は全国に一〇八社余。うち実に七〇社以上が和歌山県にある。まさに紀伊の神である。古代に紀伊国とは別の国があって(「き」の国に対して「に」の国か)、ニウツヒメはその国の王であったと考えるのが自然であろう。
総本社かつらぎ町の丹生都比売神社。式台社(名神大社)であり、紀伊国一宮、旧・官幣大社である。」
*「また、高野山の鎮守神でもある。
『今昔物語集』には、密教の道場とする地を求めていた空海の前に「南山の犬飼」という猟師が現れて高野山へ先導したとの記述があり、南山の犬飼は狩場明神と呼ばれ、後に高野御子大神と同一視されるようになった。」
*「紀氏・丹生氏の一族は、ニウツヒメを奉戴して紀伊の辰砂採掘をおこなった。この地域の水銀鉱脈は豊富であった。その財力はこの地に一種の独立国家を建設・維持するにじゅうぶんなもので、空海・高野山もその恩恵によって成立したものだ。
しかし鉱脈というものはいつかは尽きるものだ。紀伊の鉱脈が掘り尽くされたのを契機に、一族の一部は播磨に移住し、別の一族は新たな鉱脈を求めてさらに東へ移り行く。三重、岐阜、長野、静岡、千葉、埼玉、群馬に残る彼らの足跡は、あることによって辿ることができる。————それこそはすなわち、ニウツヒメ・丹生人を氏神として祀ることである。丹生は、丹の生ずるところ。つまりニウツヒメは「丹の産出するところの姫神」という意味である。」
**(松田壽男『古代の朱』〜「古代の朱 一〇 丹生高野明神」より)
*「弘法大師が高野山の金剛峯寺をはじめたのは、まさに雨師信仰がさかんになっていこうとする時期にあたっていた。つまり弘仁七年(八一六年)のこと。この年に勅許をえて、四年後の弘仁十年に落成すると、同年の五月三日には丹生・高野の二柱の神を迎えて寺の守り神とした。もちろん世のなかでは、朱砂の採掘とその利用は滅びてはいない。しかし多くの丹生神社は、そのころ丹生川上神社の祭神の水の女神(ミズハノメ)祭祀に変り、なかにはいっそう進んでオカミの祠と化していた。ところが弘法大師空海は、水神の女神ニウズヒメを敬いつづける。」
**(松田壽男『古代の朱』〜「即身仏の秘密 二 弘法大師と水銀の利用」より)
*「弘法大師空海は、単に日本における真言宗の開祖として重んぜられるばかりではない。彼は平安朝で一、二を争う知識人であった。彼は入唐して専門の学問や教義を深めた上に、いろいろな新知識を日本にもたらし帰ったようである。中国の道士が水銀の薬物としての性能を巧みに応用して不老長寿の薬としていた「丹薬」の製法が、空海によって伝えられたことが(・・・)諸事情から首肯できるであろう。」
**(谷川健一『日本の地名』〜「第二章 地名と風土/中央構造線に沿って 八 丹生通り」より)
*「吉野を根拠地とする南朝方を西北から守っていた楠木正成は河内の千早赤坂村に本拠をきずいていた。『日本鉱産誌』を見ると、千早はまさしく中央構造線上にある水銀の産地である。赤坂の地名は土の色が赤いことを示す。赤坂は辰砂の産地である。辰砂は朱砂ともいい、水銀の原鉱であり、朱の原料でもある。楠木氏はこの辰砂の用途を知っていた、その採掘権をにぎり、それを奈良や京都に売りさばいていたのではないか、というのが歴史家の中村直勝の意見である(『日本の合戦・南北朝の争乱』)。ここで水銀が問題にされていることは興味深い。
松田壽男は戦前の日本では、北海道をのぞく本州で約三十の鉱山に、水銀の産出が確認されたが、その三分の二以上は中央構造線に沿って位置するものである、と言っている(『丹生の研究』)。丹生の地名を冠する神社や地名は少なからずある。その中でも古代水銀の産地としてもっとも有名なのが櫛田川沿いにある伊勢の丹生郷(三重県多気郡勢和村丹生)である。
*「松田壽男は「丹生の研究」の中で、「伊勢の丹生から西に、数々の丹生をつらねて豊後の丹生まで、地質学での中央構造線は、まさしく「丹生通り」を形成している」と言う。」
*「黒潮が海上の大動脈として日本文化に大きな役割を果たしてきた時代があったように、中央構造線が陸における日本文化の大動脈として寄与した時代があったことを忘れるわけにはいかない。」
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
