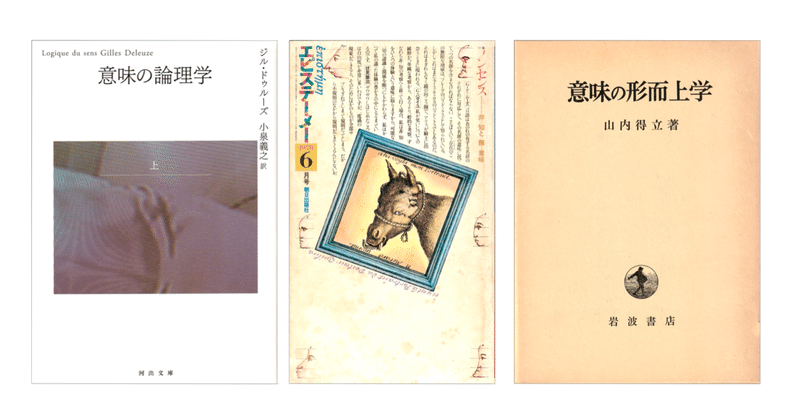
山内得立『意味の形而上学』/ジル・ドゥルーズ『意味の論理学』/『エピステーメー 1978年6月号 特集 ノンセンス・・・非=知と無=意味』
☆mediopos3512 2024.6.29
「意味」とはなにか
それについて問うことは
昨日(mediopos3511)の「笑い」にもまして
「時間」を問うときのようだ
「意味」については
mediopos2713(2022.4.21)で
山内得立『意味の形而上学』をとりあげたが
それをふまえながら
「意味がある」とはどういうことかについて
さらに考えてみることにしたい
「意味」は「木や石がそこに存在するのと
同じように存在しはしない、
それらの事物を見るように我々は意味を見ることができない」
たとえば「色と色の意味とは明らかに別のもの」であり
「色覚は人々によって異なっているが、
色の意味は凡ての人に一様であろうとする。
それは見らるべきものでなくして解せらるべきもの」である
「意味」は「存在に先立っている」
つまり「存在は現にあるものである」が
それを「規定するのは意味」である
「意味」とは
「それ自ら一つの物質的事物でもなく、精神的現象でもなく」
「精神と事物との関係」であって
「心理作用と物的事象との間にある或るもの」
さらにいえばその二つのものの
「間柄」として「成立」するもので
まさに「関係そのもの」
あるいはそこから生まれてくるものである
ある言葉の「意味」を辞書で調べるときなどを
イメージしてみるとわかるのだが
「既知の名辞1は、
その名辞1の意味を指示する名辞2へと送り返され、
名辞2は名辞3へ送り返される、等々」といったように
そこには「遡行のパラドックス、
あるいは無際限な増殖のパラドックス」が起こる
Aという言葉の意味を辞書で引くと
それはBであると書いてあるとする
次にBという言葉の意味を辞書で引くとCとある
さらにひけばD・E・F・・・となり
最後にそれはAであるとしてあったりするように・・・
「意味」を「実体」ではなく
「関係そのもの」としてとらえるのは
「華厳」的な世界観とも通じている
とはいえ「関係そのもの」が
どうして「意味」を「成立」させるのかはわからない
本書では説明されていないように思えるのだが
「意味」が「意味」としてあらわれるためには
それを「意味」としてとらえられなければならない・・・
それはなぜ世界があるのか
私が存在しているのかを問いながら
その問いそのものが生まれる根源をさらに問うようなもの
山内得立は
「ロゴスは言葉であるが、
就中言葉の中にある「意味」である」という
「ロゴスとは言葉であるよりもむしろ意味である
といった方がより適正であろう」と示唆しているが
その視点からいえば
「ロゴス」は「関係そのもの」が
「意味」として現れているものだといえる
『意味の形而上学』のいちばんおしまいに
「初めにあったものはロゴスであり単なる存在ではなかった、
神は存在なくして存在するものでなければならない」
と書いているが
そのことからすれば
「神」とは「意味」であり
それが「関係そのもの」から現れている
ということもできるだろうか
世界がなぜあるのかといえば
神がみずからを見ようとしたことから
という話があるが
その「みずからを見よう」とすることが
「関係そのもの」が現れてくる源なのかもしれない
そしてそれこそが「意味」を「意味」たらしめている・・・
そんなことを夢想してみたりもする
さて意味といえば無意味(ノンセンス)
「無−意味は、意味の鏡像、
意味との単純な関係のなかで意味に対峙するものではない」
「無−意味は、どのような特定の意味ももたないけれど、
意味の不在なのではない」
意味と無意味の関係は
対称性の破れた迷宮のようなものかもしれないが
無意味こそが
既存の意味に縛られがちな世の中から
自由であろうとする衝動なのかもしれない
山内得立も『意味の形而上学』において
「意味と価値」とが混同されることで
「人間的存在は社会にあって種々なる階型的意味と
価値とに縛られて殆ど身動きもできないくらいである」
と嘆いていたりもするが
その意味において
「意味とはなにか」を問うことは
固定化された意味から自由であろうとすることでもある
論理が論理の内部においてトートロジーであるように
意味もまたトートロジーとして閉じてしまわないように
「無意味(ノンセンス)」という対称性の破れが必要となる
■山内得立『意味の形而上学』(岩波書店 1967/4)
■『エピステーメー 1978年6月号 特集 ノンセンス・・・非=知と無=意味』(朝日出版社)
■ジル・ドゥルーズ(小泉義之訳)『意味の論理学』(河出文庫 2007/1)
*上記『エピステーメー』に掲載されている論考は「第5セリー 意味」に収録
**(山内得立『意味の形而上学』〜「序」より)
*「意味の形而上学は意味とは何であるかを研究せんとする学問である。一つの事物は種々なる意味をもち、一つの意味に対し多くの事物が対応するのであるが、これらの様々なる意味を通して意味とはそもそも如何なるものであるかを明らかにせんとする学問である。世にはそれぞれなる意味があってそれらとは別に意味そのものといったものはあり得ないと考えられるかもしれぬがそれにも拘らず意味の何たるかを問うことはそれ自ら無意味なものではない。たとえ無意味であっても無意味とは何を意味するかが問われねばならぬであろうから。それは恰も存在は種々なる仕方に於てのみ存在するがそれにも拘らず存在とは何であるかを問うことが形而上学の中心問題をなすことと同様であるであろう。単にそこに在ることをではなく、在ることの何たるかを問うことが形而上学であるとするならば意味の意味を問うことはまさに意味の形而上学であるべきであろう。現代の論理実証主義者は意味の事実と言語の運用とを研究することに専らであって存在の形而上学をのみでなく一般に形而上学そのものを排斥せんとするのであるが、私は敢えてこの風潮に対して新しく意味の形而上学を打ち立てんとするものである。」
*「意味には種々なる意味があり、種々なる意味はそれぞれなる存在理由をもっているが、価値は対立的であり一が取られ他が排せらるべき択一的な性格をもつ、意味の立場に立つことと価値の態度をとることとは時に撞着し多くの場合相容れないものであるが、しかも意義あることが価値あることと同一視せられるほど密接な関係にあることも見のがすわけにはいかない。意味が価値に転換することは何によってであるか、これは私の最後の問題であるが、また今後の哲学の重要なる問題であるを失わぬであろう。
形而上学は存在の学であり、プラトン以来存在の最も存在的なるものを求めることが形而上学の伝統となったが、現代の実存哲学はこの系譜に属しながら存在の概念を一変した、即ち実存とは単なる存在ではなく、現にそこにある存在であり、単に現象の背後にある本体ではなく、我々にとって現実にあるところの存在でなければならぬ。在るというのは我々にとって知られてあることでなければならない。この転換をなしたものはカントの認識論であるが、現代に於てはさらにまた新しき立場に於て考え直されなければならない。カントにとっては認識とは主観が客観を知ることであったが、主客の関係とか見分と相分との交渉とかいうのは勿論二元論的な立場に立つものである。カントではそこから「形式と内容」との関係移ったが、これも依然として二要素的立場を脱却するに由なきものである。カントの認識論は新しい立場によって変革せられねばならない。恰も古い存在学が現代の実存主義に転換されたように。
そしてこのことを敢えて企てるものが意味の論理学である。それは単に存在の学でなくして存在とは何であるかを問う学問である。存在の種々なる存在の仕方を検討するものでなくして存在の意味を問う学問である。認識とは主観が客観を知ることではなく、事物についてその意味を知ることであり、事物の存在をではなく、その意味を知らんとするものである。そこには主と客の区別はない、あるものはただ一つの与えられた世界又は直接なる経験のみである。問題はそれは何を意味するかを知ることにあって、それが主にあるか客にあるかはそもそも末のことである。事物の存在が我々にとっての存在であるというのも決して主観が事物を構成するということではなく、事物の何であるかが理解せられる限りに於てそれがそこに存在するということである。
事物は意味なしには実存することができない、単に存在はしても実存するとはいえないのである。しかし意味とは何であるか、意味はそれ自らとしてあるか又は事物の意味としてのみあり得るのであるか。この問題は単なる意味の論理学ではなく、意味の形而上学でなければならない、意味はあると言う、しかしこの場合の「ある」というのは如何なることであるか。一般に「ある」ことを問題とするものが形而上学であるとするならば意味のあることを、さらには意味の何であるかを問うことは形而上学でなければならぬ。我々の形而上学は単なる存在の学でなくして意味的存在の学である。存在学は意味的存在学であることによって同時に存在の認識論となり得るのであろう。実存主義が存在学の新しい展開であると同様に認識論のカント的ならざる新しい一つの立場を見出さんとすることがこの書の目的のひとつでもあったのである。」
**(山内得立『意味の形而上学』〜「第一 意味の問題」より)
*「意味は(・・・)存在に先立っている。存在はそこにあるものであるが、存在をそこにあらしむものは意味である。存在は現にあるものであるが、このものを何ものかとして規定するのは意味である。何ものかとしてこれを規定することは一見抽象的であるようであるが、事物はこれによってのみ或るものとして規定せられ得るのである。或るものとは単に何かであるというのではなく、我々にとって何ものかであり、何らかの意味をもつということである。」
**(山内得立『意味の形而上学』〜「第二 意味の成立」より)
*「先ず意味は一つの精神的な現象である、それは精神によって捉えられるのみでなく、それ自ら精神的な或るものであると考えられるであろう。意味があるというのは物質的現象としてではなく、精神的な或るものとしてでなければならない。それは木や石がそこに存在するのと同じように存在しはしない、それらの事物を見るように我々は意味を見ることができない、色と色の意味とは明らかに別のものである、花の色は移りゆくが、その意味は褪せはしない、色覚は人々によって異なっているが、色の意味は凡ての人に一様であろうとする。それは見らるべきものでなくして解せらるべきものであった。」
*「意味とはそれ自ら一つの物質的事物でもなく、精神的現象でもなくして、精神と事物との関係である。心理作用と物的事象との間にある或るものである。しかし意味がこの二つのものの間にあるとは何を意味するのであろう。世にあるものは事物か精神かであってそれ以外に何物もあり得ないとすれば、この両者の間に果して何ものがあり得るだろうか。意味が事物と事物の意識作用との間にあるというのは要するにそれが何ものでもなく無きものに等しいということではないか、しかしそれにも拘わらず意味はたしかに有る、或るものとして有るところのものでなければならない。意味は事物と心的作用の間にあるものではなくして、その間柄としてあるものである。間柄とは一つの関係であり、それ自らは所謂存在ではないが、しかもなお或るものとしてあり得るものなのである。この在り方を例えば成立(Bestehen)と名づけるならば、意味は二つのものの間に在るものではなくして、これらのものの間柄に成り立つものであり。或は間柄そのものとしてあるものである。成立するものは所謂存在するものではないがそれ故に無きものではなく、有るものであり、或るものとしてあり得るのみでなく、現にある所の或るものでなければならぬ。それはそれ故に抽象的なのではなく、却って具体的であり日常的でさえもある。成立とは二つの間に在るものではなく、これらの間にあることそのこと、即ち関係そのものであるといわねばならない。」
**(山内得立『意味の形而上学』〜「第一三 意味の階型性」より)
*「意味の系列は階型をなしてつらなっている。その階層はもとより複雑であり多岐であり無限でさえあるが我々は先ず次の三つの階層に約してその様相を記述することとしよう。」
「意味の第一階層は信号(signal)であり、第二のそれは記号(sign)であり、第三の階層に属するもおは象徴(sumbol)である。」
*「階型は意味的なものでなければならぬ。たとえそれが論理的であっても論理は意味の階層なしには階型をなすことはできない、それをなすには不足なのであり。階型の基礎論は遂に意味の領域なしには不可能であるといわねばならぬ、意味は存在ではなく、存在の言表されたもの、又はそれの表現されたものであり、それなりには一般に階層の組織が不可能であるからである。存在にも階層はありはする、否存在は階層的であるとさえ考えられたが、しかし存在の階層は徒らなる封建制度を誘致するにすぎぬ。」
*「ロゴスは言葉であるが、就中言葉の中にある「意味」である。意味なしには言葉は何なる雑音であり高々ラリアであるにすぎぬ。ロゴスとは言葉であるよりもむしろ意味であるといった方がより適正であろう。言葉の階型性は信号系の階層であり、信号系の階型は意味の階層である。」
*「意味と価値とは従来混同して用いられていたが、概念上にも内容的にも決して同一なものでなく、むしろこれらを明別することが我々の一つの目的でもあったが、それと同時に意味と価値とは同一の系譜に属するものであり、少なくとも無関係でないことだけは確かであろう。そしてこの共通の基盤を求めて我々は意味の階型的組織に達したのである。」
*「意味の世界は事物または存在についてそれぞれそこにあってその間に優劣はなく、真偽の区別さえもない。虚偽の世界もまた虚偽という意味をもつことによって然るべきである。しかし意味の世界は単にそのようにそれぞれなるままに在るのではない、必ず相によって一つの組織をつくり、集って一つの体系をなす。むしろこの全体に於いて意味が生ずるのは恰も文が語の集成でありながら却って文によって語の意味が成立することと同様であるだろう。意味は必ず体系に於てあるべきであるがこの組織をなすものが即ち階型態であるに外ならなかったのである。」
*「人間的存在は社会にあって種々なる階型的意味と価値とに縛られて殆ど身動きもできないくらいである。時としてその息苦しさに堪えかねて、価値を転換し、社会を革命せんとする。しかし転換させられた価値といえどもなお価値の体系に属する。たとえ逆転せられても依然としてこの体系組織を脱するに由なかった。そしてこれを可能にするものは恐らくは宗教を措いて外にはなかったであろう。
宗教に於いては就中価値は意味に転入する。価値は善悪を分ち、真偽を区別し美醜を分別するのみでなく、善を取り悪を捨て、正を容れ、邪を排す、その取捨選択に於て最も厳なるものは価値作用である。しかし神は罪深きが故に人間を捨てない、むしろそれ故にこれを愛し救おうとするのである。」
「神は単なる存在でなく、有りてあるところのものである、即ち単なる存在でなくして存在の表現である。アリストテレスの実存もまたそのように「かつてあったものの現にあるところのもの」であり、単なる存在ではなく、存在の表現であったのである。神を信ずるとはその存在を信ずることであっても存在の何たるかが語られることなしに信ずることができない。信ずるとは殊にその言を信ずることである。それが人の語であるか神の言であるかは問わずもあれ信ずることは常にロゴスのことでなければならなかった。ロゴスは単なる存在でなく意味的存在であり、単なる言葉ではなく意味の表現でなければならなかった。初めにあったものはロゴスであり単なる存在ではなかった、神は存在なくして存在するものでなければならない。」
**(『エピステーメー』〜ジル・ドゥルーズ(木田元+財津理訳)「無意味について」」
*「意味は単に事物と命題、名詞と動詞、指示作用と表現作用とを対峙させる二元性の二つの項のうちの一つでは決してないのだから、また意味はそれら二項の境界、それら二項を分かつ刃、ないしはそれら二項間の差異の分節でもあるのだから、さらに意味はその意味に固有でありかつその意味を映し出す不可入性を意のままに用いるのだから、意味はそれ自体で新たな一連のパラドックスのうちでおのれを展開しなければならない。
遡行のパラドックス、あるいは無際限な増殖のパラドックス。私が何ごとかを指示するとき、つねに私は、意味はすでにそこにあって理解されている、と仮定している。ベルクソンが言うように、人は音からイマージュへ、そしてイマージュから意味へ赴いたりするのではなく、「一挙に」意味のうちに身を据えるのである。意味とはあたかも、可能な指示を実現するためにもまたそれをおこなう条件を考えるためにさえも、すでに私が据えられている圏域のようなものなのである。私が話し始めるやいなや意味はつねに前提されており、この前提がなければ私は話し始めることができないだろう。換言すれば、私は自分が語っていることがらの意味は決して語らないのである。しかしそのかわりに、私はつねに私が語っていることがらの意味を他の命題の対象とすることはできるのだが、私は今度はその命題の意味を語らないことになるのである。このとき私は前提の無限な遡行のうちに入りこむ。この遡行は話す者の最大限の無力と言語(ランガージュ)の最高度の力とを同時に証言している。すなわち、私には自分が語っていることがらの意味を語る力がないということ、つまり何ごとかを語りながら同時にその意味を語る力がないということ、のみならず、言語には語(モ)について話す無限の能力があるということを証言しているのである。要するに、ある事態を指示する命題が与えられているときには、つねにその命題の意味を他の命題による被指示者(デジニエ)とすることができるのだ。命題を一つの名辞とみなすことに同意するなら、ある対象を指示するいかなる名辞〔名詞〕もそれ自体、その名辞の意味を指示する新たな名辞の対象となりうるように思われる。すなわち、既知の名辞1は、その名辞1の意味を指示する名辞2へと送り返され、名辞2は名辞3へ送り返される、等々という次第なのである。言語は、おのれの有する名辞のそれぞれに対応して、その名辞の意味に代わる一つの名辞を含まなければならない。ことばというもののこの無限な増殖は、フレーゲのパラドックスとして知られている。しかしこれはルイス・キャロルのパラドックスでもあるのだ。そのパラドックスは、まぎれもなく鏡の向こう側でアリスが騎士(ナイト)に出会うときに現れる。騎士はこれから歌おうとする歌の題名を告げる。
「歌の名前は、『鱈の目』と呼ばれる」
「まあ、それが歌の名前ですか」とアリスは入った。
「いや、そなたはわかっておらんな」と騎士は言った。「それは、その名前の呼ばれ方だ。ほんとうの名前は、『年をとった人』なのだ」
「それならわたしは『それが、その歌の呼ばれ方なのですね』と言えばよかったのですね」とアリスは言いなおした。
「いや、そう言ったとしてもだめだ。そう言うのはまったく別のことだ。その歌は、『方法』と呼ばれるが、しかしそれは、その歌の呼ばれ方にすぎんのだよ、わかるかな」
「それじゃあ、その歌はなんですか」
「今言おうとしているところだ」と騎士は言った、「その歌は、実は、『門の上にすわって』だ」」
**(『エピステーメー』〜中野幹隆「編集後記」より」
*素粒子はたしかに眼に見えない何ものかであるのだから、たとえば原子模型は、ノンセンスを象った模型であるにちがいない。けれども、コバルト六〇のベータ崩壊の実験によってたしかめられたパリティの崩壊は、いくぶん混み入ったノンセンスの迷路の扉を開いたのではなかったか。世界は、自然法則が不変でありつづけるような演算に対して必ずしも対称的である必要はなく、ベータ崩壊が示した対称性の乱れは、宇宙の非対称性にもとづくものなのだろうか。鏡という、あのノンセンスのラビリンスの特権的な扉が、左右がそっくりさかしまな像を、もはや送り返してはくれないとしたら・・・・・・。」
「無−意味は、意味の鏡像、意味との単純な関係のなかで意味に対峙するものではない。無−意味は、どのような特定の意味ももたないけれど、意味の不在なのではない。意味の欠如ではないのだ。たとえばカバン語は〈対象〉であると同時に問題群的対象を示す限りで、〈語〉でもある。〈語〉はシニフィエの系列のようなある系列を経めぐり、〈対象〉としてはシニフィアンの系列のような系列を循環し、これら二つの系列のあいだのずれをつねに生み出すのだ。こうしてノンセンスは、シニフィアンとシニフィエに意味を供給する・
「すると意味とは、それ自身が何をも意味しない諸要素の組み合わせの帰結である。もとよりそれは因果的な帰結であるというよりは。無−意味がもろもろの項の、構造をもった諸系列を経めぐることによって生み出されるものであって表面効果とでもいうべきものである。意味は、原理でも起原でもない。意味の非物体的効果である表面効果では、意味することばと意味されるものとが、非肉体的な境界線によって截然と分たれ、意味は表面に生成して、ことばがものとたち混ざることはない。認識の不在の認識、外の思考とは、この意味の無−意味を顕揚する装置のいことではなかったろうか。」
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
