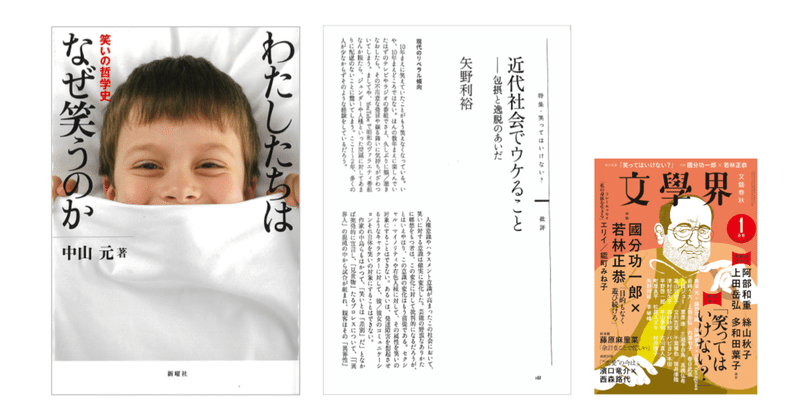
矢野利裕「近代社会でウケること/包摂と逸脱のあいだ」(『文學界 2022年1月号』)・中山元『わたしたちはなぜ笑うのか/笑いの哲学史』
☆mediopos2596 2021.12.25
Netflixで映画『浅草キッド』が公開されている
ビートたけしの自伝的な物語の映画化である
そのなかに印象的なセリフがある
幻の浅草芸人と呼ばれた深見千三郎(大泉洋)が
タケシ(柳楽優弥)にいう台詞
「笑われるんじゃねぇぞ 笑わせるんだよ」
お笑いは
「笑われる」んじゃなくて
「笑わせる」
つまり「ウケる」芸をみせる
そのウケることについて
矢野利裕「近代社会でウケること」
という論考がある
笑いに対する意識の変化にともなって
現在の笑いは10年前の笑いとは
変わってきているという
それは2010年代にさかんに論じられはじめた
ジェンダー論などを背景にした
「ポリティカル・コレクトネス」といった
社会的な意識の変化に対応していて
それが芸能の世界にも適用されることで
差別的な表現がチェックされるようになり
かつて「笑いとは「差別」だ」と
作家の中島らもがいったような笑いは
「お笑い」として成立しえなくなっているのだ
とはいえそれは「芸能もまた、
片足を社会に突っ込んでいる」からであって
「社会的価値観を追認するだけ」では
そもそも演芸として成立しえない
つまり「ウケる/ウケない」ということが
芸人の芸のあり方を規定しているのだ
芸人たちはつねに「ウケ」るであろうものを
みずからの芸のなかに反映させようとしている
『M1』や『キングオブコント』などを観ると
いまなにが「ウケ」ているのかが感じられる
ちょうどこの秋に行われた
『キングオブコント2021』で優勝した
空気階段の「火事」の例が紹介されているが
それは「登場人物の異質性を突き放して笑う」
そのような構造ではなく
異質性の「条件のもとでひたむきになにかをする、
その「夢中」さのともなった「ボケ」」が
強調されているという
そこでの笑いは「感動コント」の傾向があるというのだ
「キャラと人格を、ウソと本当を、
貫通するように存在している」芸人の身体が
ひたむきに過酷な芸人の世界を生きるものとして
コントが演じられている
今年の『M1』の優勝者である錦鯉も
その芸人そのものの
ある種のひたむきなまでのボケが
前面にでていたところがあるようだ
さて「笑い」については少し前に
(mediopos-2538/2021.10.28)
中山元『わたしたちはなぜ笑うのか/笑いの哲学史』を
とりあげたことがある
その論考ではお笑いはとりあげられてはいなかったが
その視点とあわせながら
「わたしたちはなぜ笑うのか」と問うことができる
お笑い芸人は
しばしばひたむきなまでに
じぶんをネタにしながらも
そのことで「笑われる」のではなく
ウケる芸をみせて「笑わせる」
その「笑わせる」という微妙なスタンスにおいて
「ウケる」か「ウケ」ないかは
《大衆》そのものの意識と深く関わってくることになる
笑う《大衆》は
芸人を笑いながらも
その笑いは
みずからへも向けられることになる
という視点も必要になるのだ
《大衆》の意識のなかで
みずからへ笑いが向けられたとき
みずからをスポイルするようなお笑いは
受容されにくくくなる
現在の社会的な意識に規定されながらも
笑うことでじぶんを自由にさせてくれるような
共感できる笑いが求められているのだといえるのだ
ニーチェもいうように
「笑いは人を自由にし、自由は人を笑わせる」
■矢野利裕「近代社会でウケること/包摂と逸脱のあいだ」
(『文學界 2022年1月号』文藝春秋 所収)
■中山元『わたしたちはなぜ笑うのか/笑いの哲学史』(新曜社 2021/8)
※mediopos-2538(2021.10.28)でもご紹介しました
(矢野利裕「近代社会でウケること」より)
「10年まえに笑えていたことがもう笑えなくなっている。いや、10年前どころではない。ほんの数年までの楽しんでいたはずのテレビやラジオの番組でさえ、久しぶりに観/聴きなおしたら、その不用意な発言や振る舞いに気持ちがざわついてしまう。ましてや、YouTubeで昭和のヴァラエティ番組なんか観たら、ジェンダーや人種といった問題に対してあまりに配慮のないことに驚いてしまう。ここ1〜2年、多くの人が少なからずそのような経験をしているだろう。
人権意識やハラスメント意識が高まったこの社会において、笑いに対する意識は確実に変化した。芸能の野蛮なありかたに郷愁をもつ者は、この変化に対して、その属性を笑いの対象にすることはできない。あるいは、発達障害を想起させるようなキャラクターに対して、彼/彼女のコミュニケーションそれ自体を笑いの対象にすることはできない。
作家の中島らもはかつて、「笑いとは「差別」だ」となかば挑発的に宣言し、「見世物」たるプロレスについて、「「異界人」の渾沌の中から試合が組まれ、観客はその「異界性」を外側から眺め、楽しみ、笑う」と指摘していた(・・・)。しかし、さまざまな身体的条件を社会の内側に包摂する現在にあっては、「「異界性」を外側から眺め、楽しみ、笑う」という無責任は態度は許されないだろう。
先日おこなわれた『キングオブコント2021』は、そんな笑いをめぐる意識の変化を本格的に感じさせるものだった。『キングオブコント2021』において示されたのは、「感動コント」の傾向(堀井憲一郎)という以上に、もっと具体的に、なにを笑いの対象とするか、という問題だったはずだ。
例えば、優勝した空気階段の一本目のコント「火事」は、SMクラブに通う消防士(鈴木もぐら)と警察官(水川かたまり)が登場するものの、彼らの変態性を笑い構造にはなっていない。そのセクシャルな志向はむしろ、ダイバーシティ的な価値観のもと認められるべきものとなっている。そのうえで力点が置かれているのは、それぞれの職業倫理を果たそうとする必死な姿のほうである。
(・・・)
空気階段に限らず、『キングオブコント2021』において笑いが起こったのは、コントに登場する人物たちのひたむきさに対してだった。ここで細かく分析する余裕はないが、『キングオブコント2021』において、多くのコントは、登場人物の異質性を突き放して笑うような構造にはなってはいなかった。彼らの異質性は、いち条件にすぎない。むしろ、その条件にもとでひたむきになにかをする、その「夢中」さのともなった「ボケ」(マキタスポーツ『決定版 一億総ツッコミ時代)』のほうが強調されていた。
さらに言えば、そのひたむきさはまるで、過酷な芸人の世界を生きる彼らのひたむきさを示しているようだった。芸人の身体は、キャラと人格を、ウソと本当を、貫通するように存在している。(・・・)
上記のような笑いに対する意識の変化は、もちろん社会的な意識の変化と対応している。とくに2010年代、ジェンダー論やポスト植民地主義といった学問的に成果を背景に、ポリティカル・コレクトネスの意識が広まると、それは芸能界をはじめとするエンターテイメント業界にも適用された。結果、ヴァラエティ番組やお笑い番組は、差別的な振る舞いが厳しくチェックされることになる。
このことは、人権や階級といった従来的な社会的差別に限らない。むしろ、ここ数年でとりわけ一般化しつつあるのは、ルッキズムに代表される外見的特徴を笑うことへの批判意識だろう。ヴァラエティ番組においても、例えば「ブス」といった言葉で笑いを得ようとすることは、ここ数年で完全に時代遅れになった印象がある。ここでは、このような傾向を総じて《リベラル》と呼んでおこう。」
「とはいえ、慎重にならなければならないのは、この社会の歩みがそのまま笑いの世界にパラフレーズできるのか、ということだ。やはり、芸能の論理は、演芸の論理は、社会とは別の水準にあると考えるべきではないか。」
「では、芸能の論理が社会とは別の水準にあるとはどういうことか。先ほどとは逆の方向から問うてみよう。つまり、現代的な芸人における、それ自体は好ましいと思える芸風は、本当に現代的なリベラル意識の高さから来ているのだろうか、と。演芸の論理を社会の論理とイコールで結んではいけない。そこでは、もうひとつメタの位置から考える必要がある。
例えば、寛容な態度で前向きに相手を認めていくような「ノリツッコまないボケ」(松本人志)によって「誰も傷つけない笑い」の筆頭となったぺこぱは、いかにも現代的な価値観を見すえた芸風でブレイクした。(・・・)
ぺこぱは、それまでの漫才から差異化するように「ノリツッコまないボケ」というスタイルを作り出したのであって、本人としては寛容さを目的としたわけではない。(・・・)あくまでも漫才というジャンル内のイノヴェーションとして、「ノリツッコまないボケ」という方法が生み出されたに過ぎない。それはむしろ、自らの商品価値を高めることを目指す、すぐれて資本主義的な態度だ。」
「『キングオブコント2021』も、同じ論理で捉える必要がある。」
「ここから見えてくるのは、笑いを求めることを第一義的に考える芸人の姿である。(・・・)お笑い芸人としての彼らは、当然のことながら、観客にウケることを目的としてネタを作っている。」
「だとすれば、昨今の芸人における人権意識やハラスメント意識の高まりをベタの賞賛する必要はない。突き放して言えば、そのような態度は社会的な約束事に過ぎないのであって、テレビを中心とするメディアで活躍しようという芸人であれば、放送コードと同じように守って当然のものなのだ。」
「近代社会を生きる者として、芸能の領域ではなにをしても許されるのだ、という開き直りをするつもりはない。なにより、そのような芸能ロマンは、「ドギツイ」ものとして《大衆》に「ウケない」可能性がある。芸能もまた、片足を社会に突っ込んでいるのだ。
とはいえ、社会的価値観を追認するだけのものは、演芸たりえないだろう。ましてや、舞台で演じられたものをベタに進歩的なものとして称揚する手つきは、演芸の核心を外している。そこでは。「ウケる/ウケない」という生々しい現場判断の感触が抜け落ちてしまっている。
たしかに、ここ10年ほどで笑いに対する意識は変化した。しかし、それはいつだってそうだったのだ。漫才に代表される近代演芸は、いつだって再帰的な自己チェックが入るのだ。なにより、ウケるために。だったら、近代社会と演芸の両方を信頼したうえで、こう言おう。−−−−すなわち、ウケるということをもっともっと追求するべきだ。社会を追認しているだけでもウケないし、ドギツすぎてもまたウケない。いつの時代だって、その時代に対応したものとして新しい演芸は到来する。新しい毒をもって、その移ろいやすくもしぶといありかたこそ、わたしたちの生きる近代社会の似姿である。そのようなものとして演芸を捉えるべきである。
この態度は、進歩的なリベラルの立場ではない。とはいえ、無頼さを称揚するたぐいの芸能ロマンでもない。もっと根源的に、「ウケる」という《大衆》の反応に対する信頼である。この近代社会において、「ウケる」ということについてマジで考えよう。」
(中山元『わたしたちはなぜ笑うのか/笑いの哲学史』より)
「ベルクソンは人間が社会のうちで知らず知らずに機械的な生き方をしてしまっていることに批判の目を向ける。笑いが生まれるメカニズムよりも、むしろ人間の笑うべき生き方を明らかにすることをこそ、この著作『笑い』は目指しているのである。」
「近代の笑いの理論の最後の第六の理論は、人間の自由を獲得するための批判的な笑いの理論である。人間を抑圧するものを批判する笑いによって、解放という効果が生み出されるのである。」
「こうした笑いの理論を代表する思想家はニーチェである。」
「ニーチェは、(・・・)善がそうであるように、「他人の不幸をたのしむ意地悪い悦びとか、略奪欲とか支配欲、そのほか悪と呼ばれるあらゆる本能、それらは種族本能の驚くべき経済の一部をなすものだ」と喝破する。
ニーチェによると、このことに気づかせてくれるのが、笑う者なのである。」
「このような笑う者が登場するとき、初めて「笑いが智恵と結ばれるであろう、そしておそらくそのときは〈悦ばしい知識〉だけが存在することとなるだろう」。『悦ばしい知識』は、こうした笑いと結びついた知識を模索する書物である。「笑いにとってもなお未来というものが必要である」からだ。
それだからこそ、最後の人間を超える超人を予感させるツァラトゥストラは哄笑するのだ。」
「笑いは人を自由にし、自由は人を笑わせるのだ。」
「フランクルは「ユーモアは人間的実存的なものである」とまで主張する。「患者は、不安を面と向かってみることを、いやそれを面と向かってあざ笑うことを学ばねばならない。そのためには笑うことへの勇気が必要である」。そして心に笑いが忍び込んできたとき、「患者はもう賭けに勝ったのである」。自己を含めた世界を笑いのめしながら「ユーモアをとおして患者はたやすく、自分の神経症の症状をどうにか皮肉り、最後には克服することをも学ぶのである」。この治療の手段としての笑いの効果は、わたしたちがこの閉塞された世界のうちで勁く生き抜くために必須の手段である。わたしたちを圧し潰そうとするものの一切を笑いとばそうではないか。」
◎『浅草キッド』ティーザー予告編 - Netflix
幻の浅草芸人と呼ばれた深見千三郎(大泉洋)がタケシ(柳楽優弥)にいう台詞。
「笑われるんじゃねぇぞ 笑わせるんだよ」
◎空気階段「火事」【キングオブコント2021 決勝披露ネタ】
◎ぺこぱ漫才
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
